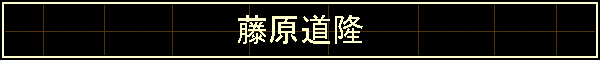藤原兼家の一男。母は藤原中正女時姫。
一条天皇の即位後、摂政となった父兼家の威光で昇進を続け、兼家の没後その地位を引き継いで摂政となった。道隆とその子女たちの一家は中関白家と呼ばれ、我が世の春を謳歌した。
一条天皇中宮は道隆の一女定子であり、中宮に仕えた清少納言は『枕草子』に、気さくで冗談好きな道隆の姿を生き生きと描いている。
ここに着目!
 | 『枕草子』の世界 |
『枕草子』で中関白家の栄華を活写した段と言えば、長徳元(995)年二月の淑景舎(藤原定子の妹)入内の様子を記した第100段、それに正暦五(994)年の積善寺一切供養を取り上げた第236段が最たるものと言えよう。そこには飾らない道隆の顔が余すところなく描かれている。
第100段では淑景舎を見たことのない清少納言が、屏風の影から淑景舎をそっと覗き見するくだりがある。登花殿には道隆と妻の貴子、中宮定子、伊周に隆家が揃っていたが、道隆は清少納言の姿を目敏く見つけ、昔からの懇意に大層みにくい娘たちを持っていると見られるのは困ると、したり顔で冗談を飛ばす。淑景舎の前に膳が運ばれてくると、早く食べて翁(道隆のこと)にもおさがりをくれと言う。道隆は「日一日、ただ猿楽言(おどけた冗談)」ばかり言っていたと、清少納言は語るのである。
第236段でもそれは変わらない。清少納言らに向かって、何が楽しくて中宮にお仕えしているのか、わたしなどは忠勤に励んでいるのに、いまだにお下がりの着物一枚もらったことがないと言い、それを聞いた女房たちは笑い転げる。道隆のいるところは、いつも笑いと華やぎに満ちていて、清少納言はその有様を手放しで賛美する。
だが、果たして道隆は中関白家の外へ目を向けていたのだろうか。正暦元(990)年6月、父兼家の病も重いときに定子が立后したことを、世間は冷たい目で見ていたようである。娘の女御に中宮の地位を与えることは、公卿たちの夢である。もし、娘が皇子を生めば、その子が立太子する確率はかなり高くなる。道隆はもちろんだが、妻の貴子の父高階家の男たちも気が急いている。ここぞとばかりに立后を押し進めた。実は、この后の称号にも問題があった。太皇太后、皇太后、皇后と、すでに3人の后がいるところへ定子を押し込まねばならない。道隆は、皇后と同義で本来同一人物を指す中宮の名称を切り離し、先帝円融上皇の后遵子を皇后に、定子を中宮に据えてしまったのである。
さらに道隆は、中宮大夫の地位を道長に任せた。道長にしてみれば、兄の娘が華々しく入内し帝の寵を得ることがおもしろいはずがない。道長自身の娘はまだほんの幼女で、定子に対抗することはできない。もし定子が皇子を生んでしまったら、政権は完全に兄のものになってしまう。そうした焦慮を感じていた道長の心情を汲まず、自分や定子に奉仕を強いるというのは、政治家としてもまずい処置である。
清少納言にとって中関白一家はあるじであり、それは非難するべき対象ではなかった。だから、道隆の行為にも批評は加えられていない。とは言え、清少納言は中関白一家を取り巻く暗雲に気付いていないわけでは決してない。道長を跪かせて歩く道隆の姿をとらえ、俯いた道長の心の奥を、清少納言は見透かしている。道隆が死んだとき、清少納言には中関白家の行く先をある程度は予想していたに違いない。『枕草子』は道隆の死後の定子たちの惨めな有様を書いていないと言われるが、清少納言は書けなかったのだろう。だが、行間には現実を直視できない、したくないという気持ちが表れている。おそらく清少納言は、心の中で道隆を咎めていることがあったのではないだろうか。道隆に今すこし人情の機微を解する気持ちがあったなら、そしてもう少し長く生きてくれていたら、中関白家は落魄しないですんだのに、と。 |