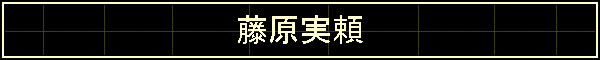関白藤原忠平の長男。母は宇多天皇皇女源傾子(順子とも)。父の死後、弟の師輔と共に左右大臣の首座を占め、公卿の最上席に立った。
人柄は真面目であったが融通性に欠け、平将門の乱の征東将軍藤原忠文の論功行賞に関して杓子定規な決定を下し、忠文の怨みを買ったりするようなこともあった。このため、ともすれば人望は度量の大きい弟師輔に集まりがちで、政治の実権はやがて弟の師輔の手に移ってしまった。
一方で有職故実に詳しく、朝儀典礼に熟達していた。忠平から伝授され、実頼の号に因んで小野宮流と呼ばれる儀礼を作り上げ、師輔の九条流と並び称された。日記に「清慎公記」がある。
ここに着目!
 | 弟師輔への劣等感 |
実頼には師輔、師尹などの弟がいるが、すべて異母弟であった。子どもは母方で育つという当時の生活習慣から言って、異母兄弟はあまり親しみを覚える存在ではないかもしれない。ただ、同母でも性格の違いはあり、また官位争いが始まると仲が険悪になるのは当然のことで、一概に親疎を計ることはできない。
実頼の場合、8歳下の弟師輔とは犬猿の仲であった。これはどうやら、性格の違いが大きいようである。『栄花物語』には、「同じ御兄弟なれど、さまざま心々にぞおはしける」として、実頼は和歌が上手で風流人だったが、本心を見せない、気難しい性質だったと述べている。それに対し、師輔はおっとりとしていて、親しい者もそうでない者も分け隔てせず、たいそう気楽に付き合ってくれたので、父忠平に仕えていた人の多くは師輔に集まったと書いている。今風に言えば、とっつきにくい実頼と、とっつきやすい師輔、という正反対の性格ということだろうか。
このような性格の二人がいた場合、人はとっつきやすい方に流れていく。実頼が特別人望がないのではないわけである。しかし、支持者を取られてしまった方は愉快ではない。実頼は兄であるから、よけいに追い立てられるような気になっていただろう。実際、官位は最初年令と同じく8年ほどの開きを見せてどちらも昇進していくが、年が経つと二人の間は縮まっていき、最後には左大臣、右大臣を兄弟で占めることになった。師輔は53歳で亡くなったので、実頼が抜かれることはなかったが、もし長生きしていたら弟の後塵を拝することになったかもしれない。
更に、後宮政策の失敗も実頼の心を暗くしていた。実頼女の述子・師輔女の安子が村上天皇の元へ入内したが、述子は早世し、安子は皇子女を数人もうけて母后となった。もはや政では師輔には勝てないと、実頼は口惜しい思いを抱いていたことだろう。
実頼が師輔より優れていたのは、和歌だった。「大鏡」にも、「和歌の道にもすぐれおはしまして」とある。師輔の生前に編まれた「後撰和歌集」は権門の歌が多く、師輔の歌は実頼の10首より多い13首である。だが、50年ほど後に成立した「拾遺和歌集」では、実頼が9首入集しているのに対して、師輔は2首と、逆転している。
また、実頼には家集「清慎公集」があり、多くの歌人たちと交流したことがわかる。紀貫之、清原元輔(清少納言の父)、平兼盛(赤染衛門の父)、大中臣能宣(伊勢大輔の祖父)など錚々たる歌人たちが、実頼の周囲に集まった。実頼は、そうした人々のパトロン的存在だったかもしれない。歌人たちにとっては、師輔より実頼の方が、敬愛すべき人だったのである。
実頼の死後、藤原為頼(紫式部の伯父)が詠んだ「世の中にあらましかばとおもふ人なきがおほくもなりにけるかな」という歌は実頼のことを偲んだものである。この歌を知ったなら、実頼は師輔への劣等感を感じないですんだかもしれない。 |