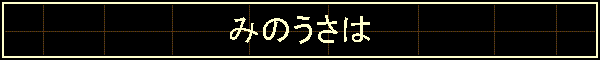はじめて内わたりを見るにも、もののあはれなれば
57 身の憂さは 心のうちに したひきて いまここのへぞ 思ひ乱るる
まだ、いとうひうひしきさまにて、古里にかへりて後、ほのかに語らひける人に
58 閉ぢたりし 岩間の氷 うち解けば を絶えの水も 影見えじやは
返し
59 深山辺の 花吹きまがふ 谷風に 結びし水も 解けざらめやは
正月十日の程に、「春の歌奉れ」とありければ、
まだ出でたちもせぬかくれがにて
60 み吉野は 春のけしきに かすめども 結ぼほれたる 雪の下草
【通釈】
初めて内裏となっている一条院御所での生活をするにつけても、
物思いに耽ることがあって
我が身の憂さは心の中に追いかけてくるように忍び寄ってきて、
いま九重と呼ばれる宮中で、幾重にも思い乱れることだ。
まだ、本当に新参者という様子で、自分の家に帰ってから後、
ほんの少し語り合った人に
凍り付いてしまった岩間の氷が溶けたならば、流れが途絶えていた水も
姿を現さないと言うことがありましょうか。春になってわたしの憂愁が消えたら、
ふたたび宮中に再び参りましょう。
返事
深山辺の花が散り乱れるほどに吹く谷の暖かな風に、氷っていた水もどうして
溶けないことがありましょうか。中宮の慈愛はわたしたち皆を包んでいますから、
あなたの凍りついた心も溶けましょう。また姿を見せてくださいな。
正月十日ごろ、「春の歌を献上せよ」との命があったので、
まだ出仕もしないまま、自分の家から、
み吉野は春がきたという雰囲気に霞んでいるけれど、雪に隠れた下草は
まだ凍り付いたままです。世の中は春が来たと寿いでいるのに、
わたしは出仕もせず、家に閉じこもっています。
【語釈】
●内裏わたり……式部が初宮仕えした寛弘初めごろは、一条院御所が内裏であった。一条大路南、大宮大路東の二町を占め、堀川大路に至る場所。一条天皇は長保元(999)年6月14日に内裏炎上でここへ渡御、長保2(1000)年10月11日、新造の内裏へ還御した。長保3(1001)年、11月18日、再び炎上して、一条院へ渡御。長保5(1003)年10月8日、還御するも、寛弘2(1004)年11月15日、炎上。寛弘3(1006)年3月4日、一条院を里内裏として遷御した。
●見るにも……内裏をただ見るだけでなく、女房として内裏での生活を体験して。
●物のあはれなれば……何かにつけて、しみじみとした感慨が湧いてきて。
●身の憂さ……身の上の悲しさ。
●慕ひ来て……後から追いかけてきて。
●九重ぞ……「幾重にも」に「宮中」を懸ける。
●うひうひしきさま……物慣れず、落ち着かない有様で。
●ほのかに語らひける人……宮中でほんの少し話した人。古来、この人は男性で、恋愛したという意味が含まれているとされてきたが、ここは同僚の女房らしい。
●閉じたりし岩間の氷……「冷たく、うちとけにくい宮中の雰囲気」「歌を贈った相手の心」「式部自身」との3説がある。
・宮中の雰囲気 『全評』『人物』 ・歌を贈った相手の心 『集成』『新書』『評釈』
・式部の憂愁 『論考』 ・式部の宮中に対する違和感 『叢書』『国文』
●うち解けば……「閉じたりし岩間の氷」が解けたなら。
●を絶えの水……緒絶え(流れの途絶えている川水−宮中)・小絶え(しばらく流れが途絶えている水−式部自身)の2説あり。
・緒絶え 『全評』 ・小絶え 『論考』
●影見えじやは……姿が、見えないことがありましょうか。わたしも再び参内いたします。
●深山辺の花……深山辺に宮前を懸けて、中宮の御前に侍る女房を花に見立てた。
●谷風……花も区別が付かぬほど、吹き匂うような暖風(中宮の慈愛の風)。
●結びし水……贈歌の「閉ぢたりし岩間の氷」と同義であろうが、宮中の雰囲気を指すという説と、心を閉ざして里居する式部を指すとする説、歌を贈られた同僚を指す説がある。
・宮中の雰囲気 『全評』『叢書』 ・式部(の憂愁) 『大系』『論考』 ・歌を贈られた相手 『集成』『評釈』
●かくれが……ひっそりと暮らしていた物陰に等しい場所。または宮仕え前に住んでいた自邸とは別の、目立たない家か。
「み吉野の山のあなたに宿もがな世の憂き時の隠れ処にせむ(『古今集』雑下)」を踏まえている。
●み吉野は……御代を懸ける。
●春の気色に霞め……春が来たという喜びにわき返っているようすを表す。
●結ぼほれたる……水などが凝固する。心が塞ぐ意を懸ける。
●雪の下草……雪の下に埋もれた草のように、人目につかず、宮中にも出仕できない式部自身。
●正月十日のほど、「春の歌たてまつれ」……式部が宮仕えしたのは寛弘2年または3年の12月29日と考えられているが、その直後の正月前後にあった立春は、寛弘2年12月29日、寛弘4年1月10日である。立春の日に出仕したなら、一言それについて言及してもよさそうなものだが、特にそうした記述もないこと、また歌を所望されたのが「正月十日」であることから、これは出仕直後の里居の折、つまり寛弘4年の歌で、出仕は寛弘3年とするのが妥当か。
【考論】
<岩間の”氷”>
当時の人々は和歌に自分の心を託して相手に気持ちを伝えていた。それも、あからさまに物事を表現しないで、物や風景に自分の心を投影する。『紫式部集』でも託意や寓意の歌が多い。もちろん当事者同士ではその意味がわかるようになっているが、第三者である我々は、語句ひとつひとつを丹念に検討しないと、何のことやらわからない。微妙な解釈のずれを生じることもある。
ここの58・59番歌もそうで、字面どおりに読んでも、何のおもしろみもない。ただの自然現象を歌っているようにしか見えない歌である。諸注釈書とも、そこに寓意を読み取って訳を付しているのはいいのだが、上記のように語句の寓意のとらえ方は各人各様である。
まず「閉じたりし岩間の氷」。宮中の雰囲気を指すとなると、式部が里へ退出した原因を宮仕え先の中宮やその女房たちの冷たさにあると責任を追及しているようで、いただけない。歌を贈る相手が親しいならいいが、ここでは「ほのかに語らひける」人で、それほど親しいわけでもない。とすると、あなたが打ち解けてくださるなら、というのも、せっかく新参者の式部に声をかけてくれた同僚に対し、もっと優しくしてと要求しているようで、どうも厚かましい。式部の憂いの心境を指すとするのが、最もおだやかだろうと思われる。
次に「を絶えの水」。氷が解けて、水になるのだから、「閉じたりし岩間の氷」が式部の心とするなら、流れが途絶えているが、解けるであろう水は式部自身とみるほかない。
そして「結びし水」。『評釈』『集成』は式部が暖かい心でいるなら、わたしも打ち解けないはずはない、と訳している。これでは同僚のほうが心を凍りつかせてしまっていることになる。とすると、「閉じたりし岩間の氷」も同僚の心を指し、式部がこの同僚と喧嘩をしているような状況になる。むろん仲直りの歌というのもあり得るが、ここではそのような解釈はできない。それは「深山辺の花吹きまがふ谷風」が氷を溶かすからで、これは中宮の慈愛を指すと思われる。この贈答歌は式部と同僚が互いの心の凍り具合や解け具合を見定めているのではなく、中宮の意を受けた同僚が、凍りついた式部の心を溶かすことに目的がある。「結びし水」も式部のことを指すとみるべきであろう。
しかし、式部はよくせき氷が好きらしい。宣孝や親友との贈答歌にも、「薄氷」や「霜氷」を使っている。寓意と言っても、個人で勝手に意味を付けるのではなく、『古今集』以降の伝統に則った語句が使われるのが普通だが、氷などという負の感情に通ずる事物を好んだというところに、式部の心のあり方が垣間見えるような気がする。