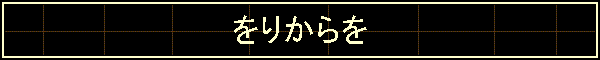(欠歌)さしあわせて、物思はしげなりと聞く人を、人につたへてとぶらひける
本に、破(や)れてうたなしと
八重山吹を折りて、あるところにたてまつれたるに、
一重の花の散りのこれるを、おこせ給へりけるに
52 折からを ひとへにめづる 花の色は うすきを見つつ うすきとも見ず
世中(よのなか)のさわがしきころ、朝顔を、おなじ所にたてまつるとて
53 消えぬ間の 身をも知る知る 朝顔の 露とあらそふ 世を嘆くかな
【通釈】
自分と同じように、(喪に服して)物思いにふけっていると聞く人を、人を介して文を出した
(もとから、破損して歌がないということだ)
八重山吹を折って、ある所に人を使って献上させたところ、
一重の花の散り残っていたのを贈ってくださった
時節に応じてひたすら愛でる一重の山吹の花の色は、薄黄色と見えても、
あなたの心を薄いとは思いません。
世間が疫病の流行などで騒然としていたころ、朝顔を、おなじ所に献上するというので
朝露が消えぬ間というのは短いものだが、朝顔がその朝露と争うようにして萎れていく、
そんな風に人も亡くなってしまう世の中を嘆くことだ
【語釈】
●本に、破れてうたなしと……もとの本に、「破れて歌なし」とあったという書写者の注。
●八重山吹……庭園などで栽培される八重の山吹。
●ある所にたてまつれたる……人をして献上させたところ。「たてまつれ」は与ふの対象敬語。相手が高貴な人だが、親しい関係にある場合に用いる。相手については諸説ある。
・具平親王 『大系』『国文』『叢書』 ・彰子の女房 『論考』 ・道長室倫子 『全評』
●一重の花……山野に自生する早咲きの一重の山吹。
●おこせ給へりけるに……送ってきてくださったのに(対して詠んだ歌)。古本系橘常樹本は「をこせたまへるに」。陽明本では「おこせ給へり(送ってきてくださった)」となっているが、このため、52番歌を式部の歌ではなく、八重山吹を贈った相手の歌と解する説もある。
・本文は「〜に」で式部の歌 『全評』『大系』『集成』 ・本文は「おこせ給へり」で相手の歌 『論考』『国文』
・本文は「〜に」で相手の歌 『叢書』
●をりから……(何かをするのに)合っている、ふさわしい時期・場合。
●ひとへにめづる……一途に・ひたすら・もっぱら愛でる。
●うすきを見つつ……散り残りの一重の山吹だから「薄黄」で、志の「薄き」を懸ける。
●世中のさわがしきころ……世の中が常ならぬころ、具体的には疫病が流行って世情不安定だったころ。
●おなじ所にたてまつる……前の52番歌と同じところに贈った歌。
●消えぬ間……露が消えるまでの、短い間。はかない命のたとえ。「消え」は「露」の縁語。
●知る知る……十分に知りながら。
●朝顔の露とあらそふ世……朝顔の花に置いた露の命と争うように、消えていく人の世。
【参考】
『玉葉集』雑四、2378
「世の中、常ならず侍りける比、朝顔の花を、人のもとにつかはすとて
消えぬまの 身をも知る知る 朝顔の 露と争ふ 世を嘆くかな」
【考論】
<山吹の花を贈ること>
52番歌を見て気になるのは、山吹の花を贈った相手、そして贈る真意は何かということだろう。
諸説の解釈は以下の通りである。
・式部(八重山吹+?(記述なし))→貴人 貴人(一重山吹+夫を亡くした式部を慰める和歌)→式部 式部(52番歌) 『評釈』
・式部(八重山吹+出仕要請を断る和歌↓)→貴人 貴人(一重山吹+52番歌)→式部 『論考』
「わが宿の八重山吹は一重だに散り残らなむ春のかたみに(『拾遺集』)」
・式部(八重山吹)→倫子 倫子(一重山吹)→式部 式部(52番歌) 『全評』
・式部(八重山吹+?(記述なし))→具平親王 親王(一重山吹+式部を励ます和歌)→式部 式部(52番歌) 『大系』
まずは式部がほかの花ではなく、八重山吹を贈ったことの意味から考えたい。
山吹の花を贈る際、和歌を付けたかどうかということでも諸説があるが、『全評』以外は山吹に和歌を付けたとしている。なぜ『全評』が歌なしに花だけを贈ったとするのかは、『源氏物語』の山吹の和歌に理由がある。
『源氏物語』において、衣の色や女性の容姿のたとえ(主に玉鬘)ではなく、純粋に花としての山吹が登場するのは10回ほどである。それも六条院などの庭の情景描写としてほかの花と列挙されることが多く、山吹でなければならない、ある意味を持つ箇所は「真木柱」の1例のみである。髭黒大将の妻となってしまった玉鬘に対し、誰にも言えない想いを源氏が吐露する場面で、
「『色に衣を』などのたまひて、
思はずに 井手のなか道 へだつとも いはでぞ恋ふる 山吹の花」
とある。「色に衣を」は「思ふとも 恋ふとも言はじ くちなしの 色に衣を 染めてこそ着め(古今六帖)」で、山吹が染料の梔子の色と共通するところから、口に出しては言わないが、決して忘れているわけではない、あなたのことを思っている。そのような意味を有する和歌が詠まれるようになった。
式部も、詞書から察するに、歌なしで山吹だけを贈ったらしい。相手は、当然あるはずの歌がないことで、古今六帖の歌などを思い出しただろう。『論考』は勅撰集には山吹の和歌は多数あり、歌を付けずに贈ったのでは何の意味かわからず判じ物だと書いているが、歌を付けないということからして、山吹の持つ意味は推察できるのではないだろうか。また、式部は相手の貴人がそれに思い至るだけの教養の持ち主であることを承知していたからこそ、花だけを贈ったのだろう。
とすると、式部がその教養に太鼓判を押せる人物だろう。
では、『全評』の言う倫子はどうか。式部が夫を亡くした悲しみを訴えたのに対し、貴人は「ひとえに(一重に)」強く生きよと励ましてきたのだとする。が、式部が倫子とそれほど親しい仲だったのかどうか。また、宮仕え後に倫子から歌を贈られているときには「あるところ」などという言い方はしていない。
中宮彰子、または側近女房(『論考』)であったということにも疑問を感じる。出仕の要請に対して断ったのが拾遺集の和歌で、52番歌は重ねて出仕を要請してきた歌だと解釈するのは難しいのではないか。
「あるところ」と相手の名を明記しない、高貴な人であるにもかかわらずかなり親しい、というところから、『大系』や『国文』の言うように、具平親王が最もふさわしい。
『国文』は、式部が具平親王に対して何らかの釈明をする必要があったとする。皇族たる具平親王は、道長を始めとする藤原氏の権勢を必ずしも好意的に見ていない。そこへ、古くから家司のような仕事を任せてきた為時が、官職ほしさに道長に尻尾を振っているとすれば、親王もおもしろかろうはずはない。式部が未婚時代に宮仕えしたという記録、証拠はないが、あるいは具平親王家に仕えていたかもしれないと考える説もあるほどだ。娘の式部までが自分を裏切って中宮彰子のもとに出仕すると聞けば、心穏やかではない。式部はそれを憂慮して、親王に半ば釈明を兼ねて、「わたしは言葉にせずとも、親王家に忠節を誓いますよ」という態度を見せなければならなかったのではないか。
そんな式部に、親王は一重の山吹を送ってきた。親王は、式部の中宮への出仕を快くは思っていないが、さりとて禁止したり阻止したりできるわけもない。「わかっていますよ、あなたの心は。出仕しなさい」と答えるより仕方がないのではないか。それはつまり、52番歌そのものなのではないか。「時節に応じて愛でる一重の山吹は、薄黄色だが薄いとは思わない」はつまり、「時勢を考えればあなたは出仕せざるを得まいが、だからといってあなたの忠誠心を薄いと思っているわけではないからね」と答えたものではないか。
このようなやりとりがあってこそ、『紫式部日記』に具平親王のことを「思ひゐたること多かり」と言えるのではないか。式部が具平親王との間に何かあったらしいのは、(宮仕えの経験があるか、あるいは恋愛関係か)この52番歌からも推察できるのである。