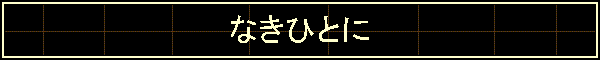絵に、物のけつきたる女のみにくき図(かた)かきたるうしろに、
鬼になりたるもとの妻(め)を、小法師のしばりたる図書きて、
をとこは経読みて、物のけ迫(せ)めたるところを見て
44 亡き人に 託言(かごと)はかけて わづらふも おのが心の 鬼にやはあらぬ
返し
45 ことわりや 君が心の 闇なれば 鬼の影とは しるく見ゆらむ
絵に、梅の花見るとて、女、妻戸おし開けて、二三人ゐたるに、
みな人々寝たる気色書いたるに、いとさだ過ぎたるおもとの、
つらつゑついて、眺めたる図(かた)あるところ
46 春の夜の 闇のまどひに 色ならぬ 心に花の 香をぞしめつる
同じ絵に、嵯峨野に花見る女車あり。
なれたる童の萩の花に立ち寄りて、折りたるところ
47 さを鹿の しかならはせる 萩なれや 立ち寄るからに おのれ折れ伏す
【通釈】
絵に、物の怪が憑いた女の醜い図を描いてある後ろに、鬼になった先妻を
小法師が縛った図を描いて、夫は経を読み、その物の怪を退散させようと責めているところを見て
亡き先妻に言いがかりをつけて病に伏せるのも、自分の心の中に巣くう、
疑心暗鬼という鬼のせいではないのか。
返し
その通りですねえ。この女の心が闇に閉ざされているから、鬼の姿がはっきり見えるのでしょう。
絵に、梅の花を見るというので、女が妻戸を押し開けて、そこに二、三人
座っていたところ、誰もみな眠ってしまった風景を描いてあるが、たいそう盛りを
過ぎた女の人が、頬杖を付いて眺めているという図のあるところ
夫を失い、春の夜の闇のような見えない迷いの中にいるわたしは、久しく色めいた
気分になったこともない、そんな心に、梅の花の香を染めたことだ。
同じ絵に、嵯峨野に花を見る女車がある。(このような行為に)物慣れた童が、
萩の花に立ち寄って、枝を折ったところを
鹿がそうするように慣れさせた萩だからだろうか、立ち寄るそばから、自分から倒れ伏していくことだ。
【語釈】
●小法師……若く僧侶としての地位も低い法師。
●責めたる……物の怪・怨霊が退散するように、祈祷し責め立てる。
●託言はかけて……託言は言いがかり。ぐち。もとの妻の仕業であろうと言いがかりを付けて。
●心の鬼……気のとがめ。疑心暗鬼。『源氏物語』では、良心の呵責という意味で用いられることが多いが、広く煩悩の意を有する。
●返し……45番歌の作者は、諸説ある。
・侍女または乳母 『大系』『全評』『集成』 ・女友だち 『論考』『評釈』 ・宣孝 『新書』
宣孝に面と向かってこの歌を詠んだとすれば、かなり嫌味と取れる。侍女や乳母にしても、主たる式部に向かって、あなたの心が闇だから、とは言えまい。もし、侍女が式部のことではなく、絵の中の男の心を忖度して言ったとしたなら可能性はあるが、『大系』『全評』『集成』ともに「君が心」は式部の心としている。式部のいわんとする「疑心暗鬼」を理解する女友だちが妥当か。
●ことはりや……なるほど、おっしゃる通りですねえ。もっともですねえ。
●心の闇……心が迷って、分別を失うこと。暗い心に閉ざされていること。
●君が心……君が心とは誰の心を指すか。
・絵の中の「男」『評釈』・『論考』 ・式部 『大系』・『全評』・『基礎』・『新書』・『集成』
「君が心」を式部とする説は、その具体的な闇の原因を「煩悩(『全評』)」「あれこれ迷って(『集成』)」とする。だがそのことが直接、絵の中の鬼の影が見えるということになるだろうか。絵の中の男の心が「良心の呵責(『評釈』)」という闇に包まれているから、鬼の姿を見てしまう、とすべきだろう。
●さだ過ぎたるおもと……さだ(盛りの年)を過ぎている、年配の。
●春の夜の闇のまどひ……前方の見えない、闇のような心の迷い。
●色ならぬ……風流気を失って、索漠とした。女の盛りを過ぎて、色気を持たなくなった?
●花の香をぞ染めつる……はなやかな気分を感じさせてくれた。梅の香を深く味わったことだ。
●なれたる童……「なれたる」の解釈が諸説ある。ここは「物慣れた」とすべきか。
・糊気が抜けた、しなやかな衣服を着た 『全評』 ・女車に乗る女主人に慣れ親しんだ 『論考』
・ものなれて気の利いた 『集成』『評釈』『大系』
●しかならはせる……雄鹿がそのように習慣づけた。鹿が萩を妻として、慕い寄ってくるという伝承があったらしい。
●立ち寄るからに……立ち寄ると同時に。
●おのれ……自分から。ひとりでに。
【参考】
『玉葉集』巻四、秋上、495
「屏風の絵に、花見る女車あり。わらはの立ちよりて、萩の花折る所
さを鹿の しかならはせる 萩なれや 立寄るからに おのれ折れ伏す」
【考論】
<物語絵の鑑賞法>
『論考』の言うように、上の歌は式部が物語絵を見ながら詠んだものだろう。女性にとって、物語を読むのは最大の楽しみだったろうが、物語に絵が付いていればさらに理解が深まり、娯楽性が高まる。式部も、侍女や女友だちと一緒になって徒然の慰めとしていた。ただ、式部がほかの女性たちのように、単なるその場限りの楽しみで終わらせなかったことである。
物語はむろん長短いろいろあるだろうが、44番歌の絵なども長編の中の一場面で、実際は男の先妻が生きていたころも語られていたのかもしれない。だから、式部は男の心の闇が見える。生前、先妻に対して酷い仕打ちをしたことが、男の心に影を作ってしまったのだ。それが闇であり、鬼の姿を見せている。式部は絵を見ながらそんな風に分析する。そして、その分析をみずから物語を書いて証明してみせたのだ。『源氏物語』「葵」の巻で葵の上が生霊に殺される場面は、まさにそれである。光源氏は、六条御息所が葵の上に乗り移ったと見た。だが、それも「心の闇」なのですよ、と式部は言いたかったのに違いない。自身も御息所の苦悩を知りながら、それを和らげることをしてこなかった、しかも世間は葵の上に憑いている物の怪は御息所だと噂している。御息所の髪に芥子の匂いが染み込んで取れない、というくだりは生々しい描写であるが、源氏もまた、疑心暗鬼という心の闇を抱えて、御息所の姿を見てしまったのである。仮に、44番歌の絵が短編であったとしても、式部はそこから想像をめぐらせて、話の前後を作り上げてしまっただろう。いろいろな絵を見ては、そこに必ず式部なりの解釈の入った物語を創り出す。一場面では短い物語が、結合すると長編にもなりうる、と気付けば、ま
ったく関係のなかった絵と絵が物語によって有機的に繋がっていく。その繰り返しが、『源氏物語』のような長編、しかも1巻ずつ取り出しても短編として成り立つような構造の物語を生んだのだと言えよう。44〜47番歌のように、式部が物語絵を鑑賞していること自体が、実は物語創作の原動力だったのである。