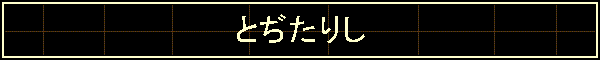文散らしけりと聞きて、「ありし文ども、取り集めておこせずは、
返りごと書かじ」と、ことばにてのみ言ひやりければ、「みな、おこす」とて、
いみじく怨じたりければ、正月十日ばかりのことなりけり
32 閉ぢたりし 上の薄氷(うすらひ) 解けながら さは絶えねとや 山の下水
すかされて、いと暗うなりたるに、おこせたる
33 こち風に 解くるばかりを 底見ゆる 石間の水は 絶えば絶えなむ
「今は、ものも聞えじ」と、腹だちたれば、笑ひて、返し
34 言ひ絶えば さこそは絶えめ なにかその みはらの池を つつみしもせむ
夜中ばかりに、又
35 たけからぬ 人かずなみは わきかへり み原の池に 立てどかひなし
【通釈】
夫がわたしの手紙をよその女に見せたと聞いて、「今までに出した手紙を
集めて寄越さなかったら、返事はもう書きません」と口だけで伝えたので、
「全部返そう」というので、たいそう怨み言を言ってきた。正月十日ほどのことであった。
凍り付いた上の薄氷が解けてきて山の下水が流れ出すように、わたしはとうにあなたのことを
許しているというのに、それではあなたは、こういう二人の仲を絶ってしまえというのですか。
のせられて、すっかり暗くなっているのに、手紙を寄越した。
東風が吹いて解けてきたという岩間の水も、底が見えているというものだ。
わたしたちの仲も、絶えてしまうならそれでいいさ。
「今は、話もしたくない」とご立腹なので、笑って、返事を書く
それなら、おっしゃるように仲を絶つといたしましょう。みはらの池の堤では
ありませんが、あなたが腹を立てていることに何で遠慮することがありましょうか。
夜中ごろに、また
わたしのように猛々しくなく、人並みでないものは、みはらの池に立っても
(腹を立てても)、かいのないことと思い知りました。
【語釈】
●文散らしけり……わたしの手紙をほかの女に見せまわっていた。
●ありし文ども……わたしがこれまでに送った手紙。
●ことばにてのみ……手紙ではなく、使者の口上だけで。
●正月十日ばかり……立春前後を表すとすれば、長保元(999)年か(下記【考論】参照)。
●薄氷解けながら……私の心は打ち解けていますのに。「ながら」は逆接助詞。通説では、式部と宣孝が結婚したことを暗示しているというが、その後、宣孝が手紙を見せびらかしたことが原因で喧嘩をしたにもかかわらず、式部が機嫌を直したことを示している、という指摘もある。また、一部結婚前とする説もある(下記【考論】参照)。
・結婚したこと 『基礎』『国文』『集成』『叢書』『新書』 ・結婚後、喧嘩したが怒りが解けたこと 『論考』
・結婚前、喧嘩をしたが怒りが解けたこと 『大系』『経緯』
●山の下水……「山麓の谷川であるが、しばしば愛しあう者同士の秘かな交流を暗示する語(『国文』)」
●すかされて……わたしの歌になだめられ、おだてられて。
●こち風に解くる……「孟春之月、東風解氷(『礼記』月令)」という一節があり、正月には東方から吹いてくる暖かい春風が氷を溶かすと考えられた。立春を表す。
●底見ゆる……水底が見えて、今にも涸れようとしている。それと同じように、離れていこうとする。
●石間の水……石と石の間の水。浅い心のお前との仲。式部を指す。
●絶えば絶えなん……仲が切れるなら、そうするといい。
●今は、ものも聞こえじ……もう、物も言わないでおこう。
●つつみしもせむ……遠慮などしません。
●人かずなみ……人数無み。人数でもない、取るに足らないわたし。「波」を懸ける。
【参考】
『夫木抄』雑五、760
「いひ絶えば さこそは絶えめ なにかその みはらの池の つつみかもせん」
【考論】
<二人の仲は?>
当家集に散見する恋愛歌の中でも、この贈答は特に小気味よい、掛け合いといった雰囲気を醸していて、第三者が見ても「笑ひ」たくなるような応酬であるが、このときすでに二人は正式に結婚した後か、それとも前か、疑問を感じるところである。
諸説は分かれていて、上記のように薄氷が解けたという語句から、これは結婚後の歌だとする説が多い。
二人の結婚の時期については、学説により多少の幅はあるものの、長徳4(998)年晩秋~長保元(999)年初春の間とする説がほとんどである。だから、上の贈答は長保元(999)年正月すぎの歌で、二人はまだ新婚の時期だというのである。
ところが、『経緯』によれば、「薄氷解け」という言葉を結婚ではなく文通のみの段階に使っている和歌が『古今集』中にあるとし、必ずしも二人が結婚したことにはならないという。そして、結婚前とすると、立春の日が正月十日前後に当たる年を探せばよく、それは正月9日に立春のあった長徳2(996)年のことであろうとする。
ちなみに、二人の結婚前後の年の立春は以下のようになっている。
長徳元(995)年 12月28日(以下前年の12月)
長徳2(996)年 1月9日
長徳3(997)年 12月20日
長徳4(998)年 1月1日
長保元(999)年 1月12日
長保2(1000)年 12月22日
こうしてみると、旧年中に立春となる長徳元・3年、長保2年だと正月十日にはすでに20日近く経っていることになり、「東風に解くる」は間が抜けている感がある。では長徳4年はどうか。10日前に立春を迎えたところで、この贈答がなされたとすると、許容できるのではないか。また、詞書の「正月十日ばかり」が1月12日のことだったとすれば、長保元年も当てはまりそうである。『経緯』の言う長徳2年と併せて、結婚前(長徳2・4年)か結婚後(長保元年)かは歌そのものから読み取るよりほかにない。
<氷が閉じ、解けるということ>
そこで、正しく解釈されるべきは、32番歌の「薄氷解け」と「山の下水」となる。『古今集』の用例はともかく、紫式部の作品にその類例をみると、
「氷」の用例:
①よそにても、思ひだにおこせたまはば、袖の氷もとけなんかし(『源氏物語』真木柱)
②閉ぢたりし 岩間の氷 うち解けば を絶えの水も 影見えじやは(58番歌)
③氷閉ぢ 石間の水は 行きなやみ そらすむ月の かげぞながるる(『源氏物語』朝顔)
④霜氷 うたて結べる 明けぐれの 空かきくらし 降るなみだかな(『源氏物語』乙女)
⑤解けわたる池の薄氷(うすごほり)、岸の柳のけしきばかりは時を忘れぬなど、(『源氏物語』賢木)
⑥うす氷 解けぬる池の 鏡には 世にたぐひなき かげぞならべる(『源氏物語』初音)
①は、髭黒大将の北の方が、玉鬘に夢中の髭黒が心ここにあらずの状態で自分のそばにいるより、ほかの女のところにいても自分を思い出してくれるほうが袖の氷も「とける」と言ったもの。
②は初出仕からいくらも経たないうちに自邸に戻ってしまった式部に対し、同僚女房が再出仕を促した際、式部が返事したもの。宮中の冷たい雰囲気が「とける」なら、出仕しましょうと答えている。
③は光源氏が朝顔の姫君を妻にするという噂で紫の上を悩ませたころ、自分と関わりのあった女性たちのことを紫の上に話し、そこで紫の上が詠む歌。自分のことを石間の水にたとえ、流れぬ水に生き悩む我が身を懸けている。
④は雲居雁と引き離され、傷心の夕霧が冬の夜明けの道を自邸に戻る折の歌。
いずれも、詠者・登場人物の鬱屈や行き場のない感情を「氷」という語句にに象徴させている。
一方、⑤⑥は池の「うすごほり」が(『源氏物語』では、「薄氷(うすらひ)」はなく、この2例のみ)解けるさまを描写している。どちらも新春、⑤は藤壺の住む三条宮、⑥は六条院の池である。①~④にあったような、暗い感情はなく、源氏が春の到来を感じている場面である。
つまり、「薄氷とけ」は春の訪れを喜ぶ気持ちが表れており、そこに「閉ぢたりし」が付くので、①~④ほどの深刻さはないが、宣孝との間に不愉快なことがあったことをにおわせている。それが、宣孝が手紙を公表した一件であり、式部はもちろん当座は怒っていたものの、時間が経つと怒りは鎮まってしまい、折しも年も明け、そろそろ仲直りしなきゃね、といった気分だったのだろう。「もう春になったことだし、長期戦なんてやめにしましょうよ」というところか。
そもそも式部が手紙を返せと言ったのは、本気ではなく、宣孝の謝り方を見たかったのだろう。「上」の薄氷という言葉に、表面上、怒ってみせたというニュアンスが感じられる。山の「下」水、心の中ではとうに氷が解けているのに、と理解しなければならないと思う。
とすると、二人はこのとき、結婚していたのだろうか。それにしては、「山の下水」という言い方と言い、手紙や言伝のみで直に逢わずに応酬するところと言い、まだ結婚までいっていないような気配があるので、長徳4年、式部が長徳3(997)年晩秋ごろ帰京した翌春、と考えるのが妥当ではないだろうか。