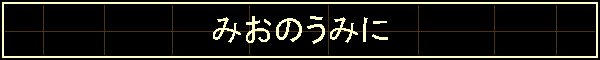近江の水海にて、三尾が崎といふ所に、網引くを見て
20 三尾の海に 網引く民の ひまもなく 立居につけて 都恋しも
又、磯の浜に、鶴の声々、鳴くを
21 磯がくれ おなじ心に 田鶴ぞ鳴く 汝が思ひいづる 人や誰ぞも
夕立しぬべしとて、空の曇りて、ひらめくに
22 かきくもり 夕立つ浪の 荒ければ 浮きたる舟ぞ 静心なき
【通釈】
琵琶湖の岸辺で、三尾が崎というところに、網を引く漁民の姿を見て
三尾が崎の水辺で手を休めるひまもなく網を引いている漁民たち。
その動作を見ていると、ここはもう都ではないのだと思い知り、都が恋しくてならないことです。
また、磯の浜辺に鶴が互いに声を合わせて鳴くのを見て
水際の岩蔭に隠れるようにして、わたしと同じように恋しい人を想って鳴いている鶴。
おまえが思い出している人はいったい誰なのかしら。
夕立が来るに違いない、というので、空が曇り、雷がひらめく様子を見て
突然に空が曇り、夕立のために浪が荒くなる。そのためにいま乗っているこの舟のように、
わたしの心も不安で揺れていることだ。
【語釈】
●三尾が崎……滋賀県高嶋郡安曇川町三尾里付近一帯。現在の舟木崎あたりから、明神崎までの広い地域を指すらしい。
●ひまもなく……定家自筆本系の群書類従本、古本系の也足叟素然本、同乙本、群書類従本・東大本、六女歌集本、大阪府立図書館本は「ひまもなく」で絶え間なく、休むことなく、終始の意味。「てまもなく」とある本が多い。手の休む間もなく、と取るべきだが、「手間」は作業をする時間のことなので、それがない、というのはおかしい。
・本文を訂正し、ひまもなく『全評』『論考』『叢書』 ・本文そのままで「手を休める暇もなく」 『新書』『集成』『大系』
●立居につけて……「立居」は「立ち居る」の名詞形。立ったり座ったりの動作だが、ここでは動作。漁民の手が休む間もなく動いている様子を見るにつけて。
●都恋しも……「も」は感動詠嘆の終助詞。都が恋しくてならないことだ。
●磯の浜……琵琶湖の東岸、滋賀県坂田郡米原町磯が該当すると言われているが、往路は琵琶湖西岸を北上していた式部たちの航路からすると不自然。復路とする説がある。
・往路 『評釈』『新書』『基礎』『世界』『叢書』『大系』 ・復路 『論考』『全評』『復元』『集成』
●鶴……「つる」だと散文、「たづ」だと歌語となる。
●声々……実践本、瑞光本以外の諸本は「声々に」。『源氏物語』では「声々」という名詞は16例あるが、副詞の「声々に」はない。ここも「鶴の声々が」と主格とみる。
●磯がくれ……磯(岩石の露出している水際)に隠れて。
「うらめしや おきつ玉もを かづくまで 磯がくれける 海人の心よ(『源氏物語』行幸)」
●おなじ心に……岩に隠れて異性を求めて鳴く鶴と、式部が恋しい人を想う心が同じだというのである。
●田鶴ぞ鳴く……用例は以下の通り。
たづが鳴き 雲居にひとり ねをぞ泣く つばさ並べし 友を恋ひつつ (『源氏物語』須磨)
ならぬみ島隠れに鳴く鶴を (『源氏物語』澪標)
夕潮満ち来て、入江の鶴も声惜しまぬほどのあはれなる折からなればにや、(『源氏物語』澪標)
●汝が思ひいづる……おまえが思い出している。古本系では「なに思ひいづる」とするが、「人」とつながらない。
・汝が 『論考』『大系』『全評』 ・なに 『集成』
●誰ぞも……強調の係助詞「ぞ」+詠嘆の助詞「も」で強い詠嘆を表す。
●夕立……急激に夕暮れのようにくもり、降り出す雨。
●かきくもり……空が真っ暗になって。自然現象のみならず、人事にも使用され、その人にとってよくない状況であることを表す。自然現象をみずからの現在の状況と重ね合わせることは、『源氏物語』では珍しくない。夕立に翻弄される舟の頼りなさが、都を出て遠い国へ行く式部の不安な心を表している。
●夕立つ……夕立が来る。陰暦6月の梅雨明けの夕立を指す。
●浮きたる舟……不安で、はかない心境・状態。
【参考】
『夫木抄』雑十五、網 1164
「みほのうみに あみひくたみの てまもなく 立ゐにつけて みやここひしも」
『新古今集』覉旅、918
「湖の舟にて、夕立のしぬべきよしを申けるを聞きて、よみ侍りける
かきくもり 夕立つ浪の 荒ければ 浮きたる舟ぞ 静心なき」
【考論】
<汝が思ひいづる人や誰ぞも>
21番歌で問題となるのは、「磯の浜」の語釈を見てもわかるとおり、往路と復路のどちらで詠まれたものか、ということだろう。どちらの説も、その根拠を挙げているので要約してみると、
①歌の配列 往路説……往路の歌の間にあり、20番歌の人恋しい気持ちを詠んだ歌と続いている。
復路説……21番歌は錯簡であり、本来復路の歌群(81~83番)の中に配置されるべきもの
②鶴の生態 往路説……『万葉集』等に夏の鶴を詠み込んだ歌があるため、夏でも鶴は見られたはずである。
復路説……鶴は晩秋に飛来、春に北の国へ帰る。夏の往路で式部たちは鶴の声を聞けない。
③航路 往路説……式部たちは琵琶湖を東岸沿いに北上したので、東岸の磯に立ち寄るのは不自然。
固有名詞でなく普通名詞、磯の浜辺と同義語とし、西岸のある浜辺と考える。
復路説……磯は岩石の多い水際、浜は砂や小石の多い平地の水際で、普通名詞ととれない。
④詞書の続き方 往路説……「又、磯の浜に」という書き方は、20番歌と続いていることを思わせる。
⑤歌の雰囲気 往路説……離京のもの悲しい気持ちを詠み込んだものである。
復路説……帰京できる喜びではずむ心を表した歌である。
①の復路説は②以下の説をもとに復路だと主張するときに導かれ、説そのものは根拠ではない。
②は、たしかに鶴は夏越前へ向かった式部は見ていないかもしれない。が、詞書から考えると、式部は鶴の声は聞いているが、鶴の姿を見ているかどうかは明白でないのである。舟の上から、岸辺にいる鳥の声を聞いて、あれは鶴の声だと思い込んだ可能性もある。鳥の声が本当に鶴の声だったのか、あるいは別の種類の鳥かもしれず、鶴の生態を云々すること自体が意味をなさない。
③は、磯の浜が固有名詞かどうかで東岸に立ち寄ったか否かを判断しようというのだが、為時一行がどの航路で越前まで行ったという記録がほかにない以上、東岸へ行くことがまったくないと言えない。
④は往路説に有利だが、復路説を採る『全評』は往路説を援護するようなことを言っている。「又」というのは前の歌と時間的にも近いことを感じさせ、錯簡で紛れ込んだ可能性を低くする。
⑤は歌の解釈は取りようによってどうとでも感じられるということであるが、もう少し掘り下げて考えられないものか。
21番歌では「汝が思ひいづる人や誰」と疑問を呈するのだから、式部も誰かを思い出しているのである。では、誰を思い出しているのかが問題になる。
・都にいる友、あるいは恋人(往路説) 『新書』
・都の恋しい人(復路説) 『全評』
・帰りゆく都の人(復路説) 『論考』
・別れてきた越前の人(復路説) 『集成』
・都の人(往路説) 『叢書』
・(17番歌に呼応するとあるので)肥前へ行った友 『大系』
21番歌と密接していると思われる20番歌については、「立ち居」という表現からも、17番の歌と呼応しているものがあることがわかる。と同時に、21番歌も鳥を詠み込んでいることや、「おなじ心」「もろともに」という表現から、17番歌を意識していると言えるだろう。
17番の歌を詠んだ友は肥前守の娘で、式部とほぼ同じ時期に都を離れて肥前へ旅立っている。出立の前には6番歌を詠み、式部と別れを惜しんでもいる。ここでも雁という鳥が式部と肥前守の娘を結ぶものとして登場しており、式部にとっては、歌を詠むときに鳥は友を連想する題材であったと言える。
『源氏物語』ではそれが顕著に表れる。須磨の巻で都を偲ぶ源氏たちの歌や、須磨へ訪ねてきた頭中将との贈答歌には、雁・千鳥・鶴、諸声、鳴く、雲、雲路、友といった言葉が多用されている。いずれも、肥前守の娘との贈答歌に詠み込まれた語句と共通しており、須磨の巻の執筆時には、まずこの一連の贈答が念頭にあったものと思われる。
沖より舟どもの歌ひののしりて漕ぎ行くなども聞こゆ。ほのかに、ただ小さき鳥の浮かべると見やらるるも、心細げなるに、雁の連ねて鳴く声、楫の音にまがへるを、うち眺めたまひて、涙こぼるるをかき払ひたまへる御手つき、黒き御数珠に映えたまへる、故郷の女恋しき人びと、心みな慰みにけり。
「初雁は恋しき人の列なれや 旅の空飛ぶ声の悲しき」
とのたまへば、良清、
「かきつらね昔のことぞ思ほゆる 雁はその世の友ならねども」
民部大輔、
「心から常世を捨てて鳴く雁を 雲のよそにも思ひけるかな」
前右近将督、
「常世出でて旅の空なる雁がねも列に遅れぬほどぞ慰む
友まどはしては、いかにはべらまし」
と言ふ。
入り方の月影、すごく見ゆるに、
「ただ是れ西に行くなり」
と、ひとりごちたまて、
「いづ方の 雲路に我も 迷ひなむ 月の見るらむ ことも恥づかし」
とひとりごちたまひて、例のまどろまれぬ暁の空に、千鳥いとあはれに鳴く。
「友千鳥 諸声に鳴く 暁は ひとり寝覚の 床も頼もし」
また起きたる人もなければ、返す返すひとりごちて臥したまへり。
日やうやうさし上がりて、心あわたたしければ、顧みのみしつつ出でたまふを、見送りたまふけしき、いとなかなかなり。
「いつまた対面は」
と申したまふに、主人、
「雲近く飛び交ふ鶴も空に見よ 我は春日の曇りなき身ぞ
かつは頼まれながら、かくなりぬる人、昔のかしこき人だに、はかばかしう世にまたまじらふこと難くはべりければ、何か、都のさかひをまた見むとなむ思ひはべらぬ」
などのたまふ。宰相、
「たづかなき雲居にひとり音をぞ鳴く 翼並べし友を恋ひつつ
かたじけなく馴れきこえはべりて、いとしもと悔しう思ひたまへらるる折多く」
など、しめやかにもあらで帰りたまひぬる名残、いとど悲しう眺め暮らしたまふ。(以上『源氏物語』須磨)
須磨の巻から思うに、21番歌で式部が思い出しているのは、むろん宣孝や都の知人、都そのものもあっただろうが、最も心に懸けた相手は、肥前守の娘だったろう。6・7番の歌で雁信の故事をテーマに歌の贈答をした二人は、それぞれ父の任地へ向かう途中でも鳥に我が思いを託した歌を作った。その友が亡くなったときにも、39番歌に雁を詠み込んでいる。長い間、友情を持ち続けた友との思い出があるからこそ、式部は源氏と頭中将との友情を描くのに、肥前守の娘との贈答歌を下地にしようと思ったのだろう。
したがって、21番歌は帰京する式部が都を思った歌とは考えられない。往路において、友を想った歌とすべきである。 |