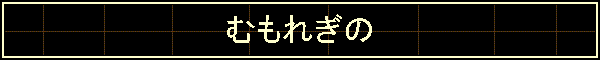紅梅を折りて、里よりまゐらすとて
103 埋(むもれ)木の 下にやつるる むめの花 香をだに散らせ 雲の上まで
卯月に八重咲ける桜の花を、内にて見、
104 九重に 匂ふを見れば 桜狩り かさねてきたる 春のさかりか
桜の花の祭の日まで散り残りたる、使の少将の插頭(かざし)に賜ふとて、葉に書く
105 神代には ありもやしけん 山ざくら けふの插頭に 折れるためしは
【通釈】
紅梅の枝を折って、自邸より宮中へ献上するというので、
人から忘れられた我が家にひっそりと咲く梅の花ではあるけれど、
せめてその香だけでも、宮中まで届いてほしいものよ。
四月になって八重に咲いた桜の花を、内裏にて見る
宮中で幾層にも咲き匂う八重桜の様子を見たので、春の盛りが
重ねてきたかと思うような、桜狩の日です。
桜の花が、賀茂祭の日まで散り残っていたのを、勅使の少将の插頭に
お与えになるというので、歌を桜の葉に結び付けた。
今日お祭りする神々のおわした神代にはまあ、山桜を今日の祭で插頭の
ために折ったという例はあったものだろうか。それにしても、珍しいことです。
【語釈】
●埋木……木の幹が土中などに埋まり、長い年月を経て化石のようになったもの。
●埋木の下にやつるるむめの花……式部が自身を卑下した言い方。埋木は人目につかない、目立たない、世に忘れられたというような意味を有する。
●九重に……「宮中に」の意味だが、「重ねて」の縁語になる。
●かさねてきたる……興福寺の桜が京の桜に比べて遅いことから、春の盛りが重ねて「来たる」と言い、衣装の「重ね」に「着たる」を懸けた。奈良興福寺の扶公僧都が例年のように桜を献上したとき、新参の伊勢大輔が道長の命により、「いにしへの奈良の都の八重桜きょう九重ににほひぬるかな」と詠んで桜を中宮に献上した。その返しが式部が中宮に代わって詠んだ、この歌である。寛弘4年4月か。
●祭の日……寛弘4年4月19日、賀茂祭の日。
●使の少将……賀茂祭の勅使(近衛府使)になる近衛府の少将。ここは藤原頼宗(道長二男)。
●挿頭……礼装のとき、髪や冠にさす草木の花や枝。賀茂祭では、フタバアオイを社前や祭人の衣冠、車のすだれなどに飾った。
●挿頭に賜ふ……賀茂祭には、葵を社前や祭人の衣冠・車などに飾るのが例であったが、このときは散り残った桜を珍重して、中宮が挿頭として与えたもの。
●山桜……4月、新葉とともに花が咲く桜の一種。京都では3月末に開花、4月上旬に満開。陰暦では2月の後半から3月初旬にかけて咲く。
【参考】
『玉葉集』春上、65の詞書
「上東門院、中宮と申し侍りける時、里より梅を折りてまゐらすとて」
『紫式部集(別本系)』の詞書
「上東門院、中宮と申し侍りける時、紅梅折りて里よりまゐらすとて」
『伊勢大輔集(彰考館本)』
「女院の中宮と申しける時、内におはしましいしに、奈良から、僧都のやへ桜を参らせたるに、『今年のとりいれ人は、今まいりぞ』とれ、紫式部のゆづりしに、入道殿聞かせ給ひて、『ただにはとり入れぬ物を』と仰せられしかば
古のならの都の八重桜けふここのへに匂ひぬるかな
殿の御まへ、殿上にとりいださせ給ひて、上達部・君達ひきつれて、よろこびにおはしたりしに、院の御返し
九重に 匂ふをみれば 桜がり かさねてきたる 春かとぞ思ふ」
『袋草紙』『十訓抄』『古本説話集』『続後拾遺集』『秋風和歌集』なども所収。
『新古今集』雑上、1483
「四月祭の日まで、花ちり残りて侍りける年、その花を、使の少将のかざしにたまふ葉に書きつけ侍りける
神代には ありもやしけん 桜花 けふのかざしに 折れるためしは」