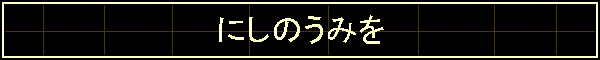筑紫へゆく人のむすめの
6 西の海を 思ひやりつつ 月見れば ただに泣かるる ころにもあるかな
返し
7 西へゆく 月のたよりに 玉章(たまづさ)の かき絶えめやは 雲の通ひ路
【通釈】
筑紫へ国司として下向する人の娘である友人がよこした歌
これからわたしの行く方角である筑紫、その筑紫へ行くべく渡る西の海に
思いを馳せながら月を見ていると、わけもなく泣けてくるこのごろです
わたしの返歌
西へ行く月に、これ幸いと託して往来させるわたしたちの手紙は、絶えることが
ありましょうか。そんなことはあり得ない、雲の通い路ですよ
【語釈】
●筑紫……九州地方全体、北九州の6国(筑前・筑後・肥前・肥後・豊前・豊後)、筑前・筑後の2国を表す場合があるが、ここは北九州。
●思ひやりつつ……何度も想像しつつ。
●月見れば……月を見るといつでも。
●ただに泣かるる……わけもなく泣けてくる。
●月のたよりに……西へ向かっていく、月を幸便と考えて。
●玉章……手紙。
●かき絶えめやは……「かき」は接頭語。「書き絶ゆ」という他動詞は平安時代には類例がないが、「書き」と掛けている。「かき(掻き)絶ゆ」はぱったりと途絶えるの意。ただし、自動詞か他動詞か、また主語(客語)が何であるかによって解釈が分かれる。
・他動詞で「雲の通ひ路」「玉章」が客語 『評釈』
・自動詞で「玉章」が主語、「雲の通ひ路」が総主語 『論考』『国文』
・自動詞で「玉章」が主語 『大系』『集成』『全評』
●雲の通ひ路……雲の行き来するはるかな路。
【考論】
<筑紫へ行く人のむすめ>
『紫式部集』はほかの女流歌人にはみられない、女ともだちとの交流を思わせる歌を数多く収めている。恋や結婚のことを夢見てはいても、まだそれらを現実として感じる必要のない娘時代の友情であるだけに、みずみずしさが歌にも溢れていて、家集を見た者の記憶に残るものを持っている。
そんな女友だちは、おそらく複数いたのだろうが、式部にとって最も仲の良い、代え難い友情を交わしたのがこの「筑紫へ行く人のむすめ」だったのではないだろうか。これ以後の歌(15番〜19番)の贈答と、39番の挽歌はこの「筑紫へ行く人のむすめ」が相手だったとされている(8番〜12番も含める説もある)。
それは、ただ歌の数が多いというだけではない。歌の配列が、この「筑紫へ行く人のむすめ」を意識してなされているのではないかと思われるからである。
1・2番の歌の贈答は、詠作の時期としては、家集に残る歌の中では最も早いことは確実だろう。越前へ行く前年(長徳元年)とする学者もあるが、もう少し溯る説(正暦4年)もある。
だが「筑紫へ行く人のむすめ」が相手かどうかは確定しがたい。諸注釈書も唯一『論考』が2番歌の詞書「遠き所へいくなりけり」と39番歌の「とを(ほ)きところへ行きし人」が共通するものがあるとして1・2番の歌の相手を「筑紫へ行く人のむすめ」と推定しているのみであるが、『論考』のように考えるほうがよいのでは、と思う。
それはなぜか。
4・5番の歌は「おぼつかな〜」、式部の家へ方違えに来た男との贈答である。相手が宣孝であるかどうかは確定できないが、後述するように、そう考えてもよいだろう。1・2番の友だちが「遠き所」へ行っている間に、式部は宣孝と交渉を持ち、自身の恋愛で悩んでいたのである。
その宣孝も、正暦元(990)年8月に筑前守となり赴任してしまう。「筑紫へゆく人のむすめ」という詞書の「筑紫へゆく人」は、そのときの宣孝のことをも掛けているのではないかと思われる。そうでなければ、後の18番歌に至って「筑紫の肥前といふところより〜」と、地名を特定しなくても、ここで肥前と書けばよいはずである。式部は詞書においても掛詞のように、一つの言葉に二つの意味を持たせているのではないか。『紫式部集』には、1・2番歌の「その人、遠きところへ行くなりけり」や、「もとより、人のむすめを得たる人なりけり」といった、前後どちらの歌についてなのか、迷う詞書が頻出する。同じ感覚で、5番歌の宣孝は「筑紫へゆく」、そして6番歌からは「筑紫へゆく人のむすめ」の歌が始まるのです、と言っているのではないか。
ただし、詞書で繋がっているとは言え、6番の歌は4・5番の贈答から5年ほど経過したころの詠と思われる。それは、後に配列されている15〜19番歌の詞書(「返しは、西の海の人なりけり」)から、「筑紫へゆく人のむすめ」と式部とは、同じ長徳2(996)年に越前と筑紫へ別れ別れになったことが判明するからである。そのころには、宣孝も当然帰京していただろう。だから今度は越前へ行く式部と宣孝の別れも存在するわけである。が、式部の関心は宣孝より、筑紫へ行く友だちのほうに注がれている。
では、この贈答の年次はいつになるのか。
二人の歌に詠まれている月は、一般には秋のものであり、他に季節を特定できる言葉もないので、いちおう秋とする。すると、式部は長徳2年夏に越前へ旅立っているから、この贈答は前年の長徳元年秋のものとなる。
それで、長徳元年に肥前守に任命された人はというと、『権記』に「」十月十八日、肥前守維将ナリ」とある。『世界』はここから、平維将とし(ただし『基礎』は維将の将の字を時と解して平維時とする)、平維将に嫁いだ伯母のむすめが、この贈答の相手だと記している。そして、『世界』によれば、8〜12番歌も、15〜19番歌の相手と同一としているので、式部はこの従姉と長徳元年秋から順に、6〜12番、15〜19番と歌を交わしたというのである。
ところが、長徳元年10月18日は、新暦では11月18日である。従姉が父の任官を知り、悩みを抱えて山荘へ行き、式部に歌を寄越すまでに、仮に十日ほどかかったとすると、もう12月に入ってしまう。8〜10番歌が紅葉を詠み込んでいるので、この贈答の相手も従姉だとすると、紅葉はまだ散らないであったのか……微妙なところである。
また、もし紅葉に間に合ったとしても、内容的にみると、この歌は出立直前の慌ただしさの中で詠んだ15番歌などと近い時期のものではないかと考えられる。父の任官直後に泣くほど悲しんだり、「お手紙を書くわね、決して絶やすことはありません」などと変化したりするのは、早すぎはしまいか。式部より幾つか年上と思われる女が、何の躊躇もなく父の赴任先へついていくことを決定事項として語る、というのは不自然な気がする。さらには、6・7番歌で筑紫へ行くと決めていて、8〜12番歌の時点ではどうも下向をためらっているのは、矛盾してしまう。つまり、8〜12番歌も従姉との贈答とするならば、その詠作順序は長徳元年秋から冬にかけて8〜12番歌、長徳2年夏以降に6・7番、15〜18番、翌長徳3年に19番、としなければならない。
なぜそのような配列にする必要があったのか。理由は、次の8〜12番歌が同じ従姉との贈答であるか否かによって変わってくるので、「つゆふかく」の考論にて述べたいと思う。
|