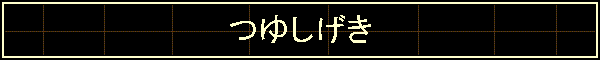「箏の琴しばし」といひたりける人、
「参りて、御手より得む」とある返事に
3 露しげき 蓬が中(もと)の 虫の音を おぼろけにてや 人のたづねむ
【通釈】
「箏の琴をちょっと貸してくださいね」と言っていた友達が、
「やはりお会いして、直にあなたの手から教えてください」と手紙に書いてきた、その返事に
(夫が亡くなり)露が滴り落ちて湿っぽく、蓬に覆われた我が家の庭、そこで鳴く虫の音の
ような音を奏でるわたしの箏の琴を、あなたはまあ、奇特にもわざわざ
訪ねてきて、習おうとおっしゃってくださるのですね。
【語釈】
●箏の琴……奈良時代に中国から伝来した13弦の琴。日本古来の琴は和琴で6弦、琴(きん)は7弦で区別がある。『源氏物語』には40例もみられるという。
●箏の琴しばし……「名詞+しばし」で「~を貸してください」の意味になる。
●参りて御手より得む……式部に直接会って、奏法を教えてほしい。
●露しげき蓬が中……荒れて庭の草木が生い茂り、たっぷりと露がおりて湿っぽい我が家。自邸を謙遜した言い方だが、露は涙のことであるから、悲哀を匂わせている。とすれば、夫の宣孝を喪ったことを指しているのだろう。『千載集』詞書より宮仕え後とする説もあるが、そうなると宣孝の死後数年は経ていることになる。寡居時代としたほうが、しっくりくる。
・寡居時代の作 『論考』 ・宮仕え中 『評釈』『復元』『全評』 ・未婚時代 『叢書』『大系』『基礎』 ・宮仕え以前 『集成』
ちなみに、『源氏物語』では「露しげし」の用例は2例しかない。
「荒れたる家の露しげきを眺めて、虫の音に競へるけしき、昔物語めきておぼえはべり」 (『源氏物語』帚木)
「露しげきむぐらの宿にいにしへの」(『源氏物語』横笛)
特に横笛の巻のほうは、柏木が昔奏でていた音色を偲んで詠んだ歌である点、やはり露は涙と考えるべきであろう。
●おぼろけにてや……いい加減な、並々の気持ちで~しようか、しない。
【参考】
『千載集』巻十六、雑上、974
「上東門院に侍りけるを、里にいでたりけるころ、女房の、消息のついでに、「箏つたへにまうでむ」と、いひ侍りければ、つかはしける
露しげき よもぎがもとの 虫の音を おぼろけにてや 人のたづねむ」
【考論】
<3番歌の配置>
この歌の配置については、諸注釈により考察のなされるところである。家集の配置はほぼ年代順であるため、『千載集』の詞書に従って詠作年次を寡居時代・宮仕え後とする場合、配列に矛盾をきたすからだ。
たしかに4・5番歌の娘らしい、女のほうから詠みかけた恐いものなしといった態度や、13番歌のような瑞々しい清涼感溢れる歌などと比べると、千載集の詞書を見るまでもなく、3番歌は年代的に後のものであるという印象を受ける。
『全評』は、「宮仕え後の歌と思われるものを、娘時代の歌のつづく中にあえて配置した式部の意図」として、夫の没後は孤愁感に沈み、琴を弾くこともなくなっていたのが、奏法を教えてほしいと言ってきた人が現れたことにより、新しい知音との出会いを感じ、1・2番歌の「別れ」の哀歌に続き、また同じ「虫の音」で繋がることから3番の歌を置いたとする。3番歌の贈答の相手が誰か不明なので新しい知音かどうか断定はできないものの、虫の音を媒介とする連繋については肯ける解釈である。
式部は1・2番歌を冒頭に置くことを決めたが、その後ろに年代的に近い宣孝との贈答を持ってきたかったのではなかったか、と推測する。
式部はおそらく、2番歌の醸す情景に限りない哀惜の念を持っていただろう。童友達と別れ別れになった秋、その悲しみに泣く自分と競うように鳴いていた籬の虫の音は、忘れられないものだったのである。
しかし、式部にはそれから、宣孝との出会いが待っていた。現実には、この二つの場面は宣孝との贈答が先で、事実とは相違があるのかもしれないが、冒頭に置きたい歌が決まっている以上、宣孝との贈答は後ろに持ってくるしかない。が、ただ並べるだけでは唐突すぎるし、芸がない。と言うより、式部は家集編纂にあたって、全歌を貫く一つの意図を持っていたに違いないのである。
それは、自分の人生をまるごと筋書きのある物語として、家集に残すこと……そのために、若いころから、家集を編纂している時点(晩年?)までに詠んだ歌を年齢の偏りなく集めたのである。『紫式部集』はその通り、娘時代、越前下向時代、結婚生活、寡居生活、宮仕え中、退下後と、詠作年次に空白の時期がない。これは自撰である根拠にもなると同時に、彼女がみずからの人生をゆるやかな時間軸で進む物語に仕立てた証であろう。歌の配列がほぼ詠作年代順なのは、当然である。
ところが、過去の手持ちの和歌をただ年代順に並べただけでは、物語としての繋がりは希薄である。ことに、女友だちとの友情は、宣孝との恋愛とは直接の関わりを持たない。詞書をもってしても、これを物語として繋ぐのは難しい。ならば、共通の言葉を使い、あるいは連想されるイメージを利用することで、物語の流れを作ってしまおう、と思ったのではないか。女友だちとの贈答歌にある「籬の虫の音」、それに宣孝を関連付けられるのは3番歌、おそらくは宣孝と死別して「露しげき」状態にある式部が亡き人の思いを胸に琴を爪弾いていた秋、の歌は、まさに2番歌と共通するイメージであり、4・5番歌の贈答の相手が宣孝であることで接点を持つことを可能にする。
人生のある一時期に詠んだ歌というものはそれぞれ点にすぎないが、それが線になるためにはこうした工夫が必要なことを、式部は知っていた。あいにく、3番歌は詠作年代順という基本方針からはずれることになってしまうが、式部はそれ以上に、家集の物語化に拘っていたのである。このことは、以降の考論においても、述べることにする。
|