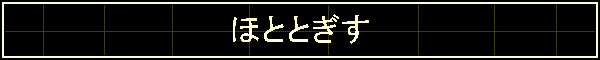賀茂にまうでたるに、「ほととぎす鳴かなむ」といふあけぼのに、
片岡のこずゑをかしく見えけり。
13 ほととぎす 声待つほどは 片岡の 杜のしづくに 立ちや濡れまし
弥生のついたち、河原に出でたるに、かたはらなる車に、
法師の、紙をかうぶりにて、博士だちをるを、憎みて
14 祓戸(はらへど)の 神の飾りの 御幣(みてぐら)に うたてもまがふ 耳はさみかな
【通釈】
上賀茂神社に詣でた折に、連れの一人が「ほととぎすよ、鳴いてちょうだい」と言ったのがあけぼののころ。
片岡の社にある森の木々の梢が情趣あふれて見えたことだった。
ほととぎすの声を待ちわびて、その間は片岡社の森の雫に立ち濡れて
みようかしら(それもいいかもしれないわ)
三月の一日、河原に出ると、傍らにある車に、法師陰陽師が紙の冠をして陰陽博士を気取っている。それを憎らしく思って
祓戸の神にお供えする御幣、あれと見間違えるような紙の冠を耳に挟んだりして、
何ともいやらしいこと(法師は髪もないのに紙を頭に戴いているなんて!)。
【語釈】
●賀茂……京都市北区上賀茂本山町の賀茂別雷神社(上賀茂神社)と、左京区下鴨泉川町の賀茂御祖神社(下鴨神社)の両社。片岡の文字があるので、ここでは上賀茂神社。
●ほととぎす鳴かなむ……ほととぎすよ、鳴いておくれ。ほととぎすは陰暦4月ごろ、渡来し鳴く。
●あけぼの……夜がほのかに明け始めるころ。
●片岡……上賀茂神社の本殿楼門の東南前にある第一摂社、片岡社の東背後に接する片岡山を指す。標高166m。
●声待つほどは……ほととぎすの声を待っている、その間は。
●立ちやぬれまし……いっそ、立ちぬれていようかしら。事実に反すること、実現不能なことを仮想する反実仮想の助動詞「まし」により、実際には無理だろうが、立ちぬれていたいという意味になる。
●弥生のつひたち……「つひたち」は『源氏物語』の用例では、月の第一日目を表し、上旬という曖昧な意味を有するときには「つひたちのほど」「つひたちごろ」などと表記している。したがって、ここは3月1日と解してよい。
●法師……法師の身でありながら、陰陽師の真似をする法師陰陽師のこと。
●紙をかうぶりにて……紙で作った簡素な冠を、陰陽師のかぶる冠の代わりにして。
●博士だちをる……まるで陰陽博士であるかのようにふるまって。
●祓戸の神……祓戸(はらへど)は神祭の際、祓を行う殿舎。祓において祭る、セオリツヒメ神・ハヤアキツヒメ神・イブキドヌシノ神・ハヤサスラヒメ神の四柱の神を指す。
●飾りの御幣……飾り物として神に捧げるものの総称。
●うたても……いやらしくも、うとましくも。
●まがふ……見違える。
●耳はさみ……顔の左右側面にある髪を肩の辺りで切りそろえ、垂らしてある短い髪が額髪であるが、これを耳に挟んで垂れてこないようにしている状態。女が労働の際、邪魔にならないように耳に挟むことが多いので、下品な様子とされた。
【参考】
『新古今集』夏、191
「賀茂に詣でて侍りけるに、人の、『ほととぎす鳴かなむ』と申しけるあけぼの、片岡の梢のをかしく見え侍りければ
ほととぎす 声待つほどは 片岡の 杜のしづくに 立ちや濡れまし」
【考論】
<思い出作りの日々>
13・14番歌の解釈は、諸註釈書で大きく異なる部分はないようである。問題になるのはやはり詠歌年次と、それに関わる配列であろう。
13番歌は、『世界』では長徳2年の越前行きの直前、賀茂に詣でた折の歌としている。こちらは家集の配列を無条件に詠作年次に当てはめ、1〜5番歌を長徳元年、6〜18番までを長徳2年の詠とするのはいささか乱暴なやり方ではないかと思われるが、13番歌が長徳2年に詠まれたことは、後述するように正しいと思われる。14番歌との関係については、ほととぎすの鳴くのは3月末ごろとみて、13番のほうが季節的には少し遅くなるとする指摘は頷ける。「家集の順序通りだと少くとも賀茂河原の祓の前年以前となるが、13・14の歌の先後はわからない(『評釈』)」「(13)(14)は配歌順が日次的でないが、これは神詣に敬意を表してのことであろう(『講座』)」という意見もある。
それから、式部がなぜ上賀茂神社に詣でたか、という理由だが、『新書』が賀茂祭としているのも間違いとは言い切れないが、『全評』・『講座』の言うように、夏に予定している越前への旅と任国での無事息災を願ってのことと考えたい。ほととぎすは「不如帰」とも書き、故郷へ帰る、望郷の念を表すことが多いといい、任国への下向で別れを惜しむとき、ほととぎすの声を待ち望んだ歌が、『清正集(式部の大叔父藤原清正の家集)』にもある。この参詣から考えて、詠歌年次として自然なのは長徳2年春から夏にかけて、ということになろうか。
14番歌については、今井源衛が「三月ついたち」を3月1日とし、これが上巳の日に当たる年で、式部の年齢と矛盾しないのは寛和2(986)年3月1日であろうとしているが、「ついたち」は初旬を表す言葉に過ぎないとする反対説がある。また、『全評』は、『源氏物語』の用法から、「ついたち」の後ろに「ごろ」「ほど」などの言葉が付いていないので3月1日と解してよいが、ただし当時の貴族は必ずしも巳の日に祓に行っているわけではないという。結局、年次を特定する材料にはならないということだろう。あるいは、13番歌の「賀茂」が(賀茂川の)河原ということで共通の語句を持つからと、実際の詠歌は長徳元年以前のものをここへ配列したとも考えられるのではないか。
女ともだちとの贈答をいくつか並べた中にこの二首を入れた理由について、明確に述べたものは「4・5番、6・7番、8・9・10番、11・12番と、贈答歌を排列して来て、また、15・16……と贈答歌が排列される、その間に、13番、14番の揶揄歌、あるいは俳諧歌と言える独詠歌を二首挿入して、明かるくユーモラスな変化を図ったものと思われる(『論考』)」くらいしかない。が、ここでもやはり式部が目指していたであろう、限りなく物語に近い家集ということを考えれば、13・14番歌にはもう少し意味があると思われる。
この二首の歌には、共通点がある。それは式部が家を出て、誰か連れと一緒に(14番のほうは連れがあったとは書いていないが、貴族の女である式部が独りで外へ行くことはなかろう)、京の町中からさほど遠くない場所へ出かけたことである。思うに、連れの中には従姉がいたのではないだろうか。式部たちはそれまでも、ちょっとした外出には一緒に出かけていたのだが、それも離京後はかなわない。せめて今のうちに、行動を共にして思い出を作っておきたいと、互いに誘い合って出かけた小旅行とでも言うべきものが上賀茂神社参詣であり、鴨川の祓なのではないか。
そのとき式部は、従姉も下向する決心がついたことを感じていただろう。式部自身も、まだこの時点では越前行きをためらっており、従姉を見て迷いを振り払ったのだろうか。後の15番歌で「よそながら別れ惜しみて」と、逢わないで歌を交わしているだけなのは、もう十分に語り合って満足した、二人の心情の表れとも取れるからである。
このように考えると、13・14番歌には、単独で解釈するだけでは感じられない、深い想いが込められていることに気付かされる。歌に詠み込まれたほととぎすも法師陰陽師も、実は式部にとってはさほど重要なものではなかった。従姉も一緒であったことが、この二首を家集に選び取った理由なのではないか。とすれば、6〜19番までの歌は、親友との間に存在した“物語”であり、その友情が式部の未婚時代を占めていた証として、家集の中でもひときわ光彩を放っていると見るべきだろう。
|