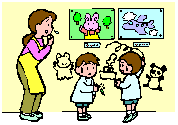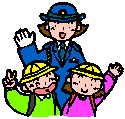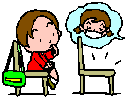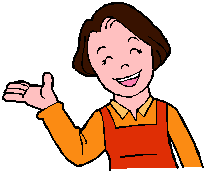|
八千代市保育園父母会
連絡会ニュースNo.43
|
2002年 5月 9日(木)発行
八千代市保育園父母会連絡会広報部
[4/19懇談会報告&5/26定期総会議案]号
|
「フレッシュタウンに150名規模保育園[学童併設]新設、社会福祉法人公募」
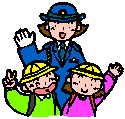
~4月19日[金]夜、児童支援課課長以下3名と連絡会加盟6園10数名の父母が懇談。~
4月19日金曜日、児童支援課と父母会連絡会の懇談会が市役所2階会議室にて開かれました。担当課からは佐々木課長・尾崎副主幹・千田高津南保育園園長(主幹)が出席し、2時間ほど懇談しました。連絡会会長は、冒頭挨拶で「父母の願いは「安心して子どもを預けられること」。このことで父母は仕事に専念できる。核家族化や少子化が進み、子どもだけでなく親達の子育て支援を考えれば、保育園の果たす役割は重要だと考える。しかし、今、政府が進めようとしているのは、保育園の企業参入や待機児ゼロを名目に詰め込み主義の保育園にしようとしている。保育の質が問われている。また、自治体も不況による税収不足と補助金や交付税のカットで財政が厳しい。この緊縮財政時に予算をどう配分するかが問われている。私たちの要望の窓口は児童支援課なので、父母の立場に立って頑張っていただきたい。」と述べました。懇談会の主な内容は以下の通りです。又、4月28日(日)定例運営委員会にて、各園父母会の近況報告をし、総会議案(裏面参照)を検討しました。
1.大和田西保育園と茶々おおわだみなみ保育園、八千代台地区の保育園の統廃合は?
課長:1998年6月の行革方針で、保育にかかるコストが高いことから、コスト削減のために民営化を進め2010年までに4~5園を民間委託にして公民半々にすることが出された。このことは現在も生きている。98年12月には「モデル園(1園)」を作ることが行革方針で打ち出され(課としての方針はなかった)、その後市長対話を2回実施。その中で「保育の質を下げない。公立保育園と同じように公的保障をする。」ことを条件に子育て支援対策委員会(父母会代表含め22名)が作られ4回開催。一致した意見を提言書にし受諾法人選考委員会に出され、「あすみ福祉会」に決まった。茶々おおわだみなみ保育園と大和田西保育園の統合問題は、子どもの減少によっては考えられるが今は増えている。敷地も問題がある(吸収できない)。保育の質を下げないという観点から、新規事業ができた。①0歳~3歳までの枠の拡大。②育児休業取得者の上の子の3歳児条件を撤廃。③障害児保育の拡充。④地域子育て支援事業の拡大(八千代台)。など、保育の需要に応えられた。茶々~の場合、東葉高速の影響で需要が増えているし、民間としてのサービスも良かった。他県からも多くの視察が来た。「行革の中で、民間委託が質を下げずにどうしてできたのか」と聞かれたが、「コスト削減だけが行革ではない」と考えたし、父母会の手助けがあったからと思っている。市民の目で行政を考え、市民とのパートナーシップが大事。しかし、これからの新設園は民間でとの考え方。現在、社会福祉法人7園、公立11園だが、将来的には大和田西、八千代台が民間になる。
連絡会:大和田西の統廃合は、児童数を見てということだがいつになるのか。
課長:大和田西の統合の時期はわからない。2004年にフレッシュタウン内に保育園を開設し、その後、茶々~の建替えを考えている。修理も無理なので、第2期実施計画に盛り込み(公費の補助)、2004年度に建替えできるよう県に要望(県の建設計画に入っている)した。安全面で茶々~からの要望もあった。ただ、定員数(120)については保育園と話を詰めなくてはならない。大和田西の児童数の状況から見て(統廃合は)当分はないのではないか。しかし、何年か後にはあることは心配している。建物も老朽化して補修の要望もある(八千代台も建物が古い。補修をしている。)が、いずれにしてもいろいろな要因が絡むので状況を見ている。児童の需要数を把握するのは難しいが。
連絡会:先日NHK-BS1「インターネット・ディベート」の取材(3/30放映,VTRテープ事務局保有)があった。その中で「『茶々~』では、保育士のうち正社員は3割、常勤職員のおよそ半数は1年契約。経験年数はこれまでの平均18年から平均5年になった。保育園側は・・・マニュアルを使うことで保育のレベルが下がらないとしている。」(http://www.nhk.or.jp/debate/th/f/05/report/f05rpt_vtr03.htm#rpt01参照)とあったが、移管条件は守られているのか。
課長:NHK-BSは見なかった。ここに書いてある内容は誰が言ったものか分からないが、(移管後)5年間は条件(園長は7年以上の保育士勤務経験を有すること。6年以上の保育経験者が1/3以上含まれること。)にしてある。確かに当初より安くできた(朝は複数の正規職員で対応し時間外の費用がういた)。しかし、毎月チェックをしている。
連絡会:父母の要望に対して、公立園と民間園では違いがでるのではないか。公立は直接市へ申出できるが、民間では間接的になってしまう。市が民間園の経営に対してどの程度指導できるのか。
課長:公立園と民間園の格差をなくすために八千代市では、公的保障という観点から独自に国の補助にプラスして補助金を出している(国費6:市費4)。茶々~に限らず市内民間保育園は同じである。他市は民間保育園の実施する事業に対しての補助金だが、八千代の場合は国費に対して一律で補助。その面で他市より指導できると思うし実際に指導している。
2.新設保育園の概要(場所・規模等)、運営形態、公募の概要(条件)・日程等は?
連絡会:4月15日付け広報で、「学童保育所を併設する新しい保育園を建設・運営(民設民営)する県内の社会福祉法人の募集」とあったが、具体的な内容はどうなっているか。
課長:具体的な要綱等は、5月1日の配布に向け決裁中なので示せない。場所はフレッシュタウン内で敷地は1,500㎡程度。定員数は学童保育所50名・保育園150名。運営形態は「民設民営」。公募の条件は、茶々~とほぼ同じ。今後の日程としては、募集期間完了後に1~2回の選考委員会(前回の役員とほぼ同じ)を開き、6月末には決定したい。8月には県のヒヤリングがあり、ある程度の建築構想が決まっていなければならない。期間的には厳しいが。
連絡会:茶々の時は全国公募だったが、今回、法人募集を「県内」に絞った理由は何か。
課長:理由はない(ただし、県外法人の場合は認可との関連がある)。社会福祉法人として運営を実施しているところ、これから始めるところ、どちらでも良いことにした。すでに問い合わせは多い。
連絡会:保育園の定員を150名とした理由は。
課長:本来90名程度が運営しやすい定員と考えるが、マンション建設等で保育需要から考えると150名が妥当と考えた。(150名以上のマンモス化になることはどうかと思う)。実際、これでも不足するかもしれない。
連絡会:先ほど、待機児童の件に触れられたが、今年度の状況はどうか。
課長:現在26名。昨年の同時期と比較しても同人数程度と思う・・・
連絡会:学童保育所の運営主体について伺うが、大和田第三学童保育所存続の請願署名で「公設公営」の表現が誤りだとして受理されなかったそうだが、「公設公営」「公設民営」のどちらなのか聞きたい。
課長:「公設公営(一部委託)」という表現を使っている。議会請願については、議員の解釈なので言えない。しかし、請願署名は6月に再度提出すると聞いている。
3.今年度からの「新規事業」とは?
課長:大きく分ければ7項目となる。
- 子ども人権ネットワーク事業・・子ども相談、子どもの虐待、親のカウンセリング等の幅広いネットワークをつくる。
- 来年度、乳幼児医療システムを立ち上げるため、秋には準備
4.その他
【児童支援課より】2001年4月1日より制度化していた「育児休業取得者の上の子の年齢撤廃」は、育休法の改正(3年間取得)により、「2年目以降の育児休業取得者の上の子の保育はできない。ただし、4,5歳は継続」としたい。実際、1年間取得する人は減っている。
連絡会:臨時の時間外申請の手続きが緩和されたと聞いたがどうなのか。
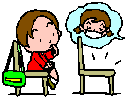
課長:臨時の場合、申請書の提出と電話連絡とで園によって統一されていない。園長権限で任せている。安易にすると悪い方向に行く危険性もあるので。
連絡会:継続的な薬の投与について簡素化できないか(処方箋を毎日つけて提出しているが、まとめて1回でできないか)。
主幹:基本的には保育園で薬の投与はしないようにしている(厳密に言うと医療法に抵触してしまうし、事故が起きてしまった場合の問題がある)。しかし、園長会議で話もあるので、「喘息など」改善する方向である。
第4回 定期総会議案(2001年度総括&2002年度方針)
~5月26日[日]午前10時~福祉センターにて、[会計報告は当日別紙にて]~
総会時に会費(100円×各園定員,定員未満は×在園児数)と「ちいさいなかま」注文数を集約します。
1.2001年度活動総括(案)
|
|
会 議・行 事 等
|
主 な 内 容
|
関連事項、他
|
|
2001.4.22
|
第1回運営委員会
|
中野の保育を考える会からの訴え、他
|
|
|
5.27
|
2001年度総会
|
活動方針の決定、他
|
|
|
5.31
|
大阪保育行財政研究会との懇談
|
公立保育所の民営化に伴う実態や質の問題などで懇談
|
|
|
6.17
|
|
|
「中野の保育を考える会」結成の集い(清水前会長が出席)
|
|
6.24
|
第2回運営委員会
|
2001年度要望書の取組みついて提案、他
|
|
|
7. 1
|
|
|
第29回ちば保育のつどい(柏市)
|
|
7. 4
|
茶茶おおわだみなみ保育園との懇談
|
保育園の視察も含め、園長、副園長と懇談
|
|
|
7. 1
|
東京新聞からの取材
|
民間委託の経緯と委託後の状況や評価
|
|
|
7.22
|
第3回運営委員会
|
要望書(案)の議論、他
|
|
|
7.24
|
要望書を提出
|
1.正規職員の増員
|
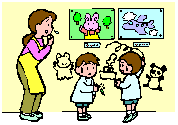
|
|
2.時間外保育条件の緩和
|
|
3.人口増に伴う計画的な保育園の新設
|
|
4.民間モデル園の評価
|
|
5.学童保育の時間延長と施設の増設
|
|
8. 1
|
赤旗日曜版からの取材
|
政府の「待機児ゼロ」政策や民営の弾力化に対する意見交換
|
|
|
8.25
|
第4回運営委員会
|
児童支援課懇談会等、日程の確認、他
|
|
|
8.31
|
市職労保育支部との懇談
|
縦割り保育、散歩・遠足、連絡帳の件などで保育士との意見交換
|
|
|
9. 9
|
|
|
・県保問協第2回運営委員会(保育セ)
|
|
・ゆりのき台学童保育所父母会との懇談
|
|
~ 9.15
|
学童市連協との連名調査
|
入所希望調査実施
|
|
|
9.25
|
第5回運営委員会
|
児童支援課との懇談会(10/12)に向けて
|
|
|
10. 6
|
|
|
学童市連協対市交渉
|
|
10.12
|
児童支援課との懇談会
|
要望書に対する回答
|
|
|
10.21
|
第6回運営委員会及び県保問協第3回父母会部会
|
児童支援課懇談会の結果報告及び、各市との意見交換
|
|
|
11.13
|
|
|
子育てキャラバン(事務局長参加)
|
|
11.25
|
第7回運営委員会
|
要望書関連の担当課回答他、「子育てのつどい」等について
|
各種署名の回収
|
|
「小中学校の少人数学級」
|
|
「30人学級請願署名」
|
|
12.2~
|
|
各園に署名協力依頼
|
ゆりのき台学童父母会より署名協力依頼
|
|
12.23
|
第8回運営委員会
|
子育てのつどいの参加企画や、統廃合計画・学童問題について
|
|
|
2002.1.11
|
市職労保育支部との懇談
|
「第3回あそぼうよ、みんなよっといで」打合等
|
|
|
1.18
|
|
|
大和田第三学童保育所移転に伴う説明会
|
|
1.26
|
|
|
大和田第三学童保育所父母会打合せ
|
|
1.27
|
「第14回子育てのつどい」及び「第3回あそぼうよ、みんなよっといで」
|
松崎運之助氏の講演及び親子のあそび
|
高津西父母会で「万華鏡づくり」を企画・運営
|
|
2.24
|
第9回運営委員会
|
児童支援課への申し入れ(統廃合計画)等
|
|
|
3.24
|
第10回運営委員会
|
2002年度総会に向けて協議、他
|
NHK-BS1「インターネット・ディベート」番組のVTR取材
|
|
4.19
|
児童支援課との懇談会
|
第3次総合計画・第2期実施計画(茶茶おおわだ南・大和田西の統廃合他)について
|
|
|
4.28
|
第1回運営委員会
|
2002年度総会議案作成
|
|
2.2002年度活動方針(案)
①「公立保育園の合理化施策」については、引き続き公的保育の質を維持・向上させるべく活動していきます。
②「公立保育園の民営化」については、「移管モデル園」となった茶々おおわだみなみ保育園父母会と連携し、『受諾法人としての条件(提言書等)』が守られているかを随時確認しつつ、市全体により良い保育環境を確保する立場で必要なことを担当課に要望していきます。
③各園父母会(保護者会)間の情報交換、交流を促進するため、前年度に倣って、運営委員会(各園代表者会議)を毎月第4日曜日に定期的に開催します。その際、「父母会ニュース」等各園独自発行の資料があれば持ち寄って、様子を知らせ合います。
④各園の意見集約を通して、2002年度要望書を作成し提出します。
⑤千葉県保育問題協議会(1999年より連絡会として加盟)と連携しながら、第34回全国保育合研(8/2~8/4静岡市)も含め、各種の保育集会、学習会、講座を紹介し参加を呼びかけます。
⑥保育者と父母を結ぶ雑誌『ちいさいなかま』購読者の拡大を目指します。そのための選任の係を運営委員として役員に組み入れます。
⑦保育園卒園後も安心して仕事を続け子育てができる安定した環境づくりのため,八千代市学童保育連絡協議会(市連協)等との連携を追求していきます。
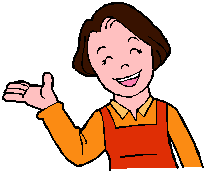
⑧上記目的達成の一手段として、又子育てや子どもの教育にかかわる市内の様々な団体との交流を兼ね、昨年までと同様、『八千代子育てのつどい』や『あそぼうよ! みんなよっといで』に実行委員会参加します。併せて、昨年実現した保育士との懇談の場を確保していきます。
⑨上記の活動を全会員に知らせていくため、定期的に「連絡会ニュース」を発行します。
⑩補助的な情報提供・情報交換の手段として、ホームページやメーリングリスト(http://www2u.biglobe.ne.jp/~TommyNet/toppage.htmlやhttp://www.egroups.co.jp/group/yachiyohuboren)等のインターネット環境を効果的に活用していきます。
3.2002年度役員・業務分担(案)以下省略

父母会連絡会のトップページに戻る