Review
2005

David Sanborn "Closer" (Verve-Universal)
David Sanborn:as Gil Goldstein:key Russell Malone:g Chris McBride:b Steve Gadd:ds Mike Mainieri:vib
Luis Quintero:perc Bob Sheppard:sax Lizz Wright:vo
国内盤先行で、昨年11月末にでてたものなんですが、ボーナストラックなしで1枚2500円?!ということで輸入盤待ちをしていましたが、
年明けて14日にやっと欧州盤が1枚2000円ほどで店頭に並びましたので、購入しました。
聴く前は、メンツもほぼ前作と同じで、「余りテイクか??」と勘ぐりたくもなりましたが、実際に、聴いてみると・・・前より全然エエです。
まず、リズム、特にガッドのタイコが前面で出てきている感じ、特に、1曲目の「ティン・ティン・ディオ」、腰のドッシリ据わったマクブライドのベースの上で、
ジャスト、ややレイドバックなリズムが踊ってます。
曲のエンディング前、フェードアウト手前のウネリまくるソロなど近年、あまり聴けなかったものではないでしょうか。
前作と同じメンツながら、全体的にも、より強力になったリズムをバックに、サンボーンのアルトもバラード的に泣くだけでなく、ウネリ感やグルーヴ感を増した
ブロウを聴かせてくれてます。
95年に作ったバラード盤「パールズ」あたりが、前作から続くこの路線のルーツなんでしょうが、その辺と聞き比べると、随分、サンボーンのアルトの音が
立体的になってるんですよね。
「泣きのサックス」が2次元から3次元に進化したような・・・80年代のマーカスと組んでた頃のサウンドの揺れ方は、2次元っぽい縦横でしたが、
ガッド=マクブライド=ゴールドスタインというリズムを得た前作~今作では、そこに、上下のグルーヴが加わった感じ?。
また、ギル・ゴールドスタインのオーケストレーションも、生楽器とキーボードの音を微妙、絶妙に組み合わせて、サウンド全体の立体化に大きな役割を果たしてます。
マイニエリのヴァイブも、ややモノトーンなサウンドの中で重要なエッセンスになってます。
前作「タイム・アゲイン」が出たときは、正直、「あ~サンボーンも終わったなぁ・・・」と感じた面も正直ありましたが、その認識は全く誤ってました、反省、反省です。。。
より少ない音数で、また、無駄に「泣く」ことなく、楽曲の良さを十二分に引き出すという難しい課題を、前作~今作の中で、サンボーンはしっかりとクリアさせています。
その結果、今までにない迫力と存在感を、本作のアルトソロから感じることが出来ます。
92年リリースの「アップ・フロント」以降の作品は、正直、あまり愛着を感じるものはありませんでしたが、久々に今作は、長期に渡って愛聴盤になりそうな感じですね。
(2005年1月18日)
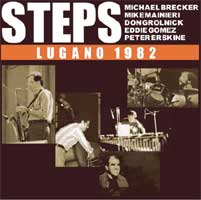
Steps “Lugano 1982”
サイバーシーカーズで販売されてファンの間で話題となっている
1982年スイスでのステップスのライブソース2枚組みを聞く機会に恵まれました。
メンバーは、マイニエリ=ブレッカー=グローニック=ゴメス=アースキン。
名盤「スモーキン・イン・ザ・ピット」とは、ドラムがガッド→アースキンにチェンジされてるだけなんですが、それとは相当、演奏のテイストが違うのにびっくり!。
よく言えば「しなやかでジャズっぽい」、逆に少しネガティヴな表現をすれば、「冷めていて"スモーキン~"での異様ともいえる音の密度や迫力を感じない」。
ステップスやチックのスリーカルテットなどでのガッドのジャズ演奏は、録音から20年以上も経った現在でも、賛否両論の喧々諤々が止まない中、好き嫌いがあるにせよ、
相当な個性があることをここでの、アースキンと比較して改めて実感させられました。
「ガッドが叩けばみなフュージョンになる・・・」とガッドに否定的な人がよく口にしますが、
粒立ちが良すぎるほど良く、ビートを揺らぐことなく正確に叩き続けるそのドラムは、ガッドファンの私が聴いても「そのとおり」だと思いますよ。
リズムの「ゆらぎ感」がジャズだとすれば、確かにガッドの叩く4ビートは、ジャズじゃないということになりそうですが・・・。
しかし、そこがまた、ガッドの叩くジャズの「新しさ」~「個性」でもあったわけで、彼のあとには、ディヴ・ウェックルやヴィニー・カリウタという
「ガッドスタイルのジャズ演奏」のフォロワーが現れた訳です。
敏腕スタジオセッションメンの集団であったステップスは、スタジオであろうとライブであろうと「スモーキン~」並みの迫力とテンションは、
ルーティンのライブでも簡単に出せてたんだろう?と簡単に考えてましたが、実はそうではなく、あのライブがある意味奇跡的なもので、
普段着の演奏が、今回耳にしたソースだったんだな、ということがはっきりと分かりました。
で、その奇跡的ともいえる「スモーキン~」の一番の立役者がガッドだったんですね。
このようなブートレグが世に出ることにより、正規盤「スモーキン・イン・ザ・ピット」の存在価値がより高まる訳ですから、ブートレグというものはやっぱり必要だと思いますね。
(2005年1月19日)

Mezzoforte "Forward Motinon" (BHM)
Mezzoforte/ Fridrik
Karlsson(g)Eythor Gunnarsson(kb)Johann Asmundsson(b)Gulli Briem(ds)
w/ Chris Cameron(horn arrange) David Wilczewski(sax)Andy
Snitzer(sax)
北欧はアイスランドのフュージョングループ「メゾフォルテ」の新作です。
80年代前半、シャカタクの「ナイトバーズ」のヒットにあやかろうと、日本のポリドールレコードが
本来芸風の異なる、このメゾフォルテやレベル42、ラ‐バンド、セカンドイメージ…などのバンドを十羽ひとからげにして「ブリティッシュ・ジャズ・ファンク」と銘打ち
プロモーションをして、そこそこ知名度があがりました。
国内でのディストリビュートは違いましたが、オランダのフュージョンバンド「フルーツケーキ」などというものも人気がありました。
が、このメゾは英国出身ではないですし、ラ‐バンドなどは、ジャズ~フュージョンと言うよりも「テクノ」としての色合いが強かったですし…
売り方としてはかなりいい加減というか強引でしたが、「ガーデン・パーティー」や「スプリング・フィーバー」などというヒットナンバーも生まれました。
「メゾフォルテ?」「そんな曲知らんわ」という人でも、TV番組などのBGMなんかで一度や二度は絶対に耳にしてるはずです。
80年代半ば以降は、フュージョンという音楽そのものが下火になり、シャカタクやレベル42など一部のバンドを除いてそのほとんどが活動を停止してしまった中、
このメゾフォルテは、ちゃんと活動を続けていたんですね。母国や英国よりも、ドイツやスイスでの人気が高く、そっちをメインに活動しているようです。
この新作、去年の5月~7月に作られたバリバリの新録。
私は未聴なんですが、90年代の末期に1枚出して以来の新譜となるようです。
その未聴の作品は、妙に陰鬱な作品で、メゾももう終ったか?と思うような出来だったそうですが、今作は80年代の「ポップ」なメゾが復活していて一安心。
もちろん、「ガーデン・パーティー」や「スプリング・フィーバー」の頃からは、25年近くも経っているんで、彼らのサウンドも随分大人にはなってますが、
「フュージョンっぽい」ヨハンのスラップベースや、ややレトロな感じもするシンセサイザーがリードする歌モノのようなメロディ、キレの良いホーンなどは健在、健在。
全体のサウンド的には、80年代末期に、LAのラリー・ウィリアムスやスティーヴ・タヴァローニなどをゲストに迎えて、アメリカのマーケット進出をねらった作品
「プレイング・フォー・タイム」をしっとりとさせたような雰囲気でしょうか。
80年代のメゾを思わせるような曲から、流行のスムースジャズテイストなもの、それに後半に収録されてるデヴィット・フォスター?というようなサウンドまで、
フュージョンファンなら、「小鼻がふくらむ」曲ばかりです。
今作も、アメリカからアンディ・スニッツァーや、チャック・ローブとの双頭ユニット「メトロ」のドイツ人ドラマー、ウルフガング・ハフナーを一部の曲でプロデューサーに迎えてるんで、
再びアメリカのフュージョン(スムースジャズ)マーケットを狙っているのかもしれません。
日本でも、ヤフオクなどでは、フルーツケーキのファースト作やセカンド作のCDが、信じられないような価格で落札されたりして、その流れで、このメゾやシャカタクなどが
ひそかにカルト的な盛り上がりを見せてる中、結構、タイムリーな新作の登場ですね。
(2005年1月24日)
Pat Metheny Group “The Way Up” (Nonesuch)
Pat Metheny:g,synth Lyle Mays:p,key Steve Rodby:b Cuong Vu:tp,voice George Maret:harm Antonio Sanchez:ds
ワーナーブラザースのジャズ部門閉鎖に伴い、WEA系のややアバンギャルドな音楽のリリースを行ってきた「ノンサッチ」へ横滑りしてきた
PMG待望の新作。余談ながら、ワーナー時代のレーベルメイトだったサックスのジョシュア・レッドマンもノンサッチへ移籍した様子。
今作は、「ザ・ウェイ・アップ」という1曲、68分10秒のみ収録。
(国内盤は、ボーナスセクションがある?というのだが、このようなきちんとしたコンセプチュアルなものにどのようにボーナスセクションを入れるのか?不明??)
一応、1.「オープニング」2.「パート・ワン」3.「パート・トゥ」4.「パート・スリー」とCDにインデックスが切れられてるものの、これはリスナーへの便宜的なサービスで
あくまでも、68分10秒、スルーで1曲、というのはパット自身が力説している。
タイトルは、世界が、特にパットの母国の合衆国がどんどん保守化、自己中心化して社会全体がどんどんと収縮の方向へと加速する中、未来はそんなんじゃダメなんだ、
どんどん高い所、崇高な場所へと登っていかなくてはならないんだ、というパットの想いが込められているという。
ま、ミュージシャンが政治的なことや宗教じみたことを言いだすと、なんかこう胡散臭さを感じて、もういいや・・・という気になるし、それを音楽と結びつけられた日にゃ~、
正直、聴く気が失せるなぁ。。。
とまぁ、聴く前は、あまり期待はしておらず、アマゾンco.jpで1580円ポッキリ、送料も1500円以上無料なんで、安いし聴いてみよかな?地雷でも被害は少ないし、みたいな。
で、聴いてみると・・・意外にもさらっと68分10秒経っちゃいました。
長時間で1曲、組曲、大仰なテーマとコンセプトという普通のリスナーなら、恐れをなして逃げ出しそうな雰囲気ですが、同じような展開が延々と続く訳でもなく、曲の雰囲気や
展開が普通のアルバムと同じくらいに変化があるので、組曲という感じがせず、普通の作品と同じように楽しめます。
全体的な雰囲気は、80年代のゲフィン時代以降のキャリアを総括したような感じで、結構、いい感じです。
アントニオ・サンチェスという稀有なリズムの良さを持つドラマーを得て、ビートが随分とシャープになってます。
「パート・トゥ」の途中で、パットのソロが4ビートになるパートがあるんですが、その辺なども特にカッコよく、超クール。
他のパートでも、ジャズっぽさを感じる箇所が、PMGのサウンドとしては結構、多いと思いますね。
複雑なリズムもいとも簡単にまた気持ちよく聴かせられるという点では、前任のポール・ワーティコも凄かったですが、サンチェスのドラムはそこに、躍動感とキレを
プラスした感じ、といって不自然にでしゃばることもなく、あくまでもPMGのサウンドの一部に溶け込んでいるんですから、さすがです。
サンチェスの他、打楽器奏者を参加させていないのも、彼ひとりで、超がつくほど複雑なポリリズムを叩きこなせるとパットが判断したからでしょう。
ここまで書いて、気がつきましたが、この大作を興味深く、また、楽しくスルーで聴けたのは、このサンチェスのリズムのおかげかも?しれません。
曲の雰囲気も、清涼感とストーリー感を感じるいかにもPMGという感じで、大仰な組曲やテーマなどを無視しても全然楽しめます。
いや~結構、このアルバム、気に入りました。
ゲフィン時代の「スティル・ライフ」や「レター・フロム・ホーム」以降は、正直なところ、PMGのアルバムで愛着のわくものはありませんでしたが、
久々にお気に入りのPMGのアルバムになりそうです。
作品全体に流れる「清涼感」「やすらぎ感」そして「躍動感」は、混沌としてドロドロと血生臭い現在の世相を1日も早くブレイクスルーして、その上のディメンションへと
登ってゆきたい、ゆかねばならない、というパットの強い想いの結晶なのでしょう。
(2005年1月28日)

John Tropea “Rock Candy”
(Video Arts)
John Tropea:g Anthony Jackson:el-b
Steve Gadd:ds Chris Palmaro:key
Lou Marini:as Dave Mann:ts
Ronnie Cuber:bs
Nicki Parrott:b
Clint de Ganon:ds
70年代よりN.Yのスタジオシーンで活躍するギター奏者ジョン・トロペイの新作。
リック・マロッタとガッドのツインドラムが炸裂する70年代中期の初リーダー作「トロペイ」や、ガッド=マロッタのツインドラムやウィル・リーらもイキまくりな
90年代に入って発掘された「7thアベニューサウス」でのライブ盤、また、80年代初期にDMPより出た「N.Y キャッツ・ダイレクト」などは、
ソリッドでグルーヴィーなN.Yフュージョンを聴きたい時には、しばしば、CDプレーヤーにのる佳作たちです。
で、本作は、アンソニー・ジャクソン=スティーヴ・ガッドという珠玉のリズムセクションを従えたトリオがメインだった前作「スタンダード・インフレンス」の続編的企画で、
タイトルどおり、今度はEW&Fの「ザッツ・ザ・ウェイ・オブ・ザ・ワールド」「アフター・ザ・ラブ・ハズ・ゴーン」バカラックの「ハウス・イズ・ノット・ア・ホーム」などの
R&Bクラシックスやジャック・マクダフの「ロック・キャンディ」、ロリンズの「セント・トーマス」、エリントンの「キャラバン」、ホレス・シルバーの「ソング・フォー・マイ・ファーザー」
マイルスの名演で有名なエディ・ハリスの「フリーダム・ジャズ・ダンス」などファンキーめなジャズなどを中心に選曲されてます。
つーことで、そんな曲をやるには、ギター=ベース=ドラムだけではちと音が薄すぎるだろう?と今回は、オルガンや3管編成のホーンも加えられたんですが、
そこがう~ん、なんというか微妙なんですなぁ。
実際のとこ、多くのファンは、トロペイ=アンソニー・ジャクソン=スティーヴ・ガッドのコアでソリッドなパフォーマンスを期待してると思うんですね。
ミシェル・ペトルチアーニ・トリオでの深い演奏までいかなくとも、70年代からの古い友人同士である3人のインティメイトな楽器での会話というか。
その辺が随分、前作に比べ、ぼやけて、みんなの知ってる曲を軽く弾き流しただけ、みたいな感じになってしまってます。
雰囲気的には、70年代初期の「CTI」のサウンド?。
その「CTI」には、ドン・セべスキーやディヴ・マシューズなんかのペンによる少々大袈裟なオーケストレーションが加わり、イージーリスニングやカクテルミュージックみたいな
味も出ていて、まぁ、それはそれで良かったんだけど、この作品には、そこまでの仕掛けはなく、ホーンやオルガンが加わってるのに、音の方がなんか薄くチープでスカスカ。
トロペイのギターが地味で別段個性的でもないサイドメンタイプなんで、ズバリ、もっと、ジャクソンやガッドを前に押し出して欲しかったんですよ。
晩年のミシェル・ペトルチアーニは、自分のピアノで、ジャクソン=ガッドのリズムを前に出したり引っ込めたりしながら、迫力のある新しいピアノトリオの形を創り出しましたが、
そのようなスケールの大きさやダイナミズムが全くないんですねぇ~、同じリズムセクションをメインに使いながら・・・。
まぁ、トロペイという人は決してバンドリーダー的な才能に長けてる訳じゃないんで、ペトと同じ役割を期待するのは酷かと思いますが、ならば、そこをプロデュースや
アレンジなんかでカバーして欲しかったですね。
本作の売りのひとつが、ガッドとの完全デュオによるエリントンの「キャラバン」なんですが・・・ギターとタイコのデュオですよ?そんなに面白いですか???。
リチャード・ティーとガッドのデュオは有名で、それにあやかってというものなのでしょうが、完全に企画倒れです。
とはいえ、ホーンのソロ回しがゴキゲンな1曲目の「ロック・キャンディ」や、アンソニーの微妙なベースの動きやフェンダーローズっぽいキーボードが心地いい
バラード「ハウス・イズ・ノット・ア・ホーム」など、気持ちよくカッコいい箇所もあるにはありますが、全体的には、やっぱり「いまいち君」?。
この次は、今作での汚名を挽回すべく、ホットなライブ盤でも作って、アンソニーやガッドをもっともっと暴れさせて欲しいものです。
(2005年1月28日)

Bobby Caldwell “Perfect Island Nights” (The Music Force Media Group)
Bobby Caldwell:vo,key.g Deniece Williams:duet on “Where is the love ?” etc・・・
90年代後半から最近まで、シナトラスタイルのジャズヴォーカルを志向していたボビー・コールドウェルが久々にAORへ戻ってきました。
CDジャケットやアルバムのタイトルからも分かるように、ややラテン的なムードもあり、
バーティー・ヒギンズの「カサブランカ」(郷ひろみが「哀愁のカサブランカ」として日本語カヴァーしたものの原曲)みたいな感じの曲もありますが、
マイナー調のメロディとフローティングしたコード感を上手く使った「ボビー節」ともいえる心地よいメロディーのAORド真ん中サウンドに一安心。
ダニー・ハサウェイ&ロバータ・フラックのデュエットで有名なR&Bクラシック「ホエア・イズ・ザ・ラブ」は、デニース・ウィリアムスとデュエット。
原曲のイメージを活かしたシンプルなカバー、デニースとのデュエットといえば、ジョニー・マティスが有名だけど、それに勝るとも劣らないなかなかの雰囲気。
ただし、デニースのハイトーンでキュートなヴォーカルはやや年老いた感じで、そこはちょい残念。。。
全体的には、80年代のボビーの名盤「ハート・オブ・マイン」をややウェットにして、ラテンのスパイスを隠し味にした感じ?。
個人的には、1曲目や2曲目のようなミディアム・テンポのメロウな「ボビー節」が光るナンバーや、5曲目に収録されてるフィル・ペリーのアルバムからのカヴァーで
ボサっぽいクールなタイトルトラックが特に気に入った。
ラストには、中村八大作、坂本九の名唱で有名な「上を向いて歩こう」を収録、温かみのある素直なカヴァーでエンディング前には、
「ウエヲムーイテー」という日本語を上手く活かしたコーラスアレンジが施されてるあたりはなかなかユニーク。
本人は凄くシナトラの影響を強く受けていて、フルバンドをバックにしたジャズヴォーカル作は、相当やりがいもあったようだけど、残念ながら、多くのボビーのファンが
期待するものとは少し遊離してように感じる。
しかし、この久々のAOR作で、長い間つのっていたファンのストレスも発散できたんじゃないかな?。
(2005年2月5日)

John “JR” Robinson “Funkshui” (Homecourt Records)
John “JR” Robinson:ds,key,perc,vo Paul Jackson,Jr. Ross Bolton Michael Thompson:g Neil Stubenhaus Lee Sklar Hussain Jifry:el-b
Jeff Lorber Aaron Zigman John Beasley David “Halk” Wolinski:key Dan Higgins Brandon Field David Boruff:sax Gary Grant:tp
Mark Williamson:vo ・・・
昔、エイベックスから「ジョン・ロビンソン」のアルバムが出た!?ということで、CD屋で調べてもらったところ、当時流行っていた「レイブ系」の
音楽をやる別人だった・・・という恥ずかしい経験をしたけど、これは、正真正銘、ドラマー、ジョン・ロビンソンの初リーダー作です。
彼の地でも、「ジョン・ロビンソン」という名前では、普通の名前で別人と間違われる?ということで、ミドルネームに「JR」が付けられてます。
チャカ・カーン&ルーファスの「マスター・ジャム」に参加してから、そのプロデューサーだったクインシー・ジョーンズに認められ、
クインシーの「愛のコリーダ」や、そのカバーツアーなどに参加、以来、LAのスタジオシーンにはなくてはならない存在のドラマーに。
ジャズ・フュージョン系のアルバムで、バリバリ叩きまくるというよりも、ベースのネイザン・イーストやニール・ステューベンハウスなどとのリズムセクションで、
デヴィット・フォスター制作の歌モノでのシュアな演奏の方が有名かも?。
知名度やキャリアの割りには数の少ないライブなJRのタイコを楽しめるジャズ・フュージョン系の名演としては
ラリー・カールトンのライブアルバム「ラスト・ナイト」がお薦め、エイブ・ラボリエルと組んで、ジャジーで渋いリズムを聴かせてくれてます。
さて、リーダー作では一体どんなことをやってるのか?凄く気になると思いますが、一言で言えば、ファンキーで少しロック風味なフュージョン。
JRのパワフルで歯切れの良いドラムをベースに、タワー・オブ・パワーみたいなザックリ感のあるトランペット=サックスのメロディが跳ねるような曲が多く、
セカンドラインのリズムからファンキー&グルーヴィーに曲が展開するホレス・シルヴァーのカヴァー「シスター・セイディ」は特にカッコいい。
また、ルーファス時代の同僚、”ホーク”ウォリンスキーもオルガンで参加してる故ジェフ・ポーカロが得意としていたようなブルージーでシャッフルビートな2曲目や、
ジェフ・ローバー色の強いグルーヴィーなフュージョンナンバーの6曲目などもカッコいい。
さすがドラマーのリーダー作ということで、ややドラムが前面にくるようにミックスされてるようですが、歌伴の超プロでもあるJRのタイコは、無駄な音がなく、
シンプルにリズムやグルーヴをキープするタイプなんで、違和感はありませんね。
むしろ、あの大きな体から繰り出されるタメの効いたスネアやズッシりと重みのあるベードラなど、JRのドラムの魅力がより強くアピールされているので、
地味な歌伴などのプレイが多く、もっとJRのタイコを聴きたい!というファンにはたまらないCDになってるのではないでしょうか。
そんなファンのためへの一番のプレゼントがラストに収録されてる完全ライブ録音のドラムソロ。
JRの力強く変幻自在な約12分半にも及ぶパワフルなソロパフォーマンスは、超一流スタジオドラマーを卒業したソロ・アーティスト、JRロビンソンを、
強くアピールするものではないでしょうか?。ヴィニー・カリウタ、何するものぞ!というくらいの凄さと迫力です。
ちなみにこのCDは、JRの自主制作のようなもので、彼の公式サイトhttp://www.johnjrrobinson.com/か、
オーディオファイルインポーツhttp://www.audiophileimports.com/ts4.php?id=1403で、入手可能です。
(2005年2月10日)

Scott Henderson “Live” (Tone Center)
Scott Henderson:g Kirk Covington:ds,vo John Humphrey:el-b
CDという狭い枠内ではなかなかその魅力が分かり辛いギタリスト、スコット・ヘンダーソンの新譜は、多くのファンが切望していたライブ盤、それも2枚組み、
そんでもって価格は1枚組みと同じ、というファンサービス満点の作品となってます。
トライバル・テックの盟友のベーシスト、ゲイリー・ウィリスが、故郷に戻ったとか?で、事実上、その活動が休止(一説によると解散)してる中、
前作のブルースアルバムと同じメンツによるライブ。
しかし、ブルース調のナンバーを延々と・・・みたいな雰囲気ではなく、ウネウネしたスコヘンお得意のちょいクレージーなフュージョンあり、
コヴィントンの歌をフィーチャーしたブルース・ロックなポップもの、それに、ウェイン・ショーターのナンバーをカヴァーしたジャズっぽい曲など、
バラエティ豊かな選曲で、トリオというシンプルな編成で2枚組みというヴォリュームながら、スコヘンのギターのファンなら、飽きることなく一気に楽しめるはず。
ゲイリー・ウィリスと組んでた演奏では、彼の細かいベースの動きに合わせるかのように細かくトリッキーだったスコ・ヘンのギターのフレーズも、
このライブでの演奏では、やや大らかになっている感じもしました。
このあたりは、近年、ブルース志向を強めて、一時のトリッキーなスタイルから少し距離を置いて、メロディを歌うことに重点を置いた方向性を反映したものなのでしょう。
ブルースをルーツに持ち、コンテンポラリーなジャズギタースタイルを作り出したパイオニアといえば、やはり、ジョン・スコフィールドの名前が頭に浮かびますが、
スコ・ヘンも、そろそろ彼の領域に接近しつつあることを、本ライブ盤を通して実感しました。
80年代のウェザーリポート解散後、ジョー・ザヴィヌルは、新しいバンド「ウェザーアップデイト」のために、まず、声をかけたのが、ジョン・スコフィールド、
マイルスバンドを脱退した直後で、自分の音楽性を優先したかったスコフィールドは、そのオファーを断り、その後、スティーヴ・カーンなどが一時的に参加したあと、
スコット・ヘンダーソンが、「ザヴィヌルシンジケート」と改名したユニットに参加し、かなりの間、ザヴィヌルと行動を共にしたという経歴だけに、
グラマビジョン時代のフュージョンなジョン・スコが好きだった、という人にも今一度、注目してもらいたい「変態系」ジャズギタリストです。
(2005年4月12日)
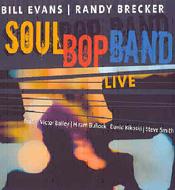
Randy Brecker / Bill Evans “Soul Bop Band Live” (BHM)
Randy Brecker:tp,vo Bill Evans:ts,ss David Kikoski:p,key Victor Bailey:el-b Steve Smith:ds Hiram Bullock:g.vo
ビクターからリリースされた国内盤がなぜか1枚組みとなっていて、納得できなかったので
わざわざ英国HMVより取り寄せたランディ・ブレッカー=ビル・エヴァンスの双頭ユニット「ソウルバップバンド」の2枚組みライブCD。
このライブCDは昨年の欧州~米国ツアー時のベストバウト集ですが、
実は、このバンド、一昨年に結成されて、ツアーも行っており、03年のライブソースを
映像と音の2通り持っているのですが、さすがライブCDとして発表する、というだけあって、
その時のバンドと較べて比較にならないほど、パワーアップ、特に、リズムのグルーヴ面で凄いことになってます。
03年は、コントラバス奏者の持ち替え楽器?という感じで、いまいちエレベの弱いクリス・ミン・ドーキーがベースで、
本人も他のメンツもそれを知ってか、コントラバスを弾いてるシーンが多かったですが、04年バンドでは、ビクター・ベイリーが参加!!
これが、04年バンド、最大の勝因です。
また、ドラマーも、03年のジョナサン・ジョセフからスティーヴ・スミスにチェンジ。
ステップスアヘッドに参加してた80年代とは別人??と思わせるしなやかなウネリ感のあるドラムとビックのベースとの相性もバッチリ。
このリズム、マジでグルーヴィーにウネリまくってます。
昨年、来日したリユニオン版ステップス・アヘッドは、スティーヴ・ガッド=ダリル・ジョーンズといういまいちしっくりこないものでしたが、
今こそ、このベイリー=スミスのリズムを再び使うべきしょう。
ギターには、ストーン・アライアンスやアダム・ホルツマンのバンドに参加してたミッチ・ステインに代って、ハイラム・ブーロックが参加。
これも、当然の如く、大正解。
彼の歌をフィーチャーした曲が2曲あり、ハイラムの一人舞台的なムードになるかと思いきや?
ハイラムも上手く自分の芸風をコントロールし、ソウルバップバンドのサウンドの中に溶け込ませてます。
ハイラムといえば、ウィルのベースなど、タテにグルーヴするリズムと共演することが多く、ノリが一本調子になることも少なくなかったですが、
ベイリー=スミスの横に揺れるリズムとのコンビで、クールにファンクする新たなハイラムの魅力が浮き彫りになった感じです。
純ジャズからこのようなファンク系フュージョンまで何でもこなすランディお抱えピアニスト、ディヴ・キコスキも03年よりもパワーアップしてます。
03年から参加してるキコスキですが、安っぽいシンセの音色を多用していた03年から一転、04年バンドでは、彼のメインであるピアノを多用し、
そのソリッドでファンキーなピアノは、スティングバンド時のケニー・カークランド?!と思わせるほどカッコいいです。
リーダーのランディとコ・リーダーのビルも、03年では、フロントラインに参加していたバリサクのロニー・キューバーとともに、
バンドの盛り上げ役を一手に引き受けていたため、演奏にいまいち集中してない感じもしましたが、04年バンドでは、芸達者なハイラムや
シュアなベイリー=スミスという新加入のメンバーを得て、演奏にタイトさが増してよりカッコよくなってます。
蛇足ながら、国内盤がなぜ2枚組みではなく、1枚組みに編集されたか?の件ですが、
1枚目が50分ちょい、2枚目が45分ちょいの収録時間なので、おそらく、これなら、2枚組み12曲から3曲削って1枚組9曲にすれば、
コストも下げられるんで、たくさん売れるんじゃない?という理由からだと思われます。
しかし、2枚組みの輸入盤にしか入ってない、「ソウルバップ」「クール・エディ」(おそらくエディ・ハリスにトリビュートしたもの?)
ランディのリーダー作からの「ハンギン・イン・ザ・シティ」(ブレッカーズの「ドント・ゲット・ファニー・ウィズ・マイ・マネー」みたいな下手ウマヴォーカルが楽しめます)
という3曲も素晴らしいものなので、少々高くともファンはやはり輸入盤の2枚組みを入手されることをお薦めします。
ところが、ビクターの陰謀なのか?欧州からの輸入盤のコストが高いからなのか、
アマゾンやタワーでは扱ってないんですね。
日本のHMVのサイトでは扱っており、2週間以内に発送?らしいのですが、欧州盤、南米盤などは、問屋の在庫が無くなり、
当分入荷の予定がなしで入手困難になるケースも多々あるので、国内サイトで購入する際は気をつけたほうがいいと思います。
おそらく、いずれは、米国盤でも発売されるでしょうから、そのときは2枚組みでも安価で入手できるでしょうが。
(2005年4月12日)

吉田美奈子 “Lightin Up” (Alfa~SME)
吉田美奈子:vo,p 佐藤博 富樫春生:key 松木恒秀 土方隆行:g 岡沢章:el-b.vo 渡嘉敷祐一:ds David Sanborn:as solo Michael Brecker:ts
solo
Randy Brecker Jon Faddis:tp Ronnie Cuber:bs 山下達郎:cho ・・・
待望の再CD化となった吉田美奈子の名作「ライトゥン・アップ」ですが、「リマスター」との情報はガセでアルファ時代のマスターと同じようでした・・・。
なんで、現在の水準で聞くと、いまいち、音の分離が悪いですが、昔の音源を妙にハイファイにしても
「あの頃」の雰囲気が出ず妙な違和感を覚えるケースも少なくないので、これはこれでよしとしましょう。
個人的イメージとしては、達郎の「ライド・オン・タイム」とこの作品が何かこう「にこいち」のような感じがしていたんですが、
15年ぶりくらいに、これを聴いて改めて「やっぱり」でした。
その理由は、やはり、1曲目のタイトルソングのムードが、「ライド・オン・タイム」なんですね。
そこでの、サンボーンのソロがやっぱりとにかく、とにかく、素晴らしい!!!
ここまでメロウに歌いながら、うねりまくるサンボーンのアルトソロはそう聴けるものではありません。
2曲目のデヴィット・フォスター風味のミディアムAORな「頬に夜の灯」とその1曲目が、やっぱりこの作品のハイライトでしょう。
ここでもサンボーンのアルトがオブリガードでボーカルに寄り添ってます。
1~2曲目のサンボーンのソロを聴くだけで、本作を購入しても、サンボーンファンなら損はないと思いますね。
いや~いくつになっても、この頃のこのサウンドを聴くと、「もう骨抜き」状態です・・・。
都会的なミディアムスロウなデュエットナンバー「風」イントロでの、マイケル・ブレッカーのテナーソロも、ビルの谷間に吹くクールな風という雰囲気で超カッコいい!。
デュエット相手、ベースの岡沢章さんのヴォーカルもいかしてますね。(岡沢さんってこんなに歌上手かったかなぁ??)
アルバム全編、その岡沢さんと渡嘉敷祐一さんのドラムという今は亡きコルゲン鈴木氏率いたプレイヤーズ
のリズムなんですが、当時のスティーヴ・ガッド=アンソニー・ジャクソン(もしくはウィル・リー)なんかと比較しても全然負けてないタイトなグルーヴで
これまた素晴らしい。日本のエリック・ゲイルと呼ばれた松木恒秀さんのギターもリズムで渋い渋い渋い。
まともで上質な音楽が「お洒落」だった時代の歴史に残る名盤ということを15年ぶりくらいに改めて聴いて再認識させられました。
もうこんな時代はこないんだろうなぁ・・・。
世界的に見ても、これほど、クオリティの高いレア・グルーヴ~AOR作品はそうないと思いますので、特に、本物の音楽を愛する若い世代の人達には
是非是非、聴いてもらいたいですね。
(2005年4月12日)

Jeff Babko “Jeff Babko Broject featuring Toss Panos” (Let’s Music Recordings)
Jeff Babko:key David "Fuze" Fiuczynski, Toshi Yanagi:guitar-(three tracks each) Michael Landau, guitar-(two tracks) Albert Wing:sax
John Daversa:trumpet Mike Elizondo:electric bass Dan Lutz, Dean Taba:acoustic bass Toss Panos:drums
Simon Phillips:loops, percussion, programming
随分前にオーディオファイルインポーツにオーダーしていたものですが、在庫切れとかで数ヶ月放置プレイ、ですっかり忘れかけていたところに、
先日、ひょこっと、郵便ポストに入ってました。
なんで、聴く前は、正直、もーどーでもいい感じで、軽い気分で、聴き始めましたが…あまりのカッコよさに、軽い気分で聞き流せず、じっくりと聴きこんでしまいました。
ジェフ・バブコという人は、1972年LA生まれの白人ピアニスト/キーボード奏者、ウィル・リーを初めとする多くにプロミュージシャンを輩出したマイアミ大学を卒業後、
今作にも参加してるべース奏者マイク・エリゾンドとバンドを結成し、LAで活動していたが当然ながら、泣かず飛ばずの状態・・・、
そんな中、ラテンポップスの超大物フリオ・イグレシアスのツアーバンドに参加し、その辺から「ツキ」が回って来はじめる。
ミッチェル・フォアマンがバンドから抜けてしまい、後任のキーボード弾き誰に?と思案していたサイモン・フィリップスから、お声がかかり、一度のオーディションで
一発採用、その後、サイモンのバンドだけでなく、彼の参加しているTOTOにも、スタジオ・ワーク多忙のデヴィット・ペイチの「トラ」として参加するなど、
一躍、LAのスタジオシーンのファーストコールとなりました。
2000年には、「ヴァンテージ・ポイント」というサイモンとのダブルネームによるアコースティック・ジャズ作をリリースしていますが、
ジェフ・バブコ単独の作品としてはこれが最初かと思います。
のっけから10分以上にも及ぶファンキーなグルーヴチューンが登場!!「叫ぶ首なし胴体」のフューズのグシャングシャンのリズムギターやソロも大活躍ですが、
なんといってもカッコいいのが、「フィーチャリング」扱いとなっているトス・パノスのドラム。
フランク・ザッパやスティーヴ・ヴァイとの活動を経て、マイク・ランドゥやデヴィット・ガーフィールドのカリズマに参加という経歴をもつトス・パノス
![The Way Up [FROM US] [IMPORT]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B0006M4SO6.01.LZZZZZZZ.jpg)