|

|
|
70s Jazz Pioneers "Live at The Town Hall,NYC" |
|
半年ほど前に、ジャズ雑誌の輸入盤レビューで発見し、その面子を見て、「これは良さそうだぞ。」と思いCDを探したものの入手出来なかった70s Jazz Pioneersというプロジェクトの作品が、8月27日にキング・レコードより国内盤リリースされました。
このプロジェクトは、その名の通り、70年代から活躍するジャズメン/ウーマンが集い、60年代~70年代のジャズの名曲を振り返ろうというものです。メンバーは、ランディ・ブレッカー(tp)バスター・ウィリアムス(b)ジョアン・ブラッキーン(p)ディヴ・リーヴマン(sax)パット・マルティーノ(g)アル・フォスター(ds)で、1938年産まれのブラッキーンを除いて、他のメンバーは1942年~46年産まれというほぼ同世代のミュージシャンという訳です。(ブラッキーンが一番年長というのは少し意外でした。)
演奏されているナンバーも、「カンタロープ・アイランド」「シュガー」「レッド・クレイ」というジャズ・ロックっぽいものから「オール・ブルース」「フット・プリンツ」などの50年代~60年代
のジャズ・メン・スタンダード、また、リターン・トゥ・フォーエヴァーの「500マイル・ハイ」スタンダードの「朝日のごとく爽やかに」とバラエティ豊かなもので、この面子がどんな風に料理しているのか興味をそそるナンバーが揃っています。
この作品はタイトル通り、1998年3月20日NYのタウン・ホールで収録されたライブ・アルバムということで、さぞ、熱いサウンドかと思う方もいらっしゃるかと思いますが、意外にもあっさりとしたもので、唯一ソプラノサックスで演奏するディヴ・リーヴマンが、いつもながらアグレッシヴにシャウトしているだけです。
やはりこの手の企画モノっぽいプロジェクトは1回限りのものがほとんどで、これだけのツワモノ達が本気でやりあうには、それなりの時間やリーダーとなる人などが必要なはずで、その準備もほとんどなさそうなこの作品では、正直あいさつ程度の軽い演奏に終わっています。また、ギターとピアノというコード楽器が2つもあるこの編成では、自由なインプロビゼーションがとりにくいという面もあり、それがまた演奏のスケールを小さくしている要因みたいです。
CDの帯には「パット・マルティーノの参加が光る!!」とデカデカと書かれていますが、これを書いた人にどこが光ってるのか尋ねてみたいくらい、マルティーノも普通です。逆に本当に光っているのは、やはりリーヴマンと、派手さは無いものの貫禄すら感じる堂々としたプレイのランディ・ブレッカーで、この2人のからみは、スリルの気薄な今作のハイライトの一つです。
まぁクロスオーヴァー全盛の70年代にしこしことジャズ・シーンを支えた人(特に超不遇な時代のアート・ブレイキーのジャズ・メッセンジャーズのピアニストだったブラッキーンなど)にスポットを当てることは良いことだとおもいますが、もう少しはじけて欲しかったです。面子が面子だけに残念な1枚です。
9.2 Update |
|
★★★ |
|

|
|
Gerald Veasley "Love Letters" |
|
グローヴァー・ワシントンJr.のサポートメンバーをやったかと思えば、ドラマーのコーネル・ロチェスターと組んでちょっぴりラディカルな音楽をやったり、コーネル・ロチェスターとともにザヴィヌル・シンジケートに参加したりと、ベース1本片手に「何でもやりまっせ~」といわんばかりの活躍を続けるグローヴァーと同じフィラデルフィア出身のベーシスト,ジェラルド・ヴィーズリー。
このヴィーズリーのソロ4枚目となるニューCD「ラブ・レターズ」が新進ジャズ・レーベルHead Upより到着しました。
本当に多彩な活動を続けるヴィーズリーですが、彼名義のソロ作となると、一貫して6弦ベースがキャッチーなメロディを奏でるフュージョン/スムース・ジャズ作となっています。
この新作でも心地の良いグルーヴにのせたスムース・ジャズ作となっており、アグレッシヴなバカテク・ベーシストとしての側面は、メロディアスなソロの中で垣間見る以外、ほとんど顔をだしません。しかし、ベーシストのソロ・アルバムということを意識させない自然なサウンド作りは見事なものです。同じHeads Upからリリースしているファースト~サードまでは、結構ソウルっぽさを残したフュージョン作だったのですが、今作では、こざっぱりとしたCDジャケット同様、アコーステック・ギターをフィーチャーしたりとかなり爽やかなサウンドとなっています。
ゲストには、グローヴァー・ワシントンJr.エリック・マリエンサル、それにヴィーズリーも参加していたスペシャルEFXのキエリ・ミヌッチなどが参加しています。
本作の聴きどころのひとつは、3曲目に収録されているダニー・ハサウェイのインスト・ナンバーのカヴァー「ヴァルデス・イン・ザ・カントリー」で、グローバーのメロウなサックスとヴィーズリーの心地よい共演を楽しむことが出来ます。
またこのCDはMac/WINのPCに対応したエンハンストCDとなっており、PCでジェラルドのバイオやディスコ・グラフィー、それに、ライブ演奏なんかも楽しめる作品となっています。
さりげないグルーヴが心地よい上質なスムース・ジャズ。
9.5 Update |
|
★★★☆ |
|

|
|
Philippe Saisse "Halfway 'Til Dawn" |
|
イメージ的には、プロデューサーやサウンド・クリエーターとしての方が強いフランスはマルセイユ出身のキーボード奏者フィリップ・セスの5枚目のリーダー作「ハーフウェイ・ティル・ドーン」が日本盤先行リリースされました。
チャカ・カーンなどのプロデュース作品では、テクノロジーを活かした近未来的なエレクトリック・サウンドを聴かせてくれるフィリップですが、彼自身のソロ・アルバムとなると、本当に美しいアコーステック・ピアノを全編にフィーチャーしたもので、特に1988年にリリースされた初ソロ作「ヴァレリアン」のナチュラルでブリリアントなサウンドは特筆すべきものがありました。
基本的なコンセプトはファースト作の「ヴァレリアン」以来そんなに変化していないのですが、94年作の「ドリーム・キャッチャー」あたりから、プログラムのドラムとアコーステック・ベースを組み合わせたヒップ・ホップ風のグルーヴィーなリズムに、クリスタルなピアノ・ソロがのっかかるという作風に変わってきたようです。これもプロデューサーとして、時代の空気を読んでの変化なのでしょう。
さて今作ですが、94年の「ドリーム・キャッチャー」97年の「ネクスト・ヴォエッジ」の流れを引き継いだものですが、いい意味ではポップに、凄く意地悪く言えば、凡庸になってきています。フィリップのソロ作の魅力は、ニューエイジ・ミュージックとジャズ、フュージョンとが交錯するアンビエントなサウンドであったと思うのですが、特に今作でははっきりとスムース・ジャズにカテゴライズされるものになっています。一般的には聴きやすくなっていいとは思うのですが…。
また今作には、アフリカ出身のシンガー、アンジェリーク・キジョーとリチャード・ボナが参加して、ちょっとしたエスニックなアクセントを加えていますが、それをフィリップは、自分の音楽の中に上手く採り込んでいます。その他には、ジェフ・ゴルブ(g)ロン・ジェンキンス(el‐b)クリス・ミン・ドーキー(ac‐b)クリス・ハンター、アンディ・スニッツァー(sax)ジェフ・ビール(tp)らが参加しています。
フィリップ・セス プロデュースのポップ作品の雰囲気に近くなった、ピアノによるスムース・ジャズ。やっぱり、このピアノの美しさと個性は、ジャンルの差はあろうかと思いますが、あのジョー・サンプルに勝るとも劣らないと思います。
9.11
Update |
|
★★★☆ |
|
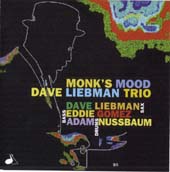
|
|
Dave Liebman "Monk's Mood" |
|
最近アーケイディア・レーベルからを中心にリリースが続いているディヴ・リーヴマンですが、このほどDouble Time・レーベルより、噂されていたリーヴマンによるモンク集「モンクス・ムード」がリリースされました。
演奏はサックス・トリオで、ディヴ・リーヴマン(ts.ss)エディ・ゴメス(b)アダム・ナスバウム(ds)のメンバーとなっています。
リーブマンのテナートリオといえば、フランスのOwl盤に、エディ・ゴメス(b)とボブ・モーゼス(ds)を従えた作品があり、こちらの方はかなりアブストラクトでアグレッシヴなものでした。それに対し、今回のトリオ作品は、モンクがテーマということもあり、かなり正統派なジャズとなっています。しかし、正統派といっても、そこはリーヴマンがやるモンク・ナンバーですから、一筋縄ではいきません。リズムやアレンジに奇を衒うのではなく、テナーとソプラノを使い分けたリーヴマンのサックスのアドリブで、「モンクス・ムード」「パノニカ」「アグリー・ビューティー」などモンク・チューンをユニークな解釈で楽しませてくれます。特に、長期間封印していたテナーサックスが、ここに来て絶好調といった感じです。
また、エディ・ゴメスのベースも素晴らしく、特にバラードでのサポートは、コード感溢れるイマジネイティヴなサウンドを聴かせてくれます。お互いを理解しあった仲でなければ出来ないようなインティメイトなプレイです。
最近は、パット・メセニーとの共演や、ラテン作などリーヴマンの魅力を100%活かしてるとは言い難い企画ものの作品が多かったように思いますが、今作は久々にリーヴマンのサックス奏者としての今の姿を確実にとらえた好盤となっています。ディヴ・リーブマンというコルトレーン派のサックス奏者の底力を改めて実感させられることでしょう。
9.11 Update |
|
★★★★ |
|
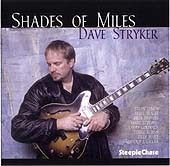
|
|
Dave Stryker "Blue To The Born" |
|
1991年にリリースされた「ストライク・ゾーン」というスティープル・チェイスからリリースされたアルバムを聴いて以来、マイ・ブーム(古い?)が続いているギタリスト、ディヴ・ストライカーの新作がスティープル・チェイスからリリースされてました。
1957年ネブラスカ産まれのストライカーは、ロックに夢中になる傍ら、ジョージ・ベンソンやジョン・コルトレーンにも影響を受け、ジャズ・ギタリストとしての道を歩みはじめました。ネブラスカからLAへ移り、クルセイダースにも参加していたギタリスト、ビリー・ロジャースに師事し、その後NYへ進出。ロニー・リストン・スミスやフレディ・ハバード、スタンリー・タレンタインなどとの共演を経て、リーダーアルバムを作るまでに成長しました。
何か安物のライナー・ノーツみたいな経歴紹介となってしまいましたが、彼のギターは、その経歴そのままの音がしているんです。彼のベーシックな素地はやはりロックとブルースやR&Bなので、ジャズ屋さん的な過剰なテクニック志向や神経質さが無く、豪快にそのグルーヴやリズムに身を任せたようにソロをとる姿は、若き日のジョン・スコフィールドを思わせるものがあります。程よくディストーションを効かせたうねるようなギターはホントかっこいいです。
さて今作ですが、タイトルから想像できるとおりのブルースにスポットを当てたもので、3年ほど前にリリースした同じような企画盤の続編となっています。とはいってもそんなに「コテコテ」じゃないのでご安心を…。メンバーは、ストライカーの盟友、スティーヴ・スレイグル(sax)ブライアン・リンチ(Tp)を始めとするホーンに、ブルース・バース(p,org)ジェイ・アンダーソン(b)アダム・ナスバウム(ds)というリズム・セクションを従えたもので、大きな編成ながら、ブルージーでファンキーなジャム・セッション的な雰囲気が伝わるものとなっています。特にジャズ・メッセンジャーズ最後のトランペッター、ブライアン・リンチとスティーヴ・スレイグルがいいソロを聴かせてくれています。3曲目のニューオリンズ・ファンク風の8ビートのファンキーなナンバーが、ストライカーというギタリストの魅力を一番ストレートに伝えるナンバーだと思います。
ウェス風、パット・マルティーノ風、ケニー・バレル風など、ジャズ・ギター界には結構生真面目な「一筋さん」が多いような気がしますが、このストライカーのような不良っぽいスタイルのギタリストは貴重だと思います。ちょっと斜に構えたカッコイイ、ジャズ・ギタリストをお探しの方は、このディヴ・ストライカーという名前は覚えておいて損は無いと思います。
9.11 Update |
|
★★★★ |
|

|
|
Tom Harrell "Time's Mirror" |
|
今やベテランの域に入った感のある人気トランペッター、トム・ハレルのBMG Classicレーベル移籍3作目にあたる新作「タイムス・ミラー」がリリースされました。
BMG Classicに移籍後の作品は、前作(97年)を含めてコンセプトにこだわった企画ものが多く、彼の温かみとクールさを併せ持ったトランペット&フリューゲルを堪能できる作品は正直ありませんでした。
今作もトム・ハレルとしては初の試みとなるビッグバンド・スタイルによるもので、店頭でCDを手に取った瞬間は嫌な予感がしました。アレンジャーや作曲家としても優れた才能を持つハレルだけに、凝ったコンポーズや頭でっかちなアレンジの妙を聴かせる作品だったら、嫌だなという心境でした。
サックスにマーク・グロス、アレックス・フォスター、ドン・ブレイデン、トランペットにアール・ガードナー、ジョー・マグナレリ、トロンボーンにコンラッド・ハーヴィッグらが中心となったホーンセクションに、ザヴィアー・ディヴィス(p)ケニー・ディヴィス(b)カール・アレン(ds)というリズム・セクションが加わったビッグ・バンド形式で、プロデュースはボブ・ベルデンとなっています。
収録曲は、コンポーズも得意なジャズ・メンだけに、ハレルのオリジナル中心ながら、「枯葉」や「チェイシン・ザ・バード」などのスタンダードも収録されています。
トム・ハレル初のビッグ・バンドですが、奇を衒ったものではなく、至極常識的なサウンドとなっています。NYを中心に長年に渡ってビッグ・バンドを運営し続けるテナー奏者ボブ・ミンツァーのビッグ・バンドを思わせるもので、ハレルのソロ以外にも、サックスやピアノのソロなども多くフィーチャーされています。また木管楽器の使い方やハーモニーなどは、ギル・エヴァンスの影響もあるのかなと思います。
常識的過ぎて、アクの部分が少ないかなという気もしますが、ハレルのイノセントなトランペット&フリューゲルを理想的なフルバンドの中で活かしきった作品として聴けばかなりのポイントとなるものだと思います。
でもバリバリやってくれるハレルがやっぱり好きなので、次作は是非、ワンホーンカルテットもしくは、サックス入りのクインテットで、フィル・ウッズ時代みたいな勢いのある作品を希望します。
余談ながら私のマイベスト作品は、82年のブラックホーク盤「プレイ・オブ・ライト」です。エイズで死んだピアニスト、アルバート・デイリーと、バリバリのハレルが印象的な作品です。中古屋で見かけたら一度聴いてみてください。
9.18 Update |
|
★★★☆ |
|

|
|
Mike Stern "Play" |
|
81年のマイルス復活時のレギュラーギタリストとして鮮烈なデビューを果たしたマイク・スターンの新作「プレイ」がリリースされました。(マイルス時代はヘヴィ・メタルのイモ野郎などとも揶揄されもしましたが…)
幻の名盤と化した83年のトリオ盤「ニーシュ」から、早くも10枚目となったこのソロ作品ですが、プロデュースはマイクとも交流の深い、NYのコンテンポラリー・ジャズ界の頭脳的存在であるキーボード奏者のジム・ベアード。サポート・メンバーもベアード(key)リンカーン・ゴーインズ(b)ベン・ペロウスキー、デニス・チェンバース(ds)ボブ・マラック(sax)とおなじみのメンバーが名前を連ねてます。
そして今回の大きなポイントは、このメンバーに、ジョン・スコフィールドとビル・フリゼールというコンテンポラリー・ジャズ界の人気ギタリストが参加しているということです。
全体の雰囲気は、従来のスターンのソロ作品を踏襲したものとなっていますが、2人の空間を生かすタイプのギタリストのゲスト参加により、スターンのギターにも変化が現れているようです。
今までのスターンのソロは、前ノリの感覚で譜面を埋め尽くすような感じだったものが、スコフィールドとフリゼールとの共演により、スターンも間を生かしたアドリブの展開になっているように思います。最初はノンディストーションでジャジーなフレーズを連発し、盛り上がればディストーションオンでロック全開で果てて行く…というお決まりのパターンに飽きが来ていただけに、このスターンの変化は歓迎すべきことだと思います。また、空間を活かすことによりスターンのギターにも勢いと迫力が増した感じもします。
スコフィールドとフリゼ‐ルという2人のギタリストとスターンの関係ですが、スコフィールドとはもちろんマイルス・バンドの同僚で、83年の「スターピープル」でも共演していました。ごく短期間だったようですが、スコフィールド/スターンというツインギターによるマイルス・バンドも存在していたようです。またフリゼールとの関係ですが、ジム・ホールに多大な影響を受けたもの同志といった関係でしょうか?。ジムのアルバムには、別々ですが2人の参加した作品があります。
そのゲストのプレイですが、スコフィールドは余裕のパフォーマンスで、スターンと軽く同窓会といった感じですが、意外と面白かったのが、フリゼールです。特に面白かったのは、アルバムラストのちょっとファンクっぽいトラックにも参加していて、スターンのソリッドなディストーションサウンドに、いつもの軟体動物のようなソロで応酬しています。スコフィールドは3曲、フリゼールは4曲参加しており、残念ながら3人の共演はありません。
最近のスターンのリーダー作にはマンネリを感じていたファンも、結構多かったのではないかと思いますが、そんなファンにもお薦めできるちょっと新鮮なスターンが聴ける1枚です。ここ数作の中では、ベストな出来のソロ作ではないかと思います。最近この手のソリッドなコンテンポラリー・ジャズに飢えていたTには、当分お気に入りの1枚になりそうです。
9.21 Update |
|
★★★★ |