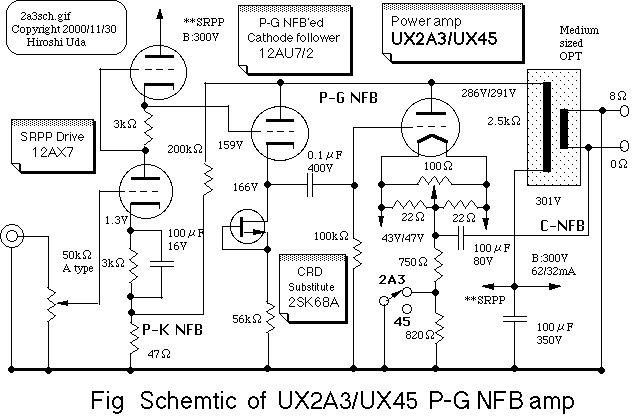
目次 (二分割しました。 本文は前半です。)
第一部 動作原理および総論 (本文です)
1 始めに
1.1 超三結アンプ事始め (小改訂)
1.2 本文の記述および改訂経過 (小改訂)
1.3 超三結 V1 の定義 rev4.0 改訂部分
1.4 回路動作の詳細 rev4.3 改訂部分
1.5 ストッピング・ダイオードとリニアライザ
1.6 超三結アンプのバリエーションとスピーカ対応
1.7 超三結アンプの再現性および信頼性の課題 rev4.3 改訂部分
第二部 実装と調整 (後半です。クリック願います)
2 実験の過程、結果および考察
2.1 製作・実験例
2.2 結果の評価
2.3 多極管への適用
2.4 三極管への適用
3 調整法と課題
3.1 終段のバイアス調整法
3.2 回路上の問題点
3.3 バイアスが深い場合の前段への配慮
3.4 初段回路〜電圧帰還管回路の組み合わせと P-K NFB 併用の課題
3.5 三極管超三結アンプの再検討と工夫余地 rev4.1 改訂部分
その後、筆者が製作した超三結アンプのプロトタイプは、比較試験の結果すべて上條氏の定義による超三結バージョン1(以下超三結 V1、または単に V1) 回路を基本としました。 また、筆者は色々な球について超三結 V1 アンプの試作を続け、課題の発掘と解決法を模索してきました。
上條信一氏の記事、および V1 と V3 との相違等については上條氏のホームページ http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/index.htm
をご参照ください。
●本文の性格の推移
筆者が初期に考えた本文の記述内容は、上條氏の発案、設計、実装された超三結アンプの「追試験版」でした。 その後実験がエスカレートし「いかなる球でも超三結アンプとして動作可能の筈、確認する」を目標に本文のタイトルを「超三極管接続回路方式によるアンプの実装法考察」に変更しました。(1999/2 Rev2)
●本文を読まれる方に
以下の説明は、真空管の「三定数」および「Eb-Ib 静特性曲線」等の予備知識を保持されていることを前提としています。 また
NFB (Negative Feed Back:負帰還) および SRPP (Shunt Regulated Push-Pull
circuit) 等の回路動作原理についても適宜、関係の教科書を参照して下さい。 教科書としては例えば、
一木典吉氏著「全日本真空管マニュアル」ラジオ技術全書002A ラジオ技術社 および
武末数馬氏著「パワーアンプの設計と製作」ラジオ技術全書011A ラジオ技術社 を挙げておきます。(1999/4 Rev3)
●メイジャー・チェンジ 本文については何人もの読者から何度も「難解である」とのご意見を頂戴していました。 昨年来、ある変形回路を実験して効果を得、説明しやすい中間的な回路でもあったので 2001/4/30 (rev3.11) 改訂に含め、今回は更に再編成して前半をメイジャー・チェンジしました。(2001/5/31 rev4.0)
なお、上記の三項目以外のマイナーな改訂関連情報は、冗長なため本文末尾の改訂記録に移動しました。(2001/12/31 rev4.2)
(1)回路形式名称:P-G NFB 併用 カソードフォロワ・ドライブ回路
→{英} P-G NFB jointed cathode follower driven circuit
超三結分類名称:準 超三結 V1 回路 →{英} Semi-STC V1 circuit
・・・説明上の都合により(超三結 V1) 原形回路とも称する。 →{英} Original circuit
・・・理解しておくと(2)の理解が大変楽になる、実用例もある回路。
・・・上條氏の解説には現われなかったので「準」がつきます。
(2)回路形式名称:P-G NFB 併用 倒立μ フォロワ・ドライブ回路
→{英} P-G NFB jointed inverted Mu follower driven circuit
超三結分類名称:純 超三結 V1 回路
→{英} (Pure-) STC V1 circuit
・・・上條氏の解説に最初に現われたもので「純」です。
(2.1)これに含まれる回路とその名称 (1) (超三結 V1) 動作原理回路
→{英} Theoretical (STC V1) circuit
・・・下記の(2.2)実用回路に先だって理解を要する中間的回路。
(2.2)これに含まれる回路とその名称 (2) (超三結 V1) 実用回路
→{英} Practical (STC V1) circuit
・・・コスト・パフォーマンスの高い、筆者の試作例に大幅に適用した回路。
上記の中から、特に製作しやすいと考えられる 原形回路 および 実用回路 について、以下に回路図を示します。
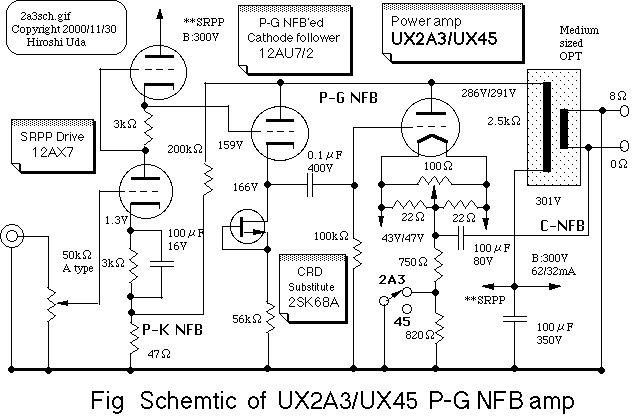
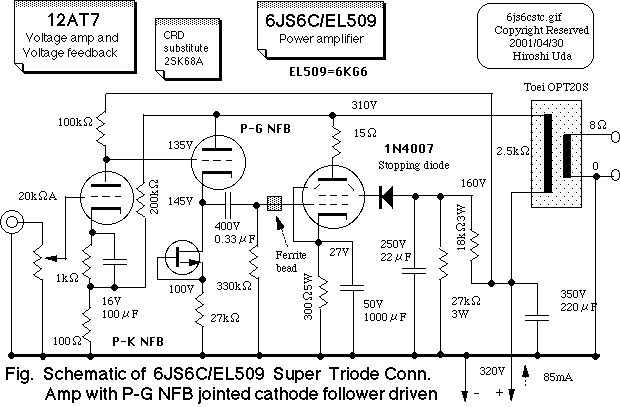
上記の回路では、実装の都合上 C/R 結合を利用しています。 直結化は不可能ではありませんが、高い B 電源電圧が必要となります。 回路構成が前記の原形回路であり、便宜上の別名としては「準」超三結です。
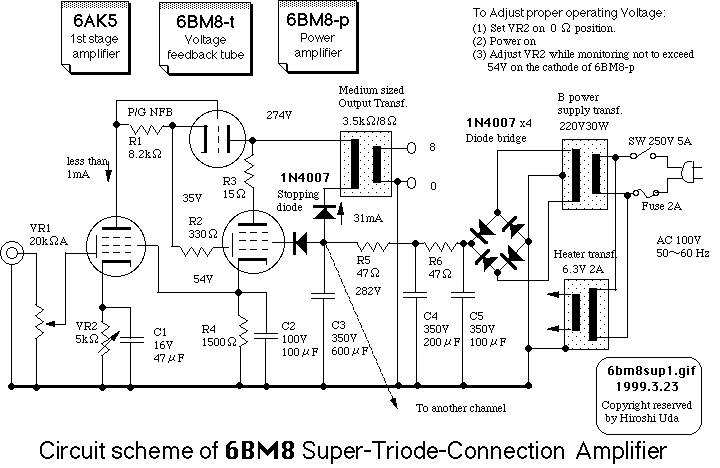
(1) まず原形回路である 準 超三結 V1
回路 にて基本動作を理解し、
(2) つぎに原形回路との関連性を考慮しながら、次のステップである
純 超三結 V1 回路を、動作原理回路として理解し、
(3) つぎに更に動作は複雑な、しかし回路は簡単で実装に適した実用回路を動作原理回路との関連性をもって理解する。
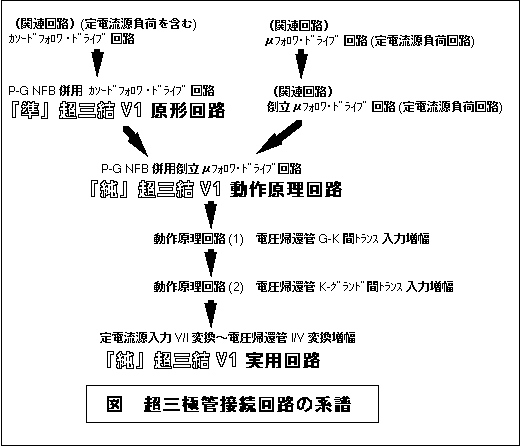
(1) 定電流源を併用する非直線素子を含む深い NFB 回路構成
(2) NFB ループに出力トランスを含めない
(3) 直結回路の原則
(4) ストッピング・ダイオードおよびリニアライザ
各段の回路の名称と機能分担を、順序が逆になりますが「1.3.1.2 実用回路」にて示した標準的な実用回路図にしたがって逐次説明します。
(A) 初段管 :図1 6AK5
入力信号電圧の電流変換 (V/I 変換) 、定電流源、電圧帰還管の負荷、
および NFB 回路分圧素子として動作する。
(B) 電圧帰還管:図1 6BM8 の三極管部
信号電流の電圧変換 (I/V 変換) および電圧増幅、終段のドライバー、
および非直線 NFB 回路分圧素子として動作する。
(C) 終段出力管:図1 6BM8 の五極管部
電圧増幅を抑制した電力増幅を行う。
(D) ダイオード:図1 6BM8 の右側
出力トランスの B 電源側および出力管のスクリーン・グリッド
に挿入され、 B 電源からの直流電圧供給機能を正常に保つ。
なお、本文中にて使用する回路名称と真空管等の用途名称を下記のように統一します。
○定電流源機能と V/I 変換を兼ねる場合でも「初段」(回路)、当該真空管は「初段管」。
相当する素子である FET またはバイポーラ・トランジスタ (以下、BJT)
についても同様とします。
○終段管に信号入力する三極管は「電圧帰還管」(回路)または「電圧増幅帰還管」(回路)。
(英語版では Voltage Feedback Tube としました。)
○終段出力段は単に「終段」(回路)、また当該真空管は「出力管」または「終段管」。
(A) 初段 :12AX7 SRPP または 12AT7/2の抵抗負荷による
単なる入力信号電圧の電圧増幅、および P-K NFB 回路として動作。
(B) 電圧帰還管:12AU7/2 または 12AT7/2 による P-G NFB カソードフォロワ
終段のドライバー、および非直線 NFB 回路分圧素子として動作する。
(C) 終段出力管:UX2A3/UX45 または 6JS6C/EL509
電圧増幅を抑制した電力増幅を行う。
(D) ダイオード:6JS6C/EL509 のG2
スクリーン・グリッドに挿入、 直流電圧供給機能を正常に保つ。
原形回路では、カソフォロ管のグリッドには終段出力管のドライブに必要なだけの入力振幅が必要なことは言うまでもありません。 筆者の実験では、2A3 等大振幅ドライブを要する終段管は、カソフォロ管の前にハイμ三極管の SRPP による電圧増幅回路が欲しい所ですが、多極終段管ならば普通のハイμ三極管の抵抗負荷による電圧増幅回路で一応足りています。
但し「(1) 定電流源を併用する非直線素子を含む深い NFB 回路」以外は超三結
V1 アンプ回路固有の要素ではありません。 しかし超三結 V1 アンプの特性をより発揮する上では不可欠な要素です。
また「(4) ストッピング・ダイオードおよびリニアライザ」の項については、これまでの通常のアンプ回路には現われなかった、筆者達の実験結果に基づく構成要素であるため、節を改め「1.4.4 ストッピング・ダイオードとリニアライザ」にて詳しく説明してあります。
以下の各小節にて、上記(1)〜(4) 項の詳細を説明します。
◆基本回路構成
上條氏の原典による「超三結極管接続回路」の発想では、オペアンプによる理想アンプに対して三極管を NFB ループに入れることにより、
終段出力管の性格を三極管の「味付け」にて純粋培養する、
との表現にて記述されていました。 その基本回路を「図2 基本回路構成」に示します。
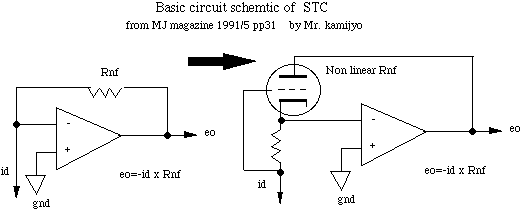
終段出力管を三極管によって極度に深い P-G NFB を掛け、それによる電圧ゲイン
〜増幅率μの抑制により、相互コンダクタンス Gm のみによる入力信号の電流変換機能
による出力を得る回路である。(2001/12/31 rev4.2)
◆定電流源および V/I 変換とは
従来の真空管回路では、電圧増幅〜電圧振幅を大きくすること〜を前提として動作を理解すれば殆ど事がたりていた事情があって、「定電流源」および「V/I 変換」という概念は一般には必要がありませんでした。 そこで、本文ではこれまでは現われなかった、超三結極管接続回路の解析と理解には絶対的に必要な「定電流源」および「V/I 変換」について補足説明します。
定電流源とは、加える電圧が変化しても流れる電流が変わりにくい性質を持つ回路のことです。 大きい抵抗値またはインピーダンスを持つことと同じ意味です。 そのような性質の回路を「定電流性を持つ」回路と言い、そのような素子も
「定電流性を持つ」と言い、そのような素子を「定電流素子」と言い、その機能を「定電流機能」と言います。
定電流素子としては、定電流ダイオードという製品がありますが、また五極管、バイポーラ・トランジスタ、FET (電界効果トランジスタ) は定電流性を持ち、定電流素子として利用できます。
そこで、定電流源の説明とともに、五極管および三極管の動作の概要について、下記の各項にて復習することにします。
●五極管の特性による定電流源
五極管の Eb-Ib 静特性曲線 を観察すると、プレート電圧が一定値までの間は崖を上り、平坦な高台に達して、それ以後はプレート電圧を変化させても、プレート電流が微増減しかしない状態に達します。 その勾配は抵抗値に換算できます。 この状態が定電流源およびインピーダンスとして利用されます。「図3 (1) 定電流性」を参照して下さい。 なぜ定電流源を使用するか、の理由は後ほど説明します。
●五極管による V/I 変換
五極管の負荷抵抗を極端に少なくすると、電圧振幅が少なく電圧増幅のゲインは取れないけれど、プレート電流の大幅な変化を捕える事ができます。 この状態を
V/I 変換に利用します。「図3 (2) 五極管の負荷抵抗 (L)」を参照して下さい。
また、併せて五極管の動作点における、直流抵抗と内部抵抗 (内部インピーダンス)
とは勾配=抵抗値が異なり、直流抵抗の方が低いことを確認して下さい。
●五極管による 電圧増幅
参考までに、従来の五極管の用法を説明します。 負荷抵抗を大きくすると、電圧振幅およびゲインがとれて、プレート電圧の大幅な変化を捕える事ができます。 この状態を一般の増幅回路に利用しています。「図3 (2) 五極管の負荷抵抗 (H)」を参照して下さい。
●五極管による定電流源と V/I 変換の同時動作
「図3 (2) 五極管の負荷抵抗 (L)」を参照して下さい。制御グリッド電圧を変化させても、プレート電流の平坦さが大幅には変らないので、定電流機能と
V/I 変換機能を同時に満たすことがわかります。
●三極管の特性
「図3 (3) 三極管の動作」を参照して下さい。三極管の Eb-Ib 静特性曲線
では勾配が急であり抵抗値が低いので、五極管の定電流性に対比して「定電圧性」を持っています。これは同一制御グリッド電圧のもとではプレート電圧の変化にプレート電流が敏感に反応する事を意味します。 また、併せて三極管の動作点における、直流抵抗と内部抵抗
(内部インピーダンス) とは勾配=抵抗値が異なり、直流抵抗の方が高いことを確認して下さい。
「図3 定電流特性および五極管・三極管の特性」に上記の動作状態の概念図を示します。
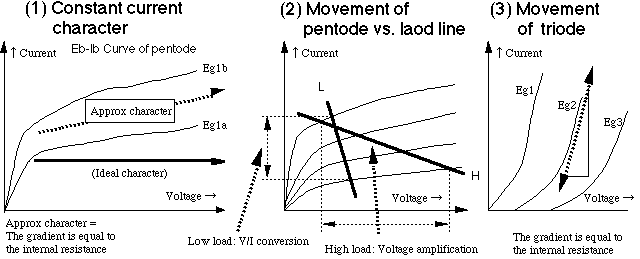
Zk/(Zi+Zk) where Zk > Zi or Zk >> Zi
の比率で戻されます。 すなわち終段で増幅して稼いだはずの電圧が逆相の電圧振幅としてグリッドに返され、うまくやれば終段の電圧ゲインを =1 近くまで抑制でき、すなわち出力信号の電圧振幅は終段グリッドへの入力信号の振幅近くにまで抑えられます。 しかし Zi はゼロにはならないので、完全に =1 にはなりません。
一方 P-G NFB では終段管の相互コンダクタンス Gm によって得られた入力電圧の変化 (ΔEin) に伴う出力電流の変化 (ΔIout) ・・・出力中の信号電流成分の量には影響せずソックリ残ります。
すなわち、P-G NFB 併用カソードフォロア・ドライブ回路の形式である原形回路は、深い P-G NFB によって従来の電力増幅方式に比べ出力電力中の電圧成分の少ない 〜または言い替えれば、電流成分比率の大きい出力が得られ、超三結 V1 回路動作の特徴を持つことになります。
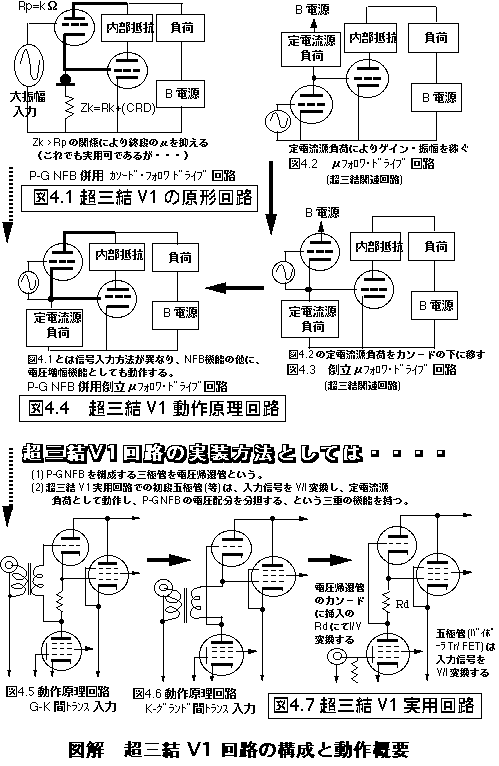
まず、初段および電圧帰還管により構成される、終段以外の回路部分の動作を解析します。 初段および電圧帰還管は、増幅、終段のドライブ、NFB 信号の配分機能を同時に行います。
●倒立μフォロワ回路の概要
「図解 超三結 V1 回路の構成と動作概要」中の「図4.3 倒立μフォロワ・ドライブ 回路」を参照してください。
倒立μフォロワ回路 (Inverted Mu follower circuit) とは、筆者が命名したμフォロワの変形回路です。 初段の負荷=定電流源を、電源と入れ替えて初段カソードの下に持ってきただけで、μフォロワ回路と全く同様の動作です。
但し困ったことに、倒立μフォロワ・ドライブ回路のアンプでは、圧倒的に一般化されている片側がアース電位にある
RCA ピンジャックによる非平衡入力ラインをそのまま入力信号に使うことができず、ライン入力トランスにてアース電位から隔離して、初段のグリッド〜カソード間に入力する必要があります。 平衡入力ラインの場合は必然的にライン入力トランスを使うので、このままの回路でよい訳ですが。
●P-G NFB 併用倒立μフォロワ・ドライブ回路の概要
「図解 超三結 V1 回路の構成と動作概要」中の「図4.4 超三結 V1 動作原理回路」を参照してください。
倒立μフォロワ回路の初段のプレートを終段のプレートで吊ると、P-G
NFB 併用倒立μフォロワ・ドライブ回路 (P-G NFB'ed inverted Mu follower
drive circuit) の回路形式となり、「原形回路」と類似動作であって、初段は単なる電圧増幅管の動作から変化して電圧帰還管<兼用>の位置付けとなります。 また電圧帰還管の負荷には、終段の負荷である出力トランスが混在しますが、本来の負荷である定電流源に比べれば殆ど無視できるオーダにあります。
信号入力される電圧帰還管は増幅動作を行うので、むしろ名称としては電圧帰還・増幅管相当の動作となり、原形回路と本回路との最大の相違は
、電圧増幅作用を行い電圧ゲインを持つ事です。 従って本回路では前置増幅段無しでソース信号を受け入れることができます。 電圧帰還管が NFB 素子として動作する点は原形回路と同じです。
● 電圧帰還管のグリッド〜カソード間に信号を入力し、
● グリッド帰路およびカソード帰路は、定電流源を架空の接地とみなし、
● (出力トランスおよび B電源を経て)定電流源を負荷とする電圧増幅機能
● P-G NFB の信号電圧配分の素子
を構成する。
● 電圧帰還管のカソード〜定電流源の間に入力信号を入力し、
● そのグリッドは定電流源を接地とする GG (=grounded grid) 回路により
● 電圧帰還管による、定電流源が負荷となる電圧増幅回路になり、
● (出力トランスおよび B電源を経て)定電流源を負荷とする電圧増幅機能
● P-G NFB の信号電圧配分の素子
を構成する。
一般の増幅回路では、「接地〜増幅素子〜負荷〜電源〜接地」というループを構成しますが、これを変形して、「接地〜負荷〜増幅素子〜電源〜接地」の順にしても、増幅素子への入力が接地から独立している限りでは、直列に接続されているので、負荷の両端に増幅出力が得られることでは、全く同じ機能であることを確認してください。(このような変形回路は、SEPP または OTL 等にてしばしば散見されます。)
結局、動作原理回路 (2) では、電圧帰還管回路にて増幅された信号出力は、終段出力管のグリッド〜カソード間に(μ-1) 倍の信号として入力されます。 -1 とは、出力端で見ると逆相となっている、カソードに挿入された入力信号分を差し引くからです。 但し実際の回路での -1分は、電圧帰還管に使用する中〜高μ三極管のμ値 (40〜100) から見て、影響は無視できる値であると考えられます。
動作原理回路 (1) および同 (2) では、信号入力箇所の接地が、回路全体の接地から浮いているため、入力信号セパレーション・トランスを必要とします。 (この GG ポイントをシャーシアースに接続する方法は、不可能ではないと思われますが、電源構成および外部雑音からの影響回避等 S/N 比の確保等に関して実装上有利とは考えられません)
上記の動作原理回路および実用回路を「図5.1 動作原理回路および実用回路」に示します。
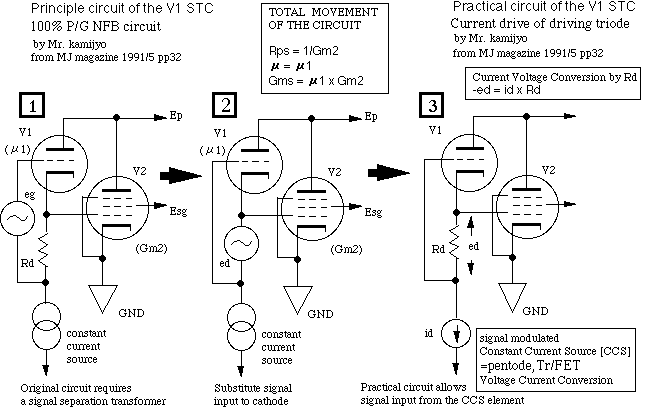
動作原理回路 実用回路
さらに、「図5.1 動作原理回路および実用回路」に示した各回路を、実際の素子にて構成すると「図5.2 動作原理回路および実用回路の実装」に示すような構成となります。
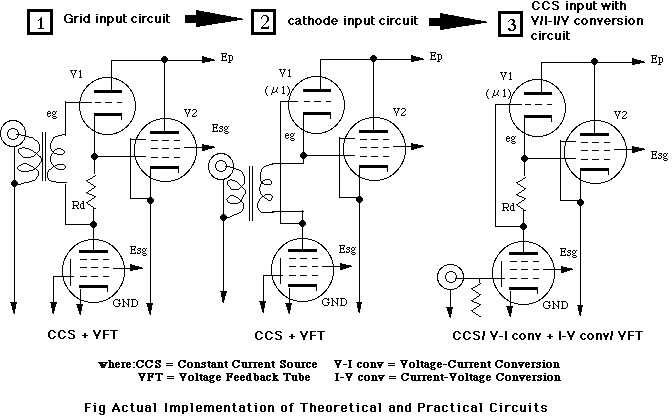
●初段は入力信号 ei を相互コンダクタンス Gm1 により
id = ei*Gm1 にて V/I 変換し、(* は掛け算記号)
●V/I 変換された初段からの信号電流 id が、電圧帰還管のカソードに
挿入された Rd に流れ、
ed = id*Rd の電圧を発生し、
●電圧帰還管回路はカソード入力回路、初段=定電流源を接地に看做した
GG 回路
(=grounded grid 回路) にて、(出力トランスおよび B電源を経て)
定電流源を負荷とする
電圧増幅回路を構成する。
●増幅された信号電圧と、内部抵抗にて発生した id による逆相の信号電圧の差
μ*ed - Ztp*id は途中に出力トランスと B 電源が入るが無視するとして、
●定電流源の両端に発生した電圧出力からカソードに発生した ed を差し引いて、
終段の G-K 間には下記の信号電圧 Efdr が入力される。
Efdr = μ*Rd*id - Ztp*id - Rd*id = id *{Rd*(μ-1) - Ztp}
「図5.3 実用回路初段入力回路の動作」を参照してください。
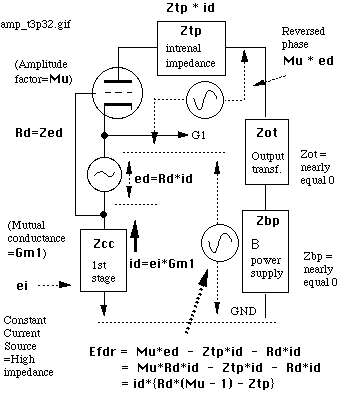
従って、I/V 変換と電圧帰還管の内部抵抗による影響を除き、以後の動作は動作原理回路 (2) とは本質的な相違はありません。
なお、P-G NFB 信号電圧配分の機能については、「動作原理回路」、「実用回路」ともに、基本機能として共通です。
従って、実用回路 (3) は下記の条件を満たす回路です。
通常用いられる不平衡入力にて、初段への入力信号セパレーション・トランスを使わない。
この場合、初段は定電流源を V/I 変換機能として使い、
初段は、電圧帰還管の負荷としての定電流源の機能はそのまま確保する。
初段は P-G NFB 信号電圧配分用のインピーダンスを確保する。
V/I 変換された信号は電圧帰還管のカソード抵抗にて I/V 変換して
電圧帰還管は、初段の定電流源機能を負荷として増幅し、
電圧帰還管は、カソードフォロワ形式にて終段へ電圧信号を入力する。
●定電流源回路 ●電圧帰還管回路 ●終段回路
筆者の発想では、実用回路については、一応下記の二要素に分離して扱い、独立の要素として考えることにしました。
●初段兼定電流源回路および電圧帰還管回路 ●終段回路
このようした理由は下記の二項です。
(1) インピーダンスおよび直流電圧の関係を保つことにより、終段のカソード、グリッド、プレートを接続点として、相互に独立の構成と看做すことができ、多種の組み合わせが可能になります。
(2) 実装試験の便宜上、色々な終段出力管について超三結極管接続回路を適用し動作試験するに際しては、便宜上前半部分の機能を一般化・共通にすれば、再利用が可能になり好都合です。
と記述されています。 この動作は、下記のように理解されます。
(1) 終段出力管は、μ=1 であり電圧増幅しないので出力電圧成分は入力振幅と同一であり、
(2) 一方グリッド入力電圧〜プレート出力電流の変換は、相互コンダクタンス= Gm の値がそのまま生きます。
例えば 10mS (ミリ・ジーメンス) ならばグリッド入力1V に対し
10mA のプレート電流変化が得られます。
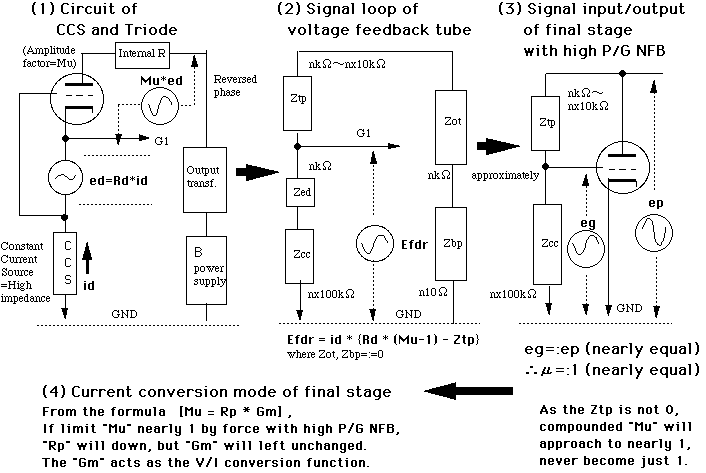
図6 (1) では、電圧帰還管のカソードに入力された信号 ed が増幅され、カソード〜プレート間にμ*ed の振幅の逆相信号が得られ、それが定電流源の上に現われることを示します。
図6 (2) では、終段のグリッド〜カソード間には id*{Rd*(μ-1)-Ztp} の振幅の逆相信号が得られることを示します。
また、電圧帰還管の増幅に関係する回路要素、および各々の概略のインピーダンス値のオーダを示します。
但し;
Zcc: 初段=定電流源のインピーダンス・・・・・・・数100kΩオーダ
Zed: 電圧帰還管への入力信号源のインピーダンス・・数kΩオーダ
Ztp: 電圧帰還管の内部インピーダンス・・・・・・・数kΩ〜数10kΩオーダ
Zot: 出力トランスのインピーダンス・・・・・・・・数kΩオーダ
Zbp: B 電源のインピーダンス・・・・・・・・・・・数10Ω〜100Ωオーダ
図6 (3) では、電圧帰還管回路での負荷インピーダンスは、厳密には Zcc/Zed/Ztp/Zot/Zbp の五個です。 しかし、Ztp は Zcc に比べて一桁少なく、また他の三者 Zed、Zot および Zbp 相対的に少であり無視できることを示します。
Ztp が Zcc に比べて一桁少ないと想定すれば、結局 Zcc 〜接地間に現われた電圧帰還管で増幅された信号電圧の殆どが、終段グリッドに入力されることになります。
終段では、更に信号を電圧増幅するが、増幅した結果終段プレートに得た信号電圧の殆どが、P-G NFB 回路も構成している、電圧帰還管の内部インピーダンス Ztp および初段=定電流源 Zcc にて電圧配分され、結局終段管自身のグリッドには
Zcc/(Ztp+Zcc) ---- ほぼ 1 に近い数値、何故ならば Zcc > Ztp
の比で戻されます。 したがって終段で電圧増幅されてプレートに現われる逆相の信号が、殆どそのままグリッドに加わることにより、ほぼ100%の電圧 NFB となって、実質の増幅率μは 1に近い値となります。
図6 (4) では、この回路動作によりμが 1 に抑えられた結果、
三定数の式:μ=Rp*Gm からμ=1 ならば 1=Rp*Gm ∴ Rp=1/Gm
となり、動作上の Rp は1/Gm と低下し、また相互コンダクタンス Gm はそのまま残ることを示します。
従って終段は理想的には「増幅率=1 の電圧増幅」となり、主として Gm によるグリッド電圧の変化をプレート電流変化に変換する機能となります。 またグリッド入力電圧は電圧増幅されずに(実際には完全に増幅率=1 にはできないため、少し増幅されて)終段のプレートに現われることを示します。
すなわち(1) 信号のV/I 変換・増幅、および (2) NFB 信号電圧配分の機能を、(3) 動作に必要な直流関係の電圧配分と、直結状態維持、の三者を同時に満足し、電源一つで済ませるには定電流源が必須なわけです。
直結回路とした意味には、更にカップリングキャパシタ等による音色づけの回避、および終段のグリッドリークが並列に接続されることによる定電流源の機能の低下を防ぐ意味(本件は、田村さんのご指摘によるものです)があります。
初段の実質的な動作は下記の四種を同時に行っています。
● 電圧帰還管への入力信号の V/I 変換を行う。 (2003/10 改訂)
● 定電流源として電圧帰還管の負荷に使う。 (2003/10 改訂)
● 電圧帰還管とともに 直流動作電圧の配分を兼ねる。 (2003/10 改訂)
● 電圧帰還管とともに P-G NFB 信号電圧の配分を兼ねる。 (2003/10 改訂)
電圧帰還管の実質的な動作は下記の四種を同時に行っています。
● カソードに挿入した抵抗 Rd による信号電流の I/V 変換を行い、
● I/V 変換された信号電圧をカソード入力 (GG) 回路にて電圧増幅する。
● P-G NFB 信号の一部を負担、終段出力管の深い NFB を確保する。
● カソード・フォロワ形式にて終段出力管の電圧ドライブを行い、
あわせて、終段のグリッド電流の影響から初段を守り、定電流特性の維持に寄与する。
◇回路全体および終段の動作
● 信号を初段 (=定電流源) から入力し、
● 初段=定電流源にて予め信号を V/I 変換し id を得、
● 電圧帰還管のカソード挿入抵抗 Rd にて信号電流を I/V 変換し ed を発生、
● ed は電圧帰還管のカソード入力回路に入力され、増幅される。
● 電圧帰還管の増幅出力が、初段=定電流源の両端に現われ、終段 G-K
間に入力される。
● 終段には深い電圧 NFB が掛けられ、出力電圧の振幅が抑制されて、電流振幅成分の比率の高い出力を得る。
P-G NFB に挿入される非直線素子としては、三極管 (接続) (原理的には
バイポーラメトランジスタ/FET も) に限らず、二極管 (接続) でも〜いわゆる真空管負荷というプレート(またはドレイン/コレクタ)
特性などと三極管との組み合わせとしても有効でしょうが、却って所要素子数が増えてしまいます。
従って、電圧帰還管回路は、実は定電流源からの電流信号の電圧変換・増幅機能、終段出力管のドライバー機能、非直線素子による100% の P-G NFB 素子、それに終段入力の直流電圧の供給の四機能を、一素子と抵抗一個だけで兼用し実現した、大変巧妙かつ実用的な回路であると、改めて感心し敬服しました。
但し、電圧帰還管の内部抵抗を非常に大きく取った場合には、初段の五極管の負荷が増えることと同義であり、増幅動作が現われ、その反面電圧帰還管の内部抵抗が、いわゆる真空管負荷として動作するため P-G NFB を併用した SRPPドライブ 回路となりうることを理解しておく必要があります。
また、理想的な超三結 V1 回路としては、電圧帰還管の内部抵抗=ゼロですが、実際には実現困難です。 実測例では Zcc:Ztp =10:1 程度の値が示されているように、実際の超三結 V1 回路は、理想的超三結 V1 回路と P-G NFB 併用 SRPP ドライブ回路との中間にて、より理想に近い位置にあるものと考えられます。(2000/4 rev3.6)
従って、超三結 V1 実用回路構成において、初段〜電圧帰還管の部分回路に対して「SRPP 回路」という名称を適用すると、一般的な SRPP 回路と混同し、誤解を招きます。
実際、メールでの質問または検討等にて判明したのですが、上記を混同する方がかなり多く、何よりも本件は以前筆者自信が混同していたことがありそれを反省し、同じ誤りは避けたいと考え(恥を忍んで!)その誤りを発見した経過についても、本文の後半「2.4.2 SRPP 回路による解決」に記しています。 いずれにしても注意が必要です。(2000/3 rev3.5)
またスピーカの挙動、いわゆる逆起電力の課題も多様です。 元来、例えば名目8Ωというスピーカであっても、信号周波数によっては共振またはインダクタンス成分によるインピーダンス変化があり、エンクロージャの影響もあり、過渡信号の塊と連続みたいな音楽信号に対しては、連続サイン波等の条件下とは全く異なり、動作時のインピーダンス挙動は千変万化し、不整合状態は常時発生しているようなものです。
0verall NFB を回避することは、このようなスピーカの影響を避け、出力トランスは単なるインピーダンス整合用法とすることと同義であると考えます。 いわゆる NO-NFB の「古典回路」に根強い人気があるのは、回路構成が NFB の技術開発以前の時代であるため、NFB 併用もなく、このような課題は発生しないから音が却ってクリアーであるためではないか?と考えられます。 したがって、この点に関しては超三結 V1 アンプとは「新古典回路」?に相当するかもしれません。
更に 0verall NFB の回避は、出力トランスの選択自由度を高める方向に作用します。 出力トランスのもつ性能諸元のうち、インピーダンス整合用法の部分のみが 利用されると考えれば、若干のインダクタンスおよび直流抵抗などの問題を含んだとしても、大抵の出力トランスならば、極端な場合にはヒータートランスでも卒なく動作してしまう・・・超三結 V1 アンプが高い再現性を実現する・・・一つの要素となるものと思われます。
前記「1.3 超三結 V1 回路の定義」にて示した、出力トランスのB 電源側に挿入したダイオードおよびスクリーングリッドに挿入したダイオードの動作については、別項の用語辞典の SD = ストッピング・ダイオード(stopping diode) および LNR = リニアライザ (Linearizer) にも説明してありますので、そちらもご参照ください。
以下は、あくまでも筆者の独断と偏見による SD/LNR に対する推論となります。 SD については、まだ完全な理論的裏づけをとれる計測が済んでいない状態です。 しかし現象的には音質改善に有効なので、理由なしに挿入している訳ではありません。 一方 LNR については実績のある直線性改善素子用法です。
●現象としてのダイオードの効果
回路図例に示した、出力トランスの B 電源側にこのダイオードを挿入すると、シングルアンプの場合では、低音域の音程がハッキリしてくると同時に振幅が確保されます。 特に小型の出力トランスでは効果が顕著です。 中〜高音域での効果は特に認められません。 またシングルアンプだけでなくプッシュプルアンプでも特定の効果があります。
挿入したダイオードの効果は、超三結アンプ固有のものではありません。 無帰還アンプ、UL接続アンプ、局部的負帰還アンプまたは超三結アンプのように複合化した局部負帰還アンプでも、効果があります。 ただし、Tさんによると、over all NFB アンプでは、信号波形を元に戻そうとして効果が失われるそうです。 筆者の実験結果では、P-K NFB (終段プレートから初段カソードに非直線素子を経由して掛ける超三結 V3 の NFB) を適用した場合、若干効果が失われました。
●ダイオードの動作原理の推理〜理想の電力増幅回路から
上記の現象は、ダイオード・スイッチの動作に似た、直流ループが回路のベースにある場合にのみ、信号が伝わる仕組みによる効果と考えられます。
理想の電力増幅回路では、真空管が信号源となり、負荷である出力トランス、ゼロ・インピーダンスの理想
B 電源の三要素が、「直流ループ」を構成します。 理想の B電源は、単に信号源に原動力を供給するだけの役割であり、信号電力の面倒は見ません。
信号電力は直流ループに乗って信号源と負荷で分け合います。信号源と負荷のインピーダンスが完全に整合していれば、信号電力は出力トランスに最大半分まで伝送され、残り半分の電力は信号源で熱となって失われます。
不整合の場合は電力の行き場がなくなり、信号源で更に熱となる一方、無理やりリアクタンス成分を持つ出力トランスに電力を「押し込む」効果があると考えられます。 一般にスピーカのインピーダンス〜出力トランスの一次側から見たインピーダンスは、信号により駆動されて常時変動し、公称
8Ω等という値が保たれる訳ではなく、常時不整合状態にあるため「押し込み」が起きやすいと想定されます。
このダイオードを省くと、すなわち出力トランスと B 電源の間を直接接続すると 〜従来の電力増幅回路は全てこの状態ですが〜 折角の出力信号エネルギーを、出力トランスのインピーダンスと
B 電源のインピーダンスとで配分します。
整流管を換えると音が変わると言われるのは、明らかに B 電源インピーダンスが、出力トランスのインピーダンスとで、扱う信号電力を配分していることの証拠であり、B 電源が信号電力の一部を消費・吸収しているわけです。{古典回路ではこの現象を「音造り」に利用する例もあります。}
現状では、このような推論内容でしか、SD による低音の音程の明瞭化と振幅確保効果の説明ができないのは残念です。
●理想の電力増幅回路に迫る
この SD および出力管自身が持つダイオード機能が B 電源の出口とリターン入口とに接続されることによって、すなわち信号源と負荷は、見かけ上は出口と入口にダイオードを持った B 電源に接続され、「専ら直流の供給を受けるだけ」の状態に近くなり、理想の電力増幅回路に近づく訳です。
すなわち、上記の二つのダイオード機能は、B 電源の持つインピーダンスの影響を直流抵抗分だけに絞る効果 〜結局、供給された直流電力の上にしか信号電力を存在させない効果、B 電源のリアクタンス/キャパシタンスの影響を最小化して直流抵抗だけにする効果、それは「真空管と負荷だけの世界に信号電力を閉じ込める」効果ではないかと考えられます。 そのような考え方で一時「閉じ込めダイオード」と呼んだこともあります。
その意味では負荷としての出力トランスも理想の電力増幅回路に近づける機能は保持していますが、直流の供給だけを受ける機能は持ち合わせていませんから、Lを大きくするだけでは根本的解決はできないでしょう。
さらに実際には B 電源の両端には十分な 〜流す電流値 mA の五倍位の
μF の〜 容量を持つキャパシタを挿入しないと効果が十分に発揮されません。 大放電容量が必要であるということは、より直流抵抗分が少ない
B電源への要求と同義であり、理想電源の必要性を示唆していることになります。
●SD の命名由来
結局このダイオードは出力トランスを通り抜けてしまった信号が B電源に流れ込むのを阻止する「閉じ込めダイオード」の機能であるとの考えに至り、stopping
diode (SD) と命名した訳です。
なお、米国で本文の英訳版を読んだ人達は「ブロッキング・ダイオード
(blocking diode)」と呼んでおり、流石にこの方が語感としてはピッタリしています。
●球の種別による SD の効き具合
定量測定はしてありませんが、五極管(高) > ビーム管(中) > 三極管(低) の順で SD の効きが悪くなります。 この現象は、明らかに出力管の内部抵抗、出力トランス、B 電源の三者のインピーダンス関係によるものと考えられます。
●スクリーングリッドの SD 効果
スクリーングリッドが B 電源に直接接続されていると B 電源のインピーダンスがスクリーングリッドの動作に反映してしまうので、プレート回路と同様にダイオードを直列に挿入するものです。 プレート回路ほどの効果はありませんが、聴感上で判る程度の効果があります。
●プッシュプルアンプの SD 効果
プッシュプル用出力トランスを使用した場合に、センタータップに SD を挿入すると、出力トランスの不平衡成分、および出力トランスを通り抜けてしまった信号成分が B 電源に流れ込むのを押し戻す、古い Western のプッシュプルアンプの回路に見られる「センターチョーク」のような効果があり、低音域がシッカリします。 但しLの大きい出力トランスでは、低音域が膨れてバランスを崩す可能性があります。
また、タッタ一例だけの実験ですが、一次巻線が分かれているプッシュプル用出力トランスを使用した
6V6GT(UL) pp アンプで、一次巻線の各々 B 電源側に独立の SD を挿入してみたら、低音域が異常に膨れ上ってしまい、上記のセンタータップに戻したことがあります。
●SD 効果を生ずる素子
出力管のプレート回路〜出力トランスの B 電源側に挿入する場合は、手軽なシリコン・ダイオードから整流管、ダンパ管、大電流の取れる出力管の二極管接続、レギュレータ管 (電圧調整管) の二極管接続などがあります。 抵抗値の殆どゼロに近いシリコン・ダイオードはややきつい音になりますがハッキリしています。 真空管では聴感上はソフトになります。 但し、内部抵抗の高い真空管では、出力を制限したり、低音域を緩くしたりで、概して不適当でした。
出力管のスクリーングリッドに挿入する場合では、プレート回路よりも電流が少ないのでシリコン・ダイオードと真空管の差は余りありませんが、やはり真空管を挿入すると音は幾分ソフトになります。
筆者の実験結果では、シリコン・ダイオードとしては専ら 1N4007 が、真空管では 6CA4 の並列、6AS7GA/6080 または 5998A の二極管接続が適用できますが、これら以外の整流管、ダンパ管等は、内部抵抗が大き過ぎて不適当でした。
回路的には、定電圧電源が供給されている直列の増幅素子と矯正素子によって構成されたアンプにて、増幅素子が発生した特性曲線の曲がりによる信号の歪みを、矯正素子が逆の特性によって吸収し、結果的に負荷の両端に生じる出力電圧は直線化される作用であると考えられます。
カソード/エミッタ/ソースを共通とした差動アンプや、素子を直列に使用した
SRPP/SEPP 回路動作にもリニアライザ類似の効果があるのではないかと考えられます。
●LNR 効果を生ずる素子
フラットアンプ等に見られるように、電圧増幅回路では同一管種の二極管接続を使用するのがベストの様です。電力増幅回路への同一管種の適用例としては別項の田村さんの
807 リニアライザアンプの例があります。 しかし、電圧増幅回路では異種の管種であっても、ある程度聴感上の効果が得られます。 例えば高周波用三極五極管の三極部の二極管接続またはハイμ三極管の二極管接続、検波用の
6AL5 等も一応有効です。
半導体ではショットキーダイオードの特定品種に使えるものがありましたが、一般的ではありません。 小電流
FET を初段に使用する場合には、同一品種のダイオード接続が使えそうです。 大電流用シリコンダイオードでも効果があるらしいですが、実験例がなく、様子が判りません。
筆者が動作試験に使用しているスピーカの機種名を記載するよう示唆した方がいました。 それは別項「自己紹介」のページに概要を記載しています。
超三結 V1 アンプを試作・追試験される方がお使いになるスピーカについては、本来、筆者には指定することはできません。 従ってスピーカの選択・調整はおまかせするしかないと考えています。 さもなければ、筆者は相当な範囲のスピーカを自宅に買い集めて並べて動作確認試験せねばならず、実際は不可能です。
現在筆者の自宅では、3〜4 種類の一般的な室内用スピーカを試験および鑑賞用に使用しており、また機会があれば他所の大型スピーカを借用して、総合的動作確認試験をしています。
むしろ課題は前段の電圧増幅管または Tr/FET、電圧帰還管及び出力管の個体差、例えば新品であっても必ず見られる標準電圧でのバラツキがありますが、これをどのように吸収するか、という点にあります。 しかし、出力段は自己バイアスにて動作するため、バラツキは、ある程度は吸収されています。
このような素子のバラツキに対して基本的知識と対策法を心得ていれば全く問題はありません。 例えば本文の表または各製作記の回路図に示した所定の値に近い値に設定できれば、動作としては殆ど問題ありません。 また、フル出力を得るための調整法は一般の回路と同様です。
実際に何人もの方が、筆者の記した個別の超三結 V1 アンプ回路図のページをブラウズして追試験し、成功しておられます。
●部品故障
一件の半固定抵抗の接触不良障害の他は、特段の問題の発生報告がない所をみると、配線方法の不適当等による発振およびその対策等、一般のアンプにも適用されるトラブルおよび対策を除外して、信頼性に関しては一応問題なしと考えています。
但し、筆者としては、経年変化等を考慮して、半年程度の周期による動作状態点検をお勧めします。
事例1.接触不良障害例
ある追試験された方の超三結 V1 アンプにて、初段の半固定抵抗(5kΩ)の摺動部接触不良にて、終段のグリッドにプラス電位がかかり、プレートが赤熱したが、自己バイアス回路によるプレート電圧の相対的低下にてかろうじて終段管が助かった例がありました。
事例1.防止対策
半固定抵抗の接触不良対策としては、必ず半固定抵抗の両端を直列に使い、それを摺動端にてショートする形式とし、決して一端と摺動端を単に直列に使用しないことです。
このように接続しておけば、たとえ摺動端が浮いて、終段のバイアス電圧が浅くなっても、自己バイアス電圧が上がり、補う方向に移動してカソード電流の大幅増加が抑制されるでしょう。(実は、実装技術上の問題です)。
FET またはバイポーラトランジスタを初段とする場合には、予期しないオープン事故に備えて、常時の動作時には起動しない開始電圧のツェナーダイオードを並列にするなどの措置が考えられます。
●初段管ヒーター断線等障害からの出力管保護について (2003/10/15)
超三結 V1 回路にて初段 (管に限らず・・以後単なる「初段」とは、初段管/ Tr/ FET の総称とします。) がオープンとなれば、出力管の制御グリッド (G1) には電圧帰還管の三極管を通してモロに B電圧がかかり、出力管は二極管状態を強いられます。 この種トラブルでは、ヒーター巻き線のショートやリップル・フィルタのケミコンの+−を誤って逆に接続した場合と同様に、B 巻き線のショート事故のように
プツンとフューズが切れてくれず、ジンワリと過熱するので大変始末が悪いです。
出力管の G1 にはプラスが掛かるからグリッド電流が流れて G1 が加熱し、Pp/Psg(許容プレート損失、同スクリーングリッド損失)はオーバーして損傷し、カソードに挿入した抵抗には正常時の何倍かの電流が流れて発熱し、並列に接続のケミコンは過剰な電圧が掛かってパンクし、出力トランスも過剰電流で発熱損傷し、B 電源回路のトランスおよび使っていればチョークも過剰電流にて発熱損傷します。
本件については、別項目「超三結 V1 アンプの出力管保護回路」にて改めて対策を系統的に纏めましたので、事故防止のため是非ご一読を戴きたく存じます。
===================改訂内容の詳細====================
●本文の性格の推移
本文の記述内容が、上條氏の超三結アンプの「追試験版」から「いかなる球でも超三結アンプとして動作可能の筈、確認する」目標に変化し、タイトルを「超三極管接続回路方式によるアンプの実装法考察」に変更した。
●本文中に記載したデータについて
手持ち電源にて一応動作確認したもので、動作確認して実用に耐えが追試験の場合には若干の調整が必要と説明。
●調整法等について
超三結 V1 アンプでは回路の動作点調整が重要、調整方法と手順を、本文後半「3.1 終段のバイアス調整法」に記載。 副次的に回路テスターのみにて超三結アンプが製作・調整できる実用性と再現性を記述。(1999/2 Rev2)
●本文を読まれる方に
真空管の「三定数」および「Eb-Ib 静特性曲線」等の予備知識の必要性の説明、および併用する教科書・参考書の紹介。
●(P-G NFB 併用の) SRPP 回路との区別
その後、筆者が動作原理をレビュー・追及していく過程にて、超三結 V1
回路と通常の三極管〜三極管による SRPP 回路との相違を明らかにして整理。(1999/4 Rev3)
準超三結回路の再定義
「準」超三結 V1 回路の定義を、原形回路にて回路構成した場合に適用するように変更。 (2001/5/31 rev4.0)
●電圧振幅抑制電力増幅回路
筆者が超三結 V1 回路の動作原理を見直した結果、通常の「電力増幅」回路ではなく、電圧増幅率を抑制し、相対的に電流変換機能を強調した回路であり「電圧振幅抑制」電力増幅回路が、より適切な名称であると考えるに至り、説明資料等にはその旨並記した。 なお、終段入力は電圧ドライブであり、出力には終段ドライブ電圧成分がそのまま残るため「電流アンプ」との名称は不適当。(1999/8 Rev3.3)
●電圧帰還管、同回路、回路図等について
超三結 V1 回路の電圧帰還機能を担う素子 〜電圧増幅三極管〜 の名称が上條氏の定義により明らかにされ、以前は「三極管ドライバー」と称していたものを「電圧帰還管」と変更し、それを含む回路部分を「電圧帰還管回路」と変更した。 本文のメンテナンスの便を考慮して、回路図等の図面類および表類は、全て英語表示とし、英語版と共通にした。(1999/8 Rev3.3)
●ストッピング・ダイオードの名称
本文を英訳した英語版を1999/8 に完成した。これを読んだ米国の方が、ストッピング・ダイオードをブロッキング・ダイオード (Blocking diode) と読み替えており、語感としてはそのほうが適切と考えられるが、以前のままとした。(1999/8 Rev3.3)
●大振幅三極管の課題〜削除
大振幅ドライブ三極管の超三結アンプ化の実用的意味に疑問を感じて、全面削除。(2000/1 Rev3.4)・・・復活もありえる。(2001/5/31 rev4.0)
●再び電圧帰還管、同回路、未解明の要素 しかしその後の検討では、電圧帰還管は電圧増幅機能を果たしており「電圧増幅帰還管」の名称が適切、と河口さんと見解が一致。 但し当座は「電圧帰還管」「電圧帰還管回路」のまま。 現状では、ストッピング・ダイオードの動作、電圧帰還管回路の設計と電圧帰還管の選択には、何れも未解明の要素が残っている。(2000/2-3 Rev3.5)
●超三結 V1 回路と超三結 V1 アンプとの区別
超三結 V1 アンプを試作された方から、初段〜電圧帰還管〜終段の構成要素の塊を「超三結 V1 回路」と称し、実装された個別のアンプに対して「超三結 V1 アンプ」として区別すべきとのご意見を戴き、本文中の表現を点検・修正した。(2000/4 Rev3.6)
●本文の分割と部分修正
本文が長大にすぎて、ブラウズおよび保守に不便なため、内容の修正とは別途に、前半(第一部 動作原理および総論)および後半(第二部 実装と調整)に
html を分割した。 前半の一部に記述順序の不適当な箇所があり、これを修正した。(2000/3 Rev3.5) さらに動作原理に関する図面および説明文の一部を増補した。(2000/4 Rev3.6-3.7)
●説明不足箇所の部分追加修正
バイアスの深い三極出力管を直結する場合の初段スクリーン・グリッド電圧供給方法について。(2000/5 Rev3.8) +側/−側クリップ点のアンバランスについて。(2000/7 Rev3.9)
●試験対象球の表への追加
随時追加していた、数種類の試験対象球の動作点情報を後半の表1 に追加した。 (2001/1 Rev3.10)
●より判りやすい動作原理回路の追加
本文前半「1.3 超三結 V1 回路の定義」に P-G NFB 併用カソード・フォロワ・ドライブ回路による「準超三結」回路の動作説明を追加した。(2001/4
Rev3.11)
●動作原理の説明部分の改訂
P-G NFB 併用カソード・フォロワ・ドライブ回路を「原形回路」として、動作原理の説明ステップに組み込み、P-G NFB 併用倒立μフォロワ・ドライブ回路との親和性を保ちつつ、原形回路〜動作原理回路〜実用回路の連動性を保持して、動作原理の理解容易性を改善した。(2001/5/31 rev4.0)
●動作原理の説明部分の改訂ほか
超三結 V1 回路の定義について、NFB に非直線素子を含むことよりも、終段の深い P-G NFB による電圧電流変換機能を、従来型の電圧アンプとの相違点および特徴として全面に出すよう方針を変更し、表現を補足した。 なお、マイナーな改訂関連情報は、冗長なため本文末尾の改訂記録に移動した。(2001/12/31 rev4.2)
●1.4 回路動作の詳細、1.4.5 実用回路のレビューの改訂ほか
「1.4.5 実用回路のレビュー」の文中にて、初段の実質的な動作の四項目の説明内容が誤って電圧帰還管と同一、これを正しく訂正した。(2003/10/15 rev4.3)
End of file