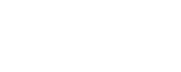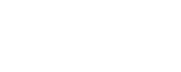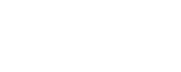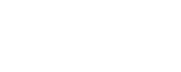小学校3年か4年生頃です。その頃、私は本を買ってもらうのがとても楽しみな子供でした。
誕生日だとか、クリスマスだとか、その他何かうまい具合に機会を見つけては家族に本をプレゼントしてもらい、
しつこく何度も読んでいたのでした。
−−−が、買ってもらった中で2冊だけ、扱いに困ってしまった本があります。
「赤いろうそくと人魚 小川未明童話集」 と 「泣いた赤鬼 浜田廣介童話集」
の2冊です。
なにがなんだといって、この2冊、内容がむちゃくちゃ暗い!
私は当時、読んだ本の雰囲気に飲み込まれるたちでしたから、
ホラーと怪談と戦争実話は、落ち込むやら怖いやら陰々滅々とするやらで、
とにかく読まないことにしてたのです、
が・・・この2冊がそれと同じくらいに、どうしようもなく暗いっ!
内容をご存じない方のためにちょっと書いておくと、
「泣いた赤鬼」 は、文体は柔らかくてあたりがよいのですが、中身がけっこうエグイ!
善人(??)で村人と仲良くお茶を飲みたい赤鬼が主人公で、
鬼を怖がる村人に「赤鬼はこわくない」とわからせるために、
友達の青鬼の提案で、「こわい青鬼」をやっつける芝居を村人の前で
して見せて、すっかり安心した村人が赤鬼の所へ遊びに来るようになって
メデタシメデタシ・・・
と思ったら、赤鬼が久々に友達の青鬼の家に遊びに行くと、
空き家になっていて「僕がいるとまたみんなが怖がるから遠くに行きます」
と別れの張り紙がしてある。赤鬼はさめざめと泣きました。
・・・という、泣かせる話なんですが・・・
「エエ話やなぁ・・・」
ってほのぼのできる状態じゃなくて、「ちょっと待てぇっ! それじゃヘンだろうっ!」
と、子供の私は思わず突っ込んでいました。
まず、鬼が「いい人」だという設定がヘンです。
いや、「鬼」が本当にいい人だいう前提なら、
なぜこんなに村人にいやがられて怖がられて、顔を見るだけで逃げられてしまうのかという、
その説明が一切ないのが物語の設定として不条理です。
この赤鬼が突然変異で、他の凶悪な鬼と全く違う性格の「善鬼」だと考えられないわけでもありませんが、
もう一人の「青鬼」もずいぶんいい人みたいですし、話の中にはこの2人しか「鬼」という種族が
出てこないのですから、2人中の2人(つまり2/2で100%)が「善鬼」だという事になります。
しかも 「この2人が鬼の中では非常に特殊なタイプで、普通の鬼から仲間はずれにされている、
普通の仲間とは違うはぐれ鬼たちだった」 という説明もなかったようです。
つまり、「普通の鬼」がこんなふうにいい人達なのでは、
村人たちが、昔からなぜそんなに「鬼」を怖がって赤鬼に近付かなかったか・・・
という理由が宙に消え去ってしまうのです。
さて、おまけに、この赤鬼と青鬼の行動パターンがちょっとヘンです。
「こわい鬼退治をしてみせて、コンタクトの最初の一歩を作ろう」というアイデアはわかります。
しかし、実際には悪役をやった青鬼も「怖くない優しい鬼」なわけですから、
赤鬼くんとしては、「ところであの青鬼もいいやつなんです、
実はみんなが怖がっているもんで、これこれこうで・・・」
と、仲良くなってから村人に事情を説明していけばいい訳で、
青鬼は友情に厚いいいヤツのようですので、
きっと村人とも仲良くやるんではないかと思うのですが、
赤鬼君はいっかなそういう事情説明をする気配はなく、
青鬼君も「自分も村の人と仲良くしよう」と新たな努力を始めるでもなく、
おまけに赤鬼君が「ううう、青鬼君がいなくなっちゃったよー」と泣くのが
予想できるにもかかわらず、勝手に自分だけ姿を消しやがって、
こいつ、友達としてサイテー!
・・・と、まぁ、こんなにはっきり理屈にはなっていなかったんですが、
そのような事を感じて、子供のサカタヤスコはその本を捨ててしまいました。
(こらこらこら)
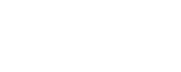
さて、浜田廣介はそれで済んだのですが、小川未明はどうしようもなく
暗くて救いのない話なのにもかかわらず、捨てられずにひっかかっていました。
頭を抱えるほど陰鬱な話なのですが、浜田廣介のように設定上の矛盾とか
被害者意識のようなもの(自分はものすごくいい人なのにみんながいじめるんだ
・・・とかそういうヤツですね)は感じなかった上に、
何か、どこかに惹かれるひっかかりがあったんですね。
しかし、子供では読み続けられないほど暗澹とし、鬱々とした話だったので、
私はそれをとりあえずの間、封印しておく事にしました。
「いつかこれを、雰囲気にめげずに読めるんじゃないかな・・・」
などと思ったわけです。
で、なんとか小川未明を読めるようになったのは、中学くらいの時でした。
(時々、本棚からとり出してはまた戻しておったわけですね)
これも、ストーリーをご存じない方のために 「赤いろうそくと人魚」
の内容をかいつまんで説明しますと
北の暗い海に棲む人魚の母親が、「今から生まれてくる子供を、
こんな寒くて暗い北の海の底ではなく人間の明るい世界に住ませてやりたい、
人間はとても親切だそうだから、きっと子供を育ててくれるだろう」
と海辺の町に捨て子をします。
その人魚の子供を、海岸の崖にある神社の下でろうそくを売っている老夫婦が拾って育てるのですが、
この娘が白いろうそくに貝や海草の絵を描いて売ったところ評判が良く、
しかもそのろうそくの燃えさしを持って船出すると
絶対に船が沈まないという噂がたって大人気。
ところが、うわさを聞きつけた香具師が人魚の娘を見せ物にしようと老夫婦に
話を持ちかけ、大金に目がくらんだ老夫婦は、娘が「ここにおいてください」と頼むのにも関わらず、
娘を香具師に売る事に決めてしまいます。 (と、このあたりまでは「夕鶴」と同じ展開です)
さて、娘が香具師に連れて行かれる間際、
娘はろうそくに絵を描き終える事ができずに、
手に持っていた筆で真っ赤にろうそくを塗りつぶしたまま、
檻に入れられて、そのまま連れて行かれてしまうのですが、
その夜遅く、ろうそく屋に女の客が来て、
真っ赤に塗りつぶされたろうそくを黙って買って行きます。
女が帰った後、受け取ったお金を見ると、それはお金ではなく貝殻で・・・
−−−と、このあたりから話はどんどん怖くなってきて、
その晩、崖の上の神社のお堂に赤いろうそくが燃え、海は大しけになって、
人魚の娘を乗せた香具師の船を始め、
数え切れないほどの船が難船して大勢の人が海で死に、
それから後も、赤いろうそくがお宮にともるとかならず海が荒れて大嵐になり、
赤いろうそくを見ただけでも海に溺れて死ぬというので、
老夫婦は店を閉め、お宮は鬼門となり、
もう誰も近づかないはずなのに、たびたびお宮には赤いろうそくがともり続け
「真っ黒な、星も見えない雨の晩に、波の上から赤いろうそくのともしびが
漂って、お宮をさしてちろちろと登っていくのを見た人がいました」
・・・という、ものすごい事態になって、
「幾年もたたずして、そのふもとの町は滅びてしまいました。」
といって話が終わるのですが、
この、「金に目がくらんで遠慮なく娘を売ってしまう老夫婦」もすごいけど、
「期待していた人間の存在に絶望して、
徹底的に復讐を続ける人魚のお母さん」の恨み方もなんだかスゴイ!
で、このエンディングが暗いながらも妙に納得できる爽快感のようなものがあるのは、
お母さんの恨みが、「勝手に預けたくせに ”私の娘に何するのよー” という
”勘違い逆恨みモード” 」じゃなくて、
「何で私はこんなやつらに期待してしまったの? 私のバカバカバカ!」
という、「自分でやりきれないので八つ当たりしてしまう化け物的思考モード」
に入っている事で、それが最後に海を荒れさせて船を難破させてしまう、
超常的パワーを使う妖怪的バックボーンになっているし、
何よりちゃんとしているのは、売られて檻に入れられていったかわいそうな
人魚の娘が、母親の手で助けられているだろう事です。
(最後の悲劇性が薄れるのではっきりとは書いてありませんが、老夫婦が
「こんな嵐では娘を乗せた船が沖合で難破した事だろう」とふるえているので、
娘は人魚ですから、きっと船が沈んだときに母親が海中で助け出した事でしょう)
「なるほど・・・これは辻褄がちゃんとしてるわ・・・」と思って、
それからあとの話も落ち着いて読んでみると、
この後も「怖いような、きれいなような話」がずっと続いていて−−−
たとえば 「月夜とめがね」 というのは
夜なべ仕事をしている一軒家のおばぁさんのところに、
人間の少女に化けた「胡蝶」が訪ねてくる話で、
春の月夜の菜の花畑を背景に、この一人暮らしのおばぁさんは、
怪我をしましたという胡蝶に化かされるでもなく、
手当をしてやるでもなく、ただ春の月夜の野辺を連れて歩いてやっている内に、
いつしか胡蝶の姿は消えていました・・・ という、
民間の伝承説話によくある 「たぬきに化かされる話」 の変形のような、
まったくさりげない話ですが、「春のおだやかな月の夜」に「人を化かす」のが
「少女の姿をした胡蝶」だという意表をついた設定がものすごくて、
頭にこびりついて離れない強烈な作品の一つです。
あともう一つ、「みなとについた黒んぼ」
タイトルと設定が使用禁止用語の団体なので、
多分、現在原文のままでは収録されていないのではないかと思うのですが、
目の見えない10歳くらいの弟と、弟思いの姉、という姉弟の乞食の物語です。
弟が笛を吹き、美しい姉が歌と踊りを踊って、物乞いをして港で生計を立てている2人のもとに、
お大尽の使いという人が姉を呼びに来て、「お大尽が呼んでいるのでどうしても屋敷に来て欲しい」
と言われて姉は断りきれず
「では弟を待たせているので、必ず1時間で帰らせてください」と約束して、
姉は弟を野原に待たせて馬車に乗って出かけて行きます。
すっかり日が暮れた夏の野原で、弟がいつまで待っても姉は帰ってきません。
自分の笛の音が聞こえたら帰ってくれるだろうと、弟が笛を吹いていると、
子供をなくしたばかりの白鳥が、訴えるような笛の音にひかれて降りてきて、
姉が戻って来ないというのを聞いて「じゃあ、白鳥になって南の島に私と一緒に行きましょう」 と
弟を白鳥に変えて連れて行ってしまいます。
で、姉はというと、かなり遅れて慌てて戻ってくるのですが、
弟はもう約束した野原にはいなくて、半狂乱で港のあちこちを探しても見つからない。
姉が絶望して悲しみに沈んでいる内に、南の国から船が着いて、
その船からおりてきた「黒んぼ」が、
「あなたを南の島で見ました、目の見えない弟の吹く笛にあわせて歌って踊っていました。
王様から迎えの輿が来たけれど、弟がかわいそうだと言って断っていました」
と言うのを聞いて
「世の中にはもっと親切でもっと善良な”自分”がいて、
その人が弟を連れて行ってしまったのだ」
と思うという話です。
最後は「どうにかしてその島に行ってみたい」 という姉に
「それははるか彼方でとても容易に行けるところではない」 とくろんぼが答えて、
「この時夏の日は暮れかかって、海の上が彩られ、空は昨日のように、真っ赤に
燃えて見られました」
という、壮絶な夕暮れの描写で終わっています。
「これじゃあ、弟思いのお姉ちゃんがかわいそうでしょう!」と思うのですが、
赤い夕日の落ちる港で、盲目の弟の吹く笛に合わせて、
水色の着物で踊る物乞いのむすめ・・・というイメージの強烈さがすばらしく、
小川未明の作品は、物語というよりは全体として「詩」に近いもののようで、
暗くて怖い上に、壮絶にきれいなのであります。
というわけで、「この本はとっといてよかった・・・」 などとだいぶ後で思ったのですが、
こんな暗い話を 「童話」 と言い張ってしまう小川未明はすごい!(こらこら)
−−−さてここからは余談ですが、
だいぶ前に、「糸杉」という姉と弟の話を描いた事があります。
ほんの少し、この物語の記憶があったのかもしれません。
子供の頃に読んだ話は断片として頭の中に残って、さまざまな形で繰り返し出てきます。
本当のオリジナルなど自分の作品にはないなぁ・・・と思っています。
「本歌取り」としてすでにあるイメージを共有化し、自分のイメージを加算し、
次の段階へ発展したり新しく派生したりして行く創作・・・
すでにある莫大な過去からの遺産を引き継いで、別の方向性や小さい変化や、
磨きをかけてまた全世界へ返していく制作。
「版権」とか「著作権」とか「個人の所有権」とか・・・そういうものの方向性を考えたとき、
私はどうしても自分のマンガの描き方に戻ってしまって、
「でも、私のものに本当のオリジナルなんかないのになぁ」
と思って考え込んでいたりします。
私は 「読んだマンガの中身の記憶はそれを読んだ読者のもの」 だと思っています。
100人が同じ本を読んでも、100種類の記憶になって保存されるのではないかと思っています。
オリジナリティって、どういうものなんでしょうか・・・・ 不思議ですね。
ちょっと理屈っぽくなってしまいました。 子供の頃に読んだ本のお話でした。
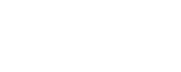
* 「糸杉」= 早川JA文庫<花模様の迷路>収録 .