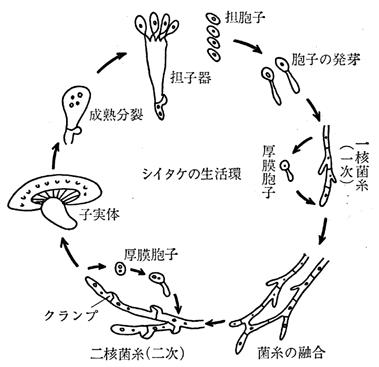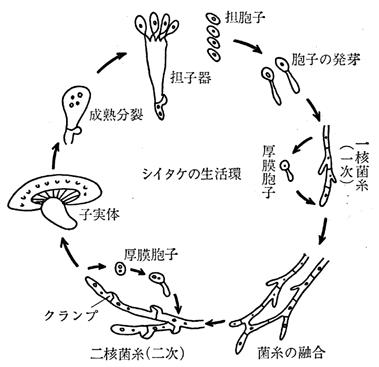|
椎茸の生活と性質
1.シイタケはどんな生活をしているか
(1)シイタケはどんなキノコか
|
シイタケは菌類と呼ばれる物の仲間で、ケカビや酵母、アオカビ、イモチ病菌などとは親戚にあたる。
「キノコ」という言葉は「木の子」という意味で、シイタケやサルノコシカケなどの様に、風で倒れた木や立木などに生える物を指していたが、いつの間にかマツタケやハツタケのように地面や落葉、またツクリタケのように藁などに生える物まで含めるようになった。
したがって「キノコ」というのは便宜上のよび名で、学問的な名前ではない。高等植物の花や果実に相当する菌糸の固まりをキノコ(学問的には子実体という)と呼んで、キノコをつくる菌類の仲間をキノコ類、学問的には高等菌類である。
菌類は高等植物と違って葉緑体を持たないから、炭素同化作用で自分の生活に必要な栄養分を作ることが出来ない。動物や植物、時として他の菌類に寄生して腐らせ、栄養源としている。
生きている物につくか、死んだ物に付くかによって、活物寄生菌と死物寄生菌とに分けられている。
シイタケは日本各地の山間部に野生しているのが見られ、ミズナラなどの風倒木や、立ち枯れした物に生えているから、シイタケは死物寄生菌の仲間に入る。
枯れた木材を栄養とし、とくに木材の主要な構成分であるセルローズやリグニンを分解し、それを利用して菌糸を繁殖させ、キノコを作っているのである。このように、木材を栄養源としているキノコの仲間を、木材腐朽菌とよんでいる。
シイタケ栽培の上で害菌となるカワラタケやカイガラタケも、木材腐朽菌の仲間である。自然界でたくさんの仲間と競争したり、協力したりシイタケは進化したに違いない。 |
(2)シイタケの形
|
シイタケはどんな形をしているは誰でも知っているが、少し詳しく観察してみよう。キノコ(子実体)は笠(菌傘)と柄(菌柄)から出来ている、笠も柄もいろいろな形をした菌糸が集まって出来た物である。
笠は大小さまざまであるが、普通5~10センチ、円形ではじめ縁は内側に巻いている。色は淡渇色や茶褐色をしているものが多いが、中には真白でこれがシイタケかと思われるような変った色の物もある。
ルソン島やニューギニアの赤道の近くに自生しているシイタケは日本のものより色がうすくて、明るい色をしている。シイタケは、かさの色の善し悪しにり市場での値段が違う。
笠の表面には斑点があるが、これは「リン皮」と呼ばれる。リン皮は白いものや笠の色と同じで目立たない物など、色や形は様々である。大きくなると消えてしまうものもある。これはシイタケの品種を見分ける目安になって便利である。
キノコが芽(菌蕾)を出して間もない頃は、笠と柄は白い綿毛状の膜で包まれているが、笠が開いてくると膜はやぶれて、中にたくさんのヒダ(菌褶)が見える。このヒダを顕微鏡で拡大すると、梶棒の形をした担子器が沢山ある。
一つの担子器からは短い角の様な担子梗が4つ出て、その先に一個ずつ胞子が出来る。
胞子は植物でいえば花粉や胚のう、動物でいえば精子や卵子に相当するものである。胞子の大きさは幅が3から5ミクロン、長きが6から8ミクロンで、白ゴマを小さくした様な形をしている。 キノコの形は、かさの色や大きさ、柄の長さや太さなどシイタケの品種によって特徴があり、キノコが育つ環境によって変化する。2、3月の寒い時期に発生するキノコは、笠に亀裂が出来て肉も厚いが、4月になって気温が上がり、雨も多くなると、かさの平らな肉の薄いものになる。
| 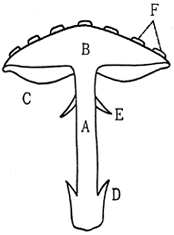
シイタケの断面
A柄(菌柄) B笠(菌笠)
Cヒダ(菌褶) Dツボ(脚苞)
Eツバ(下環帯) Fリン皮
|
(3)シイタケの一生
| 笠の裏のヒダにつくられた胞子は、キノコが成熟すると飛び散り、風によって遠くまで運ばれる。シイタケはこのように、胞子によって繁殖する。木口や樹皮の割れ日に落ちた胞子は、適当な温度と湿度があると発芽して菌糸になる。
胞子はかなり厚い膜に覆われ保護されていて、乾燥した温度の低い所に保存すると、3ヵ月以上も生きている。しかし70から80度の高温に会うと、4、5分で発芽力が弱くなる。また直射日光に曝されると、2、3分で発芽しなくなる。シイタケの胞子が風に飛ばされて適当な木に到着し、発芽して菌糸を伸ばすのはよほど運が良くなければならない。
胞子から発芽した菌糸を顕微鏡でみると、ところどころ横に膜(隔膜)がある細長い枝分かれした管の様である。膜と膜の間が菌糸の細胞である。この細胞も高等植物と同じように、1個の核を持っている。この菌糸のことを一核菌糸という。しかし、その核は半数の染色体組しか持っていない。
シイタケの場合、一核菌糸(一次菌糸)は、木材の中で増殖してもキノコを作らない。キノコを作るには、「性」の異なる他の一核菌糸と接合し、二核菌糸にならなければならない。この菌糸(二次菌糸)は細胞の中に、接合した両方の核を二つ持っている。
二核菌糸は特別な分裂をする。細胞と細胞の間にふくらみ(クランプ・コネクション、またはかすがい状突起)が出来る。これにより、一核菌糸とはっきり区別することができる。
二核菌糸は養分をとりながら増殖するが、やがて、綿の繊維のようにばらばらに伸びていた菌糸は集り方向性をもって生育する様になる。これがキノコのもと(原基)になるのである。このようにキノコになろうとして分化をはじめた菌糸を、三次菌糸と呼ぶこともある。
キノコの原基は適当な条件があたえられると、生育してキノコになる。若いキノコのヒダでは、それまで二核のまま分裂した核は担子器の中で合体して二倍体核になり、すぐ特殊の分裂を2回繰り返し(成熟分裂)、4個の半数性の核を作る。
それらは1つずつ若い胞子の中を移動して、キノコが生育するにつれて胞子も成熟し、飛び散るようになるのである。 |
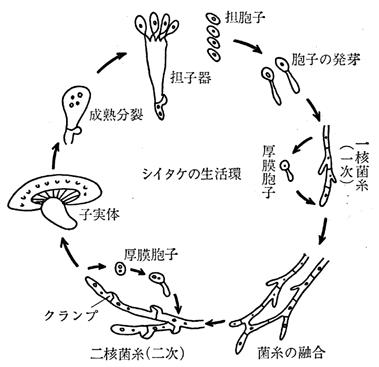
(4)シイタケの性
| 草や木は雄ずいの花粉が雌ずいの柱頭について受精が行なわれる。これは有性生殖というが、シイタケも性の異なる一核菌糸が接合しなければ、キノコが出来る二核菌糸にならない、動物や高等植物の様に有性生殖をしているのである。
一核菌糸すなわち胞子の性はどの様にして決まるのであろうか。1個のシイタケから沢山の胞子を取り、寒天培地に蒔くと2、3日で発芽する。これを単胞子分離といっている。
発芽した胞子を顕微鏡を使って、1個ずつ試験管の寒天培地に移す。これを単胞子分離と言っている。発芽した胞子は生育を続けて一核菌糸になる。
一核菌糸のいくつかを、一対ずつの組になるよう組合せて一本の試験管に接種する。これは柱頭に花粉をつけてやるのと同じ交配である。しかし、組合せによってクランプ・コネクションが出来るものと、出来ない物がある。クランプ・ヨネクションは接合が行なわれ二核菌糸になったことを示している。
このようにして調べてみると、一核菌糸を4つのグループに分けることが出来る。接合が行われるのは一定のグループ間だけである。
つまり1個のシイタケにつくられる胞子はAとBの二つの「性因子(不和合性因子とをもち、AB2つの因子の組合せによって4つのグループに分けられる。接合はAB二因子が異なるグループ間で起きるのである。この関係を「四極性」とよんで、シイタケでは昭和10年に西門義一博士によって発見されたものである。
ところが、系統の違ったシイタケから得た一核菌糸間で交配を行なうと、どの組合せもみな二核菌糸になる。系統の違うシイタケからの一核菌糸では、ABの性因子も違っているからである。
これらの発見によって、シイタケも農作物や草花と同じように、品種間の交配によって品種改良が出来るようになり、優良品種を種菌として原木に植える人工栽培が全国的に普及した。 |
2.シイタケ菌の性質
| シイタケの生活の仕方のあらましを述べた。シイタケの菌糸をよく繁殖させ、キノコをたくさん発生させるには、菌糸がどんな環境でどんな生活をするか、その性質を知る事が大切である。
特に人工栽培は人の手で環境をつくり、調節する栽培法であるから、菌の生態を知り、適切な管理を行なえば一層成果を上げることが出来る。 |
(1) 菌糸の生育と環境
|
①温 度
グラフから品種によって多少の違いはあるが、シイタケの菌糸は3、4度から33、4度の範囲で生長し、25度の時がもっとも良く伸びるが、品種によって生長最適温度が25度以下のもの、また25度以上の物があることが分かる。
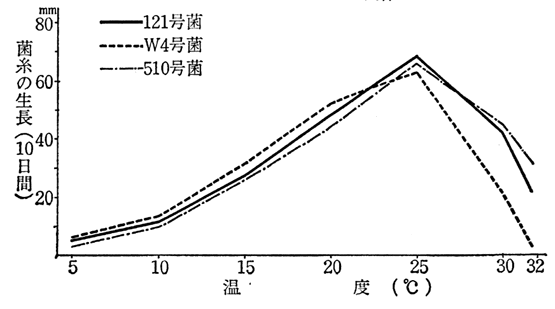 菌糸生長と温度の関係
冬には温度が0度以下になったり、夏には35度以上になることもある。このように温度が菌糸の生長温度の範囲を越えるとどうなるだろうか。
一般に菌糸は低温に対する抵抗力は強く、氷点下20度にホダ木を置いても菌糸は死ななかったという報告がある。北海道や高冷な山地でも栽培が行なわれていることから、菌糸の低温に対する抵抗力は強いことが分かる。
反対に高温に対してはどうだろうか。ホダ木を高温にさらし、ホダ木内の菌糸が何日間生存しているかを調べた。菌糸は高温で短時間で死んでしまう。
40度50度という高温は実際には起こらないと思うが、夏の直射日光をホダ木に当て、樹皮部の温度変化を調べたが、わずか数分で50度ぐらいになる。このことから、ホダ木は直射日光が当たらないように管理しなければならない。
② 水 分
菌糸が伸びるには温度とともに適当な水分が必要である。その水分には原木内の水分と空気中の湿度があるが、とくに原木内の水分が菌糸の増殖に大きな影響を持つ。
オガクズ培地を使って、菌糸の生長と水分の関係を調べると、60%の含水率の時が最も良く菌糸が伸びる。それより多くても少なくてもいけない。これはそのまま原木に当てはまらないが、原木を水に漬けて飽水状態にすると菌糸は伸びないし、また乾かし過ぎて、木材の繊維部分は飽水しているが空隙には全く水分のない状態(繊維飽和点という)の20から26%以下になれば菌糸の伸びは悪くなる。原木内での菌糸の繁殖には25から45%ぐらいの合水率が最も良い。 |
原木含水量と菌の伸長
| 原木含水率 |
菌の初期伸長(90日間) |
(乾量ベース)
38.2% |
(湿量ベース)
27.6% |
1.2㎜ |
| 42.5 |
29.8 |
3.4 |
| 45.3 |
31.2 |
9.1 |
| 47.9 |
32.4 |
13.9 |
| 51.6 |
34.0 |
24.4 |
| 53.3 |
34.8 |
36.8 |
| 60.4 |
37.7 |
44.7 |
| 61.4 |
38.0 |
46.9 |
| 65.4 |
40.0 |
55.2 |
| 70.3 |
41.3 |
55.2 |
(秋山種菌研究室) |
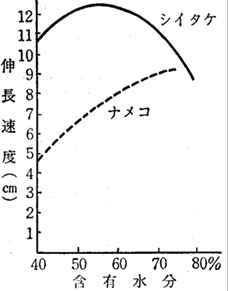 オガクズ培養基の含水量と成長 |
|
③ 酸素
菌類には、空気を好む好気性菌と、空気のない所でよく生育する嫌気性菌とに分けられる。シイタケは好気性菌で、その菌糸は空気のない所では育たない。
原木を飽水状態にすると菌糸は伸びないと前に述べたが、これは水分の問題ではなく、水分が多くなるとそれだけ空気が少なくなり、酸素不足になることも原因している。原木内にシイタケ菌糸がもっともよく生育するのは空隙率が20%をやや下まわった時であるといわれている。
④水素イオン濃度
酸性かアルカリ性かはpHの数字で表される。pH7が中性で、7より大きい時はアルカリ、小さい時は酸性であることを示す。
シイタケの菌糸とpHの関係をみると、pH4.6から6.0までの微酸性で最も良く生育し、強い酸性やアルカリ性では生育は悪くなる。
ホダ木を浸水するとき、新しいコンクリートの水槽では、アルカリ性になっていることがあるので注意しなければならない。強いアルカリ性の水に浸水すると、次回からのキノコの発生が悪くなる。
⑤光 線
シイタケ菌糸の生長には光線は必要でない。実験室的には暗黒状態の方が、よい生長をするという実験例が得られている。しかし実際の栽培では、枝のしげった暗いホダ場は温度が低く、風通しも悪い。このような所では原木内への菌糸の広がり悪くなる。チラチラと木洩れ日がさすくらいの所がよい。 |
(2)キノコの発生と環境
| でたらめな方向に生長していた菌糸が、どうして一定の方向に向かって生長を始め、多数集まって原基になり、キノコに生育してくるかという研究がヒトヨタケやスエヒロタケを使ってなされてきている。同じキノコの仲間であるシイタケにも、これら研究成果はある程度あてはまるはずである。
① 温 度
キノコは一般に低温が刺激になって原基を作るといわれている。これはシイタケにも当てはまり、品種によってかなり長い期間低い温度にさらされる必要のあるもの、高温時に短い時間低温処理されれば良いもの、ある期間高温と低温の変動の繰り返しによってキノコが出るものなどがある。
暖冬の年は不作だとか、日照りの夏は収量が少ないなどと言われて来たが、これは低温刺激が適当に与えられないためと考えられる。
キノコが発生してから生長する時の温度は、低温の方が充実した品質の良いキノコになるが、採取できるまでの時間がかかる。高温ではキノコの質が柔らかくなり、小さいうちに笠が開き柄も長くなって品質の劣った物になる。
②水 分
キノコの発生にはホダ木に含まれる水分と、ホダ木を取り巻く空気湿度が関係するが、キノコが生長する時はより多くの水分が必要である。
ホダ木の水分が多くなると菌糸の生長は妨げられ、逆にキノコは発生し易くなるが、乾燥し過ぎて含水率が25%以下になると発生は著しく悪くなる。
キノコが生育するには80、90%の空気湿度が適当で、これより少ないと発生したキノコは生長を止めてしまう。また湿度が多すぎると、キノコが水分を含みすぎて商品価値が落ちる。
③ 光 線
菌糸の発育には、光は必要としないが、キノコの原基ができ、それが生長するには光が必要である。暗黒状態ではキノコは全く出来ない。
寒天培地でシイタケ菌糸を光をあてて培養したときは、20、25日目くらいからキノコの原基が出来はじめるが、光を全くあてないと何日おいてもキノコを作らない。また、最初光をあてて、あとは暗黒の状態にしておくと、キノコの原基は出来るが、キノコに生長しないで、また菌糸にもどってしま。
ホダ木の場合も光線の無いとキノコが発生しないし、発生しても光が少ないと笠の色が薄くなったり、柄が長くなったりして形が崩れ易い。品質の良いシイタケをたくさん発生させるには、ホダ場を明るくすることが必要である。
|
|