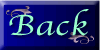
私は自宅のリビングで、一人ソファーに沈み込んでいた。足元には出していなければならなかった、封筒が落ちている。
私の親友からの連絡はない。
ついていけば良かったと後悔していた。俺は大丈夫だからと、言い張った彼に、私は置き去りにされたのだ。
そのままどこへ行く気にもなれず、よろよろとエレベーターを上った。
外はすっかり夜が更け、車の行き交う音だけが、虚しく響いている。
その重い空間を破るように、電話のベルが鳴り響いた。
私は奪うように受話器を取った。
「火村か!」
「い……、いえ。あの、片桐ですが」
張り詰めた気持ちが弛んで、その場にしゃがみこんでしまった。
「何かあったんですか?」
心配そうな片桐の声に、私は無理に元気を装った。
「何もないです。何も」
そう言って、はっと気がついた。フロッピーは私の足元にある。
「あの、片桐くん。原稿のことやろ?」
「はい。送って頂けたでしょうか」
「ごめん、まだここにある。原稿はあがってるよ」
そんなあーと叫ぶ彼に謝り通して、明日必ず発送することを約束した。
通話を切ったとたん、またベルが鳴った。
「有栖川さんですか?」
電話は船曳警部からだった。わざわざ事後報告に掛けてきてくれた。
やはり父親を殺したのは、弟の真一の方だったという。酔って帰った父親が子供部屋に入ってきて暴力を振るうのに、真一は突き飛ばし、尻もちをついたところへバットを振り下ろした。正当防衛がとられにくいと判断した姉は、遺体をリビングに移し、辺りを散らかし、自分がやったことにした。
父親が八つ当りで投げつけた馬券を片付ける際、一枚だけ見逃してしまったらしい。火村がバットだけが部屋の外にあるのはおかしいと判断した点だが、弟は関係ないとするために、玄関やリビングにあったものをわざわざ運び込んだのだという。
「天網恢恢疎にして漏らさず。悪事は必ず露見するものですわ」
ちょっと比喩が違うような気がしたが、私は笑える気分ではなかったので不問にした。
「あんな馬券、見つけなければ良かった……」
「いや、有栖川さん。有栖川さんが見つけなかったとしても、我々が見つけてました。あんまり気にせんといてください。むしろ、容疑者を間違えずに済んで、感謝しとるくらいです」
警部は私があの姉弟を追い詰めたと気にしていると思ったのか、隠そうとしたことを責めず、それどころか慰めてくれようとする。
けれど私は、自分が火村をハンターにしてしまったことを悔いていた。
警部の言うように、警察はすぐに、あの馬券を見つけただろう。それならそれで良かったのだ。警察があの姉弟の企みを暴くのは、ちっともかまわないとさえ、今では思っている。私は自分が隠したことで、あの場で火村に謎を解かせてしまったことを、今一番悔やんでいるのだ。警部には申し訳ないけれど。
「火村はどうしました?」
「そちらに行かれたんやないのですか?」
「いいえ」
私は一歩も動けず待っていた。
「かなり前に出ていかれました。てっきり、有栖川さんの所におられるとばかり思ってたんですが」
明日も講義があるから帰ったんでしょうと、私は警部と自分を誤魔化して、電話を切った。明日、火村の講義はない曜日だと、誰よりも知っているくせに。
私は馬鹿野郎と呟いて、ベッドに潜り込んだ。くたくたなのに、なかなか寝つけなかった。
……貴方なんか生まれてこなければ良かったのよ。
誰かが夢の中で私に向かって言っている。
誰だろう。
……貴方がいるから、私は幸せになれないわ。
酷い。自分の不幸を人のせいするなんて。
他人に責任をなすりつけて生きるのは、さぞかし楽だろう。
……貴方なんか、いなくなればいい。
それはあんたが当たり散らす相手をなくすことだよ。
私は言葉にはせず、心の中で嘲ら笑っている。
……貴方なんか死ねばいい。
それなら母さん、あんたこそ死ねばいい。
とっても楽になれるよ。
人を羨むことも、邪魔にすることも、何にもなくなって、心が綺麗になるよ。
すごく、楽だよ。
死になよ。
とっても、とっても、楽になれるよ……。
「わ・・・・っっ!」
私は飛び起きた。
恐怖で心臓が早鐘のように打ちつけ、汗をびっしりかいている。
肩が激しく上下する。両腕で自分の身体を抱きかかえるようにしてみても、身体の震えは止まらなかった。
どうしてあんな夢を見たのだろう。私の母親は、自分の息子に、有栖川という名字に、有栖という名前を付けるくらい、お茶目な人物なのだ。どう引っ繰り返しても、あんな会話をするはずがない。
それとも、母親の身に何かあったのだろうかと、急に不安になってきた。
時計を見ると、午前四時。元気かと、電話をするような時間ではなかった。せめて後三時間、待ってからにしよう。緊急のことがあれば、きっと父親が報せてくれると言い聞かせて、待つことにした。
のろのろとベッドを這い出て、洗面台の前に立った。
酷い顔をしている。顔を洗おうと思い、勢い良く水を出したところで、私は愕然とした。
どこかで出会った光景。
知りたいと思い、話してほしいと願った答えが、そこにあった。
流れ出る水もそのまま、私は鏡の中に、哀しい友人の顔を見た。
夜が明ける。
明けぬ夜などないのだと。けれど、夜明けを待てぬ人はどうすればいいのか、誰も教えてくれはしない。
私は一人の男を待っていた。
必ず来る。
私にあの夢を見せた男は、必ずやってくるだろう。
星が消えてゆき、月が色を失くす頃、控えめなノックの音がした。
私は急いでドアを開けた。
火村は憔悴しきった顔で、ぼんやりと佇んでいた。
「アリス……」
「待ってた」
それ以上の言葉は必要なかった。
ドアの中に入ると、火村は私にしがみつき、決して力を緩めようとはしなかった。
「助けて……くれ」
初めて聞く、彼のSOS。
「俺はいつでも、お前の為にいるよ」
火村は私を抱き上げ、仄暗い部屋へ足を踏み入れた。
「アリス……」
私を呼ぶ擦れた声に、荒い息を堪えて目を開けてみると、火村は縋るような眼でこちらを見ていた。
「キスしても……、いいか……?」
今更な問いに、私は笑ってしまった。痛みを堪えているためか、それは彼の眼には儚なく映ったらしい。そんなたまではないのは、お互いに百も承知のはずなのだが。
火村は綿毛に触れるように、そっと唇を重ねてきた。
触れるだけのキスは、息を継ぐ間もなく、深くなっていった。熱い舌に蹂躙され、身体ごと揺さ振られ、やがて私は灼熱の夢の中に堕ちていった。
火村は眠っていた。安らかな息をしている。それが私にはとても嬉しい。
高い鼻梁と、切れ長の目。薄く開いた唇の色は、生気を取り戻していた。
細い喉、思いの外筋肉のついた双肩。
彼の身体を辿っていて、目を止めた。幾度か一緒に風呂に入ったことがあるが、気づかなかったものを見つけてしまった。
左胸、乳首よりやや中央寄りに、一センチほどの白いラインがあった。
何だろうと思って指先で辿ると、火村が目を開いた。
「アリス?」
擦れた声に、何故か恥ずかしくなり、私は顔を逸らした。
「これはな、昔、ある人に刺された時のものだ」
あっさりと火村が告白するのに、私はひどく驚いて、彼の顔をまじまじと見た。
「そんなに驚くなって。果物ナイフだった。殺そうという気は、なかったのかもな」
「でも」
「お互いにお互いが邪魔だった。相手は俺がいなければいいと思い、俺もそんなに思うなら、お前が死ねばいいと思った。お互い様だよ。行動に出た分、相手の方が利口だったのかもしれないぜ。俺が殺し損ねたのは、ただ単に、タイミングの問題だった」
「止せ」
「それから、俺は相手を真剣に殺そうと思った。何度も計画を練った。けれどな、完全犯罪なんて、とうてい無理なんだと思い知った。そこで初めて、俺は自分の心の中の悪魔に気がついた。人の死を真剣に願うなんて、あいつと同じだよ。それがとてつもなく腹立たしかった。犯罪社会学を学んだのは、そんな自分を少しでも、解放したかったからだ。どこまでも、エゴイストだよな」
「もういいから!」
私はたまらず火村にしがみついた。
「聞いてほしいんだ」
穏やかな声に、そっと顔を上げると、火村は優しい表情で、静かに私を見ていた。
「アリスに聞いてほしい。駄目か?」
「ええよ。それでお前が少しでも救われるなら、俺はどんなことでも聞く」
ありがとうと、火村の唇が動いた。私は初めて自分から、彼に口づけた。火村は嬉しそうに笑った。