|
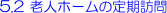
- 一年目の独居老人の訪問調査、二年目の福祉部クライエントのケースワークなどを通して、私もようやく福祉部スタッフとしての位置を占めることができた。私たちは、ケースによって、福祉士、心理士、医師、看護婦、作業療法士等の専門職とのチームワークで仕事を進めるようになっていた。クライエントは私が日本語で、その家族とは三世職員がポルトガル語でコンタクトを持ち、家庭訪問には二人ペアで出かけたりもした。
さて、三年目に私に与えられた仕事は、援協傘下の二つの老人ホームの定期訪問だった。この仕事は、それまでスタッフの一人である心理士が担当していたが、退職したために私に回ってきた。彼女のあと、入ってきたスタッフは、二人とも三世で日本語はほとんどできない。ところが、ホームの入居者は大部分が一世のため、日本語でのコンタクトがよいだろうとの、福祉部長の判断だった。
私にとって、荷が重かったのは、両施設ともサンパウロから数十キロ離れていたことだった。一つは、サントス市、もう一つはスザノ市にあった。サントス市はサンパウロのはずれから長距離バスで一時間ほど山を下った港町である。スザノ市は、やはりもう一方のはずれから、電車で一時間、そこからバスで山を上ること三〇分、徒歩で一五分とわが家からはたっぷり二時間半かかる。朝7時、子供たちが家を出るのと同時に、私も出発しなければならなかった。出張日には、子供たちのお弁当もなるべく簡略化し、夫の朝食をテーブルに並べて出かける。ちょっぴり夫に迷惑をかけるなと思いつつも、これはもう、私の仕事として自分の中にしっかり定着していた。
ただ、どうしても夫に話せなかったのは、道中多少の危険が伴うことだった。サントスの方はまだ高級バスで行けるし、街中なのであまり問題はなかったのだが、スザノの方は、電車で行くのだが、これが二時間乗っても五〇円くらいの低運賃の国鉄だ。いなかからサンパウロに仕事に出てくる貧しい人々の足になっている。ドアはこわれて開け放しで、冬などほんとに寒い。窓はガラスだと割れて危険だからか、プラスチック。しかし、それがキズだらけで、外はよく見えない。乗っている人も一見ちょっと危ない感じの人たちだ。いつもより、より一層身なりには気を使い、靴も汚れたものをはいた。電車の中では、ありとあらゆる物を売り歩いている。新聞、ガム、ポップコーン、アイスクリーム、ひげそり、ライター、おもちゃ、バンドエイド、ノート、ボールペン…。ひっきりなしに売りにくる。朝はラッシュと逆方向だが、都心に向かう人々は電車にぶら下がるようにして乗ってくる。時々ふり落とされるという事故も起こるが、車輛を修理するお金もないらしい。たまに、スケートボードに両足のない人が乗ってくる。手でボードを動かしながら物乞いをするのだ。人々はさっとサイフから小銭を出して、施す。自分が貧しくても、働けない者には、おしまず与える。これが、ブラジル人なのだ。またバスも電車も、懇切ていねいなアナウンスなど無いので、キョロキョロしながら、自分の降りる所を確認しなければならない。
しかし、慣れるにしたがって、この小旅行も楽しめる余裕が出てきた。
|
