|
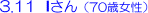
- Iさんは、静かな住宅街のアパートに住んでいる。隣りに住むHさんの紹介だ。一月に夫を亡くし、一人暮らしと聞く。援協から調査の旨を伝える。わりと大柄な白髪のおばあさん。部屋の中は薄暗く何か生気の無いさえない顔が気になる。夫を亡くしてまだ半年と少し。しかもガンとわかってから四〇日、あまりに急な夫の死にようやく適応してきたといったところか、あまり元気がない。テーブルに向かうと部屋の電気をつける。「援協」という言葉で思い出したように語り始める。
「夫が病気になる前、イタケエラ地区にロッテ(土地)があるんで援協の病院に寄付しようと思って、援協の人に相談したんですよ。私たちも年とって病気になったらお願いしようと思ってね。でも、インポスト(税金)の関係で待った方がいいって言うんでそのままになっちゃったんです。
主人は、去年十一月に胃ガンだとわかり、一月に亡くなってしまいました。だから寄付の話はお断りしようと思ったんです。夫はね、ある日、首にグリグリができてるって言うんですよ。痛くもないし、気付かなかったようです。それで、早く援協に行ってみてもらいなさいってすすめてね、さっそく勤めの帰りに寄ったんです。そしたらすぐに、あちこち検査だって。シャッパ(レントゲン)撮ったり、採尿やら胃カメラやらされて…。その後結果を聞きに行ったんです、二人で。先生は、夫にはね『胃カイヨウだから手術しなくちゃいけない』って言われたんです。でも夫がトイレに行っている間に、私に『奥さん、ご主人は胃ガンです』と伝えました。それでびっくりして…今までは何でもなかったし、食欲だって年寄だから日によってはあまり無いこともありました。でも、特に変ったことはなかったんです。
それで娘の一人が医者なので、そこの病院にシャッパやら診断書を持って行ったんです。そしたら、そこで手術できるということでね、頼んだんです。ま、医者が悪いわけじゃないけど、胃を切って縫ったところがくっつかなくて、開いてしまうんです。それで、入院して四〇日で亡くなってしまいました。ガンと聞いた時から覚悟はしてましたけどね。こんなに早く亡くなるなんて思いませんでした。78歳でした」
「じゃあ、まだ気持ちが落ち着かれませんね」
「ええ、生活費の方は夫が長く勤めていたので死後半年はお給料もらってましたし、今は夫のペンソン(年金)もらってますから。ぜいたくしなければ、私一人食べていけます。ここの管理費が一〇ミルくらい。それに電気、ガス、電話でしょ。子供は六人。娘四人息子二人。みな結婚しています。一人でやっていけるうちは自分で生きたいと思うんです。『いつまでも、こうしてても仕方ない』と子供たちは言うんですけれどね。今さら子供たちの家族へ入り込む余地は無いですよ。私がそこへ行くのは困難ですよ。それに、子供の所へ行ったら、家事はしなくなるし、支払いなんかもしなくて済むから…。そうやって頼って生きてるとボケるんじゃないかと思うんです。一人暮らしだと光熱費などの期日も覚えておかないと、罰金をとられてしまうし、食事だって、何か作って食べなきゃならない。老化防止になると思うんですよ」
夫の死後半年ほどで悲しみもまだ癒えてはいないが、「一人で生きたい、一人で生きなきゃ」という気持が出てきたのだろう。精神的自立へ向かっているように見受けられる。
「アクリマソン地区に末の娘が住んでますから、週一ぺん、フェイラ(青空市場)に一緒に行ったり、小さい孫のお守りに泊りに行ったりしますよ。フェイラの帰りにお茶飲んだりしてきます」
「体の具合はいかがですか」
「時々ふらつくんです。前にあんまりふらふらするから人に聞いて、頭のてっぺんにお灸をすえるようになったんです。そしたらよくなったんで。その時は夫にやってもらったんですが。お向かいの家にやっぱり日本人がいるんですよ。奥さんがとても良い人で、その人に頼んでやってもらおうかと思うんですけど。道路を渡る時に右左と頭を振るでしょ。ゆっくりやらないとふらつくんです。だけどゆっくりしてると車がくるから危なくて、あんまり外には出ないんです。あんまり具合が悪かったら娘のところに行きます」
「毎日、どんな風に過されますか」
「そうね、主人が生きていた頃は毎朝早く起きてたんだけど。カーマ(ベッド)の中でね、一人で起きても何するでもなし、と思うから8時頃まで寝てますね。カフェ(朝食)して、家事したりして。お昼は1時頃。一人だから一合半炊いても何日もあるでしょ。だから、小さい鍋で温め直して食べるんです。私は小さい頃から裁縫してましたから自分の物はほとんど何でも縫います。ボルダード(刺しゅう)もしますけどトリコ(編物)だけは嫌いなんです」
と言って隣りの部屋に案内してくれる。夫の部屋だったとか。ベッドと机が一つ。ベッドの上にはズボンの型紙と布地が裁ってある。
「今、ズボンを作ってるんです。いろいろ売ってるけど老人に向くようなのはなかなか無くて。孫の布団カバーを五組作ってやったり、誕生日にパジャマを作ってやったりしています。でも、目が悪くなってなかなかね…。まあ、何やかやして毎日過してますけれど。一番いけないのは夕方。夕方が一番いや。誰も帰ってくるわけじゃないしね。食事を作る気もないし…。暗くなるし…。どうしようもない時はお向かいの奥さんのところへ行っておしゃべりしてくるんです。」
彼女は、夕方の淋しさに耐えられないというように強く訴えた。
「ブラジルに来て、リベロンプレットに入りました。モジアナの。一九二八年に来ました。カフェやら綿やら作ってました。一九四一年コチアに移って野菜作りになったんです。その頃日本語教師をしてた夫と結婚しました。でも子供の学校の問題で一九五三年にサンパウロに出てきたんです。それから夫はスポーツ関係の仕事をしてました。65歳で定年してからも、週三日くらい出勤してました。あの人は折紙が好きで、会社に行かない日は一日中、部屋で折紙の研究してました。ここに出ているのがあの人の作品なんです」
と言って日本折紙協会発行の雑誌を見せてくれる。
「亡くなる前に、掲載されることはわかっていたんですが、雑誌が届いたのはつい最近。とても残念です。これは主人の作品です」
と、隣りの部屋の戸棚の中の作品を見せてくれる。スクラップしてるものもある。作り方も書いてある。ポルトガル語の解説書を作るのが夢だったそうで、その準備もしていたという。ブラジル人に教えたこともあったが、かれらは簡単なものを覚えるだけで長続きせず収入にはならなかったそうだ。
「孫たちも時々ここに入ってはイタズラするんですよ。今、孫の一人が折紙に興味を持ってね。これを見ながらけっこう器用に作るんですよ」
「それは楽しみですね。やっぱり血は争えない。ご主人も喜んでらっしゃいますよ」
「ええ!」
とうれしそうに目を細めた。
ご主人を亡くしたという「悲哀の仕事」がまだ完全に済んでいないようだが、徐々に一人暮らしへの適応が進んでいる。子供たちが近くにいることが救いとなっているようだ。
最後に、
「私も、もう少し落ち着いたらボランティアでもしたいと思うんです。あのペンソンMで日系婦人たちが縫い物のボランティアをしてるでしょ。そうすれば、少し気が晴れると思うんです」
と言った。
|
