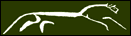
BACK
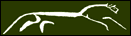
クライング・ゲーム"The Crying Game"1992年英:ニール・ジョーダン監督
IRA 組織が英国軍兵士を拉致する手口(性的手段を含む : 現在は IRA でもこの手口は禁じられている)について詳しく書かれた記事を読んだ監督が、長年あたためていた脚本。本作でアカデミーオリジナル脚本賞を受賞した。
ジョーダン監督は言う:
私は黒人でも、兵士でも、IRA 組織の一員でもないから準備にあたり慎重にならねばならなかった。IRA を異常な殺人集団として描きたくもなかった。ただ彼らは非常につよい信念に基づくあまり、人々に、また時には 彼ら自身にも受け容れがたい行動をとってしまう。主役の IRA 兵士ファーガスには、初監督作『殺人天使』 "Angel" からの常連スティーブン・レイ。色仕掛けで拉致される英国軍兵士にフォレスト・ウィテカー。 監督は "The Color of Money" での彼をみて、この役に他の俳優は考えられないと思ったという。
この作品に使われた曲を演奏するミュージシャン、プロデューサーにもジョーダン監督は隠し味をを施している。
ミランダ・リチャードソン。『ダメージ』での政府高官(ジェレミー・アイアンズ)の妻でジュリエット・ビノシュに夫を盗られてしまう役では、不実な夫をののしる際にも無意識のうちに ヤカンを火にかけようとする仕草に日常の家事が全身にしみついた哀れさを見事に表現していたが、ここではフォレスト・ウィテカーを色仕掛けで誘惑し、同志ファーガスにつきまとう妖婦ジュード。囚われの身となったジョディ(ウィテカー)との間に奇妙な友情が芽生えだしたファーガスが、彼から聞くおとぎ話。カエルとサソリ。川を渡りたいが泳げないサソリをカエルがおぶって渡ってやる。しかしサソリはカエルをその毒針で刺してしまう。 カエルが「なぜそんなことを?」と苦しみながら尋ねると、サソリは答える「それがぼくの性(さが)だから」。 物語はこの寓話を下敷きに進む。自分でさえ予期しなかった行動をとったファーガスはそれを「自分の性」と言って、ただ肩をすくめるのだ。
パーマーの危機脱出 "Funeral In Berlin"1966年英:ガイ・ハミルトン監督
この作品を偶然テレビでみなければ、マイケル・ケインに対してここまで思い入れることはなかったものを。ランブリング・ローズ"Rambling Rose"1991年米:マーサ・クーリッジ監督
原作はレン・デイトン『ベルリンの葬送』。「スパイ小説の詩人」と異名をとる作家で、「私」(一人称)で語られる、オックスブリッジを出て「いない」異色のスパイを主人公にした作品群で知られる。 ほんとうは『イプクレス・ファイル(邦題:国際諜報局)』(処女作)とその映画化されたものの評価がもっとも高いのだが、私個人の好みは『ベルリンの葬送』なのでこちらを。『国際諜報局』〜『パーマーの危機脱出』〜『10億ドルの頭脳』とシリーズ化されている。いずれも主演はマイケル・ケイン。便宜上ハリー・パーマー(ケインによるともっともマヌケで平凡な名前をあれこれスタッフで考えた末の命名)と名づけられた主人公のスパイ活動を淡々と描いたもの。 主人公と上司ロス大佐は3作を通してなかなかスリリングかつ英国的な絡みをみせてくれる。大佐は山高帽とこうもり傘の似合うエリートである(英国の諜報機関はオックスフォード、ケンブリッジ卒で占められていたのだから当然か)。家ではガーデニングに精を出し、スクールセーター(わははは)を着用と 一部の隙もない英国紳士であるが、パーマーとばったりスーパーの食料品売場で鉢合わせするところなど、実は奥様の尻に敷かれているのがありあり。
一方パーマー。もともと陸軍の伍長で、どうも物資の横流しをして服役中にその才覚を買われ、身柄釈放と引き替えに諜報活動を強いられているという立場らしく上層部への忠誠心などあったものではない。黒縁の眼鏡にネクタイを締め、寝室のないフラットで自炊(得意)する生活。ベッドの端から女物の下着がのぞいていたりする あたり品行方正な生活とも思えない。目覚まし時計で起き、コーヒー(紅茶は飲まない)をわかし、新聞の求人欄からまずチェックする・・・。 このふたりがぎしぎしとかみ合わないながら組み、土曜の朝(週休2日制のサラリーマンスパイである)にロスから呼び出しを受け、いやいやながらバスで郊外にある彼の屋敷に出向くパーマーがおかしい。
"Good morning, Sir"
"Good afternoon Palmer." この嫌味な掛け合いでファンになってしまった。ここから舞台は「壁」のあるベルリンに移るが長くなるので筋は省略。シリーズを通して共通するのは、パーマーが決して人を殺さないこと、上司への忠誠心はないが、基本的に祖国を守ろうという信念は持っていること。 上司との交渉で給料の上乗せやクルマを要求するが、最終的に報償としてそれを提示されると"I'll walk." と断りオフィスをあとにする。サラリーマンスパイであっても、彼にしかわかり得ない哲学があるようだ。
2作目、3作目に登場するソ連 KGB のStok(シュトーク)大佐。敵ながらパーマーの無表情な仮面の奥にある反骨精神と公正さが好きで、彼と奇妙な友情を結んでいる。
"English! (イギリス人!)" とひとなつこっく声をかけ、(コーヒー党の彼に)金属コップにいれたまずそうな配給の紅茶をふるまう大佐の方が上司のロスよりよほど人間味あふれる親父として描かれている。 ハヤカワ文庫『イプクレス・ファイル』『ベルリンの葬送』『10億ドルの頭脳』が絶版。ビデオは大きなレンタル店には置いてあるかもしれません。
申し添えておくと『オースティン・パワーズ』のモデルはこのハリー・パーマー。
ロケーションに使われたのは築150年を経たヴィクトリアンハウス(舞台設定はジョージア州だが撮影はノースカロライナ州)。ローズの、花びらのような衣装をデザインしたのは英国のデザイナーである ジェーン・ロビンソン("Dreamchild", "Blue Sky"など。"A Handhul of Dust" ではアカデミー賞にノミネートされた)。
冒頭でローズが履いているスエードの茶色い靴はアンティークだったため、その日の撮影終了時にはもう破れてしまっていたという。 彼女というものをいちばん端的にあらわしているのがその着こなしである。ひらひらの薄い、透ける布地でできたワンピースにたくさんのばらのつぼみを縫いつけ、下着はつけず、胸は半分露わになっている。ピンクの頬紅、赤い口紅を塗った顔が童女のように幼い。 きれいなものをこどもが着飾るように身につけているだけなのだ。胸を出しているのもスカートが透けているのも、男を誘うためではなく、田舎ものの彼女の精一杯のおしゃれに過ぎない。13歳の少年 Buddy (ルーカス・ハース)の目を通した、彼がその夏に出会った19歳のお手伝いローズ(ローラ・ダーン)との交流と別れ、ひとことで言えばそうなのだが、この心優しい少女は自分でもどうにもならない性欲の強さに苦しんでいた。Buddy は少年の好奇心からローズを愛撫し、彼女が達してもその意味までは理解できないが、彼女がそのことでひどく罪悪感を抱いていることを知る。 「私はきっとあたまがおかしいんだわ、お願い、このことは誰にも言わないで、ここを追い出されたくない」と泣いて懇願する彼女に秘密を守ると約束した時から、彼は少年から「紳士」になったのだ。このことは彼の服装(これ以後半ズボンを履いていない)で控えめに表現されている。
ルーカス・ハースはロバート・デュバルの演技をよく観察し、立ち姿まで同じように腰に手を当てている。彼は撮影当時役柄と同じ13歳で、Buddy の抱く興味や女の子に対する感情はごく自然なものとして理解できたという「ぼくも彼と一緒に成長したんだ」。
チカチーロ "Citizen X" 1994年米:クリス・ジェロルモ監督
1992年にロシアで死刑判決を受けた実在の殺人鬼、アンドレイ・チカチーロ(ジェフリー・デ・マン)と彼を10年かけて逮捕に追い込んだ捜査官の実話に基づく作品。 事件の凄惨さを描くより、ここで強調されているのは、被害者がみつかるたびに涙を流し、捜査員たちに「死者に礼くらい尽くせ!」と声を張り上げる捜査官ブラコフ(スティーヴン・レイ)と、 最初のうちこそ彼をもて余し気味だったが、次第にその情熱に感化され、窮地に立たされた彼を支援する上司(ドナルド・サザーランド)との交流である。
指揮をとるだけでなくみずからも張り込みを続け、物資不足で冬でもコートすらない警官に自分のを「事件が解決したら返してくれ」と差し出すブラコフ、捜査員たちがみるみる「ブラコフ組」と 呼びたくなるような生え抜きに変わっていく。
ブラコフは張り込み中駅の待合室で不審な挙動をみせたチカチーロを逮捕するものの、彼が共産党員だという理由で釈放を命じられる。共産主義社会に犯罪が発生するはずがない、党員ならなおさらだと主張し捜査の障害になるのは市長をはじめとする党幹部達である。同性愛者、ジプシーなど社会的弱者からまず調べるよう強要され、思わず「死体の方がまだ有益だ。指紋もとれる」とこぼした言葉は職場の身内によって密告され、「そんなに死体が見たいのか、この変態め」と揶揄される。 ブラコフはプレッシャーから精神のバランスを崩し一時は休職し療養生活を送ることになる。
上司フェチソフは幹部のひとりのスキャンダルをつかみ、ブラコフを後方から守ってやる。10年の捜査のあいだにソ連はペレストロイカを迎え、フェチソフは警視総監に昇進し、ブラコフにとってさらに心強い味方となった。駅ごとに捜査員を配置し、不審者に尋問する大がかりな捜査が可能になったころ、 以前逮捕したチカチーロの名前を無人駅での尋問メモにみたふたりは森で新たな被害者を発見する。二度目の逮捕でチカチーロはついに犯行を認め、死刑が宣告された。Stephen Raeは "Crying Game" をはじめとするNeil Jordan監督作品の常連でアイルランド出身の、自分でも劇団を主宰する才人である。すこしくたびれたような目元の、あまり風采のあがらない容貌だが芯に1本筋が通っているような役柄を演じるとたいへん魅力的だ。
ケーブルテレビ用に制作され、全編ハンガリーで撮影された。 くずれかけた漆喰の壁や、枯れたひまわりの続く野原など、豊かな資本主義社会に住まう者の目にはいかにも貧しげに映る当時の共産圏の様子を上手にとらえている。
→ロバート・カレン『子どもたちは森に消えた』(ハヤカワ文庫)
小間使の日記"Le Journal D'une Femme de Chambre"1963年仏=伊:ルイス・ブニュエル監督
音楽も知的な会話もないのに「しみじみとおかしい」映画だった。ひとの価値基準や善悪の基準はさまざまだと日頃から思っていたつもりなのに、さらに上手をいく生き物たちがこの地上にはあたりまえに存在することをたっぷり見せてくれる。脱帽。単調な車窓の風景が続く冒頭部分。刺激もなく退屈な生活を一見予想させるものの、なんのなんの。列車から降り立ったのは若くないがパリ仕立てのコートと物憂いムードが人目をひかずにいられないセレスティーヌ(ジャンヌ・モロー)。彼女が新しく小間使いとして仕えることになった屋敷の主もその使用人も、みな一筋縄ではいかないものばかり。
潔癖性の奥様。女好きの婿養子。紳士のようでいて婦人靴を戸棚にしまい込んでいる大旦那(「これを履いて歩いてみておくれ、まるで靴が生きているようだ・・・」)。革命家気取りの不気味な下男。 「私は恋に生きる男なんだ」と初日から婿に言い寄られ、大旦那に「マリーと呼んでいいかな。小間使いはみなこの名で呼んだ。・・・ところで靴の大きさは?」と聞かれ、彼女に平穏な生活とは縁がなさそうだ。大旦那お気に入りの靴を履いて本を朗読するよう頼まれた彼女(奥様から禁止されたはずの香水をつけて部屋に向かうところ、曲者である)、大旦那は手づから彼女の靴を脱がせ、そのままうっとりと寝室にこもってしまった。そのころ、セレスティーヌのかわいがっていた少女が森で下男と立ち話をして別れた後彼の表情が一変、少女の後を追うように駆け出していった・・・
森の下草の陰からタイツを履いた足が投げ出されているのをカメラが映している。少女がかごに入れていたカタツムリが2匹、その上を触角を突き出しながら這っているのが、哀れな少女の身に起こったことを暗示している。結局、大旦那は寝台で靴を抱いてこときれていた。セレスティーヌは暇をもらい、駅で列車を待っているところに少女が森で死体となって見つかったことを知る。
「私にわかっているのはあの子が好きだったということだけ」下男が少女に妙な目つきを向けていたのを見ていた彼女は屋敷に戻り、男が殺した証拠をみつけようとするが尻尾をつかむことができない。下男は彼女に気のあることを告白、「お前も同類だ。俺にはわかる。一緒になってシェルブールで店をやらないか」と求婚する。セレスティーヌは色仕掛けで迫るものの、 「お前は特別だから、式を挙げるまではだめだ」と拒まれるとあっさり求婚を受け容れる。男の宗教的な貞操観念とその犯罪の落差には目もくらむほどである。「あの子を殺したわね?」「よせ」彼女の執念がみのり油断した男は逮捕され、彼女自身も彼女に気のあった退役軍人の妻の座におさまり、亭主を顎でつかうよい暮らしを手に入れる。彼女に執心していた婿養子はあきらめよく頭の鈍い下女に目を転じ、「私は恋に生きる男・・・」と納屋に連れ込み、奥様は夫から解放され、めでたくなるはずだったのだが、逮捕された男が証拠不十分で放免されたことを知ったセレスティーヌの気持ちは最後になっておさまらない。
エンドマーク(仏語だから"FIN")の出る直前に雷鳴がとどろき、人間のいとなみをあざ笑うかのように物語の幕を閉じる。
ブニュエルは難しい、でもブニュエルはおもしろい。監督は観るものに肩すかしをくらわせてほくそ笑んでいるに違いない。また、神同様神を「信じる」ものたちの描写も意地が悪い(下男はあれで敬虔な信者である)。 村人が聖職者に向ける目も同様。少女を殺した犯人を推理しあううちにこともあろうに、「あの物乞いをしていたふたりの巡礼神父かも」とひどいものだ。無垢な魂の持ち主であるこどもが命を奪われ、おのれの欲望にのみ忠実なおとなたちが世間的には幸せと呼べる結末を迎えるところなど、無神論者の彼ならではである。
ところで時代は第一次大戦のあとくらい?歴史に疎いもので。
パーティ Party1968年米:ブレーク・エドワーズ監督
「俺の映画から消えてくれ」「じゃテレビならいい?」
ロケ地を吹き飛ばしてしまったインド人俳優バクシを解雇するようにという連絡メモが手違いでハリウッド大物プロデューサーのパーティ招待客リストに書かれてしまったため、招待状を手にした彼が会場の先々で巻き起こす騒動。
バクシに扮するは「ピンク・パンサー」シリーズで名高いピーター・セラーズ。顔を塗り、インド訛らしい怪しげな英語。招待客も映画会社の社長、監督、ガタイはいいがおつむに栄養のまわっていないテキサス出身のカウボーイ役者にいかにもなヘアドレッサー(スープを飲む手つきも小指を立てて)、オーディション待ちの女優の卵など。セラーズは手を後ろで組んでほほえみながら会場を歩き回るだけで絵になる。自分で何かをすることよりも、しでかした結果を眺めながら固まっているリアクションの方が滑稽だ。彼とともに騒動に輪をかけているのが、酒好きなウェイター。トレイの酒を客が断るごと自分が飲んでしまい、千鳥足の度を深めていく。彼はたいてい客の後ろに小さく映っているのだがその姿を目で追わずにいられない。いつも、きわどいところで酒のグラスだけは落とさない(ただし料理は必ずひっくり返す)。
騒動は、主催者の娘が連れてきた反戦運動仲間たちとスローガンをペイントされたゾウの乱入でピークを迎える。
「奥様がプールに落ちました」「宝石だけは拾え」バクシはプールにゾウを入れ、ブラシでペンキを荒い流してやる。石鹸の泡が会場いっぱいに雪のように舞い上がるのは壮観だ。女性客の髪型、メイク、衣装がいかにも60年代(オースティン・パワーズ・・・)でおもしろい。セラーズの演じているのは人騒がせな男に間違いないが、善意に満ちた優しい人物で、ラストはほのぼの。排気筒からぷすぷす煙をあげる小さな三輪のカートで去ってゆく彼をずっと見送っていたい気分である。
ミニミニ大作戦"The Italain Job"1969年英:ピーター・コリンソン監督
目先の利くサギ師チャーリー・クローカー(マイケル・ケイン)が出所後計画した大仕事とは、トリノで行われる英国対イタリアのサッカー試合に乗じて、この都市の交通機関をストップさせ、その隙に現金輸送車を襲い金塊の山を分捕ることだった・・・。 彼は、規則正しい生活と完全な警備に守られている刑務所生活をみずから選び、所長以下を従え君臨するギャングのボス(ノエル・カワード)の支援のもと、この大博打のために周到な計画を練り、トリノの交通監視システムに入り込むため大女好きのコンピュータ権威(ベニー・ヒル)を誘い、いよいよ海を渡りアルプスを越え、イタリアを目指すのだが、マフィアの一味がそれを見逃すはずもなかった・・・。見所はなんといってもミニ3台が一糸乱れずトリノの街を走り抜けるカースタント。ユニオンジャックカラー(赤、白、青)3色のミニがイタリアのデカい車を小気味よくかわし疾走する。このカースタントにはいっさい特撮を使っていない。
あらすじはさておき、こぼれ話。まずコメディアンのベニー・ヒル、彼はコンピュータの権威で大学教授。世間知らずの教授を懐柔するためにクローカーがとった作戦は、彼の大好物である大女の調達。「イタリアには大女がいっぱいいるよ(フェリーニをおちょくっているのかどうか知らないが)」と手なずけてしまう。彼は目的地の交通監視システムをマヒさせる大役のあとにももうひとつおいしい仕事が待っていた、それはみてのお楽しみ。 マイケル・ケインは言う:彼と仕事をするのは楽しかった、しかし彼と本当の交流はついにもてなかった・・・彼はキャスト、スタッフの誰に対しても親切でプロフェッショナルだったが、心底孤独な人物でだれとも付き合わなかった。たとえ一緒の宿に泊まっていようとも。私の知る多くのコメディアン同様に、彼は悲しい人物にみえた。
ノエル・カワード。エリザベス女王の写真を刑務所の独房(というより豪華な個室)にべたべた切り抜いてピンナップしている彼はギャングのボス。刑期を終えて出所するクローカーがイタリアで一仕事することを聞き、「パスタは好きかな。イタリアの刑務所では日に4度出るぞ」と毒づく親父である。この意外なキャスティングが成立したのは監督コリンソンが孤児で、カワードがその後見人だったから。これが遺作となったが堂々としたボスぶり。 彼はサヴォイ・ホテルにその生涯を閉じるまで(無期限に)タダで滞在する権利を有していた。なぜか?第二次大戦中ホテルのキャバレーでショーを行っていた彼は大空襲のその晩でさえ出演を続け、朝まで脱出不可能な宿泊客の気持ちを鎮め、混乱を防いだことに対するホテル側の感謝のしるしだったのだ。
この映画はコメディである。最後の最後におバカなどんでんがえしがあるのでお楽しみに。こんな不条理なおわりかたがあっていいのか?
真夜中の戦場〜クリスマスを贈ります〜"A Midnight Clear"1991年米:キース・ゴードン監督
余韻のある音楽はMark Isham。真っ白な雪によってほんのひととき覆い隠された戦争の醜さが、やがてぬかるみの泥とともによみがえる演出が巧みで哀しい。
1944年12月。フランス、アルデンヌの森に駐屯するウォントの部隊はドイツ軍の潜伏する場所近くの廃屋で情報収集を命じられる。26歳の「マザー(口うるさく世話好きなため)」を最年長とするほとんど少年兵と言った方がよさそうな6人は実戦経験も乏しく、ユダヤ人のシューツァーを除いては敵への関心も薄い。 ウォントとシューツァー、聖職者志望の「ファーザー」は、ドイツ軍司令部のある民家を偵察したあとの帰り道で敵3人に遭遇するが、相手はなぜか攻撃を仕掛けてこない。動転してその場に地図を落としてきた彼らだったが、翌日地図を捜しに行ったシューツァーはヒトラーを模した雪だるまをつくり、「ヒトラーのくそったれ」と木の枝で書いて帰ったと笑う。 外で見張りをしたウォントにドイツ兵から雪玉が投げつけられる。雪合戦が済み彼らの去ったあとには落とした地図を刺した雪だるまが残されていた。ドイツ語を片言話せるシューツァーを伴い、ウォントは敵の指揮官に指定された場所で初めて間近に顔を合わせる。ロシア戦線から回されたという彼らは兵不足のため老人と子供で編成されていた。近々援軍が来て総攻撃を開始するが、自分たちは戦意を喪失しているので投降したいのだという。
「我々はナチではない、ただの兵士だ」その夜。ドイツ兵がウォント達のいる廃屋のそばにやってきた。紙の飾りとロウソクで飾られた手製のクリスマスツリーを持参し、「樅の木」を歌っている。ドイツ語で何か話しかける彼らにファーザーがワインの瓶を手渡す。我知らず、ウォントも彼らに合わせて「きよしこの夜」を歌っていた。夜空には輝く月。 ドイツ兵達は「メリークリスマス」「贈り物」と繰り返していたのだった。
戦闘以外で敵と会いたくないというマザーを残し、残りの5人は最善策を講じる。ドイツ兵は、捕虜になりたいが無抵抗のまま投降した事が知れたら家族が迫害されるので、見せかけの戦闘をして味方を納得させたいのだという。 裏切られれば自分たちが全滅する危険を承知で、ウォント達もその計画に協力する。 マザーが味方を助けドイツ兵を捕らえたという報告書を送り、彼の手柄に してやれば、故郷で我が子を亡くしたばかりの彼の慰めにもなるだろうと考えたのだ。 ドイツ兵と味方がそれぞれ合図とともに空に向けて発砲する。 事情を知らないマザーがドイツ兵を撃ったことがきっかけで、制止しようと駆け出したファーザーが射たれ、シューツァーも弾を受ける。
「なぜファーザーは私に撃つなと?絶好の位置にいたのに」
「ファーザーは・・・慌て者だったのさ」ウォントは「本当の事は言うな」と口止めをされていた。知れば彼は激しく後悔するだろう、ファーザーの遺志を無駄にしたくなかったのだ。基地からやってきた少佐から厳重注意を受けたウォント達はそのまま待機を命じられる。 ドイツ兵の遺したクリスマスツリーを部屋に飾り、ファーザーの亡骸を丁寧に洗ってやることが彼への最後のクリスマスプレゼントだった。
ドイツ軍の総攻撃からなんとか身をかわしたウォント達が戻った基地には人影もなく、味方からも見捨てられていた。 彼らは武器を捨て、ファーザーの口から流れる血でヘルメットに十字を記しシーツをまとい、彼を肩の上に掲げて行進する。
原題 "Midnight Clear" (夜空の晴れ間)のとおり戦闘の合間にわずかに訪れた敵味方を超えた心の交流もつかの間、ふたたび闇が訪れる。原作はウィリアム・ウォートン「クリスマスを贈ります(新潮文庫)」、映画「バーディ」「晩秋」の原作者としても知られる。
長距離走者の孤独"The Loneliness of the Long Distance Runner"1962年英:トニー・リチャードソン監督
原作者アラン・シリトーが自ら脚本を担当した映画。一番好きな映画のひとつ。パン屋に忍び込み感化院送りになった労働者階級の少年コリン。彼の俊足に目をつけた院長は、近くのパブリックスクールとの親善試合で最大の呼び物となるクロスカントリーに彼を抜擢する。 スポーツを通して少年の更正に成功したとの評判をとりたい一心で、院長は特別に感化院の外を走る事を許可する。毎朝のロードワークの間、彼の意識にカットバックされる家族、恋人、彼の青春。入院費がかさむと入院を拒み誰にも看取られず死んだ父。工場からの弔慰金で毛皮や家具をいそいそと買い替え愛人を連れ込む母。 幼い頃に家族で遊びに行った土地を再び恋人と訪れ、「わかっているのはきみを好きだという事だけだ」。
一緒に金庫を盗んだ幼なじみもまた感化院に収容され、コリンが院長から受けている特別待遇に「院長のイヌになってるのか」と非難の目を向ける。親善試合当日。パブリックスクールの生徒たちは屈託がなく、自信満々である。父兄や教育関係者が興味深く見守るなか、クロスカントリーがスタートする。木立を抜け、コリンの胸に去来するのはこれまでの自分が抱えていた漠然とした怒りだった。競技場に先頭をきって とびこんできたコリンを皆の目がとらえる。したり顔の院長、声援を送る院の仲間たち・・・コリンはスピードを落とし、ついに立ち止まる。逃げ足の速さを誇るのはやめた。追いついたライバルに一礼して道を譲り、騒ぎ立てるゴール前の連中を見据えて不敵に笑う・・・。彼は勝ったのだ。彼を従え、飼い慣らそうとするものに。そして怒りを燻らせていた彼自身に。
繰り返し使用される『エルサレム』。もうひとつの英国らしい「走る映画」『炎のランナー』でもこの雄々しい曲を聖歌隊の美しいコーラスで聴くことができる。トム・コートネイの面構えが英国の怒れる若者を見事にあらわしている。 余談ながら出世欲に燃えた感化院の院長はマイケル・レッドグレーヴ(ヴァネッサ、リンの父)。
ピクニック・アット・ハンギングロック Picnic at Hanging Rock1975年豪:ピーター・ウィアー監督
1900年にメルボルンで実際に起きた事件をもとに映画化したもの。 観るものが最大限に想像力を駆使できる作品。火山活動の名残りである巨大な岩が屹立する「ハンギングロック」にピクニックに出かけた全寮制女子校の生徒と引率の教師。 昼食をとり、生徒数人はハンギングロック散策に、残りは午後のまどろみに入る。散策に出かけた3人と、残って本を読んでいたはずの女教師がそのまま失踪してしまう。 学校では生徒が自殺、校長も変死体となって発見されるのだが、映画は「なぜ」をすべて観るものに委ねて終わってしまう。
ヴィクトリア朝の厳しい道徳観を受け継いで、真夏でも襟を詰め、肌を出すことを禁じられているはずの少女達がストッキングをするりと脱ぎ(裸にも等しい)、何者かに呼び寄せられるように岩肌を登っていく。 いかにもきまじめそうな教師はペチコート姿でハンギングロックに向かうところを目撃されている。 彼女たちになにがあったのか。カメラがハンギングロックに向けられる時、それはまるで命あるもののように映る。「この岩は100万年もここで待っていたのね・・・私と同じ。私も、待ち続けていたの」
また別の少女はポオの詩の幻想的な一節 "All that we see or seem / is but a dream within a dream..."を暗誦する。 昼下がりの砂地にはケーキにたかるアリ、毒を持つという蛇の姿もみられ、まるで彼女達に早く立ち去るよう警告しているようだ。失踪した少女のひとりが意識不明の状態で発見され、看護婦が言いにくそうに、「彼女、コルセットをつけていないんです」と警官に告げる。少女に事件の記憶はない。 あらゆるところにセクシャルな香りが感じられる女子校の特殊な雰囲気、男性的なハンギングロック。犯罪か、それとも神隠しか。謎を残したままふつりと物語が終わるので得体の知れない「ちから」の存在を漠然と感じたまますうっと背中に冷たい汗が伝うような気分にさせられる。
ボッティチェリの天使、とたとえられる少女ミランダの美しさ。この世のものでないなにかをも魅了してしまったとしても不思議はない。 素朴な笛の音色、少女の白いドレス、優雅な身のこなしが幻想的。映画に説明を求めるタイプのひとには不満が残ると思うけれど。
王になろうとした男 "The Man Who Would Be King" 1975年米:ジョン・ヒューストン監督
ダニー(ショーン・コネリー)とピーチー(マイケル・ケイン)はともにインドに駐留した女王陛下の軍隊所属の兵士だった。ふたりは財宝の眠るヒマラヤの奥地カフリスタンに旅立つ途中で、同じフリーメイソン仲間であるキプリング(クリストファー・プラマー)と知り合い奇妙な友情を結ぶ。 困難の末たどり着いたカフリスタンでふたり、特にダニーは胸ポケットに入れたメイソンのバッジのおかげで心臓に矢を受けても血を流すことがなく、現地の人々から神と崇められ財宝も捧げられる。
春が来たら財宝を持ち帰ろうと提案するピーチーの言葉にダニーは耳を貸さず、神は妻帯を禁じられているにもかかわらず見初めた娘(シャキーラ・ケイン:ケインの妻)との婚礼を強行する。神への畏怖でトランス状態に陥った花嫁に頬を噛みつかれ血を流したダニーを見た群衆が神と偽っていた彼らを追い詰め、ダニーは吊り橋から身を投じ誇り高い死を選ぶ。数年後、インドのキプリングの新聞社に凍傷で指を失い面影もなくなったピーチーが現れる。彼は驚くキプリングにふたりの辿った運命を語り、布で覆われた汚い包みを託して立ち去る。
キプリングが包みを解くと、それは輝く王冠を戴いたダニーのしゃれこうべだった。ラドヤード・キプリングの短編を少年時代に読んだヒューストンが長い間暖めていた企画。ダニーにクラーク・ゲイブル、ピーチーにハンフリー・ボガードを想定していたがボガードが癌で世を去ったため映画化をあきらめていた。 その後"The Misfits"でゲイブルと仕事をする機会ができたのでゲイブルとロバート・ミッチャムで話を進めたところ、 皮肉なことに映画の完成した翌日に今度はゲイブルが急死。 企画はまたも頓挫してしまった。
ヒューストンはあきらめず、3つの異なる脚本を用意させリチャード・バートンとピーター・オトゥールを主役に迎えようとしたのだが、1973年プロデューサーのジョン・フォアマンの目にとまったのは4本目の脚本(ヒューストン自身も共同執筆したもの)だった。 ヒューストンはこの時にはポール・ニューマンとロバート・レッドフォードで(・・・・)実現させようと、 ニューマンに脚本を送ったところ、彼はこの映画は英国人が演じるべきだと、役者としてでなくこの話に興味を持つひとりの人間としてコネリーとケインの名を挙げた。 フォアマンはふたりに脚本の写しを送り、翌週にはこのキャスティングが決定した。ご苦労様でした。カフリスタンでふたりが出会うインド人の英国軍兵士に、『マイ・ビューティフル・ランドレット』にパキスタン系の主人公オマールの叔父役で出演しているサイード・ジャフリー。
ケインの妻シャキーラは演技経験なし、新婚でロケに同行していたところこの映画への出演が決まったという。
バンデットQ "Time Bandits"1981年英:テリー・ギリアム監督
マイケル・ペイリンが脚本を担当。(アメリカの)キッズムービーも子役も嫌い("I hate..." と言うくらいだから相当なものだ)と言ってはばからないギリアムがつくりあげた、少年ケヴィンが巻き込まれた壮大な時間旅行。
「バンデットQ」というタイトルでビデオが出ているので詳細は省くとして、ケヴィンと冒険を共にする盗賊を演じた俳優のうちふたりがすでに故人となっている。盗賊のリーダー格デヴィッド・ラヴァポートは元教師という経歴の持ち主で、スティングの主演作「ブライド」でも サーカスの芸人役で主役を食ってしまう名演を見せ、英国ではきちんとしたキャリアを築いていたが、ハリウッドに招かれてから自殺したそうだ。
「彼はハリウッドで仕事をするにはあまりに知的すぎた。敬意を払われてしかるべき俳優だった。」ギリアムがわざわざ「ハリウッド」を強調するところ、猛烈な反感を胸に(腹に)持っているということが感じられる。彼らの冒険の舞台はすべてケヴィンが読んだ歴史の本に登場したところで、ナポレオン、ロビン・フッド、アガメムノン王、タイタニック号などなじみ深いものばかり。イアン・ホルムのナポレオンはペイリンが真っ先にキャスティングしたそうで、彼はセットでも大変 楽しい人物だったようだ。みずからも背の低さにコンプレックスを持っているナポレオンの、盗賊達に対する手厚いもてなしがおかしい。また、フランスでは英雄である彼が、この作品ではまったくの芸術音痴として描かれていて、戦利品の山の中に無造作に置かれているモナリザの絵には 大いに笑わせてもらった。酔いつぶれたナポレオンの右手(いつもは懐に入れているので知られていないが実はキンピカの義手だったという黒いギャグ)まで頂戴して去っていく盗賊達。
マイケル・ペイリンとシェリー・デュバルのコンビはロビン・フッドとタイタニック号の二箇所で登場。いつもいいところで盗賊達の邪魔が入り、追い剥ぎに木にくくりつけられたりカツラを飛ばされたり。
義賊ロビン・フッドはジョン・クリーズが客演。愛想笑いをふりまきながら、長身を折り畳むようにして盗賊達と握手をかわし、彼らの戦利品を貧しい者に寄付させたあとで、「バーカ」とひとこと。妻に裏切られるアガメムノン王に、ショーン・コネリー。ケヴィン役のクレイグ君は緊張のあまり何度もNG出したんだそうだ。現実の父よりもこの王に惹かれていたケヴィンが、宴の余興を装ってやってきた盗賊達を玉座の隣から見たときの「げっ!」という表情がギリアムはお気に入りだという。さすが、お子様に媚びない監督。
悪の大王を演ずるはデヴィッド・ワーナー。シナリオ段階ではイメージを視覚化することができなかったと正直に告白している。ギリアムの尊敬すべき点は(他の監督と違い)役者が演じやすい雰囲気をじっくりと盛り上げてくれたことだという。実際、彼のコワイ雰囲気はじゅうぶん引き出されている。 大王と盗賊達、そしてケヴィンが戦う舞台は巨大なレゴブロックのセット。時間旅行でありながら、肉体は自分の子供部屋のベッドにあるケヴィン。絶体絶命の危機に瀕した彼を助けようと盗賊達が引き連れてきたのもすべて壁のポスターやオモチャの戦車、戦闘機を実体化したものばかり。なぜかカウボーイまで投げ縄を手に現れる。
トリをとるのはラルフ・リチャードソン演じる超越者。背広姿の老紳士だが神様なんてそんなものかもしれない。
ギリアムの想定したのは、不完全な神による不完全な世界。ケヴィンはもといた世界に引き戻され、今までの事は夢だったかと思うのだが、写真は冒険のすべてを映していた。 ケヴィンと一緒に向こうの世界から運ばれてきた「邪悪」の残り、ケヴィンの「触っちゃだめだ!」の声に耳を貸さないパパとママが吹っ飛んだところで、ケヴィンが独りで戦わなくてはならない本当の冒険が始まる。ギリアムは言う
「おとなたちは子供の言うことをまともに取り合わなくて、そのために命を落とすんだ。」
「これを観た子供達が人生とは怖くて複雑なものだと学んで、これから気をつけるべきことは自分で判断しようと思ってくれれば満足さ。」ああ、この映画にもジム・ブロードベントが(テレビのプレゼンター)。
リタと大学教授 "Educating Rita"1983年英:ルイス・ギルバート監督
原作はウィリー・ラッセルの舞台劇、"Alfie"のルイス・ギルバート監督が再びマイケル・ケインと組んだ作品。ジュリー・ウォルターズはタイトルロールのリタを舞台でも演じている。
ワーキングクラスの主婦スーザンはリタ・メイ・ブラウンの"Rubyfruit Jungle"に触発され、大学の公開講座に応募する。彼女の個人指導の担当は、筆を折った詩人で今はアルコール依存症のブライアント教授。 27歳の彼女は子どもを欲しがる夫と対立しながらも勉強を続け、教授は彼女に天性の才能を見いだし、指導に情熱を傾けるようになる。 子どもをあきらめ、夫にも去られた彼女は憑かれたように勉強を続け、夏期講習から戻った時には教授の予定した作家(難解とされるブレイク)をすでに終えているほどだった。教授にとってお荷物だった彼女は次第に、ひとりの女性として大切な存在となる。 長年眠っていた知識を授ける喜び、詩や小説を初めて読んだときの感動を思い出した教授が彼女を必要とするようになるのと反対に、彼女は若い学生たちに混じって文学論を闘わすことに夢中になり、彼から離れ始める。 論文も大学生と遜色ないほど上達し、編入試験も可能な実力をつけた彼女が、もはや最初のすぐれた作品対する新鮮な感動を忘れてしまったことを教授は嘆き、
「きみはもっとましな歌をみつけたいと言ったが、きみは別の歌をみつけた・・・」
大衆小説の著者にちなんで「リタ」と自称したことを恥ずかしいと思っている彼女を見据え、言葉を続ける。
「私も改名しよう。これからはメアリーと呼んでくれ。フランケンシュタインの作者だ」「リタなんて呼ぶのはあなただけよ、そんなバカな名前はとうの昔に捨てたわ」
「今度はジェーン(マンスフィールド)、シャーロット、エミリー(ブロンテ姉妹)、それともヴァージニア(ウルフ)なら満足か」ここからは彼女が借り物でない自分を取り戻す話になる。教授が教えてくれたのは知識だけでなく、素晴らしい文学作品に触れることで得る喜びだったことを思い出したリタは、大学の編入試験を受ける。
教授は彼女への報われない想いをつのらせ、酔って教壇に立ちすでに大学を追われていた。彼はオーストラリアに職を得て「未来の国に一緒に来ないか」と彼女を誘う。彼女はとどまることを選ぶ。ここに「愛」という言葉は登場しない。お互いへの思いは言葉を必要としないからだ。彼女の未来は彼女自身のもので、彼は教え子が自分のもとから巣立つことを心から祝福する。
"I'm proud of you, Rita."
"I'm proud both of us."合格したリタが教授に応える。マイケル・ケインはこの作品のために体重を増やし、髭を生やし、間違ってもリタがこの酔っぱらいに恋愛感情を抱く可能性のないよう役作りをしたという。彼がもっとも誇りに思う演技だとのこと。演じるにあたり念頭に置いたのは「嘆きの天使」でエミール・ヤニングスの演じた、マレーネ・ディートリッヒに恋い焦がれる教授だったそうだ。撮影はすべてアイルランドで行われ、大学はダブリンのトリニティ・カレッジが使われた。
プリンセス・ブライド・ストーリー "The Princess Bride"1987年米:ロブ・ライナー監督
アカデミー賞常連脚本家ウイリアム・ゴールドマン原作"The Princess Bride"(ハヤカワ文庫刊)の映画化。 物語は二重になっていて、カゼで寝ている孫を見舞ったおじいちゃん(ピーター・フォーク)が読み聞かせるおとぎ話の題名がこれ。ファミコン世代の孫が「本なんて」という顔をすると、「フェンシング、戦闘、拷問、復讐、大男、モンスター、追跡、脱出、真実の愛と奇跡に満ちたすばらしい本なんだよ」と 構わず朗読を始める・・・。まず美男美女、お話の主役となるふたりにはケーリー・エルウィズとロビン・ライト。 きれいなのにどこかピントがずれているふたりは結婚を誓い合った仲。故郷に錦を飾るその日まで待っているわと彼の帰りを待つキンポウゲ(彼女の名前)は、彼が海賊ロバーツに殺されたと聞いて心を閉ざし、自暴自棄のまま王子(クリス・サランドン)の求婚を受け容れる。 おとぎ話につきものの悪役3人組はグリーンランドからやってきた大男(アンドレ・ザ・ジャイアント)、父の仇である6本指の男を討つために剣の達人となったスペイン人(マンディ・パティンキン:今回は歌わないよ)イニゴ・モントイヤ、そして小男(ウォーレス・ショーン)。
怪傑ゾロそっくりのマスクにひげの海賊ロバーツ。そして怪しげな王子の側近(クリストファー・ゲスト:ジェイミー・リー・カーティスの旦那さん)。地下の洞窟で拷問の下働きをするアルビノにはあのメル・スミスが登場。キンポウゲと王子の婚礼を司る、ろれつがまわらず王子をいらつかせる司祭がピーター・クック。
奇跡を呼ぶ薬を調合する魔法使いにアカデミー賞授賞式に欠かせなくなったビリー・クリスタル。とにかく英米コメディ界で知られた面々が次々に登場して彩りを添えてくれる。おとぎ話だから、もちろん彼と彼女は再会し、白馬に乗って城を脱出、サンセット・キスにてハッピー・エンドとなるのだが、本を読み終えたおじいちゃんが帰る間際、孫が「また本を読んでくれる?」とはにかんだように尋ね、おじいちゃんがひとこと
"As you wish!"「仰せの通りに」。これは、「いつもおまえのことを愛しているよ」というメッセージ、なのだ。音楽はマーク・ノップラー。サントラも美しい。
Victim1961年英:Basil Dearden監督
メルヴィル・ファーは小学校教師の妻を持つ法廷弁護士である。仕事も順調、夫婦仲もよく彼の人生は順風満帆のようだったが、ある事件を境に一変する。 彼は同性愛者で、書店主ハロルドの斡旋でバレットという青年と関係した過去がある。バレットの交際相手に次々と逢い引き場面の写真を同封した脅迫状が 届き、受け取った人物はいちように動揺する。脅迫容疑で警察に追われたバレットは逃亡中にファーにも助けを求めるものの冷たく拒否される。逮捕された彼は 獄中で首を吊り、ファーは強い自責の念にかられ、最初は単独で、やがて警察とともに犯人を追うが、それは彼のこれまでの輝かしいキャリア、結婚生活と 引き替えにした正義であった。
妻のローラがファーを問いつめる場面「私は憶測するよりも知りたいの。あなたはどうして彼と会うのを止めなかったの?」「私は彼が欲しかったんだ。」妻の父親が娘を訪ねる。車庫の扉に白いペンキででかでかと書かれた言葉を父娘が見て絶句する:
"FARR IS QUEER"
父は離婚して人生をやり直すよう娘を説得しようとするが、「彼を愛しているの」と彼女は首を縦に振らない。ファーは、自分が囮になってネガと引き替えの代金を指定された受け渡し場所に置き、犯人逮捕にこぎつけるが、失った代償は大きい。帰宅した彼を妻が待っている。「公判が始まれば最低2週間。かつての 友人も私をあの"filthy name(=queer)"で呼んで蔑むだろう。」「私、いつか戻ってきていいかしら?」妻はそう言って去り、彼は彼の人生を変えた、しかし彼の生き方をも 変えた1枚の写真を暖炉の火にくべる・・・。ダーク・ボガードが甘い二枚目路線をかなぐり捨てた記念すべき作品。妻役のシルヴィア・シムズのグラマラスな体型が皮肉。
映画のなかで"queer"という言葉を初めて言わせた作品でもあり、英国公開時は成人指定だった。
フルーク 生まれ変わったパパ "Fluke"1995年米:カルロ・カルレイ監督
人間の言葉を理解する子犬フルーク(FLUKE:まぐれあたり)、彼は自動車事故で死んだ青年社長の生まれ変わりだった。徐々にフラッシュバックされる記憶をたどり、 彼は成犬になったときに自分の愛する家族のもとに帰り、彼らを守ろうと決心する。犬の姿の自分を転生した夫、または父と知らない家族。どうしても自分の正体を知らせたくて 二本足で立ってみたり、屋根裏部屋にしまってあった自分の帽子をかぶって妻に見せてみたり。
息子と妻に笑いが戻り幸せを感じたのもつかの間、妻が、自分が命を落とした事故に関わりのあるらしい親友と 新生活を歩み始めていることを知った彼は後をつけ、運転席の背後から襲う。薄れてゆく意識の中で彼は、自動車事故の真相を思いだした…。転生した男が愛する家族と再会し、元の姿に戻り再び幸せに暮らしましたというおとぎ話ではない。 夫として、父親としての彼の存在が時とともに薄れていくのは新しい家族の誕生とともに受け入れるべき現実であり、彼がそれに気づき自分自身の新しい生を歩むまでの再生の物語だと思う。
Blood For Dracula1974年米:ポール・モリセイ監督
アンディ・ウォーホルが出資してモリセイが撮った作品はこれと前作"Flesh For Frankenstein"(邦題「悪魔のはらわた」)。この作品も「処女の生血」という、レンタルでは借りにくい邦題がつけられている。 ラース・フォン・トリアー、ガス・ヴァン・サント監督のお気に入り俳優ウド・キアの数少ない主演作である。
NHK衛星第2チャンネルで2回放映されているからなんとなくリモコン合わせて仰天した人も多かったかもしれない。軸になる3人は前作と同じウド・キア、ジョー・ダレッサンドロ(ジュ・テーム・・・の彼)、そして読み方がわからないArno Juerging(ドイツ人なんだもーん)。当時低予算でたくさん映画を撮っていたモリセイ、「悪魔のはらわた」クランクアップパーティで静かにワイングラスを傾けている(たぶん赤だったろう)ウド・キアのところにやってきて、「2週間後にはまた映画撮るんだ」と次回作の話を始めた。 「で、今度はドラキュラものなんだよ、ドイツ人の」「へぇ。誰がやるの?」「きみだよ」で、出演が決まったという。汚れなき乙女の血により命をつないでいる吸血鬼一族であるが、さすがにルーマニアの乙女はあらかた吸い尽くしてしまい、もはや弱り果てた跡取りのドラキュラ伯爵という設定なので、彼はひたすら食事を抜いて10キロ体重を落としたそうだ(あっぱれ)。伯爵は執事(これがまた主人より横柄)アントンに「イタリアはカトリックの国、きっと処女も多いことでしょう」とうながされ、歩くのもやっとの体ながら黒塗りの車に寝台である棺桶と車椅子をくくりつけ、目指せイタリアへ!
とある落ちぶれた貴族のお屋敷。主人は賭事で受け継いだ財産を食いつぶし(ビットリオ・デ・シーカなんだよ)、奥様は4人の娘をなんとか玉の輿にのせようと腐心しているところへやってきたのが旅行中という(そうは見えない黒服なんだが)異国の伯爵様。娘に色仕掛けで迫らせて結婚にこぎつけようと喜ぶ奥様、娘が4人も、こりゃ幸先いいわとほくそ笑む執事の思惑が一致、しばらく逗留することになる。
屋敷にはもうひとり住人がいて、主人達に対しあからさまな軽蔑のまなざしをむけるコミュニストのマッチョな下男(ダレッサンドロ)。伯爵はこの下男と娘たちができていることを知らないため食事を運んできた娘にかぶりつくのだが、とたんに顔色が変わって苦しみ出すのだった・・・。そう、これはホラーコメディなのだ。でも、どの登場人物よりも人間らしいのはこのドラキュラ伯爵だったというひとこまがある。実はこの屋敷の長女は昔破談になった過去を持つオールドミスで、彼女が野菜の皮むきを(使用人を雇えないので)しながら伯爵と心を通わす場面。自力で歩くことも困難な伯爵が、哀れみの表情で手をさしのべる下男をふりきるように階段を這い上がっていく場面。
そもそもこの作品に出る予定のなかったウド・キア、1日だけ別の契約で仕方なく撮影を離れる日があり、その日彼の穴を埋めてくれたボランティアがロマン・ポランスキーだったそうだ。彼は酒場のシーンで執事と賭をする村人としてカメオ出演しています。
「悪魔のはらわた」はつまらなかった(観てる・・・)がこちらはなかなかポエティックでいいよ。カルトだけど・・・。
Birdy1984年米:アラン・パーカー監督
ピーター・ガブリエルが音楽担当。ソロアルバム"peter gabriel"収録の"Wallflower"をアレンジしたものがテーマ。
マシュー・モディンは最初ニコラス・ケイジが演じたアルの役でオーディションを受けに来たそうだ。アラン・パーカーは彼をカメラであらゆる角度から映し、本読みなしで、バーディ役に決めたという(監督のコメントより)。 原作は第2次世界大戦下に時代を設定しているが映画ではベトナム戦争。アルとバーディふたりのモノローグで進行する原作は、バーディ部分がイタリック体で表記されているため、たいへん読みやすい。映画では純粋培養的なバーディが、原作では思春期に共通のそれなりの欲求を備えた少年である。
ニコラス・ケイジは役づくりのため実際に歯を麻酔なしで抜いたそうだ。彼は生きたゴキブリを本当に食べてみたり(バンパイア・キッス)、ご苦労様。
原作にのみ描かれるバーディのふつうじゃない感覚は、たとえば彼がカナリアのパータと結婚生活を送っている(もちろん彼の夢想である)ため、川に浮かんでいる使用済みの避妊具を拾ってきてきれいに洗い、眠る前に装着して朝下着を汚さないよう気をつけるといった描写にも表れている。
こんなことを考えつく作者もたいしたものだが相当な変人らしい。ウイリアム・ウォートンの「晩秋」は読んでいないけれど「クリスマスを贈ります」も「バーディ」同様へんな作品だった(好き)。 あのとんでもないラスト、原作はああじゃなくて、野球のボールがいっぱいつまったトランクで玄関の前を塞ぎ、堂々と歩いて門の外にでることをバーディが提案する。
どうかな、アル。人生はつらいよ、誰も逃げられやしない。でも、生きてみる価値はある。
The Last Butterfly 日本未公開:1994年英=仏=チェコスロバキア Karel Kachyna監督
アントワン(トム・コートネイ)はパントマイムのパフォーマーとして知られた存在だが、ドイツ占領下のパリで酒浸りの日々を送る。 レジスタンスの恋人が殺され、彼も身柄を拘束され、ナチスがユダヤ人の芸術的な才能を高く評価し、各国から集められたユダヤ人芸術家と子供達のために恵まれた環境を与え、その芸術をはぐくんでいることを宣伝する為の街テレジンで舞台に立つよう迫られる。
テレジンに着いた彼は街を見て回るが、人々は判で押したように「私たちはここで暮らすことができて幸せです」と言うばかり。 やがてこの街の片隅から毎週出発する貨物列車に乗せられるのはもはや労働力として役に立たない病人や老人であることを彼は知る。赤十字をあざむくためのプロパガンダ劇の上演に加担させられたことを知ったアントワンは、帰国させて欲しいと申し出るが相手にされない。ここにいる子供達も自分も、やがてあの線路の先の絶滅収容所に送り込まれるのだ。 彼と有志、子供達は秘密裏に劇を書き換え、赤十字の視察団とゲシュタポの前で、お菓子の家の壁の後ろに閉じ込められているのは家族と引き離された子供達・・・という無言劇を上演する。 邪悪な魔女は死に、平和の鐘とともに皆が家族と再会を果たす劇に命がけで取り組む子どもたちに、使節団はある確信を持つ。 無言で佇むアントワン、オーケストラ、子どもたちにナチスは、憮然とした表情で拍手するほかなかった。
収容所行きの貨物列車に乗り込む彼ら。そのまえに、アントワンは昔パリで観客を沸かせ、逮捕される原因となったヒットラーを茶化したマイムで子供達を笑わせるのだった。「蝶」とはアントワンの十八番で、病身のため夫を残し翌朝の列車に乗せられる老婦人の心を慰めるために披露する美しいパントマイム。 ビデオはamazon.comで入手可。
将軍たちの夜 "Night of the Generals" 1967年英:アナトール・リトヴァク監督
ピーター・オトゥールの気持ち悪さ全開。デカダン・アートにこだわり、ゴッホの自画像(あの耳を切り落とした直後に描かれたもの)を見つめるうちに震え出すところ、ああ怖かった。
彼を追うオマー・シャリフ、彼に翻弄され人生を狂わされるトム・コートネイ、シャリフの遺志をついで彼の犯罪を暴き出すフランス人刑事フィリップ・ノワレなどそうそうたる顔ぶれだが、これが猟奇殺人をテーマにした映画だというのだから、イギリス(というよりサム・スピーゲル)、何を考えているのか。
presented by ぱと If you want to say something...