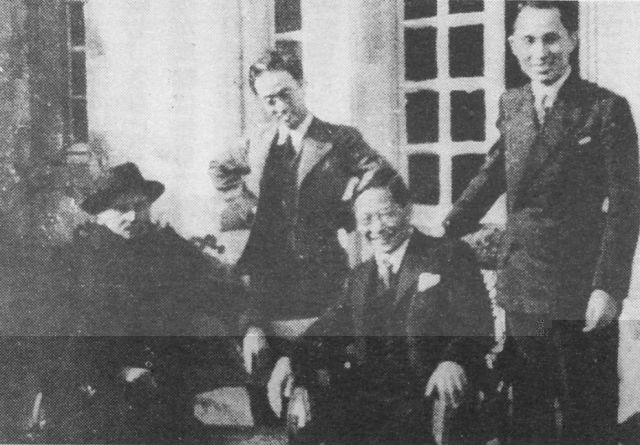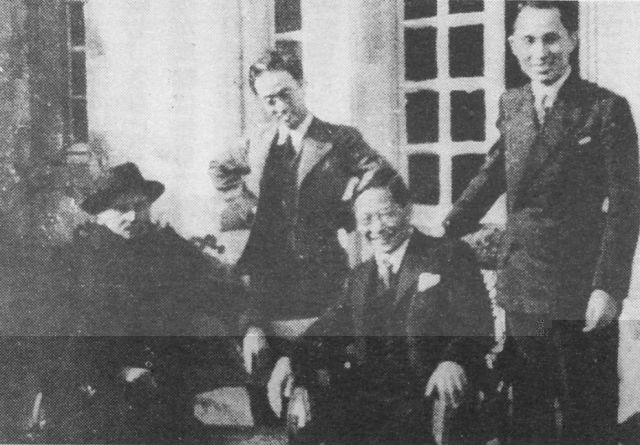ロマン・ロランに親しくお目にかかれたあの忘れがたい日、私は持参した“Pierre et Luce”に署名をいただいたが、ロランはその一隅に30 avril 1940としるしておられる。
思えば、あの日からすでに半世紀以上の歳月が流れ去っているのである。しかし眼をとじると、ロランの秋空のように碧く澄み切ったまなざしがいまだにありありと瞼に浮ぶ。
私は、あれほど大きく、英知の霊気に輝く双眸を、それ以前にも、また以後にも見たことがない。七十四歳の老人の眼でありながら二十歳の若者の眼よりも敏活に動き、時としては、相手の心の奥底まで見ぬくようにまっすぐ見つめるのである。ロランは、インドの聖者ラマクリシュナの「眼は魂の十字窓」(Les yeux sont les croisées de l'Âme)ということばを著書「ラマクリシュナの生涯」中に引用しておられるが、ロランの眼こそ正に魂の交叉する十字窓にほかならなかった。われわれはその窓の奥に彼の高貴な魂をうかがい見る一方、その窓から射出する彼の魂の光りに威奮させられるのであった。
この地上に、世にもまれな偉大な知性が存在している、その人の名はロマン・ロラン、──ということを、私がはじめて知ったのは、それより先きの一九二二年、私がまだ七年制東京高等学校尋常科二年(一般中学の二年)に在学していたときであった。
その日私は、同窓生吉田順五(のちの北大教授)の家に遊びに行っていたが、書棚にあった「ジャン・クリストフ」(豊島与志雄訳)にふと眼をとめて取り出し、何心なく読み出すと、たちまち魅惑されてしまった。そこで友人たちの談笑からはなれて、部屋の一隅で読みふけった。
それはたまたま第六章「アントワネット」であったが、銀行頭取の父親が失敗自殺したために、破産没落して夜逃げ同様にパリに出たジャンナン一家のなかで、それまでいたずら好きの無邪気な少女であったアントワネットが、悲運に苦しむ母親をけなげに支え、幼い弟オリヴィエが成人するまで献身しつくした短い生涯は私を深く感動させた。あの日の熱い心情をいまふりかえってみると、モーツァルトの楽曲の光芒にも似た愛の切ないまでに美しい物語の魅力もさることながら、その行間からあふれる著者の人格的香気──人間への深い洞察とあたたかい情愛──が私を引きつけ、教えを乞うべき賢者がここにいると思いこませたものとおもわれる。
帰宅後、私は、「ジャン・クリストフ」をはじめ当時刊行されていたロランの訳書を買い集めた。そして、くりかえし読んでいるうちに、どうしてもそれらを原書で読まなければならないと決心するにいたった。そこで高等科一年(一般旧制高校の一年)に進級するとき、何のためらいもなく第一外国語にフランス語をえらんだ。
そのとき教授のひとりとして赴任されたのが、東大仏文科を出て間もない若々しい渡辺一夫先生であった。白皙の美青年で、一見恥ずかしがりやのテレ屋にみえたが、その教育は猛烈をきわめた。文法についても、こういうものにいつまでもかかわらないで、さっさと上げてしまいましょうといって、一学期の間に動詞の変化などをしゃにむに暗記させ、二学期からはフランス文学の名作講読に進んだ。
おかげで、私は、二年生になるとロランの作品を辞典片手に何とか読めるようになった。そこで、こんどはロランのような高邁な作家を生んだフランス文学を研究したいという希望が押えがたくなり、東大に入学するに当っては、ふたたび何のためらいもなく仏文科をえらんだ。 当時の東大仏文科は独立してからまだ日が浅く、主任の辰野隆先生は助教授、鈴木信太郎先生もまだ講師で、東大図書館勤務の山田珠樹先生が助教授、「ジャン・クリストフ」の翻訳者で小説家の豊島与志雄氏が講師として、それぞれ補助的に出講しておられた。
さて開講の日には、辰野先生が明るくあたたかい歓迎のことばをのべられたが、その最後に「君たちはフランス文学を勉強しても、それだけではメシは食えませんよ」とはっきり引導をわたされた。これは冷たいようにみえてまことに親切な忠告であった。
そのころ、国、公立や私立の諸大学のみならず専門学校でもフランス語の講座のあるところはきわめて少なく、高等学校でもフランス語を教えているところは指折り数えるほどであった。しかもそれらの教職は、それぞれ数年前までに卒業した若い先輩たちに占められていたので、当分空席の出る見こみはなかった。それ故新入生は、早や目に卒業後の身のふりかたを考えておかないと、あとでとまどうおそれが多分にあったのである。
ただ私は、将来の進路についてすでに大体の見当をつけていた。その指針となったのは、ロマン・ロランが「ジャン・クリストフ」の執筆中に公刊した「ミケランジェロの生涯」の序文中の次の一節であった。“Il n’y a qu’un héroïsme au monde: C’est de voir le monde
tel qu’il est, et de l’aimer”
私は、このことばを、「この世をありのままにみて、そしてこの世を愛することが人間の最高の生きかたである」という意味に受けとっていた。そしてまず「この世をありのままに見る」のにもっとも適した職業は何かと考えたあげく、それは新聞記者であろうと思いいたったのである。幸いに、三年生になったとき、東大に新聞研究室(のちの新聞研究所、現在の社会情報研究所)が開設されたので、早速その研究生を志望し、河合栄治郎、南原繁両教授や小野秀雄講師の面接試験に合格して、ジャーナリズムの基礎知識を学ぶことができた。
一方、仏文科の卒業論文としては、私はロマン・ロラン以外のテーマを取り上げる気は全くなかった。そして当時はまだロランの回想記、自叙伝などが発表されていなかったので、そういう一次資料の欠ける現存作家については、作品中の登場人物が人生の岐路に立ったとき、どのように決断し、どのような行動に出たかを分析することも、その作家自体の思想構造を察知し得る一つの方法であり得るであろうとの前提に立って、試論“Petit Essai Analytique sur le Système de Romain Rolland”を提出して、無事卒業した。そして、新聞聯合社(のちの同盟通信社、現在の共同通信社の前身)に入社して、ジャーナリストとしての一歩を踏み出すことができた。その後、同社岩永裕吉社長の推薦で、国民新聞社の社長秘書となったが、一九三六年には結核のため辞職して療養につとめる身となった。
病気はほどなく回復に向ったが、もはや社会での激務につくのは無理と思われたので、読書研究に専念すべく、翌年春東大大学院に入学した。
同じ年、渡辺一夫先生のおすすめによって、ピエール・ロティの日記(「ロティの日記」白水社)を翻訳出版したが、それが機縁となって、思想も文藻も全く対照的なピエール・ロティとロマン・ロランとを見くらべながら研究する立場をとることになった。
その結果まず行き当たった疑問は、ロティもロランも、少年時代にキリスト教の信仰を見失ったことは全く同一なのに、ロティの方は、この世のすべてはたえず変化し、生滅し、結局は暗黒の深渕に沈むとの虚無感におちいったのにたいし、ロランは、同じく鋭敏で傷つき易い感性の持主であったにもかかわらず、そうした虚無感にとりつかれることなく、積極的に永遠の実在を肯定し、独自の信念を樹立したが、それはなぜかということであった。
そして、その謎を解明し得ないまま、私は、ロティ芸術の独創性の一つである憂愁の詩情に親しみを覚え、かつそれを生んだのがひたむきで真剣な彼の虚無感であったことを認める一方、この世に生きる姿勢としては、ロランに学ぶほかはないという気持を強めて行ったのであった。
私が東大大学院に随時通学していた間に、日中戦争は、北支から上海へ、そして中支へと飛火した。そして、しだいに高まる社会の熱気のなかで、私自身は亡父の遺産で徒食し、他人の生産物を消費しながら、社会に何のお返しもしていない寄生虫、無用の人間だというやましさにたえずなやまされるようになった。そこへ、一九三八年四月、高校時代からの親友で外務省情報部の事務官をしていた松井明(のちの駐仏大便、国連大使)が電話をかけてきて、「君の語学とジャーナリストとしての経験を生かして、情報部の仕事を手つだってみないか」とすすめてくれた。幸いに健康もほぼ回復していたので、この親友の厚意にしたがって外務省に顔を出してみると、すぐにも嘱託として働いてくれといわれた。
仕事は、海外からの資料を翻訳したり、各種情報を検討分析したりすることであったが、翌一九三九年の夏にはヨーロッパで第二次世界大戦が始まったので、急にいそがしくなった。
そして、その秋に河相達夫情報部長が無任所公使として欧米各国を巡歴査察することになったとき、また松井明から同公使の秘書格として随行する気はないかとの話がもちこまれた。
この地球を広く見てまわるということは私の宿願でもあったので喜んで応諾し、新婚早々であったが、同年十二月十四日、河相公使とともに横浜を出帆し、サン・フランシスコに上陸して北米大陸を横断、ニューヨークで用務をすませたのち、マイアミから航空機で中米、南米諸国をめぐり、ふたたびニューヨークにもどった。そして、ニューヨークからイタリア豪華船で大西洋をわたり、三月九日ナポリではじめてヨーロッパ大陸の土をふんだ。
そして、ローマで数日をすごしたのち、列車でフランスに入り、パリに到着、会議などを終えたのち、ドーヴァー海峡を連絡船で越えて、ロンドンに赴いた。
ここで私の任務は終り、河相公使の以後の旅程であるドイツ方面やソ連などの語学に堪能な人と交代することになった。そこで私はパリに引きかえし、帰国の船便を待つという名義で三月末から四月にかけて滞在した。
陽春のパリは、相変わらず世界からの観光客でにぎわっていた。それに入りまじって、私もまたフランス人のよくいう“La joie de vivre”(生きる歓び)を味わうことができた。
しかし、四月八日、それまで約半年間も独仏国境で英仏軍と睨み合ったまま、休戦状態をつづけてきたドイツ軍が、突如ノールウェイ、デンマークを攻撃占領した。
パリ市民は、高まる不安を胸に秘めつつ、マジノ要塞線の難攻不落を心頼みに、その日その日の平穏をせめても楽しもうとしていた。
都心では、名優ルイ・ジューヴェの演出・主演するジャン・ジロードウ作「オンディーヌ」が人気を集め、当時全盛のシャンソン歌手リュシエンヌ・ボアイエは彼女のキャバレ・シエ・ゼルで「パルレ・モア・ダムール」を絶唱していた。そして、リドの舞台では、カンカン帽を小意気にかぶったモーリス・シュヴァリエが、渦巻く美女の群のただなかを歩きまわりながら、「青春は五期あるが、私はいまでも第三期」と軽快にしゃベって、満場を沸かせ、フォリー・ベルジュールでは、ジョセフィーヌ・ベーカーが、褐色の肉体をうねらせて、「ジェ・ドゥ・ザムール・モン・ペイ・エ・パリ」と歌っていた。
そうした日々のなかのある夜、私は日本大使館のパーティーで、改造社の山本実彦社長とことばをかわす機会を得た。そのとき山本氏はふと近くヴェズレ一にロマン・ロランを訪問するともらした。私はさっそく同行を希望し、山本氏は快く承諾してくれた。
数日後、私はマロニエの街路樹の下で、山本氏と案内役の彫刻家高田博厚氏とを運んできた自動車にのりこみ、パリを出発した。
夜来の雨でやや増水したセーヌ河やヨンヌ河のなごやかにうるおす新緑の沃野をわれわれはひたすら東南に二百キロほど走った。そして風景がようやくブルゴーニュの高原らしくなったころ、丘と丘との峡間のかなたに、突然ひろびろとした見晴らしが開けた。
広大な空一面にひろがる雲には、いくつかの裂け目ができていて、そこから光線の束が地上にふりそそぎ、その天と地を結ぶ光りの列柱を背景に、大寺院を頂上にいただく丘が孤島のように盛り上がっていた。それが聖王ルイや十字軍の歴史で名高いヴェズレーの古雅な姿であった。
ロラン家は、丘の頂上のサント・マドレーヌ大聖堂へとのぼる道の右がわにあった。灰色の石壁の真中にある門からはいると、石畳みのこじんまりとした前庭があり、その右手に質素な玄関がつき出ていた。いなか娘らしく血色のゆたかな、いかにも気だてのよさそうな若い女中さんにみちびかれて、玄関を通りすぎたとき、私は、二階に通じる階段口に、灰色のマントを羽織って、階上を仰ぎみている長身の老人を見た。
ロマン・ロラン! かねてから写真で見知っていた彫りの深い端厳な横顔であった。
その階段口につづく広間を通りぬけると、つき当りが応接間になっていた。幅約六メートル、奥行き約四メートルの横に長い部屋で、左手には暖炉の前に椅子・テーブルがならべられ、右手にはりっぱなグラン・ピアノが置かれていた。光線は正面にたてつらなる硝子戸からきていたが、そのそばに立ちよると、いきなり眼の下に、なだらかな谷間や新緑の木立ちが広く遠く見わたせた。
やがて、当時四十歳代半ばのマリー夫人がにこやかに姿をあらわした。そして、われわれはさらに奥の別室で、夫人心づくしの茶菓でもてなされた。山本氏と高田氏とがテーブルをはさんでロランと向い合ったので、私はロランの隣に腰かけることになった。
話題は、ロラン夫妻のソ連訪問(一九三五年)に移り、マキシム・ゴリキーの歓待を受けた想い出話に及んだ。そして、やや粗野で冗談好きなスターリンとその側近たち、ことにゴリキーを毒殺したと疑われているゲ・ペ・ウ長官ヤコダなどの噂も出た。私はもっぱら諸先輩の会話の聞き手になっていたが、ついにかねがね心にわだかまっていた疑問をおさえきれなくなり、思わず口をはさんだ。
「ソ連の指導者たちはほんとうに民衆のためを思うことで行動しているのでしょうか。どうも疑われてなりません。」
すると、ロランは、コーヒーカップを受け皿において、「なぜですか」と私に向き直った。そして、今日出会ったばかりの異国の若者の云い分にもじっくり耳を傾けようとする誠意のこもったまなざしで、私を見つめた。
「なぜなら同じ理想を実現するために、ともに命をかけてたたかってきたはずなのに、革命が成功するとすぐに疑い合ったり、憎み合ったり、はてはかっての同志を殺したりします。それではいわゆる政治屋が私利私欲のために互いに術策や陰謀をたくましくして争い合い、打倒し合うのと余り変りはないのではないでしょうか。」
と、私はことばを選びながら、ぽつりぽつりと述べた。そうしているうちに、それまでに若さの余り、世の中には醜い争いが多すぎると思いつめていた気持が、胸一ぱいにこみ上げてくるのを覚えた。まじろぎもせず私の眼に見入っていたロランの顔が、そのとき不意に人なつこく、やさしくほほえんだ。
“C’est ce que c’est que la politique, monsieur.”
〔それはね、政治はどういうものかということなんですよ、きみ。〕
私の胸の奥底まで見とおしたこの的確簡潔な回答を耳にして、私はあたりがばつと明るくなるのを感じた。日ごろロランの作品を読んでばらばらに得ていた知識が、その瞬間にさっとより集って生きものになったといおうか、不意に生き生きと動き出した思いであった。その上、私は、ロランの慈父のようなまなざしに、「しっかりしたまえ、負けるんじゃないよ」という無言の励ましも読みとっていた。
ロランは、周知のとおり、第一次世界大戦が勃発したとき、自己の信念に忠実であろうとするやむにやまれないまごころから、黙っていることはできなかった。そして、「誰も他の人のいわなかった」反戦平和の訴えを世界によびかけたが、同調する知識人はきわめて少なかった。のみならず、ドイツ憎悪と抗戦の熱情に燃えていた祖国の人々のなかから彼を非国民あるいは裏切者と嘲罵する声さえ上がり、彼はスイスに引きこもって、国際赤十字の仕事に奉仕することで寂寞の想いを慰める日々を余儀なくされた。しかし、その後また好戦的なファッショやナチズムの抬頭によって、第二次大戦の脅威が高まると、彼はふたたび反戦平和のために立ち上った。そして、とくにソ連共産党の抵抗に期待し、敢て声援もしたが、そのソ連自体が、あろうことか、宿敵ドイツと手を組んで、ポーランドを分割領有し、弱肉強食の同じ本性を暴露したのである。それ故、ロランはもはや人類の救い難さに絶望しておられるのではないか、と私は半ば想像していた。が、まのあたりにみる彼の眼光は、この世の悪や不正を見きわめ知りつくしながら、なおも人類を愛して、その調和統一のためにたたかおうとする不屈の勇気を明かに示していた。
その日から十日ののち、ドイツ軍は、まずオランダ、ベルギーを奇襲したのち、五月十四日には、空陸協同の集中作戦でマジノ要塞線をたちまち突破し、フランス国内になだれこんだ。パリの新聞は第一面に地図をのせて、ドイツ軍の占領地域が日ごとに拡大して行く状況を黒枠で図示した。そしてその黒枠はみるみる大きくなって行った。
パリ市内では、中小商店のみならず、デパートまでが投げ売りをはじめ、各街道には気の早い避難民がひしめき流れ出した。
私は混乱のパリに心を残しながら、マルセイユに南下し、燈火管制下のホテルの一室で、ロランにお礼とお暇乞いの手紙をしたためたのち、藤田嗣治画伯夫妻たちと同じ邦人引揚船で、地中海から印度洋を通って帰国し、世界一周の旅を終った。
帰国してから数ヶ月後に、外務省情報部は内閣情報局に統合されたので、私も内閣に移って「国際月報」などの編集を担当していたが、やがて内閣の情報官に任命された。そして、一九四五年八月十五日の敗戦の日を迎えた。
ついで、私は終戦連絡事務局連絡官として仙台に派遣され、アメリカ占領軍との交渉に当ったが、翌年春には健康を害して辞任し、家族の疎開していた盛岡に引きこもった。
一九四八年になると、健康の回復した私は、地方新聞の専務取締役に選任されたが、一九五一年、民放制度の開設により創立されたTBS東京放送(当時ラジオ東京)に入社し、いくつかの管理職を歴任したのち、最後は関連会社日音の役員となった。そして一九八一年すべての役職を離れたときには、すでに七十歳を越えていた。
その間、マスメディアに関与するサラリーマンとして、任務に公正であろうとする志は失わなかったつもりであるが、さきのロマン・ロランのことばの「この世をありのままに見る」努力を先行させたために、「この世を愛する」努力はゆるがせになり、ひいてはロランの教えにもとったのではないかとの悔いが残った。それはいまなお私の胸中にくすぶりつづけている。
性格の弱さや才能のとぼしさから、私は運命に流されるままに、いろいろな職務を転々としたが、ことに戦後の混乱と窮乏のなかでは、家族の生活を守るのが精一ぱいであった。しかし、やがて経済的にも時間的にも多少の余裕を生じたので、ロラン晩年の諸著作、とりわけ没後に公表された回想録や自叙伝、書簡集などを入手して、ロラン研究を進めることができた。そのさい私の関心は、おのずから彼が少年時代に既成の形式的な「教会の神」と訣別したあと、その精神的空白をどのようにして克服したのかということに集中した。
ロランは、十六歳からエコール・ノルマルに入学する二十歳までの数年間に、「三つの閃光」の直観的神秘体験によって、自己と宇宙の万物とは本質的に同一であり、またすべては永遠の実在のなかにあることを覚知している。そしてそれを哲学(ことにスピノザ)研究によって裏付けつつ、二十三歳のとき論文「異なるが故に信じる」を書き上げて、信条の基盤を定立し、さらにその後もたゆみない省察をつづけ、また晩年にはインド思想研究の成果も加えて、人間をふくむ宇宙のすべては永遠の実在=「神」に包摂統一されるという「ユニテ」の信念を成就した、──と、私なりに理解した。
他方、私は、ピエール・ロティの研究もつづけ、一九九二年「ピエール・ロティ──人と作品」(駿河台出版社)を刊行してそれを総括したが、はしなくもその過程で私のロマン・ロランへの心服はゆるぎないものとなった。たとえば、ロティは肉体をもつ特定の人間すなわち個人をもっぱらその愛の対象としたので、その対象が必ず死ぬことに絶望して虚無感に圧倒されたが、ロランは、人間存在そのものを広く愛し、その人間のなかにも「神」すなわち永遠の実在の厳存することを確認して、不抜の信念を達成している。そのことだけでも、ロランが求道の精神においてロティより徹底していたこと、そしてそのために、宏大無二の信念を悟得したことが明らかであり、その点彼は賢哲としてロティより優位に立っているのである。
しかも、その信念確立にいたるロランの真理探求は、人間はなんであるか、そしていかに生きるべきかの問題意識から出発している。
それ故、人間すなわち自己のうちにも他人のうちにも「神」を見た彼は、利他奉仕の人類愛の良心的実践に踏み入り、たとえば、第一次大戦勃発時のような受難の重荷をも進んでになったのである。かくして彼は、あの偉大な文筆活動によってその信念を発揚する一方、人類協和を追求する実際行動をも貫き通し、信念と実践との、そして知と愛との、誠実無比な言行一致の範を示したのであった。
いま混迷する人類は、ロランの信念に背反する方向に走りつづけているようにみえる。せっかく冷戦が終ったのに、こんどは宗教の相異や民族の対立に基づく血まみれの抗争やテロが世界各地で続発し、止まるところを知らない。が、そのことで失望し、無力感におちいってはならないであろう。
ロランは、生涯の大部分にわたり、フランス革命劇を構想連作したが、そのさい彼は、世界をゆるがせたあの大事件も、宇宙を支配する諸原則により過渡的に生起した「社会の嵐」(Tempête sociale)とみている。このことは、歴史家としてのロランが、動乱流血の大革命も相対的な現象界に起伏する風波(仮象)にすぎず、その本源には永遠不滅の「神」すなわち真理の諸法則とその秩序が実在し、すべてを進歩統一の方向にみちびくとの透徹した認識を保持していたことを思い知らせる。そしてこの認識(歴史観)は、彼の信念の必然的所産であるが故に、終始変らなかった。現にロランは、フランス敗戦の暗い最晩年の日々に、ヴェズレーの家のテラスから、ドイツ侵入軍のまき上げる砂塵を眺めたときにも、
「国と国との衝突、虐殺、狂暴な精神錯乱を超えて上方にある『運命』の最高の手とその大きな諸法則とが、人類を、その諸目的にみちびいている。なんたる多くの混乱を通じて!なんたる多くの障害を通じて!……」(「内面の旅路」(片山敏彦訳))
と達観し、さらに
「だが車軸は無事である。そして雲々のあいだを、太陽の車がその道を進みつづけている。──もろもろの宇宙を
支配している秩序にしたがって」(同上)
と銘記して、「太陽の車」を駆る「神」が、人類最悪の敵すらも「人間進歩の道具」(同上)に使って、最後に勝つと不敗の信念を確保し、「神」とともに前進すべきこのたたかいにおいて、「おちついて、しつかりして、しんぼう強くあるがいい!」(同上)とわれわれを励ましている。
このロランの雄々しいことばを信じないで、いま誰のいうことが信じられよう。 |