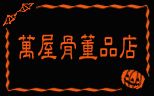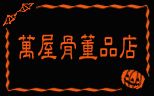迷宮都市カイロの魔法街キリエ。
占い師や魔道士の屋敷が立ち並ぶその一画に、ちょっぴり風変わりな一軒の店がある。
淡い燐光を放つターコイズブルーの看板が目印のその店の名前は萬屋骨董品店。
白い髪の主と二匹の猫が棲むその店に、またしても何やら不思議な品が持ち込まれたようだ。
■□■
カランカランと涼やかに鈴が鳴って、通りに面した扉が開く。
「Happy Halloween!」
いつもと違う挨拶でお客サマを出迎えたのは、白いケープに真っ白な羽の橙の髪の天使ルーと黒いマントに蝙蝠翼の蒼い髪をした小悪魔デュー。
異国の祭りに乗じて愛らしく仮装した看板息子と看板娘に、常連客のサヴァは相好を崩す。
「やー、相変わらずカワイイねー」
そのままデューを抱き上げようとしてルーに牙を剥かれるという毎度お約束の見慣れた光景を繰り広げていると、カウンターの奥から溜め息混じりの声が投げかけられた。
「久し振りですね、サヴァ」
こちらは金色の大きな三角耳にふさふさの尻尾を生やして妖狐に扮したサカキは、馴染みのトレジャーハンターの姿を一瞥すると、僅かに首を傾げてみせる。
「今回は、北の国への遠征ですか?」
大柄ながら女性らしいラインの体型を強調するようなぴったりしたデザインのレザーのコートも、折り返しにファーのついたロングブーツも、秋の終わりのカイロの街には少々暖か過ぎる装いではある。
それで北国帰りなのだろうと当たりをつけたサカキの問いに、サヴァは朗らかに頷いた。
「そーなんだ」
北の大陸で新しい遺跡が見つかって、研究への協力を条件に探索者を募っているという知らせが届いたのが夏の初めの事で、サヴァもお宝を求めて遠征していたのだ。
歴史的価値のある品や引き取り手の判っている遺品の類は当初の契約通り現地の関係者に引き渡したものの、それ以外でも随分と掘り出し物が出たらしい。
ほくほく顔で彼女が鞄から取り出す古代の硬貨や装飾品といった品々に、サカキも興味を示す。
鑑定は後日という事で取り敢えずの商談を済ませたところで、サヴァは鞄の奥から両手で囲めるくらいの大きさの小箱を取り出した。
「で、こっちはお土産」
蓋を開けると、中には陶器で出来た人形が一揃い入っている。
苔色のローブを纏い樫の杖を手にした魔法使いに、魔女やお化けに仮装した子供達、パンプキンヘッドの案山子や黒猫といったモチーフから察するに、ハロウィンの祭りの為に作られたものなのだろう。
「主が急逝して店仕舞いする事になったっていう工房で売りに出してたんだ。結構良く出来てるし、この時期に飾るには丁度良いだろ?」
確かに、人形の顔はどれも活き活きとしているし、衣装も細部まで見事に再現されていて、一目で良品と知れる細工物ではある。
しかも、折良くハロウィン当日の来店とくれば、なかなかに気の利いた土産と言えるだろう。
だが、目を輝かせて小箱を覗き込むルーとデューを他所に、サカキは頭痛を堪えるような仕草で丸メガネの縁を抑えて深々と溜め息を落とした。
「…どうして貴女は毎度毎度厄介な代物を持ち込みますかねぇ」
「どういう事だい?」
きょとんとした顔で目を瞬かせるサヴァはの表情はいっそ無邪気なもので、彼女に悪意がない事だけは充分に伝わって来る。
サカキは、諦めたようにもう一度溜め息を吐いてから、サヴァにこう問いかけた。
「ハロウィンの謂れはご存知ですね?」
「あぁ、確かあの世とこの世が繋がる夜なんだっけ?」
以前この店で仕入れた知識を浚ったサヴァは、やっぱり訳が解らないと首を捻る。
「で?それとコレとどーゆー関係があるわけ?」
「…とにかく、夜を待ちましょう」
そう言って、サカキはそっと小箱の蓋を閉じた。
■□■
その夜の事。
萬屋骨董品店の裏庭には、店主のサカキとルーとデュー、客であるサヴァの4人が顔を揃えていた。
彼等の目の前には、昼間サヴァが持ち込んだ例の人形が、それぞれにかなりの距離を開けて並べられている。
「…なんでわざわざこんな場所なワケ?」
「すぐに解りますよ」
仄暗い庭の石畳に人形を並べる行為に何の意味があるのかと訝しむサヴァだったが、サカキははぐらかすようにそう言うだけで、まともに応えようとはしなかった。
そのまま待つ事暫し、屋敷を囲む壁を越えた三日月から、蒼白い光が裏庭へと降り注ぎ始める。
すると、月の光を浴びた人形達に、変化が訪れた。
冷たい陶器の肌に瑞々しい温もりが灯り、堅固な筈の身体がゆっくりと動き出す。
それと同時に、その大きさも本物の人間のものへと変わっていった。
「この人形達は、魂の器なんですよ」
作り物の人形に命が宿る過程を固唾をのんで見守る一同に、サカキが静かに語り掛ける。
「ハロウィンには死者がこの世に戻ると言われています。普通は身寄りの家に惹かれるものですが、中には帰る場所を持たない幼い子供もいますからね。彼等が迷う事がないよう、標となるものが必要なんです」
サヴァが立ち寄った工房は、魔法仕掛けのからくり細工師が営んでいたのだろう。
細工師は、行き場のない稚い魂の憑坐としてこの人形を作ったのだ。
一同が見つめる先では、目覚めた子供達が魔法使いを取り囲むように集まっている。
魔法使いの翁は、子供達の一人一人にJack-o'lanternを手渡しながら、穏やかな調子でこう言い聞かせた。
「良いかい?このかぼちゃのランタンが消えるまでに、此処に戻って来るんだよ?万が一朝日を浴びてしまったら、二度と還れなくなってしまうからね?」
「はぁい」
素直に元気良く頷いて、子供達は夜の街へと駆けて行く。
子供達を送り出した魔法使いは、同じように彼等の後ろ姿を見送っていたサカキ達の方へと向き直ると、ゆったりとした手つきでフードを下した。
フードの下から現れたその顔に、サヴァが「あっ!」と声を上げる。
「その顔、あんた、工房の!」
サヴァが人形の入った小箱を買った工房の窓辺には、主の横顔を象ったレリーフが看板代わりに飾ってあった。
目元に刻まれた笑い皺に寄る年波を感じさせはするものの、彼等に微笑みかける魔法使いの顔は、確かに彼の工房主のものだった。
魔法使いに扮した工房主の細工師は、一同に向けて深々と頭を下げる。
己が遺品を託そうという彼の意を汲んだサカキは、微かな苦笑を浮かべて肩を竦めてみせた。
■□■
迷宮都市カイロの魔法街キリエ。
占い師や魔道士の屋敷が立ち並ぶその一画に、ちょっぴり風変わりな一軒の店がある。
淡い燐光を放つターコイズブルーの看板が目印のその店の名前は萬屋骨董品店。
白い髪の主と二匹の猫が棲むその店には、曰く付きのお宝が日々増殖中だとか。
|