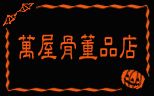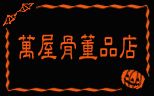迷宮都市カイロの魔法街キリエ。
占い師や魔道士の屋敷が立ち並ぶその一画に、ちょっぴり風変わりな一軒の店がある。
淡い燐光を放つターコイズブルーの看板が目印のその店の名前は萬屋骨董品店。
白い髪の主と二匹の猫が棲むその店は、その日に限ってなにやらいつも以上に風変わりな様相を呈していた。
■□■
カランカランと涼やかに鈴が鳴って、通りに面した扉が開く。
何の気構えもなしに店内に足を踏み入れたサヴァは、いきなりの珍妙なご挨拶に少々面食らう破目に陥った。
「Trick or Treat?」
綺麗に揃った声の主はいつもと同じ色違いの立て襟の服を着て色違いの橙と蒼の髪をしたルーとデューで、背中に仲良く片方ずつ蝙蝠の羽を背負った2人は何やら期待に満ちた瞳でサヴァを見上げている。
サヴァがきょとんとしていると、2人はことりと首を傾げてもう1度同じ言葉を発した。
「Trick or Treat?」
「…え?え、何?」
それでも意味が解らず困惑するサヴァを見かねて、店の奥のカウンターから主のサカキが助け舟を出す。
「ご馳走してくれないと悪戯しちゃうぞって言ってるんですよ」
あからさまに安堵の表情を浮かべて振り返ったサヴァは、サカキの姿を目にした瞬間思いっきり顔を引き攣らせた。
外套付きの黒いロングジャケットという出で立ちは普段と変わらないが、本日の彼は暗赤色の紅を刷いた薄い唇から鋭い犬歯を模した牙を覗かせている。
ご丁寧に金赤色のカラーコンタクトと長い付け爪のオプションまで身につけたその姿は、生来の白皙の美貌と相俟ってそれはもう立派に吸血鬼に見えた。
当のサカキは、力一杯退きまくっているサヴァの反応など何処吹く風で、おっとりのんびりした口調でマイペースに解説を続ける。
「言われた方は、I'm scared!って答えて、お菓子をご馳走するのがハロウィンのお約束なんです」
「…って、言うか、ハロウィンって何?」
最早何から突っ込んで良いのか解らなくなったサヴァは、とりあえず最も基本的と思われる疑問を口にした。
サカキは、接客モードで愛想良く薀蓄を披露する。
「一部の国々で行われている一種の宗教的儀式と言うか、まぁお祭りみたいなものですね。万聖節前夜なんて言い方もするようですけど、元々はとある神話における此岸と彼岸の繋がる特別な夜の事だとか」
一部の国々とかとある神話とか、そういう知識をサカキは一体何処から仕入れてくるのだろう、とサヴァは常々不思議に思っている事に改めて思いを巡らせながら説明を聞いていた。
尤も、半分くらいは聞き流している、と言った方が正しい状態ではあったが。
「それがいつの間にかお祭り色が濃くなって、こうして異界の住人の格好をした子供達が付近の家々を訪ね回ってお菓子を強請ったり、仮装パーティーを開いたりするようになったそうです」
「…で?」
ようやく調子を取り戻して胡乱気に結論を促すサヴァに、サカキはにっこりと非の打ち所のない営業用スマイルを浮かべてみせる。
「せっかくだから、ウチでもそのお祭りに肖ってみようかと思いまして」
そう言われてみれば、店の中の様子もいつもと違っているようだ。
もともと骨董品に特有の時間と記憶の重みに店主や店番の子供――時に仔猫だったりする――の謎めいた雰囲気も加わってどことなく妖しげな魅力を醸し出してはいるのだけれど、今日のそれは神秘的なのを通り越してどこかおどろおどろしくさえある。
入り口から顔を出して確かめると、看板までいつものターコイズブルーのものから暗闇で妖火が踊る細工の物に変わっていた。
「店内の明かりは、Jack-o'lantern氏にお願いしました。なかなか凝ってるでしょう?」
呆れ半分で感心するサヴァに、ふよふよと宙を彷徨うオレンジ色のかぼちゃを刳り貫いたランタンのお化けが笑いかける。
狐火を照明に使う骨董品屋というのも大概珍しいだろうとサヴァは思う。
いわくつきのお宝だけでは飽き足らず人外の生物まで呼び寄せてしまうサカキとこの店の特性は相変わらずらしい。
「もちろん、商品の方も今宵限りの特別な品揃えになっています。これは1日と1晩だけ死者を蘇らせる【地返し灯篭(ちがえしとうろう)】、こちらは彼岸への道を示す【夜見路の杖(よみじのつえ)】。貴方のように感性のあまり強くない方には、異界の方々の姿が見えるようになる【遠幻鏡(とおげんきょう)】なんてモノもご用意してますよ」
いつの間にか仔猫姿になったルーを右肩に乗せ、デューを左腕に抱いてにこやかに商品の説明を続けるサカキをじっと見つめながら、サヴァはしかし言いようのない違和感を抱いていた。
コレはオカシイ。
幾多の危険を乗り越えてきたトレジャーハンターとしての勘が、サヴァに危険信号を送ってくる。
確かにこの店には風変わりな商品も数多く持ち込まれる――何しろ彼女自身、その一端を担う「お得意サマ」だ――けれど、こんな風に危険な品物を面白半分で売りに出したりはしない。
その辺り、サカキには店主として相応の分別も責任感もある筈だ。
「…あんた、誰?」
恐る恐る尋ねたサヴァに、サカキは唇の端を持ち上げてにぃっこりと微笑んだ。
■□■
「サヴァ!サヴァってば!」
「うわ!」
耳元で大きな声で名前を呼ばれて、サヴァは勢い良く跳ね起きた。
「サヴァ?」
目の前には、心配そうにこちらを覗き込んでくるデューの蒼灰色の瞳がある。
「あれ?」
驚いた所為ばかりでなくどきどきする胸を押さえて周りを見回せば、其処はサカキの店のカウンターだった。
異国の祭りにちなんだ飾り付けの施された店内をきょろきょろと眺め回すサヴァを、ルーがけらけらと笑い飛ばす。
「何こんなトコで寝てんだよ?」
どうやら、店を訪れたら偶々誰もいなくて、帰りを待っている間にカウンターに突っ伏して眠ってしまったらしい。
と、すると、さっきのは悪い夢だったのだろうか?
釈然としない思いで首を捻るサヴァを横目に、ルーとデューはこっそり顔を見合わせて頷きあってから、徐に揃って口を開く。
「Trick or Treat?」
とても楽しそうににこにこと微笑む2人の背中には、片方ずつの蝙蝠の羽が仲良く生えていた。
|