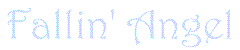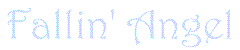※※※はじまりの祈り※※※
それははじまりの祈り。
神の領域に踏み込んだ彼でさえ、胸の裡で請わずにいられぬ願い。
――どうか、この世に生まれくる子供達に祝福を。
+ + +
硬く強張ったケイの声が、戸惑いがちに目の前の人物を呼ぶ。
「…博士?」
見覚えのある…懐かしいとさえ言える微笑みに、アイもまた困惑していた。
だが、自分を護るようにして立つケイの背中を見るうちに、波立っていた感情が凪いでいく。
最初の衝撃から醒めさえすれば、アイには容易く男の正体を見抜く事ができた。
「…違う」
震える声を低く抑えて、アイはそっとケイの腕に手を添えて口を開く。
「彼は『天使』だわ」
「…さすがはアイ」
彼の人と同じ鳶色の髪、同じ声を持つ『天使』は、悪びれた様子も見せずににっこりと微笑んだ。
「そう、僕は「J」。残念ながら翼はないけど、君達と同じ「熾天使」だよ」
人好きのするその笑顔はやはり「彼」に似ているけれど、アイはもう躊躇う事はなかった。
油断なく腕の鞭を構えつつ、ひたと視線を据えて静かに問いを投げかける。
「どうして貴方がその姿をしているの?」
それに対して、ジェイはおどけた仕草で肩を竦めてみせた。
「おやおや、随分乱暴者に育っちゃったなぁ。やっぱり《告死天使》なんかにされた所為かな?」
「博士は事故で亡くなった筈よ」
どこまでも本気を感じさせないジェイとは対照的な真摯さで、アイがぴしゃりとそう断じる。
アイは、ジェイの存在が罠であるかもしれないという疑念を抱いていた。
『天使』の能力を利用する一方で恐れてもいた組織の人間が、よりによって「熾天使」から識別信号を外す事は考え難いが、現に博士の姿を模した彼にアイ達は惑わされたのだ。
彼の真意が解るまで警戒を解くわけにはいかない。
一方、ジェイはアイの言葉にふっと笑みの質を変えた。
「ヴィに聞いたのかい?あの子は、賢い子だからね」
そう呟く声音は、子供を慈しむ親のものに近い。
ジェイは、1度瞼を伏せた後、驚くほど真面目な――けれどどこか謎めかした表情でこう切り出した。
「そう。確かにジュン=タチバナは研究所で起きた爆発に巻き込まれて死亡した。ただし、事故ではないけれどね」
アイとケイの瞳が僅かに揺らぐのを見て取りながら、更に予想外の事実をふたりに告げる。
「あの爆発は、タチバナ博士自身が仕組んだ事なんだ」
+ + +
――私は罪深い。
両脇に幾つもの扉が並ぶ廊下をゆったりとした足取りで歩きながら、ジュン=タチバナは密かに告悔する。
つい先刻、彼の育て上げた『天使』アイが「堕天」したという連絡が入った。
消息を絶つ直前まで、彼女は同じ「熾天使」で《守護天使》のケイと接触していた筈だった。
――あのふたりが出逢えたのなら、大丈夫。
タチバナは、僅かな安堵感を覚える。
組織の人間は、ケイに続いて《告死天使》のアイまで堕天した事に危機感を募らせているようだった。
それはそうだろう。《堕天使》を狩る《告死天使》として他の『天使』以上に情動への制限を課せられていたアイでさえ自らの意志を持って叛乱を起こすのなら、人を超えた力を持つ『天使』の存在は人類にとって脅威になりかねない。
遅かれ早かれ、組織は『天使』達から完全に感情や意思を奪おうとするだろう。
そうなる前に、計画を実行に移さなければいけない。
タチバナは、「J」と記された扉の前で足を止めた。
そもそも、タチバナの研究テーマは人工的に人体の一部を作り出す事だった。
当時、病気治療の為の臓器移植は本人の細胞を元にクローニングした、言わば本人の予備の部品を用いたものが主流になっていた。
この方法なら臓器提供者を待つ必要がないし、拒絶反応の怖れもない。
だが、一方で本人が遺伝子疾患に罹っていると、新たに臓器を作成しても再び発症する可能性があるという欠点があった。
予め遺伝子治療を施す時間的余裕があれば良いが、緊急時には対処しきれない場合もあり得る。
そこでタチバナが考えたのが、原子レベルから人体を作り上げる方法だった。
解析されたヒトゲノムを基に、人体を構成する物質を用いて移植を受ける人物に最適な状態の臓器を組み立てる――だが、その過程で、彼は人体の一部ではなく人間そのものを創り出す技術を発見してしまった。
無機物から有機物を――生命を生み出す科学という名の錬金術。
そうして生まれた生命は、胎児の状態から育成すれば人間と同じように成長する。
それどころか、遺伝子の操作や構成物質を変える事でより優れた能力を与える事さえできるのだ。
それは、タチバナにとって非常に危険で、魅力的な発見だった。
科学者という人種は、多かれ少なかれ子供じみた部分を持っている。
研究にのめり込むと周りの事が一切目に入らなくなって。
新しいものを見つけるとそれを試したくて仕方なくて。
手に入れた力を、それがどんな結果をもたらすかなど考えもせずに、加減もせずに使いたがる。
タチバナも、その誘惑には抗えなかった。
それが倫理にもとる事は承知で、彼は『天使』シリーズを生み出した。
彼が自分の罪に気づいたのは、研究チームが某組織の傘下に収められてからだ。
組織の人間は、『天使』達を利用価値の高い商品としてしか見なかった。
『天使』の人格を無視し、兵器として戦場に駆り出す彼等の遣り方に、タチバナはようやく己の過ちを悟った。
高い戦闘能力や特殊な技能を持つ『天使』が軍事利用される事など、少し考えれば予測できた筈なのに、目先の成果に浮かれた彼は現実を見ていなかった。
――こんなつもりではなかったのに。
『天使』達を不幸になどしたくなかった。
ただ、普通の子供達と同じように生きて欲しかった。
ある意味本当の子供のように、タチバナは彼等を慈しんでいたのだ。
…タチバナの孤独な戦いが始まった。
タチバナは、『天使』達に魔法をかけた。
それは、恋という名の魔法。
誰かを愛し、誰かに愛される事で、彼等が人間らしく生きられるように。
「魂」を得る事ができるように。
そしてもうひとつ、彼の用意した魔法があった。
「すまない、ジェイ」
今はまだ保護容器の中で眠る最後の『天使』に、タチバナは静かに話しかける。
だが、たとえジェイが目を覚ましていたとしても、応えが返る事はなかったろう。
ジェイには、他の『天使』のような意識は存在しない。
彼に与えられているのは人工知能が掌る擬似人格と、ある特定の記憶のみだ。
そう細工したのは、他ならぬタチバナ自身だった。
「私は、この期に及んで更に罪を重ねようとしている」
神に背いて新たな生命を作り出し、その上今度はその生命を自分のエゴの為に奪おうというのだ。
これを罪と呼ばずしてなんと呼ぼう。
保護容器のガラスをそっと指で辿って、タチバナは言葉を紡ぐ。
「それでも、私はあの子達を護りたい」
タチバナと同じ容姿をしたジェイは、彼の罪深さの象徴でもあった。
+ + +
「タチバナ博士は、事故を装って自らの頭脳ごと『天使』に関する情報をこの世から抹消した」
ジェイが告げた事実は、アイ達にとってショッキングなものだった。
「幸い、組織が所有していたデータは博士の遺志を悟ったヴィが壊して行ってくれた。研究チームのメンバーも博士の手法の肝腎な部分は知らされていなかったから、もうこれ以上『天使』が増える事はないよ」
それなのに、淡々と告げるジェイの口調は、晴れ晴れとしているようにさえ聞こえる。
顔を伏せ、何か思い詰めるように唇を噛み締めて彼の言葉を聞いていたアイは、やがて俯いたまま消え入りそうな声で呟いた。
「…私達は存在するべきではないの?」
「アイ…」
痛々しげに眉を寄せたケイが、他に為す術もなく震えるアイの肩を抱き寄せる。
アイは、顔を上げると悲痛な表情でジェイに訴えかけた。
「答えて。私達は罪の証なの?」
3人の間に、沈痛な空気が漂う。
しばしの沈黙の後、ジェイが口にしたのは謎めいた台詞だった。
「JはJOKERの「J」。そして同時に、ジュン=タチバナの頭文字でもある」
追い詰められた精神状態にあるふたりには、その意味が解らない。
ジェイは、彼らにも理解できるように言葉を重ねる。
「博士は、僕を彼のコピーとして造った。僕には彼の姿形とすべての記憶が与えられているんだ」
それから、穏やかであたたかい「ジュン=タチバナ」の笑顔で、ジェイはふたりに向かってこう語りかけた。
「大切なのは、何の為に生まれたのかではなくて、生まれてきて何を思い、何を為すのかだよ」
大きく瞳を瞠るアイに、ジェイは悪戯っぽく微笑みかける。
「これが、博士からの伝言。生きる事の意味なんて、自分で創れば良いんだよ」
それは、赦しの言葉だった。
自然の摂理に背く生まれを否定する事はないのだと――そうして、望むままに生きれば良いのだと、彼は言う。
アイは、泣きたい気持ちを堪えるように掌で口許を覆った。
だが、優しい感傷はそう長くは続かなかった。
突然の爆音が、彼等に再び緊張を強いる。
「あぁ、もう時間がないな」
その場を支配する緊迫した雰囲気に似合わない口調で、ジェイがぽつりと呟いた。
一瞬何処か遠くに視線を飛ばして、それからアイ達に向き直って口を開く。
「この研究所は、あと10分程で倒壊する。早いところ逃げた方が良いよ」
その態度に何となく悪い予感がして、ケイは躊躇いがちに問いかけた。
「君はどうするつもりなんだ?」
ジェイは、案の定曖昧な笑みを浮かべて首を横に振る。
「僕の役目は君達に博士の言葉を伝える事。それを終えた今、僕に与えられた記憶は『天使』達を危険に晒すものでしかない」
「逆に言えば、僕が此処で消えれば君達は自由になれるって事だろう?」と笑って告げるジェイに、アイが必死に言い募る。
「イヤよ!ジェイを残してなんて行けない!」
しかし、ジェイはあくまで首を縦に振ろうとはしなかった。
「わがままはダメだよ、アイ」
困ったような表情でジェイが宥めるようにアイの頬に掌を滑らせると、ふっとアイの身体から力が抜ける。
「心配ない。ちょっと電脳部分に働きかけて眠ってもらっただけだよ」
意識を喪ったアイを抱き止めたケイを安心させるようにそう言って、ジェイは一転して強い調子で促した。
「さぁ、行くんだ」
そうしている間にも、爆発の余波は次第に近づいている。
ケイは、両腕でアイを抱き上げると覚悟を決めて踵を返した。
彼が部屋の出口に差し掛かったところで、ふとジェイがその背中を呼び止める。
「ケイ」
振り返ったケイが見たのは、ひどく柔らかなジェイの微笑みだった。
「アイを頼むよ」
その言葉と、限りない愛情の込もった眼差しに、ケイは最初にジェイを見た時と同じ困惑に陥る。
「君…貴方、は…」
だが、ジェイはケイにその先の疑問を口に出す隙を与えなかった。
その代わりに、彼はとっておきの秘密を告白する。
「アイっていうのはね。幼い頃に病死したタチバナ博士の娘の名前なんだ」
「え――?」
驚愕の余り問い返そうとしたケイの目の前で、無常にも扉は閉ざされた。
+ + +
崩れゆく建物の中で、ジェイは――ジュン=タチバナは静かに瞑目する。
「幸せに、私の子供達」
罪深い《堕天使》の祈りは、誰にも聞き咎められる事なく闇に溶けた。
+ + +
翌日の新聞各誌には、多国籍系某複合企業体の研究施設で起きた大規模な爆発事故のニュースが取り上げられていた。
この施設では以前にも事故が起きて研究者が死亡していた事から、管理状態に問題があったのではないかという声が上がっているらしい。
更に研究内容についても取り沙汰されていたが、こちらは施設そのものが壊滅的なダメージを受けており、痕跡を辿る事さえできそうにないというのが専門家の見解だった。
いずれにせよ、人々はけして知る事はない。
この事件の陰に、多くの哀しみと愛しみに彩られた《堕天使》達の物語が秘められていた事を。
「お待ちどうさま、ケイ」
頭上から降ってきた声に顔を上げたケイは、眩しそうに目を細めて微笑んだ。
長かった髪をばっさりと切ったアイが、僅かに首を傾げて彼を見つめている。
ケイは、読んでいた新聞を畳むと、ゆっくりとベンチから立ち上がった。
「行こうか」
そう言って手を差し出せば、アイもそっと指を絡める。
ふたりは、仲の良い恋人同士のように互いに寄り添って歩き出した。
|