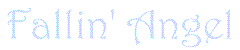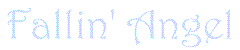※※※魔法の鍵※※※
「大切な何か」なんていらないと思っていた。
+ + +
シュンッと空気を斬り裂いて、銀の閃光が走った。
一瞬の後に、ばらばらという音と共に断ち切られた鉄条網が地面に落ちる。
金属製の鞭をブレスレットに収めたアイは、とんと軽い身のこなしで外壁を飛び越えた。
一足遅れて、警報装置に意識を集中していたケイがその後を追う。
2人が侵入を果たしたのは、彼等が生まれた研究施設だった。
懐かしい、という感情は湧き起こらない。
2度と戻る事などないと思っていた場所。
すべてが始まったこの場所に、探し求める答えがあるとヴィは言った。
その言葉を頼りに、2人は無人の廊下をひた走る。
事故で閉鎖されたとはいえ、施設の中は機密保持の為に厳重な警備が敷かれている筈だ。
だが、監視カメラも巡回中の警備メカも彼等の姿を捉える事はなかった。
赤外線センサーを備えた迎撃システムも一切反応を示さない。
護る者と狩る者――それぞれの頂点に立つ「熾天使」であるケイとアイの前に、それらはいとも容易く無効化される。
やがて、2人の進む先に居住区と表示されたドアが現れた。
+ + +
目が醒めて最初に感じたのは喪失感だった。
次いで、言い知れない寒さに身を震わせる。
室温は快適な状態に保たれていると肉体の中のセンサーが告げていた。
そうではなくて…そういう物理的なレベルではないところで、アイはただ「寒い」と思う。
夢の中で、ずっとすぐそばに誰かを感じていた。
ひたむきでまっすぐであたたかな眼差しと愛しげに名を呼ぶ声に柔らかく包み込まれる感覚が心地良くて、いつまでもそのまま微睡んでいたかった。
覚醒と同時にするりと指先をすり抜けていった幸福の代わりに手に入れた世界は、冷たいばかりで優しさの欠片もない。
白々とした蛍光灯の光に痛みを覚えつつぼんやりとくすんだ灰色の天井を見上げるアイの視界に、明るい鳶色が割り込んできた。
それが人間の頭髪の色だと認識する前に、頭上から声が投げかけられる。
「お目覚めかい?」
目線を上げると、30歳そこそこの男がアイを逆さまに覗き込んでいた。
その声が夢の中で聴いていたものではない事にアイは僅かに落胆する。
男は、それに気を悪くした風もなく穏やかに微笑んだ。
「私の名前はジュン=タチバナ。一応、君の生みの親という事になるのかな」
当時まだ調整中だったJを含む「熾天使」の3人は、覚醒後間もなく組織に連れて行かれる他の『天使』達と違って任務に就く直前までタチバナ博士の保護下に置かれていた。
それが、『天使』シリーズの開発チームが組織の傘下に収まる時に博士が提示した条件だったのだ。
アイは、いつものように博士の私室でカウンセリングを受けていた。
「恋は魔法のようだと思わないかい?」
温かい紅茶の入ったカップをアイに差し出した博士は、馥郁たる香りを愉しむように瞼を伏せてそう問いかける。
「誰かを愛しく想う気持ちは、人の心に優しさと情熱を呼び覚ます」
それに対して、アイは微かに眉を顰めた。
「激情は人の心を狂わせるわ」
恋は、けして綺麗なばかりのものではない。
報われないせつなさもあれば、失う痛みもある。
独占欲、嫉妬、猜疑心――自分の中にあるそうした醜い感情を突きつけられ平気でいられる人間はいないだろう。
そうして追い詰められた精神は過ちを犯す。
周囲を傷つけ、己自身を壊すような破滅的な恋など迷惑なだけだとアイは言う。
「それに、大切なものを抱えていたら闘えないでしょう?護らなければいけないものなんて足手まといだし、弱みになるもの」
「そうだね」
「大切なもの」を知らないが故の強さで嘯くアイに、博士はほんの少し淋しげな笑顔で呟いた。
「でも、何かを護ろうとして人は強くもなれるんだよ」
その想いは、時に不可能を可能にする奇跡になる。
だが、彼の願いは、アイには届かなかった。
「そうだとしても、私には必要のないものだわ」
両手で包むようにして持ったカップに視線を落として、アイは素っ気なく言い放つ。
「私は「狩る者」だもの」
+ + +
両脇にずらりと扉が並ぶ廊下に差し掛かったところで、アイの足が止まった。
AからZまで26のアルファベットが記された部屋は、『天使』達ひとりひとりが眠っていた調整室だ。
アイの脳裏に、自らの手で狩った『天使』達が蘇る。
任務を強制する為に組織に連れ戻すだけでなく、時には組織と敵対しようとする者を殺めた事もあった。
アイの心に刻まれた、消える事のない過ちの記憶。
望んで生まれたわけでもなく、それでも確かに生きる事を求めた彼等に何の罪があったろう。
――罰を受けるべきなのは私。
赦しを希うつもりはアイにはない。それは、許されない事だから…。
知らず握り締めていた右手を、ケイの大きな掌が包み込む。
触れ合った肌から伝わる温もりが、ともすれば思い詰めてしまいがちなアイの心を和らげる。
彼の長い指に、アイもそっと指を絡めた。
+ + +
ケイと出逢って、ケイを好きになって、あの時の言葉の意味が少しだけ解る気がした。
大切なものの為に強くなる。
怖いと思う事もある。
喪失の予感に胸が軋んで眠れない夜を幾つも過ごした。
夢から醒めて、隣で微笑む彼に安堵する朝を何度も迎えた。
見つめあうだけで幸せで、声を聴くだけでせつなくて、名前を呼ぶだけで泣きたいくらいときめいて。
告死天使として感情を抑制され数々の制約を受けていた時には知らなかった苦しみと喜びを数えきれないくらい手に入れた今だから言える。
強くありたい。この想いと、大切なケイを護れるように。
+ + +
いつしか、2人は通い慣れた道を辿り、タチバナ博士の私室の前まで来ていた。
博士自身は事故で亡くなったと聞いていたが、彼の部屋はそのままになっているようだ。
ただ、アイに対してはいつでも開かれていた扉に鍵が掛けられているという事が、博士がもういないのだという事実を彼等に思い知らせる。
そのままその場を立ち去りかけたアイは、ふと部屋の中の気配に気づいて立ち止まった。
振り返ると、ケイも何か感じ取った様子でじっと扉を見つめている。
閉鎖された研究施設に人がいるとは思えない。
だが、警備メカの動きは止めた筈だ。
それなら、今、部屋の中にいるのは――。
「…J?」
半信半疑で呟いたアイの声に応えるように、扉がスライドした。
どうやら、扉の鍵はアイの声紋だったらしい。
一瞬の逡巡の後に、2人は部屋の中へと足を踏み入れた。
予想に反して晧々と明かりの灯った室内に視線を廻らせると、窓辺に佇む人影が目に留まる。
明るい鳶色の髪のその人物は、肩越しに2人を見遣って顔を綻ばせた。
人好きのする柔らかな微笑みと穏やかな眼差しが、2人の記憶を刺激する。
「…嘘…」
そう呟いたきり口許を覆って絶句したアイをその身で庇うように、ケイが一歩足を踏み出した。
険しい視線をひたと据えて、慎重に問いを投げかける。
「…博士?」
2人に向けられた笑みが、ふっと深みを増した。
|