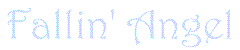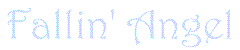※※※小さな灯火※※※
夜の闇を切り裂いて列車が走る。
人気のない車両の1番後ろの2人掛けの席で、ケイは遠くに揺れる街の灯りを見るともなしに眺めていた。
隣では、ケイの肩に寄りかかるようにしてアイが小さな寝息を立てている。
冷房の効き過ぎた車内は肌寒いくらいで、アイは心許無げな様子で自分の腕を抱いていた。
今は、ケイの上着が彼女の華奢な肩を包んでいる。
本当は、アイが感じているのは寒さばかりではないと気づいているけれど。
それでも、こんな風に温もりを分け与える事くらいしかできないケイは、せめて彼女の見る夢が安らかなものであって欲しいと祈る。
「おまえは本当にアイが好きだね」
ケイの脳裏に、今は亡き人の笑みを含んだ声がふと蘇った。
+ + +
訓練のない時間をその部屋で過ごす事が、その頃のケイの日課だった。
窓ひとつない部屋の中、用途も解らない無数の計測機器とたくさんのコードに囲まれた寝台の上に、少女が横たわっている。
ケイは、静かに部屋を横切ると寝台の枕許に膝をついた。
片方の腕でシーツの上に頬杖をつき、もう片方の手で少女の長い髪を一房取って口許へと運ぶ。
端整な横顔に夢見るような微笑を浮かべて、ケイは滑らかな髪にそっとくちづけた。
無粋な機械に囲まれて眠る生まれたばかりの彼女は、1度もケイの前で目を醒ました事がない。
けれど、ケイは確かに少女に惹かれていた。
だいじなだいじな、ケイの眠り姫。
「また此処にいたのか」
冷たい床を苦にするでもなくにこにこと少女を見守る彼の背後から、苦笑交じりの声がかかる。
振り返った先に立つ男の顔は廊下の明かりの所為で逆光になってよく見えないけれど、その声からは温かな人柄が伝わってくる。
この男こそ、ケイ達『天使』シリーズの生みの親だった。
解析されたヒトゲノムを基に無機物から生命を生み出した現代の錬金術師は、人好きのする笑顔でこう問いかける。
「眠っている子を見つめていて楽しいかい?」
ケイは、満面の笑顔で「もちろん」と応えた。
「彼女のそばにいると、優しい気持ちになれるんだ。それに、どんな瞳の色をしてるんだろう?どんな声で話すんだろう?どんな風に笑うんだろう?そういう事考えるだけで凄くどきどきする」
そう言って瞳を輝かせるケイに、男は眩しげに目を細める。
「おまえは本当にアイが好きだね」
「うん!」と屈託のない笑顔でケイは頷いた。
それから、愛しげな眼差しをアイに向けて口を開く。
「ねぇ博士。僕は、誰かを護る為に生まれたんでしょう?」
その言葉に、男の表情が僅かに翳った。
だが、彼に背を向けたケイはその変化に気づかないまま、真摯な面持ちで夢を語る。
「それなら、僕はアイを護りたい」
+ + +
あの頃、ケイは疑う事を知らない無邪気な子供だった。
だから考えもしなかったのだ。その気持ちがプログラムされたものでしかないのかもしれないなどと。
真っ白な知能に閉ざされた空間で偏った知識と情報だけを与え、限られた体験だけを繰り返させれば、洗脳する事は容易い。
『守護天使』にとって、誰かを護るというのは目的であると同時に存在理由でもある。
人間と同じに作られた肉体に改造を施し、武器の扱いを覚え込ませ、生体の脳を補助するAIまで埋め込んだ組織の人間なら、ケイの気持ちを利用する事にも何ら躊躇いを覚えはしないだろう。
その事にケイが気づいたのは、だいぶ後になってからだった。
何度か任務で誰かを護る仕事につくうちに、ケイは次第に混乱状態に陥っていった。
アイを護りたいと思う。
その情熱は契約で成り立つものではない、純粋な保護欲からくるものの筈だ。
それなのに、この胸に宿る仄かな想いさえ刷り込まれたものでしかないというのか?
自然の摂理に背いて生み出された自分のこの感情さえも作り物なのだとしたら、本当の「自分」はどこにいる?
自分自身さえ信じられなくなりそうだったケイを救ったのは、彼等の創造主且つ庇護者で唯一の理解者でもあった博士の一言だった。
「おまえは、アイを選んだんだね」
アイを護りたいと誓った日、彼の髪を撫でてそう呟いた博士の愛しみに満ちた言葉が、ケイを答えへと導く。
ケイの望み、それは、「誰か」ではなく「アイを」護る事。
その願いこそが、彼を彼たらしめるのだ。
やがて来るべき日の為に、アイの目覚めを待たずにケイが組織を離れたのは、それから数日後の事だった。
+ + +
窓の外を流れ行く景色に彷徨わせていた視線の片隅を過ぎるガラスに映ったアイの寝顔に、ケイは束の間の追憶から醒める。
肩に感じる微かな熱と柔らかな重みと、甘やかな髪の香りに誘われて、ケイは自然と口許を綻ばせた。
すべてを彼に委ねて眠るアイの、稚いその寝顔を護りたいとケイは切に願う。
この気持ちがどこから来るのかは解らないけれど。
この恋さえ仕組まれたものだというのなら、それはそれで構わないと思う。
たとえどんな出逢いでも、彼女を愛しく想うのは紛れもなくケイ自身なのだから…。
「ん」と小さく身じろいだアイの指先が、無意識の内に重ねたケイの指をきゅっと握り締める。
一回り小さな掌を優しく握り返して、進むべき道を示す小さな灯火にも似た想いを胸に、ケイもまた静かにその瞳を閉じた。
|