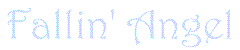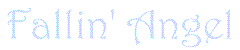※※※還るべき場所※※※
教会の前の小さな広場で、少年が小鳥達と戯れている。
麗らかな春の陽射しを弾くハニーブロンドに乳白色の柔らかそうな肌。瞳の色は「天上の青」と呼ばれるウルトラマリン。
無邪気に空へと手を伸ばす彼の背後で、石畳にコツンと足音が響く。
ばさばさっと羽音をたてて、小鳥達が一斉に飛び去った。
ひらひらと羽根が舞い散る中、少年が振り返る。
「ひさしぶり」
そう言って微笑む姿は、さながら宗教画の中から抜け出した天使のようだった。
+ + +
其処は、山間にある小さな町だった。
これといった観光名所があるわけでもなければ交通の要所に位置するでもない、長閑さだけが売りのような田舎町だ。
それも、ここ数年は山ひとつ隔てた隣国で起きている民族紛争のあおりを受けて、町民の間に漠然とした不安が広がりつつある。
少年がこの町にやって来たのは、そんなある日の事だった。
町の裏手にある森で発見された時、少年は肉体的にも精神的にも衰弱しきっていた。
薄汚れた衣服には、僅かだが血の付着した痕が残っている。
おそらく、戦場から逃げてきたのだろう。13、4歳かそこらの子供が1人で山を越えられただけでも僥倖というものだ。
その場で意識を喪った少年は、年若い神父の家に引き取られた。
3日3晩の昏睡状態から目覚めた後も、少年はほとんど口を利こうとはしなかったしなかった。
声が出ないのかと試しに紙と鉛筆を与えて名前を尋ねてみると「V」と1文字だけ書きつけた。
だから、町の人達は少年の事を「ヴィ」という愛称で呼んでいる。
少年が言葉を話さないのは、精神的なショックによるものだろうと彼の保護者でもある神父は考えていた。
喋らないのではなく、喋れないのだ。
彼の5歳になる姪が、両親を火事で失ったばかりの時にも同じような症状を見せていた。
今でこそ屈託ない笑顔をみせるようになったけれど、ここまでくるのはけして簡単な道程ではなかった。
少年が言葉を取り戻すのに必要なのは、時間と本人の意志だ。
30歳そこそこという人生経験の長さから言えばまだまだ若造の部類に入るくせに、職業柄年不相応に達観した部分も持ち合わせている神父は、黙って少年の様子を見守っている。
ヴィは、日長1日教会の前の階段に腰掛けて、ぼんやりと地面を眺めていた。
大きな青い瞳に、感情の彩はない。
笑えばさぞ愛らしいだろうと思われる整った貌立ちをしているだけに、虚ろなその面差しは見るものを痛々しい気持ちにさせる。
だが、遠巻きに寄せられる同情は、ヴィの心にはけして届かなかった。
彼の瞳が捉えているのは目の前にある景色ではなくて、脳裏に灼きつけられた地獄絵図なのだ。
ヴィにとって、それはいつもの訓練の延長だった。
装甲車の後部席でコンピュータのモニタと向かい合い、キーボードに指を滑らせていく。
敵の所有する軍事衛星に侵入し、そこに蓄積された情報を解読した後、データを改竄する。
レーダーの無効化、情報の攪乱、対空砲及びミサイル迎撃システムの停止。
電子頭脳を操る事に特化するように創られ、専門の訓練を受けたヴィには簡単な仕事だ。
訓練通りに作業を終えたヴィは、だが、訓練終了の文字を表示する代わりに突然乱れた画面に、一抹の不安を覚えた。
この時、ヴィはまだ自分のした事の意味を理解していなかった。
彼の中では、コンピューターのハッキングもそれに伴う結果も、あくまでシミュレーションでしかなかったのだ。
車の外に出たヴィは、目の前に広がる光景に愕然として立ち尽くした。
街が燃えていた。
病院も、学校も、教会も…何もかもが無防備に攻撃に曝され、焼かれていく。
「…あ…」
ヴィは、震える足で後退さった。
こんな事は知らない。
こんな風に多くの命を奪う事になるなんて、知らなかった。
無意識のうちに首を横に振りながら、一方で有能なヴィの頭脳は冷酷に現実を突きつける。
これは罪だ。
どんなに言い訳を重ねても、これは間違いなく自分の罪だ。
「――っ!!」
声にならない悲鳴を上げて、ヴィはその場から逃げ出した。
「っ!!」
目を閉じ、耳をふさいでも蘇る記憶の奔流に流されかけていたヴィは、ふと自分に向けられる視線を感じて目を開いた。
顔を上げると、目の前に小さな女の子が立っている。
「どぉしたの?」
世話になっている神父の姪は、心配そうにヴィの顔を覗き込んで首を傾げた。
「どっか痛いの?それとも、お腹空いたの?」
子供らしい発想に、ヴィはただゆるゆると首を振る。
すると、童女はふと何かを思いついたというように手にしていた籠を探りだした。
そうして、小さな手でヴィの手を取って、そこから取り出したものを乗せる。
それは、小さな苺だった。
突如として目の前に示されたその色に、ヴィの精神は揺すぶられる。
赤い、実…炎の赤、血の赤…罪の、赤。
命を奪う為だけになんて生まれてきたくなかった。
違う。そうじゃない。
生まれてきてはいけなかった――。
その時、あどけない童女の声が、再び記憶の向こうに攫われかけたヴィの意識を現実へと呼び戻した。
「叔父さんと一緒に、お庭で取ってきたの。絶対美味しいから、ヴィも食べて」
にこにこと笑う童女の無邪気さに気圧されるように、ヴィは苺を一粒口に含む。
まだちょっと酸っぱいその実は、だけどヴィにはとても甘く感じられた。
「…甘い」
小さな呟きと共に、澄んだ青い瞳から涙がはらりと零れ落ちる。
「どうしたの、ヴィ?泣かないで?ねぇ、ヴィ…」
自分を気遣う幼い少女の舌足らずな声と口の中に広がる苺の味が教えてくれるもの。
罪を犯した自分にさえ、世界は優しい。
「…ありがとう」
驚く童女を抱き寄せて、ヴィはこの世のすべてに感謝した。
それから、ヴィはその町で暮らし始めた。
普段は教会の手伝いをして過ごして、日曜日のミサの後には町の子供達と話をする。
ヴィは、子供達にたくさんの事を話して聞かせた。
知っていれば避けられる罪を犯さずに済むように。
自分の意志で、進むべき道を選べるように。
天使のように綺麗で優しいヴィに町の子供達はすぐに懐いたし、ヴィも子供達をとても可愛がった。
そうして3ヶ月が過ぎた頃、転機がやってきた。
その日も、町外れの大きな木の下で子供達の相手をしていたヴィは、遠くからこちらを見つめる少女に気づいた。
腰まである茶色の綺麗な髪をした彼女をヴィは知らなかったけれど、彼女が自分に会いに来た事は何となく解った。
子供達を家に帰した後、ヴィは近づいて来た少女に自分から話しかけた。
「君は、僕の仲間なんだね」
少女は、それには応えずに淡々と用件を告げる。
「私は告死天使I。告知天使V、貴方を狩りに来ました」
「僕を殺すの?」
落ち着いた声そう尋ねるヴィに、アイは無表情に首を横に振った。
「私が受けた指令は、戦線から逃亡した貴方を連れ戻す事だけ」
それでも、ここでヴィが抵抗すれば、アイは無理にでも彼を連れ去るだろう。
下手をすれば、町の人達まで巻き込みかねない。
ヴィは、優しいこの町の人々を傷つけたくなかった。
だから、人当たりの良い笑顔のままで口を開く。
「解った。でも、少しだけ待っててくれる?このまま僕が急にいなくなったら不自然でしょう?」
アイは、彼の言い分を黙って受け入れた。
教会に戻ると、神父は丁度ミサの後片付けを終えたところだった。
「お別れを言いに来ました」
彼には多くの言葉は必要ないような気がして、ヴィは端的にそれだけを告げる。
「そうですか」
ヴィの想像通りの穏やかさで、神父は頷いた。
それから、ポケットを探ってペンダントを取り出す。
「これを」
差し出されたその鎖の先には、ヴィの寝泊りしていた部屋の鍵がかかっていた。
大きく眼を瞠るヴィに、神父が微笑みかける。
「私は大抵はこの町にいますけど、たまには出かける事もありますから」
いつでも、此処に帰って来られるように。
それは、ヴィに与えられた赦しだった。
+ + +
「きっと会いに来ると思ってた」
そんな風に、ヴィはにこやかにアイとケイを迎える。
この町にヴィがいる事を、アイ達はユウから聞いて来た。
それでも、1度は組織に連れ戻した筈のヴィが此処にいる理由がアイには解らない。
彼女の困惑に心当たりがあるヴィは、教会の前の指定席に腰掛けると徐に話を切り出した。
「君が失踪してすぐに、「天使」シリーズの生みの親である博士が研究中の事故で亡くなったんだ」
「博士が?」
その言葉に、アイよりも先にケイが反応を示す。
ヴィは、慎重な表情で頷いた。
「本当は、事故かどうか解らないけどね。告死天使として教育されたアイまで意志を持って叛乱した事に、上層部はかなり危機感を抱いてたみたいだし」
人類より優れた能力を持つように造られた彼等は、それ故に創造主である人間にとって危険な存在となり得る。
だから、組織は彼らに任務に関係のない知識や必要以上の感情を与える事を避けていた。
特に、同胞を狩る為に生み出された告死天使は他の個体以上に自我や情動への制限を受けていた筈だ。
「最高クラスの「熾天使」のうち2体が堕天したところに博士の事故が重なって、組織はかなり混乱をきたしてた。おかげで、簡単に抜け出せたよ」
ついでに、組織にあった「天使」シリーズに関するデータはすべて破壊して来たから、とヴィは言い添える。
いくらケイが優秀な守護天使だとはいえまったく追っ手のかかる気配がないのはおかしいと思っていたのだが、どうやらそれが理由だったらしい。
ヴィは、ほんの少し淋しげな、でもどこか安堵に満ちた表情で続ける。
「博士もいない今、僕達みたいな存在が生み出される事は、もうないんだ」
ヴィのその一言は、アイの胸に小さな漣を立てた。
確かに、アイ達「天使」は不自然な存在だし、これ以上こんな生命を増やしてはいけないと思う。
でも、それなら自分達は、許されない存在なのだろうか?
「ヴィは、私達が生まれて来てはいけなかったと思うの?」
心なしか傷ついた瞳でそう訊いたアイに答えようと視線を上げたヴィが、ふっと相好を崩した。
それが自分ではなくその向こうにいる相手に向けられたものだと気づいたアイが振り返るより早く、女の子が元気良く駆けて来る。
童女は、ヴィの前までやって来ると、彼に向かって手を伸ばした。
小さな掌には、甘酸っぱい芳香を放つ木の実が乗っている。
「ヴィ!見て見て!初摘みのブルーベリーよ!」
「あぁ、ほんとだ。美味しそうだね」
「でしょう?ヴィの好きなジャムをいっぱい作るね!」
笑顔で頷くヴィに嬉しそうにそう言って、童女は来た時と同じ軽やかさで駆けて行った。
それを見送ってから、ヴィはアイに視線を戻す。
「生まれてきたのが正しいとか正しくないとか、そういうんじゃなくて」
言いかけた事はたぶんもうアイにも解っただろうけれど、敢えて言葉にする事を、ヴィは選んだ。
「少なくとも、僕には還る場所があるから」
それが、ヴィの出した答え。
おそらく、ヴィは組織に捕らえられていた間に自分達の秘密を知っている。
でも、彼は、それ以外の場所に答えを見出した。
童女を追う為に教会の前の階段から腰を上げたヴィは、アイとケイに1枚の紙片を差し出す。
それは、ある施設の住所と詳細な見取り図だった。
2人とすれ違い様、ヴィがその紙片に託した意味を告げる。
「「J」は、組織の研究所にいるよ」
彼等がこの町を訪れた目的に、ヴィは気づいていたのだ。
「…君達が捜し求めてるものも一緒に」
僅かな間を置いて残された言葉が、アイには何故だか謎かけのように感じられた。
|