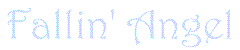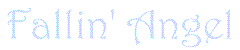※※※戒めの呪文※※※
その街には、いつもどこか特別な雰囲気が漂っていた。
近代的なビルが乱立する眺めは都会ではありふれたものだし、世界中の様々な文化様式が無秩序に混在しているのも国際的な大都市では然程珍しい事ではない。
だが、世界各地から流れ込む人と物を貪欲に呑み込みながら、その街は本質的な部分での「その街らしさ」を常に保ち続けていた。
それはたぶん、此処で生まれ育った人々の心に血族への帰属意識と確たる誇りが宿っているからだろう。
以前訪れた時と同じ感慨を、アイは抱く。
あの時はひとつの任務を終えたばかりで、より人間らしい振る舞いを学ぶ為に観光客として滞在していた。
今は、「同志を捜せ」というディーの遺言を頼りに、ケイと2人で街を歩いている。
ただ1人、アイが仕事以外で出逢った堕天使と再会する為に。
+ + +
民族色の濃い商店街は、倦んだ熱気と食べ物の匂いで満たされていた。
人込みに酔ったアイは、軽い頭痛を覚えつつ機械的に足を運ぶ。
この通りを抜ければ、広場に出られる筈だった。
高台の上にあるその広場からは、眼下に広がる街並みが一望にできるらしい。
そこからの眺めは大変美しく、夜にはライトに彩られた摩天楼をして「百万ドルの夜景」と呼び習わされているのだとデータにはあった。
だが、今のアイは景色の美しさなど念頭にない。ただこの人いきれから解放されたいだけだ。
そもそも、告死天使の仕事に合わせて作られた特別製のセンサーを持つアイに、この人波は少々酷だった。
研究所に帰ったら、都市部での仕事の際はもう少し感度を落とすよう報告しなければ――そう考えていた彼女の感覚に、微かなシグナルが引っかかる。
それは、同胞である『天使』の発する信号だった。
相手もそれに気づいたのだろう。
思わず顔を上げたアイの視線の先で、癖のない長い黒髪をひとつに結わえた長身の青年が立ち止まってこちらを見返している。
青年の腕に纏わりつくようにして隣を歩いていた12、3歳の少女が、突然足を止めた彼を不思議そうな表情で見上げて首を傾げた。
「ユウ?どうしたの?」
その声に、呼びかけられた青年が我に返る。
驚愕から醒めた青年は、柔らかな瞳をして少女に微笑みかけた。
「ちょっと、知り合いがいたので」
それから、アイをまっすぐに見つめて声をかけてくる。
「こんにちは」
「…こんにちは」
アイは、戸惑いがちにそう応えた。
広場に出るといきなり目の前の景色が開けた。
神経に障る喧騒から解放されたアイは、自分でも気づかぬ内にほっと息をつく。
だが、一方でアイは告死天使としての感覚を鋭敏に研ぎ澄ましていた。
原因は、ユウと呼ばれた青年にある。
彼は、連れの少女にアイと話したい事があるからしばらく2人きりにさせてくれと申し出た。
目の届く範囲で遊んでいるようにと告げた彼に頷いて、少女は広場の中で1番空に近い手摺際へと駆けて行く。
その後姿を温かな眼差しで見守るユウの横顔をじっと見据えて、アイは冷たい声を放った。
「…貴方は死天使ね?」
「さすがは告死天使ですね」
確認ではなく断定の口調で尋ねたアイに、ユウは人当たりのよい笑顔を向ける。
「確かに、俺は死天使です。それも、不完全なプロトタイプの」
そう言って、ユウは何気ない所作で上着の袖を捲った。
細く筋肉質な腕に、片翼の紋章が浮かび上がる。
それを目にしても、アイの表情は変わらなかった。
表面上は愛らしい顔立ちに似合いの仕草で小首を傾げながら、感情のこもらない声音で問いかける。
「何故死天使がボディガードの真似事なんてしてるの?」
ユウは、ちょっと困ったように曖昧な微笑を浮かべた。
彼と彼の連れている少女とは、同じ黒髪という事もあってどこか似通った印象を与えがちだった。
仲良く連れ立って歩く様は、傍目には歳の離れた兄弟か従兄妹同士にしか見えないだろう
だが、アイの眼は、ユウの一挙手一投足に込められた相手を護ろうとする意志を読み取っていた。
ややあって、ユウがぽつりと口を開く。
「彼女の父親は、華僑系コンツェルンの開発部門で働いていました」
過去形で語る彼の言葉尻から、少女の父親が既に亡くなっている事をアイは理解した。
おそらく、機密漏洩を怖れる幹部に抹殺を命じられたか、利権争いに巻き込まれるかしたのだろう。大企業の裏側では然程珍しい事ではない。
案の定、続くユウの言葉はアイの推測を肯定するものだった。
「俺に与えられた指令は、娘の家庭教師としてターゲットに近づき、折をみて暗殺者を手引きする事でした」
当然、何かあれば最近被害者に近づいたユウに嫌疑がかけられる事になる。
初めからそれを想定した上での人選だった。
たとえ高性能なバイオノイドである『天使』シリーズでも、プロトタイプの扱いは使い捨てに等しい。
「俺は、すぐに彼女と彼女の父親の信頼を得ました」
善人のふりだけはしっかり仕込まれてますから。そう言って苦笑するユウは、最上クラスのアイより余程人間らしい。
「作戦は、すべてうまくいきました」
その時の事を思い出すように僅かに目を細めて、ユウは続ける。
「あの夜、強盗を装った暗殺者の仕事を見届けて、俺は姿を消すつもりでした。共犯に仕立て上げられるのは構わなくても、身柄を拘束されてこの身体の秘密を暴かれるわけにはいきませんからね」
血生臭い罪さえ何でもない事のように淡々と話し続けていたユウが、「でも」と呟いてふわりと微笑んだ。
優しく、おかしそうな…それでいて痛みを内包したせつないその笑顔に、アイは思わず眉を顰める。
だが、ユウ本人は自分が今どんな表情をしているのか、まるで気づいていないようだった。
それまでと同じ穏やかな、感情の起伏に欠ける調子で言葉を紡ぐ。
「物音に気づいて、彼女が目を醒ましてしまったんです。当然、暗殺者は彼女も殺そうとしました。だけど、俺は思わず彼女を庇ってしまったんです」
死天使としての本来の能力からすれば、たかが人間の暗殺者を殺す事など容易い事だった。
少女の証言もあって正当防衛が認められ、無罪放免されたユウは、そのまま今日まで少女のそばに留まっているというわけだ。
「…それは、罪滅ぼしのつもりなの?」
ユウの独白を聞き終えたアイは、硬い表情のままでそう尋ねた。
そこに蔑みや詰るような意思は感じられない。
ただ単純に、アイにはユウの心情が理解できないのだ。
そんな彼女の胸の裡を知ってか知らずか、ユウはあっさりとこう応えた。
「解りません」
アイが訝しむように目を細めるのを見ても慌てるわけでもなく、おっとりと足りない言葉を補う。
「ふざけているのではなくて、本当に解らないんです。何故あの時彼女を庇ったのかも、人を殺す事が仕事の筈の俺がどうしてこれほど彼女を護りたいと思うのかも…」
ただ、と言いかけたユウを、不意に少女が振り返った。
「ユウ!」と彼の名を呼んで手を振る少女に、ユウは相好を崩す。
そうして少女を愛しげに見つめたまま、途中になっていた告白の続きを口にした。
「彼女のあの声が――俺を「U」という記号ではなく「ユウ」という名で呼ぶ声が、俺を呪縛するんです」
アイは、そんなユウをやはり理解できないという表情で見遣る。
少女に手を振り返したユウは、アイを振り返るとふっと目許を和らげて問いかけた。
「俺を狩りますか?」
その笑顔があまりにも透き通って見えて、アイは痛みを覚える。
僅かな躊躇いの後、アイはふるふると首を横に振った。
「貴方を狩る事は命じられてないから」
ユウは、一瞬目を瞠る。
それから、それまでで1番優しい瞳で、幸せそうに微笑んだ。
+ + +
あの時と同じ道程を辿って、アイはケイと共にその広場へと辿り着いた。
さやさやと鳴る梢の陰、街を見下ろす断崖の手摺のそばに、ふたつの人影がある。
1人は、マオカラーのワンピースに身を包んだ14、5歳の少女。
そしてもう1人、長い髪を三つ編みにした青年が、気配に気づいてアイ達の方を振り返る。
青年は――ユウは、あの日と変わらぬ穏やかな笑顔で2人を迎えた。
「…そうですか…」
一通り話を聞き終えたユウは、溜息混じりにそう呟いた。
初めて出逢った時より幾分大人びた少女を同じように愛しげに見守るユウに、アイは真摯な眼差しで問う。
「ユウ、ディーの言う通り、貴方は生きる事の意味を知っているの?」
「どうでしょう?」
ユウは、口許に手をやって考え込む素振りを見せた。
「俺にとっての生きる意味なら、とうの昔に決まってるんですけど」
だが、それはあくまで彼個人の価値観に基づくものであって、アイやケイに当てはまるものではない。
しばらくそうして黙り込んでいたユウは、切羽詰ったアイの様子に気圧されて重い口を開いた。
「…或いは、「J」ならその答えを知ってるかもしれません」
「「J」?」
鸚鵡返しにするアイに、ユウは重々しく首を縦に振る。
「『天使』シリーズの中でも、貴方とケイ、それから「J」は、『天使』の生みの親である博士自らが創り出した個体なんです。6枚羽根の熾天使も貴方達3体だけの筈ですし、組織の人間も把握していない何らかの秘密が隠されていても不思議じゃない」
「どうしてそんな事を?」
深刻な面持ちで話すユウに、アイが強い警戒を示す。
それを怯えと受け取ったユウは、幾分肩の力を抜いて口調を和らげた。
「堕天使の中には、優秀な元告知天使もいますから」
アイの脳裏に、かつて彼女が狩った同胞の名前が浮かぶ。
「…ヴィ?」
ユウは、それに答えないまま彼の意見を述べた。
「彼に訊けば、「J」について何か解るかもしれません。それから、行方不明になっている博士の事も」
「解ったわ」
ゆっくりと頷いて、アイが手摺に凭れかけていた身体を起こす。
「ありがとう、ユウ。ヴィに会いに行ってみる」
そう言って、少女の相手をしているケイの許へ向かいかけたアイの背中に、ユウが声をかけた。
「アイ」
肩越しに振り返ったアイに、ユウは慈愛に満ちた眼差しを向ける。
「貴方も、貴方を呪縛するものをみつけたんですね」
「…えぇ」
ユウの問いかけに力強く頷いて、アイは再び足を踏み出した。
|