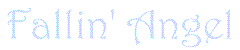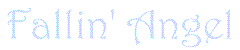※※※神様にも解けない魔法※※※
今にも泣き出しそうな空を見上げて、アイはひとつ溜息を落とした。
「晴れたら良い天気」というのは勝手な言い分だと思うけれど、やっぱり雨は好きになれない。体が重くなるような気がするし、第一お気に入りの服が汚れてしまう。
交差点で立ち止まって、ショーウィンドウに自分の姿を映して見る。
真っ白いふわふわのコートに身を包み、透き通った蜂蜜色の瞳でこちらを見つめ返す小柄な少女。首を傾げると、腰まである明るい色の髪がさらさらと揺れる。整いすぎて、ともすれば冷たい印象を与えがちな顔立ちは、やや幼い印象を与える表情豊かな瞳と形の良い赤い唇の鮮やかさに彩られて生き生きと輝いて見えた。
「天使のような」という表現が相応しい愛らしい容貌に、アイは満足げに微笑む。
そして、信号が青に変わるのを待って、弾むような足取りで歩き出した。
折りしも今日は12月24日、街はクリスマス気分一色に染め上げられている。
風に乗って聞こえてくるクリスマスキャロル、立ち並ぶ店のディスプレイは赤と緑のイルミネーションでショーアップされ、街路樹は色とりどりのライトと銀糸の魔法でクリスマスツリーに早変わり。
通りを行き交う人達も何故だか妙に浮ついていて、地に足がついていない。
神を信じ聖なる夜を祝う習慣はなくても、純粋に祭りとして宗教行事を楽しんでしまえるこの街らしいひとときの夢に溢れる人の波を、アイは確かな目的を持ってすり抜けていく。
見せ掛けだけの幸福感や一夜限りのお伽噺なんかに惑わされている時間はない。
今夜こそ、彼に話し掛けるのだ。
その為に、しっかり準備もして来たんだし。
アイは、迫り来る夜の気配に歩みを少し速めた。
駅前の広場から延びる大きな通りのひとつ、緩やかな上り坂の途中に、高層ビルに埋もれるように教会が建っている。
けして小さくはないその建物は、それでも周りの景色と比べると肩身の狭い思いをしているように見える。
その教会の、道路を挿んで反対側の歩道が、彼の指定席だ。
彼は、毎日夕暮れの頃に現れて、大抵は黒いコートかジャケット姿でガードレールに腰掛けて、何をするわけでもなく、道行く人々や車の流れや、消えそうな星の瞬きを飽きる事なく眺めている。
今夜の彼の出で立ちは、スリムのブラックジーンズに黒のロングコート。髪も靴も真っ黒だから、遠くから見るとそこだけ人の形に闇を切り抜いてきたみたいだ。
ただでさえ人目につきやすい綺麗な顔をした青年が黒ずくめで佇むその姿は、華やいだ街の景色には馴染まない。それが、誰かと待ち合わせというのでもなく、何時間もひとりでいれば尚更だ。
今だって、会社帰りらしい女の子のふたり連れが、彼の方を盗み見ながら何やらはしゃいだ声を上げている。
でも、当の本人は、そんな事はちっとも気にしていなかった。
今夜彼の気を惹いているのは通りの向こう側の教会らしい。
特別なこの夜にも、華やかな街並みとは対照的に、教会の前には派手な飾りつけもツリーもない。ただ、ミサの開催を告げる案内板が出され、いつもは重く閉ざされている扉が祈りを捧げに訪れる者の為に開かれているだけだ。
そうして穏やかに生誕祭の夜を迎える教会の神聖さと、その様子を眺めている青年とは、どことなく似ているような気がする。
通りがかりの人にふと興味を持たせるところと、無防備に其処に在るのに近寄り難い気分にさせるところ。
別に攻撃的に構えているわけではないのだけれど、何となく触れてはいけないもののようで、それぞれの想いを胸に遠巻きにするしかできないところ。
それから、見ているだけで満たされたように感じて、それ以上の望みは欲張りな事だと思わせてしまうところ。
実は、アイ自身もここ数日毎日此処に来て彼の姿を眺めていながら、声もかけられずにいたのだ。
だけど、今日は違う。今夜は特別なのだから…。
どきどきするのは、多分、早足で歩いてきた所為ばかりじゃないだろう。
目を閉じて、小さな胸に手を当てて、弾む呼吸を整える。
そうして思い切りをつけて、アイは足を踏み出した。
「こんばんは」
雑踏に声を消されないように、手の届く距離まで近づいて話しかけたアイを、青年が振り返る。
少し長めの前髪越しに何か不思議なものを眺めるように見つめ返す瞳は、真夜中の湖の色。どこまでも深く澄んでいて、吸い込まれてしまいそうだ。
これまでにも、こんな風に声をかけてきた誰かを不思議そうに見つめたりしたのだろうか。
ぼんやりとそんな事を考えながら、アイはできるだけ自然な態度を装って青年に問いかけた。
「いつも此処にいるけど、何してるの?」
「人を待ってるんだ」
特に身構えるでもない無防備な笑顔で、青年が応える。
それにつられるように、アイもにっこりと微笑んだ。
「奇遇ね。私は、人を捜してるの」
でも、やっと見つけられたみたい。
そう言って、アイは悪戯っぽく首を傾げる。
「ねぇ、名前、訊いても良い?」
青年は、それに対してなんの躊躇いも無く答えた。
「僕の名前はケイ。君は?」
問い返されたアイもまた、迷わず応えを返す。
「私は、アイっていうの」
それを聞いて、ケイと名乗った青年が一瞬目を瞠った。
「あぁ、それじゃ…」
それから、まるで蕾が綻ぶようにうっとりと破顔する。
「君が僕に遣わされた告死天使なんだね」
刹那、アイの顔から明るい笑みが消え去った。
道路の向こう側で、ミサの開始時間を迎えた教会の扉が静かに閉ざされる。
ふたりの間を、冷たい風が通り過ぎた。
+ + +
この世界には、『天使』と呼ばれる者が存在する。
人の形をした人でない者である彼等は、お伽噺のように天に仕える生き物ではなく、軍事利用を目的に神ならぬ人の手によって生み出された有機物と機械との融合体――異形の生命だった。
作られたのは、全部で26体。アルファベットに准えた名前をつけられた彼等の身体には、お互いの間でのみ識別可能な信号が組み込まれている。
『天使』の名に相応しく翼を象ったそれは能力値に応じてプロトタイプの片翼から最高レベルの6枚羽根まで段階別に分かれていた。
更に、基本的な戦闘能力以外に個体毎に専門分野が設定されており、それぞれコードネームが与えられている。
情報戦を得意とする《告知天使》、要人警護向きの《守護天使》、暗殺者仕様の《死天使》――。
そして、《死天使》の中でも組織に背いた《堕天使》を狩る為に生まれたのが《告死天使》だった。
+ + +
「…気がついていたの?」
俯いたまま小さく尋ねるアイの髪を、凍てつくような風が弄る。
その額に浮かぶのは3対6枚の翼。
「知っていたよ」
ケイは、穏やかな眼差しをアイに向けて口を開いた。
彼の手の甲にも、3対の羽根が描かれている。
「だって、僕はずっと君を待っていたんだから」
「私に狩られるのを待っていたの!?」
自分でも理解できない激情に駆られて顔を上げたアイが目にしたのは、慈愛に満ちたケイの微笑だった。
時計は午後9時を廻り、閉店する店が増えるに連れて人の波もかなり疎らになってきている。
喧騒が遠のく中で、静謐な強さを湛えたケイの声が淡々と語り始めた。
「僕達『天使』シリーズは最初から軍事用に開発されたわけじゃない。その証拠に、僕達は個々の自我や感情を持っている。もっとも、研究グループが僕達の能力に目をつけた某企業体の傘下に収められてからは、兵器に心は必要ないという理由で情動を押さえるよう制限が施されるようになったけれどね。彼等が求めたのは、それこそ神に忠誠を誓う天使みたいに疑う事を知らない戦闘人形なんだ」
ケイが告げる言葉は冷酷な現実。
それなのに、どうして彼はこんなにも凪いだ心でいられるのだろう。
「でも、研究者の中にはそれを快く思わない者もいた。彼は、僕達に魔法をかけた。いつか僕達が僕達自身の為に生きられる時が来るように…」
どこか怯えた表情で立ち尽くすアイに、ケイは柔らかく微笑みかける。
「僕達は恋に堕ちる。激しく深く――誰かを愛しく想って、僕達は初めて大切なものを知る。そうして目覚めた僕達は、もう何も知らずにいた『天使』には戻れない。誰にも止められないこの想いこそ、僕達にかけられた魔法なんだ」
指先まで整った綺麗な手を胸に当ててそう語るケイは、何故だかとても幸せそうに見えた。
「そんな事…」
そんなケイの言葉を拒むように、アイはゆるゆると首を横に振る。
昂ぶる感情のまま、アイは悲鳴にも似た声で叫んだ。
「そんな事、私は知らない!私は、何人も同胞を狩ってきた。あなた達を狩る為に存在しているのよ!」
「でも、今君は躊躇っている。何かがおかしいと感じ始めている」
「違う!違う違うっ!」
揺れる思いを認めるのが怖くて、アイは何度も何度も頭を振る。
その耳元で、不意に何者かがアイに呼びかけた。
『I、何をしている?目標と接触したのか?』
イアリング型の通信機から聞こえる声は、アイに任務の遂行を促す。
『騒ぎになるとまずい。目標と接触したのなら直ちに捕縛しろ』
どうすれば良いのか解らずに硬直するアイに、ケイは手を差し伸べた。
「一緒に行こう。僕は、ずっと捜していたんだ。僕が護るべき魂の半身を…アイ、君の事を」
一方、通信機から聞こえる声は異常を察して彼女を急かす。
『I?聞いているのか?応答しろI!』
「さぁ」
「…だめよ」
アイは、途方に暮れた瞳をして呟いた。
「私は行けない。この手で何人もの仲間を狩ったのよ」
「それは君の罪じゃない」
応えるケイの声は優しく毅い。
「過ちは償う事ができる」
「逃げ切れる筈がないわ!」
「大丈夫だよ」
泣き出しそうに顔を歪めるアイに頷いてみせたケイの手の甲で、6枚の羽根が淡い燐光を放った。
「僕は君の守護天使なんだから」
彼の言葉を証明するように、通信機の音声に乱れが生じる。
『…I?ど…した?…イ、何が…』
「約束するよ。僕がアイを護る。だから、何も怖がらなくて良い」
大きく見開かれたアイの瞳から、涙が一粒零れ落ちた。
ケイの冷たい指が、震えるアイの頬を包む。
「僕達が生まれた意味をふたりで捜しに行こう」
カツンと乾いた音をたてて、アスファルトの歩道にアイのイアリングが落ちた。
冷え切った夜の空気に、澄んだ鐘の音が響く。
小さなリースに飾られた教会の扉が開き、ミサを終えた人々が満ち足りた笑みを浮かべて通りへと出て来た。
彼等は、或いは家族や友人と連れ立ち、或いはひとりで、思い思いの方向へと去っていく。
その中に、手を繋いで歩くアイとケイの姿があった。
びゅうっと一際強く風が吹いて、乱れた髪を押さえたアイがふと空を見上げる。
その視界を、ちらちらと白い物が過ぎった。
「雪!」
風に運ばれて来た雪の華は、地面に触れるまもなく儚く溶けて消えてしまう。
それでも、特別なこの夜を祝福するように、白い雪はひらひらと舞い続けた。
|