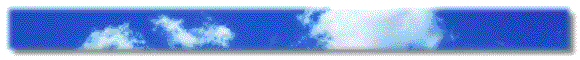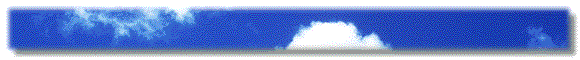
人工内耳友の会−東海−
|
難聴、新生児期に発見を 平成12年1月23日(日)岐阜新聞 「新検査法が実用化」 赤ちゃんの難聴を誕生直後に発見し、6ヶ月ごろから補聴器をつけるなど早く療育を始めれば、言語機能は発達する。難聴児の早期発見はこれまで難しかったが、状況は変わった。新生児の聴覚を聴性脳幹反応で簡単に検査できる装置が米国で開発されたからだ。日本にも普及しつつあり、厚生省研究所が検診と療育法の確立に取り組んでいる。 「早期療育なら言語習得可能」 研究班の中心になっている小児科医の三科潤・東京女子医大助教授は「放っておけばしゃべれない難聴の赤ちゃんは千人に一人か二人。早期発見が重要。新生児期の検査が望ましい」。 「パソコンで判定」 新生児用聴力検査装置が実用化され、欧米の一部では新生児全員に検査(スクリーニング)が実施されている。自動聴性脳幹反応や耳音響放射を測る装置だ。 東京女子医大病院で検査の様子を見た。赤ちゃんの耳にカバーを当て35デシベルのやわらかな音を聞かせる。額とうなじ、肩に電極を張り、脳幹が発する脳波を測定する。 パソコンが正常児の脳波と比べ、正常か検査し直す必要があるか、平均5分で判定する。この間、赤ちゃんはすやすやと眠ったまま。 特別な遮音室でなく、通常の病室で検査できるのもスクリーニングに向いている。この装置は国内で約200台普及している。2回検査して聴覚障害の疑いがあれば、本格的な聴性脳幹反応などで確定診断する。 「3歳では遅い」 研究班は、首都圏、名古屋、関西の19病院で、親の同意を得て新生児の聴覚を検査している。1998年から3000人に実施し、5人の難聴児を見つけた。検査の意義を確認するため、1万人まで症例数を増やして、追跡調査する方針だ。 日本では現在、3歳児健診で難聴を調べているが、方法がばらばら。しかも2、3歳時に気づいてケアしても言語の習得が難しい。 難聴児の療育に長年取り組んできた耳鼻科医の田中美郷・帝京大教授は「言語活動は2歳ごろからだが、聴覚は初期からある。できるだけ早く難聴を発見し、補聴器をつけて聴能訓練をすれば、言語発達の遅れは防げる」と話す。 「子供が難聴」と診断されると、親は不安に陥ってしまう。「いろんな音を聞かせるなど、早くから適切に対応すれば、言語を習得できる。親を励ますことが大事だ」と田中教授。 「将来は全員に」 厚生省は2000年度の予算案で新生児聴覚検査モデル事業として4600万円を充てた。今年10月から年間約5万人の新生児を対象に検査を始め、将来は全国で実施したい意向だ。 こうした聴覚検査は欧米で急速に広がっている。ただ、年間の出産が千以上の大規模な産婦人科病院が多い米国に比べ、日本は年出産数百−四百が大半で、新生児期に検査しにくい。検査費も約七千円と高い。一歳未満の難聴児をケアできる専門家が少ないなど課題は山積している。 そのためにも「産科と小児科、耳鼻科の医師がもっと連携する必要がある」と三科助教授は提言する。 |
メールはこちらへ |
各種情報メニューへ |