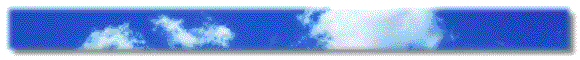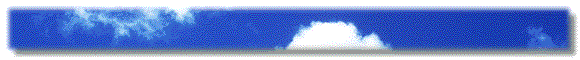
人工内耳友の会-東海-
|
NHK総合:おはよう日本 【よみがえる感覚】 平成13年2月15日(木) 【皆さまへ。】 こんにちは。☆宮下あけみ☆と申します。 akemizo@beige.ocn.ne.jp 2月15日(木) NHK総合(全国放送) 番組タイトル「おはよう日本」内、<7:49~8:57>の“約8分間”、【特集:よみがえる感覚】の【文字版】を作りました。 「聞こえてくる限りのもの」を「文字化」させていただきましたので、会話もそのままです。また、聞き取りにくい声や音は、自分に聞こえたまま、打たせていただきました。 また、「映像」と【文字版】を照らし合わせやすいように、この【文字版】の中には、「(番組表示時刻○:○○ 映像:番組司会者)」のように、カッコ書き( )で、「画面の状況」を入れさせていただきました。 この番組「特集:よみがえる感覚【文字版】」の、 ①FAX・M.L.・印刷等での、投稿・配信・配布。 ②ホームページへの掲載。 ③上映会等の開催(営利を目的としない。) =この際、【文字版】の「画面状況説明部分」や「句読点」を省く等、見やすいように【文字版】を加工しても良い。 これらのご了解を得ることが出来ました。 【著作権】は、【NHK名古屋】です。 聴覚障害者の方々がこの番組を視聴なさる時には、ご活用下さいませ。 この文字版は【NHK名古屋】より、私、宮下が個人的に了解を得たものです。 しかし、著作権を持つ【NHK名古屋】より、「字幕を付けたかったのですが、諸般の事情により、付ける事が出来ませんでした。今回、この様な形(M.L.・ホームページ及びFAX等)を通して、多くの方々に番組をご覧いただける事は、こちらとしても嬉しい事です。」と、お言葉をいただきました。 従って、この【文字版】の個人、団体等への【メール及びFAX、印刷での配信・配布】、【ホームページへの掲載】は「自由」です。自由ですが、もし、「団体あて」に転送、或いは「ホームページへ掲載」されたような事がございましたら、恐れ入りますが、宮下まで、ご一報下さいませ。 尚、今回のNHK総合【特集:よみがえる感覚】は、平成13年2月2日、NHK名古屋にて制作、東海・北陸7県で放送されました、【よみがえる人体機能~最前線の医療工学~」(25分間番組)】のダイジェスト版です。これにつきましても【文字版】を作成・配布しておりますので、あわせてご覧下さいませ。この【よみがえる人体機能】の【文字版】は、「人工内耳友の会:東海」のホームページ http://www2u.biglobe.ne.jp/~momo1/ に掲載されております。今後とも、宜しくお願い申し上げます。 <文字版作成>☆宮下あけみ☆ 【E-mall】akemizo@beige.ocn.ne.jp 【FAX】048-774-8387 NHK総合:おはよう日本 【よみがえる感覚】 平成13年2月15日(木) (7:49 映像:番組司会者) 司会:特集です。「事故とか病気で失われてしまった人の感覚をよみがえらせよう。」という、取り組みについてです。名古屋放送局の茶園(ちゃぞの)ディレクターが取材しました。よろしくお願いします。 茶園昌弘(NHK名古屋):おはようございます。 司会:あの…、人のですねぇ、耳とか目というのは、とってもこう、複雑なものだと思うんですけれども、感覚をよみがえらせる事ができるんですか? 茶園:えぇ、そうなんです。あの、例えば耳の感覚、「聴覚」なんですけれども、補聴器を使ってもですね、音が聞こえない重い聴覚障害の方というのは、日本にはおよそ17万人いらっしゃいます。こうした方々の耳の障害というのはですね、これまで医学の力だけでは治療が難しかったんですが、あの、テクノロジーの進歩でですね、音を取り戻すことがですね、可能になってきました。 (7:50 映像:東京 港区 虎ノ門病院) ナレーター(=以下、「ナ」と記す。):東京の虎ノ門病院では、聴覚に重い障害がある人だけを診察する外来が設けられています。 (映像:待合室で話しをしている女性、2名) ナ:去年、聴力を失った、児玉房子(ふさこ)さんです。月に一度、この外来に通っています。 (7:51 映像:耳から脳への断面図) ナ:耳に入ってきた音は、鼓膜を振動させます。鼓膜の奥にある蝸牛(かぎゅう)と呼ばれる器官は、この振動を弱い電気に変えます。この電気が脳に伝わり、人は音を感じます。 ところが、病気などで蝸牛が機能を失うと、鼓膜の振動を電気に変えることができません。児玉さんは中耳炎が悪化し、蝸牛の機能を失ってしまいました。そこで児玉さんは去年の11月、「人工内耳」の埋め込み手術を受けました。 (映像:診察室→断面図) ナ:「人工内耳」は、2年前から急速に性能が上がってきた医療機具です。「人工内耳のしくみ」です。「耳にかけたマイク」と、「頭に埋め込まれた集積回路(しゅうせきかいろ)」、そして「聴神経につながる電気ケーブル」で構成されます。耳にかけたマイクは音を電気に変えます。電気は、機能を失った蝸牛の先にある聴神経へ、直接伝えられます。この「人工内耳」で、児玉さんは音を取り戻しました。 (7:52 映像:児玉さん) 児玉房子さん:やぁ~、もう、スゴイも凄いも、いいところだと思います。大感謝です。これほど聞こえると思いませんでした。現に、こう、お話できるんですものね。全く聞こえなかったんですよ。それが、この機械があることによって、普通の会話でしたら不自由ないです。 ナ:人工内耳を通して聞こえる音は、コンピュータの急激な進歩にともなって、より自然な音に近づいています。児玉さん達に聞こえている音を、コンピュータで再現しました。 「再現した音」:「このテープを皆様がお聞きになる頃には、日本では、桜の花が咲き始める頃かと思います。」(※宮下→しわがれたような声。言葉の1つ1つは、はっきり聞こえる。男性の声。) ナ:最新式の人工内耳は、コンピュータで音を調整して、つけた人が一番心地よく感じる音を作り出すことが出来ます。 機械の音:プー、ピー…。(※宮下→7つの、違う高さの機械音。) ナ:児玉さんは月に一度、専門の技師に、人工内耳の調整をしてもらいます。 調整中の音:あー、いー、うー、えー、おー。(※宮下→男性の声。次のナレーションと音声が重なる。) ナ:高い音から低い音まで、聴神経に送り出す電気の強さを微妙にかえて、音を聞き取りやすくしています。 調整中の音:あー、いー。 虎ノ門病院耳鼻咽喉科 医長 熊川孝三さん:今まで外科的に、そういう高度の難聴の方を治す手立てというものを、僕らは持っていなかったわけですが、「人工内耳」の出現によって、はじめてそれが可能になったわけですね。 (7:53 映像:スタジオ) 司会:はぁ。この「人工内耳」で、どれくらいの人が救われてるのですか? 茶園:はい。えーと、これまで、この「人工内耳」によってですね、世界ではおよそ3万人、日本でも1,900人以上の方がですね、音を取り戻しているんです。 司会:はぁー。 茶園:それに、「外出して人と会うのが怖かった。」という方々もですね、あの、積極的に出かけられるようになってですね、世界が広がったという声を、多く聞きました。 司会:「聴覚」以外の分野でも、こういう取り組み、行われてるんですか? 茶園:はい。え、ありまして、より複雑な機能を持った、「目」の感覚、「視覚」ですね。 司会:はい。 茶園:に、ついてもですね、今、研究が世界中で進められています。で、あの、こちらの映像(英字の映し出されたスクリーン)なんですけれども、こちらにあるのは、全く目の見えない人がですね、これだけの映像を見る事ができるようになるという、一つの例なんですけれども。 司会:文字が見えるようになるのですか? 茶園:えぇ。この研究の最前線というのを取材しました。 (7:54 映像:英字画面) 男性の声:エヴリ デイ イン … ナ:これは名古屋大学ですすめられている実験です。「市販の小型カメラがとらえた文字を、そのまま脳に伝えよう。」という挑戦です。取り組んでいるのは、医学ではなく電子工学の研究者たちです。代表の八木透(やぎ とおる)さんは、ロボットの目の技術を役立てようと、この研究をはじめました。 (映像:目から脳への断面図) ナ:人の「目」のしくみです。映像は角膜(かくまく)と水晶体(すいしょうたい)を通して網膜(もうまく)に映されます。網膜はその映像を電気に変えます。この電気が視神経を通じて脳に伝えられ、人は映像を感じる事ができます。 角膜や水晶体は傷ついても、移植などの治療が可能です。じかし、事故や病気などで網膜が機能しなくなった場合、これまで治す方法はありませんでした。 名古屋大学工学研究科 助手 八木透さん:失明の治療法っていうものが、あの、全くない状況です。で、失明しないように、或いは、失明を遅らせるような治療っていうのは、あるらしいんですけれども、まだまだ、根本的な解決には、まだ、至っていない。 (映像:実験室→目から脳への断面図) ナ:八木さん達は今、この問題を解決するため、今、半導体で網膜を作ろうとしています。八木さん達が研究、開発している失明の治療法です。傷ついた網膜にかわって、目の中に半導体を埋め込みます。そこに、カメラが捕らえた映像が送り込まれます。半導体は送られてきた映像を電気に変えます。電気は半導体と繋がれた視神経に伝えられます。その電気が脳に伝わり、映像を感じるしくみです。 実験室では半導体と、人の視神経をつなぐ研究が進められています。半導体の上に神経細胞を培養します。これは、半導体の上で培養された神経細胞の写真です。神経細胞が視神経と半導体を結ぶ、“つなぎ目”の役割を果たします。 八木:視覚障害の方の集まりとか出たりする時にですね、「何とかならないか?」という事を言われるわけですね。叶えてあげるためにも実現をですね、一刻も早くしたなぁ…と考えております。 (7:57 映像:スタジオ) 司会:あの…、「目の感覚」を取り戻す研究、実用化はいつ頃なんですか? 茶園:はい。あの、日常生活に支障がないほど見えるようになるにはですね、やはり20年ぐらいの時間が必要になると言われています。 司会:あぁー、そうですか。でも、やっぱり、あの、「医学の進歩」っていうのは急速なんですね。 茶園:えぇ、そうですね。この5年程の間にですね、コンピュータの情報処理速度というのが劇的に速くなっています。そしてまた、医療機器というのがですね、人の体の中に埋め込むことができるほど、小型化してまして、また、埋め込んでも安全な材料というのが開発されています。 で、まぁ、今後もですね、こうした「テクノロジーと医学の融合」というのが、ますます進んでいくんではないかと思います。 司会:はい。「最新のテクノロジーで、人の感覚を取り戻そう。」という試み。茶園ディレクターの報告でした。 以上 【文字版制作】☆宮下あけみ☆ 【E-mail】akemizo@beige.ocn.ne.jp 【FAX】048-774-8387 |
メールはこちらへ |
各種情報メニューへ |