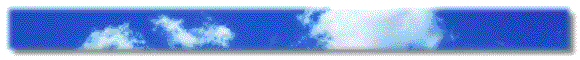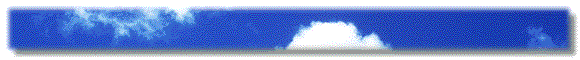
人工内耳友の会−東海−
|
平成17年2月27日(日)
愛知県産業貿易会館西館9階第2会議室 人工内耳友の会−東海−総会兼懇談会 難聴者の聴覚補償と情報保障 国立大学法人筑波技術短期大学 学長 大 沼 直 紀 皆さん、こんにちは。人工内耳友の会東海は勉強熱心な会と前から聞いていましたので、今日はどれくらいお役に立てるか自信がありませんが、お呼び頂いて、ありがたいと思っています。難聴者の情報保障という話を中心にお話ししたいと思います。 最初のスライドは、「みる」という漢字と「きく」がどのくらいあるかです。「みる」は178。「きく」は13。これが難聴を一般の人に理解してもらうときの困難さを反映している数の比率だと思います。 「みる」という漢字は見学の「見」と書きます。これは「なんとなく見る」という漢字です。「なんとなく見る」という漢字から、だんだん漢字が増えていって、我々がよく見る、視聴覚の視、これは「注意してみる」という意味です。「注意してみる」ということに近い漢字がたくさんあるのですが、さらにもっと「監督」、野球の監督をするときの「みる」という漢字、これはすごく詳しく奥底まで見ないと、判断を誤ります。我々がよく使う観察の「観」、この「みる」は意味が深い。目の前で見えてないものも見ることができるという、「心でみる」という漢字です。なんとなく目に入る「みる」と比べると、大変高度な見方をすることになります。 こういった「みる」という漢字を集めると187もあるということは、どういうことかというと、人間は誰でも「みる」ということに関して、そうとう関心が深いということです。ですから、いろいろな種類の漢字が作られました。漢字の数の多さがその国民がどれだけそのことに関心が深いかを表わすバロメーターになります。 この「みる」ということに対して「きく」はたった13。この差は何か?聞くことが当たり前のことで、誰もが聞こえなくなるなどと考えない。自分の耳が聞こえなくなったり、家族に聞こえない人がいる、そういうときに初めて「きく」ことに関心が持てる。だから漢字の数も少ないと思うのです。 小さい子は「もし自分の目が見えなくなったらどうするのだろう」と、心を悩ませるものです。皆さんも小さいときに「もし自分の目がみえなくなったら」と恐れ、怖がった経験があったと思います。人間は「目が見えなくなったらどうしよう」と、比較的簡単に想像できるし、怖さを感じられますから、それだけ身近です。身に近い障害です。 目の見えない人に対する情報保障や視覚補償は比較的受けやすいです。それに比べて、耳が聞こえないことに対しての聴覚補償はなかなか説明しても、一般にわかってもらえない、そういう差が出てきます。 「何となくきく」とは新聞の「聞」を書きますが、さらに「ちらっときく」という漢字、あるいは「注意してきく」聴覚の「聴」、耳へんに制服の制と書く「きく」もあります。これなんかは、そうとうじっくり「深くきく」意味です。しかし、上の「心できく」という漢字は作られていないのです。 例えば、対話していると、ものすごくやさしそうで話し相手になってくれているから、すごくわたしに同情的で親切だろうなと思ってると、実は心の中ではそうでもなかったり。 逆に厳しい顔の上司が、その顔を見ただけでは怒っていて嫌っているとしか見えないのに、心では自分を心配して、思いやってくれている。それがみえるかどうか。これが観察の「観」、「こころでみる」ことです。 この「心できく」という漢字はないのですが、わたしは目の見えない人とも、ずいぶんつきあっていますが、目の見えない人は、心で聞いている人が多いなぁという印象を持ちます。あるいは、目の見えない人が見えないわけだから、見えないものは見えないだろうと思っていると、見えない人にすごく自分の心が見透かされていることがある。全盲の人と向かい合っていると、「おや、この人は見えていないはずなのに、私は見透かされている」と思うほど、心を読み取ることができる盲人がずいぶんいます。 そう言う意味で、今日情報保障ということを話しますが、見える人と見えない人、聞こえる人と聞こえない人、視覚障害者と聴覚障害者その立場をそれぞれ考えてみると、耳の聞こえない人にとっての情報保障は何が大事なのかがもっとはっきりわかってくると思います。 わたしの大学は、二つのキャンパスがあって、目の見えない人たちだけが集まっているキャンパスと、耳の聞こえない方のキャンパス、併せて270人おります。それと、教職員が200人います。200人で270人の目や耳の聞こえない学生を教えている国立のただ一つの大学です。 実は目の見えない人の大学は、それだけで一つ作ったらいいのではとか、耳の聞こえない人の大学は、それだけで作った方がいいのではないか、そういう議論もあったのですが、いろんな事情で一緒の大学を作りました。そこでわたしは両方のキャンパスをまとめる学長としての、今仕事をしておりますが、目の見えない人を通して耳の聞こえない人を、もっと理解することができるようになった。目の見えない人をよく知ることは、耳の聞こえない人ももっと深く知ることになるだろうなとだんだんわかってきた。 聴覚障害者の方は、聞こえない障害はあったにしても、見えるわけです。よく見える目をもっている。見えるはずの青年が、意外と見えない障害になっている。あんなによく目が使えて手話が使えて、文字が読めて、目が働いている。気がきいて、ちょっとした目でいろんな情報をとる能力に長けているはずの聴覚障害の青年が意外と、「観」ができていない。「なんとなく見る」とか、「注意してみる」のは得意。しかし、目の前で見えていることしか信じられず、見えているものが全てと信じて、見えていないものを観ようとしない。そういう落とし穴があります。 盲の人は耳が不自由ではないからよく聞いているはずと思っても、意外と聞いていることだけが全てと思って、聞こえていないことを聞こうとしない。「目の見えない人が、耳を人一倍よく働かす」と言われます。「耳の聞こえない人は、かわりにものすごく目が発達する」と言われている。ほんとかな?と思うことがあります。そんなことを注意する時代に入ったのではないかと思い、最初にこの話をしました。 わたしの大学では、目の見えない学生が1年間に40人入学します。耳の聞こえない学生が50人入学してきます。併せて、90人、入学式を迎えます。同時に入学式をします。階段状になっている講堂で、右の方には、耳の聞こえない新入生が50人並びます。左側には目の見えない40人がいます。その後に、保護者が入って満杯になります。 そうやって入学式をしますが、そのときにわたしが、今から紹介します入学式の式辞を話すとき、大変緊張します。耳の聞こえない学生向きには、この仕事、わたし40年やっていますから、大丈夫、ちゃんと伝えられます。情報保障が自分でできます。自分で手話を使いながら、式辞を読み上げます。しかし左側の目の見えない40人の学生、あるいは、保護者にも目の見えない方がいます。そうなると目の見えない人向けにもっとクリアにしゃべって、目に入らない情報は、声に出してもっと詳しくいわないと伝わりません。 私がくどくど言葉でしゃべればしゃべるほど、聴覚障害の学生は「くどいな、手話で一発やればもうわかるのに、なんであんなくどくどしゃべるのだ」と思われます。聴覚障害と視覚障害は、うらはらの関係、距離の遠い障害。それを一緒に理解してもらうというのは、大変です。しかし、目の見えない人に通じさせる配慮を身につけた人は耳の聞こえない人への情報保障もものすごくよくできる。聞こえない人としかつきあわなかった40年間でしたが、目の見えない人と、おつきあい始めてわたしはいい勉強をしました。 大学はいつも閉鎖的だったが、これからは大学の経営は学長だけが、あるいは教授会だけがやるのではなく、外から人を呼ぶということで、わたしの大学も副学長クラスを2人外部から呼んできました。吉野先生という聴覚障害の研究で有名な人です。朝日新聞の論説委員で、福祉や医療のことで社説を書いていた大熊由紀子さん、この二人を迎え、ずいぶん大学内でも変わってきています。 聴覚障害や視覚障害者の世界は自分たちだけで事を運ぶのではなく、外の人がどんどん見てくれる世の中に代わってきています。人工内耳友の会でも、会員だけが親密に情報交換すればいいという時代から、外の人に人工内耳友の会をみてもらったり、加わってもらう、そういう形に変化していかないと、だんだん自分だけの世界で満足してしまうようなこともあり得ると思いますから、世の中どんどん外からの目を入れる必要がある。 入学式で90人の目の見えない学生と耳の聞こえない学生を前に、わたしはがんばってくださいという話をしました。これは、当たり前に聞こえますが、実は最近、障害者を持っている親御さんたちの主張の一つは、自分たち、障害者を持った家族や本人は、がんばる必要はないのだとこの頃強く言い始めています。障害者だからと言ってがんばらさせられる必要はない、がんばるなんてことは必要ない。がんばらないで生きていくべきだと堂々と言い始めた。これについて、私は大変疑問を持っています。 人間は聴覚障害児や視覚障害児を持っている親や本人だけが障害を持っているのではなく、誰でもがいつでも障害を大なり小なりもっていていて、その障害を克服することで、人間らしく進歩する。それをどうして初めから障害者はがんばる必要がないというのかと、大変私は不満です。 しかし、情緒障害などの非常に重いお子さんを育てていくとき、家族は全部滅亡するくらいに大変な実態があります。そのためにすべてが犠牲になり、家族全員がんばらないと、生きていけない。世の中に対してちゃんとその子をがんばって育てないと、外に出せないとか、ものすごいがんばり方をしています。初めから聴覚障害関係の親から「がんばる必要はない」といった話が出たのではなく、たぶん、聴覚障害以外の障害の親御さんから、障害を持っているからといって、がんばる必要がないという発言が出たと思います。それがこのごろよくわかるようになりました。 あれだけ大変な子育てをするとき、これがどうして自分だけががんばる必要があるのか?社会が変わっていかないといけないのに、どうして自分ががんばるのかというところにやっぱり行き着くと思います。ですから障害者だけががんばるのはやめよう。社会ががんばってほしいといいたくて、がんばれと言われたくないと考え始めたのだと思います。それがよくわかるようになりました。 ただ、例外は聴覚障害だと思います。がんばっただけのことがある障害だと思います。がんばらない方がいいといったら、終わりです。ですから、入学式には「がんばるなという風潮にだまされてはいけない。君たちはがんばるために入ってきたんだ。日本で唯一の国立の障害者のための大学に入ったのは、キャンパスで楽にすごしていい暮らしをするために、税金を使わせてもらうのではなく、君たちならがんばらせがいがある。君たちががんばったら、きっと世の中が変わるという一人に選ばれたんだから、必死にがんばって勉強してほしい」、そういう話を入学式にしました。 そこで、昔の人はよくがんばったぞといっても、年寄りの戯言になりそうなので、わたしは入学式で時間をとって、ヘレンケラーとサリバンとベルの話をしました。 視覚障害者にとってもヘレンケラーは身近なあこがれの先輩ですから知っています。聴覚障害者も知っています。しかし、電話のグラハムベルが、なんでヘレンケラーやサリバンとつながっているのか?特に視覚障害の方やお子さんは、グラハムベルとヘレンケラーがつながりがあるとは夢にも思っていません。マスコミの人も「え?ベル?グラハムベル?どうして?」という顔でした。そこで、わたしはこの写真を見せて始めました。 グラハムベル46歳ぐらいですか。それから、ヘレンケラー、サリバン先生。もう大きく育って、結構、よく落ち着いてしゃべれるころです。3人の写真が残っています。ベルとヘレンケラーは指を動かしながら、指文字をさわり合ってコミュニケーションしています。手話を使ったりもしている。今、盲ろう者が使っている指点字も使っている。 ヘレンケラーとサリバン先生はヘレンの人差し指と中指と親指が、鼻と唇とのどにあたっている。そして、サリバン先生がしゃべっているときの口の動きや、のどの動き、唇の形の変化で話を読み取っています。こういう方法を昔使った。もちろんベルとサリバン先生は、目と耳と口でつながってコミュニケーションをとっています。140年ぐらい前にこんな風にコミュニケーションをとっていた3人がいたわけです。 これは、ベルが26歳の時、聾学校の先生の時の写真です。ボストン聾学校というところで、発音指導を教えていた頃のベルです。電話の発明もこの頃です。彼の教え子はたくさんいて、当時は耳が聞こえない人はしゃべれないと思われていた時代に、よく話をできる子を育てたのもグラハムベルです。16歳の時から、聾学校の教師をしていました。 これ、ベルのお母さんの写真です。聾者だった。しかし、補聴器なんて考えもしなかった時代に、すでに伝声管というラッパのついた長い管の補聴器で耳を補償していました。聴覚補償を自分でやっていた。ピアノも上手に弾けたお母さんです。当時、耳が聞こえなくなると社会から抹殺されるような大変な障害だった。耳が聞こえない=ことばができない=宗教の対象にならない。それくらいに耳が聞こえないのは、精薄者や狂人と同じ扱いを受けた時代に社交界にも入り、補聴器をつけピアノも弾いたという大変進んだ聴覚障害のお母さんをベルは持っていた。 ベルは自分の発音指導でいろいろお子さんを育てました。教え子の一人だった聴覚障害のメーベルの小さいときの写真です。このメーベルさんが後にベルの妻になります。 これはサリバン先生とヘレンケラーが7歳の最初の頃の出会いの写真です。サリバン先生が一生懸命言葉を教えている頃の写真です。ヘレンケラー家は大変お金持ちだったが、ヘレンケラーのお父さんが、ベルがアメリカで一番聴覚障害の教育で優れていたので、ベルに指導をお願いしようと最初依頼したのですが、そのときは電話を発明し、ベル電話会社を作って大金持ちになっていましたから、ヘレンケラーのためだけに指導するわけにいかない地位だったので、かわりにサリバン先生をパーキンス盲学校にお願いして、ヘレンケラー家に送り届けるのですが、それからこの教育が始まっていきました。 ベルとヘレンケラーとサリバン先生、ずーっと長くつきあい、ヘレンケラー自身は自分の自叙伝の中で、恩人のアレキサンダー・グラハム・ベルのことを次のように書いています。 「聴覚障害の人々には話すことを教え、耳の聞こえる人には大西洋からロッキー山脈まで話を聞くことを可能にした人、そのベルに私は生涯の物語を捧げる」という文章を書いています。あまりこのことは紹介されていません。このくらいベルとヘレンケラーのつながりは深かったのです。ベルは難聴者の教師として一生を貫いたのです。 補聴器の進歩の歴史を解説する表があります。電話が発明された1876年。これが補聴器のスタート。聴覚補償、情報保障のスタート。真空管、ICなど進歩するたびに補聴器が発達してきた。1980年以降、人工内耳の開発とデジタル補聴器にどんどん向かっていきました。 わたしが人工内耳と最初にふれたのは1980年だったのですが、CID中央ろう研究所というアメリカ最先端の聴覚の研究所に留学しました。地下室ではチンチラという動物が飼われていました。研究所の中で生まれて世の中のバイキンにふれさせず、その中で一生終えているチンチラがいっぱい飼われていました。チンチラの耳は聴覚の実験にやりやすい作りだったものですから、チンチラの耳をつかって人工内耳の埋め込みや電極の実験をやっていました。そのとき初めて人工内耳という言葉を聞いた。それ以来人工内耳と25年間つきあっています。 その当時は、これは実験段階であって、これが人間にできるなんて、わたしが生きている間、実現するはずはないと、ほんとに夢のようだと思っていました。それがまさに人工内耳をつけた人が、こんなに当たり前にいるなんて考えもしなかったです。それくらい科学の急激に予想を超えて、進歩しています。その源は、ベルが発明した電話でした。 グラハムベルは29歳の時に電話を発明しますが、それが全ての情報保障の原点になった。そして、耳の日も3月3日なのは、語呂合わせもありますし、3が耳の形に似ているとか、いろんな理由がありますが、3月3日がベルの誕生日というのも一つの理由です。音の単位をデシベルdBといいます。これももちろんベルの名を記念したのです。お父さんとお母さんの聴力検査をする機械を発明しました。もとはカチカチとボリュームを上げると正確に強さがかわっていく機械を発明しないと、聴力の測定ができないので、聴力測定器の原理を発明し、音には単位をつけるべきだということで、単位を作りました。それを記念してベルのBをつけたのです。 もちろん、グラハムベルは、聾学校の教師をしながら口を見ると発音も読み取りも正しくなるという指導方法を編み出しました。視話法です。ヘレンケラーのところにサリバン先生を自分の代わりに使わしたと先いいましたが、それも自分の誕生日のその日にヘレンケラーとサリバン先生が会う日を設定した。そういうことも逸話として残っています。いずれにしてもベルは、日本にも相当いろんな影響を与えた。そんな話を入学式にしました。 グラハムベルは耳の聞こえない人と目の見えない人に共通の先生だったのですね。 そして、わたしはさらに、話を続けたのは、せっかく目の見えない人とキャンパスで3年間一緒にくらすのだから、目の見えない人とのつきあいをしてくださいということでした。実は、17年にもなるんです、私たちの大学できてから・・。聴覚障害者と視覚障害者の交流はほとんどないのです。入学式と卒業式に初めてあってお別れするだけ。 聴覚障害の学生たちは、大学生活を満喫するだけでなく、聴覚障害者というのはなんて素晴らしいのだろう、聴覚障害者どうしで話をするとどうしてこんなに理解し合えるんだという喜び、その喜びと同時にもっと手話を広めたい、どうして自分たちの言語は手話だと主張してこなかったのか?という新しい運動に駆られていくのです。そして、他の障害どころじゃなくなる。聴覚障害者だけが世界で一番大変な障害であるとか、聴覚障害に誇りを持とう、それがアイデンティティだと言い始める。 そういうキャンパス生活ですから、目の見えない人にかまっておられない。それくらい余裕のない3年間を過ごします。しかし、自分と異なった障害をもつ友人がいるのだから、その人たちと友人になってみてはどうだ?という話をしました。 10年前にデザイン学科を卒業した、聴覚障害者の松森果林さんがいます。果林ちゃんは大学入学の前の年に、私の研究室を訪ね、この大学がもし自分に合うなら入学したいと言った。そしてわたしがこの大学は、こういう大学ですと説明しました。そのついでに、「でも、果林ちゃん、あなた将来なにになりたい?夢はなんなの?」と聞いたら「小説を書きたい。本を出版したい。」と言った。耳の聞こえない人が、言語で身を立てていくのはもっとも難しいと想っていたものですから、また夢みたいだなと思ったが、がんばりなさい、と言った。そして私の大学に入ってきました。一般の高校だったので手話を知らなかったのが、こんなに素晴らしい聴覚障害に通じるものがあると知って、本当にびっくりしたのと同時に、朝から晩まで聴覚障害のための運動をするような活動家になりました。 もちろん、ですから視覚障害者のほうには関心が向かなかった。聴覚障害者のことしか考えない3年を送り、東京の一流の印刷会社に就職しました。しかし、就職先で変化が起きました。目の見えない障害者と友だちになって、その人と大変仲良しになったのです。 話を戻します。松森果林ちゃんから、ある日私に宅急便が届いて、その中に本が入っていました。この本です。 「聴力を失って知った新たな世界」という副題で「星の音が聞こえますか」といういい本でした。中身も読み応えがあります。 本の中には手紙が入っていました。「最初にあった日のことを覚えていますか?将来何になりたい?夢は?と聞かれて、私の夢は本を書きたいと言いました。わたしの夢が実現しました。」とあった。なるほど、夢は実現するのだなあ。 その後、また別の本が送られてきました。 「ゆうことカリンのバリアフリーコミュニケーション」というこの本です。 芳賀優子さんという目の不自由な人と、聴覚障害者のかりんちゃんとの共著です。 聴覚障害者と視覚障害者の間のコミュニケーションを考える青年が少なからず出てきたのです。 このユニバーサルデザインという概念、バリアフリーを飛び越してユニバーサルデザインという概念で聴覚障害者が活躍できるはずです。自分の障害に対して情報保障してくれ、手話通訳をつけてくれ、ノートテイカーをつけないのが悪いという人間じゃなくて、自分がバリアフリー、ユニバーサルデザインに向かっていく、そういう人間になってほしい。 障害に甘えちゃ行けないという話をしました。自分たちだけの利益追求に走り、周りがみえなくなる。それが進むと障害者のアイデンティティにめざめるだけじゃなくて、自分の障害を盾にとってしまうことがある。思いやりが持てなくなる。このことを注意しなさいという話をしました。 思いやりをなくしたら人間として障害があろうとなかろうとだめです。そういった話をして、障害に甘えてはいけないどころか、障害を盾にとって問題をすり替える人間になってほしくない。君たちはそんな学生にはならないはずという話をしました。 この年は約800人の聴覚障害者の赤ちゃんが生まれています。今日もどこかの病院で2人ほど生まれています。うちひしがれて、自殺しかねないほどショックをうけている親御さんが今日もいるはずだ・・そういう人たちがもう一度がんばれると想うのは、ここに君たちがモデルとしているからなのです。 一人一人のこれからの生き方に、親御さんたちは期待しているのだといいました。 「聴覚障害の子どもが育つには補聴器をつけない方がいい。人工内耳なんてとんでもない。補聴器をつけない教育、声を出させない教育をしてほしい」という運動を起こしている人々がいます。 「耳を使うことが悪いのだ、耳が聞こえない人に発音訓練をすることが悪いのだ、これをやめさせないことにはいけない」というのです。 「耳が聞こえない赤ちゃんが、補聴器をつけたってだめだ。人工内耳なんてとんでもない。ろう児はろう児なのだ。それより手話でろうであることを誇りに思って、聾の手話を第一言語にして、日本中を手話でとりまく社会を作る。」なんてことを、聴覚障害を宣告された子どものお母さんが動揺しているときに、そういうガイダンスをされたのでは大変な犠牲者が出ると思う。 空気中に生まれた生物としての人間、われわれは音の刺激にふれ、恩恵に浴する権利があるということです。 今まで誤解をよんだのは、耳を使う、補聴器を使う方がいいとか、人工内耳を早くした方がいいという説明、理由付けに、耳を使えばぺらぺらしゃべれるし、電話もできるようなるから。だから、人工内耳を使いなさい、補聴器をつかいなさいと説明してきた。これはもう通用しない。 耳が開いているだけで、音声の聞き分けはむずかしくとも、音が聞こえるだけで、人間は安定して感性が豊かになる。このことを丁寧に今まで説明していなかった。耳が聞こえると言葉がしゃべれる。電話がとれる・・だからだと。しかし、これは聴覚の役割のほんの一部です。 聴覚を補償するということは、「音」を補償すること。「音声」を補償するのはその後でいい、そういう考え方です。 例えば、地下鉄のプラットフォームに立って、電車が入ってくるのを耳を全く閉じた人が立っていたとしたら、目の右のはじに電車がちらっと入ったときに、初めて電車が存在して、目の左から電車が抜けたとたん、電車が存在しなくなる、そういう感覚で生きるのです。 ところが我々は聴覚が開いていると、電車が目の前に来る前から電車を予測できて、「今日はこんでいるのかな」とか「どうしようか・・一本まとうか?」とかいろんな感慨がわく。電車が走り去った後も「5分たったら、隣の駅に着くのだろうな・・」とか、「次の電車でも間に合うかな」とか、いろんなことが広がる。 それが聴覚の感性を閉じると、目だけの世界で、狭いものになります。音は補償できるように150ヘルツ200ヘルツには、人工内耳しかないと言われた人でも残存聴力は残っている。それは何のためかというと、音が補償できるからです。言葉が入らなくても、音が入るのです。音が入ることに原点を求めるべきです。 これからの世の中は、情報保障の環境がどんどん進んでいきます。情報保障の場合は「保障」と書きます。聴覚補償の場合は「補償」と書いて、私は使い分けています。失った聴覚を人工内耳や補聴器で補ったり償ったりすることは「聴覚補償」です。また、手話を覚えて、聴覚の補いをすることも聴覚補償の一つです。英語の聞き分けがなかなかできないから、ヒヤリングで訓練する。これも補償です。自分の難聴を自らの力で補っていく、新しい能力を身につけていく、これが聴覚補償です。「情報保障」というのは、どちらかというと、自分だけの努力で情報の欠如を埋めようとするのではなく、周囲が聴覚補償をしようとしている聴覚障害者に対して、情報が伝わるように配慮すること、その環境つくりのことを指します。 本人はなんら聴覚補償の努力をせずに、ただ周囲の人々からの情報保障だけを求めるのでは、うまくいきません。また逆に、人工内耳をつけて聴覚補償ができたからといって、周囲からの情報保障の申し出を受け付けないというのであってはいけない。 デジタル補聴器が世の中に出たときも誤解が多かったように、人工内耳に対する誤解も未だ多いのです。意図的な誤解もあれば、無知な誤解、いろいろあります。これを解消していく活動もどんどんやらないと、人工内耳装用者が自らの情報保障が受けにくくなります。人工内耳がどんな人に適応するのかについての誤解も解かなければなりません。軽い難聴や高齢者難聴にも有効だと思っている人が少なくありません。ニーズとシーズのミスマッチが起きないようしないと、人工内耳の価値をかえって低める結果となります。特に最重度な聴覚障害児にとっては、これまでの補聴器に比べて人工内耳から良質の音、音環境が補償されることのメリットが理解されるべきです。言葉ではなく音の環境をまず補償する。次に音声も期待通りに補償されるかどうかは本人の資質や努力、情報保障の環境次第です。 人工内耳をつけても期待したほどに言葉の聞こえが改善されないような人について、あの人は失敗だ、電話もできない…と言うのはあたっていません。失敗ではない。人工内耳のおかげで日常の生活環境からの音がこれまで以上に入力される。音の補償ができているということは大変な人工内耳の効果です。せっかく人工内耳の手術を受けたのに、まだ手話を使っているから、人工内耳の効果はないというのもあたっていません。聾者=手話という図式が塗り替えられようとしています。新しい聾の青年「人工内耳をつけて手話を使うろう者」も生まれつつあるのです。 筑波技術短期大学の学生たちはの聴力は、100デシベル以上の重度な学生が中心です。彼らは今、「音を感じる世界と言葉を見る世界」、この2つをうまく融合させて生きています。 彼らは仲間の共通の最も便利な手話を第一にし、さらに書き言葉を中心にし、相当難しいことがらでも、うまくコミュニケーションできています。しかも学生のほぼ全員が補聴器を手放しません。彼らが補聴器を装用したときの聞こえのレベルは、主に1000Hzより低い周波数の音が可聴範囲に入るような状態です。母音は聞こえるが、カ行、タ行、サ行などの子音は聞こえにくいというレベルで聴覚補償されています。それでも補聴器を使い続けている。手話や文字情報で十分に生活できるキャンパス生活なのに補聴器を手放さない理由は、言葉がよく分かることではなく音が聞こえることなのです。毎日の生活に音楽を聞くことが欠かせないという聴覚障害青年が多いのです。手話や読話を駆使してコミュニケーションしているときでも、補聴器にスイッチが入っていることにより、よりよく理解できるというのです。聾者は手話だけで十分と考えている聾の青年はいません。できるだけ自らの聴覚補償をした上で、周囲の情報保障の環境を整えたいと考えているのです。 例えば、「頑固親父」「ガンコオヤジ」という音声の「コ」だけを抜き取った音源テープを作成し、健聴な人に聞いてもらい、なんて聞こえたかを問う実験です。誰もが音がないはずの「コ」を穴埋めしてちゃんと「がんこおやじ」と答える。言葉は音声の一つ一つが正確に聞こえないと理解できない訳ではない。脳が聴いているわけです。これが「聴能」の働きです。 目からと耳からの刺激を同期させないと大変なことが起こることを示したマガークという人の実験があります。目からは「ダ」という口の開きを見せておいて、スピーカーからは「バ」という音を聞かせる。なんと聞こえたかを問うと、ほとんどの人が「ガ」でも「バ」でもなく「ダ」と答えます。人間は耳から正確に音が入ったとしても、目から違う刺激が入ってくると、無意識にだまされてしまう。逆に目からも耳からも同時に同期した正しい刺激が入ってくると、たとえ両方とも曖昧な口の開き、歪んだ音であっても正確に脳で聴くことができるということになります。 次の絵はヘルドという人の実験です。能動子猫と受動子猫という双子の子猫を大きな筒の中で飼います。両方とも知能指数がよく、性格もいい。視力も聴力も正常な双子です。能動子猫はベルトでつながれていますが思い通りに自由に動けます。一方の受動子猫のほうは、仕掛けがあって、宙づりの箱に乗せられて首かせをさせられ自由には動けません。能動子猫の周りにネズミを鳴かせ走らせると能動子猫は直ぐにそちらに向かって飛びかかりますが、反対の受動子猫はその動きに反して反対に振り回されてしまいます。聞こえた方に動こうとしたり、見たいと思った物を見ようとすると、とたんに意に反して反対の動きをさせられてしまいますから、次第に刺激に対して反応することを自ら止めて感覚を働かせない、聞けども聞けず、見えども見えずの猫になってしまいます。 人間は刺激にきちんと向かい合わないといけない。親の都合でこっちを見なさい聞きなさいではなく、本人が一番興味を持った刺激に向かわせるのが一番耳が働く状況です。人工内耳の小さい子もそうです。お母さんがせっかく苦労してつけた人工内耳、みんなががんばってつけてくれた人工内耳だからといって、子どもの興味や意志を無視した聴能訓練内容ばかりをそろえても、心から聞く姿勢は育たない。 時間がなくなりましたが、情報保障の在り方について述べます。一般大学にも聴覚障害者がいっぱい入ってくるようになりました。教室の一人の聴覚障害学生のために、要約筆記のグループで取り囲み大仰なコンピュータ設備を配置し情報保障をする場面も珍しくなくなりました。それはそれで嬉しいことなのですが、しかし、これは本物じゃない。情報保障はもっとさりげなく自然にやるべきです。情報保障の人材や機器は舞台から陰の方に向かうべきです。 教えたいと思う教師が習いたいと思う学生に直接に伝えようとするのが本物の教育です。間に通訳者がいて、通訳者の顔しか見ないままに授業が進む、これは本物じゃない。ダイレクトに教えたいことが伝えられる人を増やすのが情報保障の向かうべきところです。情報保障の仲立ちをする人を増やすのはまだ仮の姿なのです。また、情報保障に甘えすぎると、やってもらうことが当たり前になってしまい、聴覚障害者が情報保障する側への思いやりに欠けることも心配されます。 筑波技術短期大学では一般の大学向けにも情報保障をし始めています。遠隔地の大学に在籍する聴覚障害学生が受けている教室の画像と音声を筑波のスタジオで受けて、大学からリアルタイムに手話と文字を遠隔地の学生の手元に届けます。 これは、筑波のスタジオで情報保障している場面です。学生が実験などでテーブルを離れても手持ちのモニタで情報保障できる装置も考えられています。 情報保障の環境の一つとして、教室の机の配置にも配慮が必要です。聾学校によくある馬蹄形で授業をするのが普通ですが、いつまでもそのスタイルにこだわる必要ないと気づき、最近はV字型にしたり、丸形で組み合わせやすい机を使ったりします。 なお、筑波技術短期大学は今年の10月1日から、4年制の大学になることが決まりました。来年4月に新しい大学「筑波技術大学」の第1期生が入学します。 聴覚補償と情報保障の関係については、本日配布した資料にくわしく解説してありますのでぜひお読みください。 最後に、卒業式で私が話したことを付け加えます。最近の若者の多くもそうなのかもしれませんが、聴覚障害青年でも、自分の信条や座右の銘を持っていない青年が多いようです。聴覚障害児の言語獲得の過程では、言語は教えられるもの、言語は他の人とのコミュニケーションのために努力して身につけるべきものという考え方に従って行われてきましたから、無理もないことかもしれません。本来、言語の大事な機能には、自分の気持ちや考え、行動、生き方などを整理しコントロールするという側面があります。自らを把握するため自分の信条はこうだと、自分を律する、そういった役割を果たす言葉の働きに及ぶ余裕がなかったように思われます。 私自身の信条は「自灯明」ですと、昨年の卒業式に話し学生を社会に送り出しました。お釈迦様が死の床に集まった弟子達に残した言葉です。他の人から道を灯してもらうのではなく、灯明のロウソクのように自分自身を燃やして周囲を明るく照らすような生き方をしてほしいという意味です。 聴覚障害者は耳が不自由なので、その分だけ「みる」能力が代わりによく発達している。あるいは、視覚障害者は目が不自由なので、その代わり「きく」能力がよく発達している、と言われています。確かにそのような傾向があることは分かります。しかし、目がよく見えているはずの聴覚障害者なのに、物事がよく見えていない人もいます。目の前でみえている手話や文字や物事を「見」たり「視」たりすることは得意なのですが、見えていることだけが全てだと思ってしまい、その後ろにある、隠れているかも知れない真実に気がつかない場合があるのです。一方、目の不自由な視覚障害者が、「見」たり「視」たりすることに依存しないゆえに、かえって物事をとてもよく見極めている、心でみる、「観」えている場合があるのです。聴覚障害者は見えていることに安心せずに心でも観ることを心がけてみることも必要です。 ご清聴ありがとうございました。 |
各種情報メニューへ |