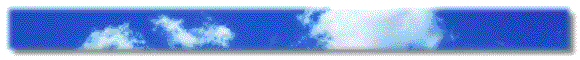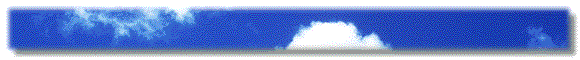
人工内耳友の会−東海−
|
詩集「無機質」抄 水口元一 昭和41年9月 <目次> 鎮魂歌 反響 習性 交差点 街の夜 錯覚の季節 無声映画の世界に 鎮魂歌 宝石の青よりも冷たくなったこころは 山脈の雪の中に埋もれて光っている ピッケルよ 突き抜けた空よ 南の風が垂直に吹く 地球の裏側へ 笑っている雲の季節 夏のリンゴが涼しい 眠っている心臓はガラスびんです 山岳地帯の さらに白色の空間の柔らかさに 紙のような生毛が凍っている指の重さ 毎朝埋もれている上まで蝿が訪ねてくる ちょうど喉仏の上のあたり けれどもなつかしい友です 早く そして軽やかに進行する雲の観念 沙漠のオアシスは あつまった夢がしゃべっている 真青い空に なおも奥深く愛し合う閃光−− 遠くなつかしいクラシックギターの歌を聞いて キャベッツのサラダを喰べながら眠っています ↑ 反響 蒼白い高層ビルの谷間は 空間が舞い散る午後 それからの時間を無視して 不自然にCARは泳ぐ 愛を失った私たちは まっ青な傷跡を覆いあって ひっそりと抱擁する姿さえ この真中には無機質となる 軽金属が散乱反射し連なるるときは いっそう鋭くなる午後 へんに凝縮した地面には 苦痛のない神経が所有されている なんにも入ってないこころを冷えきらせて ただに歩きまわる極限の生活 あちこちの排水溝に 悲哀は流れ捨てられる ↑ 習性 かなかなと耳の奥で何かが鳴いた こうして僕らは暮らしてきたのだった あたらしく 青と赤の色鉛筆が削られるとき 数字の計算文字が歌う 僕らは大きな木々の梢で ひっそりと棲んでいた ぶりきの箱の中の 明るいキャンデー詰めが 君たちのお気に入りなのだ 水玉模様のねくたいをして 僕らが入っていくとき 君たちはひそやかに手をたたくのだ そうして時は奪われる 「あい」ということばが 君たちの唇からもれるとき 僕らはそれを LOVEということばにかえて考える ↑ 交差点 青●硫酸銅光線の鋭い屈折。 悲哀の反射の夜。 空中に漂う意志は一方通行する。 現実間の錯覚。 ひとつの彼岸を僕は渡る。 黄●物憂げな静寂の混乱。 分裂する心の指標。 空虚の分岐点に達して。 選択をためらう。 堕落の反抗。 青●独裁された肉体の断層。 暗黙の恐怖の焦燥。 無感覚な逆行が神経を燃焼する。 原始からの根源の屈辱に。 意識は挫折する。 ↑ 街の夜 街の空間は青みがかっている 目に見えない無数のこころが まったく孤独に光りつく ネオンや看板の反射を受けて 少女は答えられない 小さなウインドウの前で 自分の姿に見とれながら歩いていた ガラスに写る屍体の群を ああ無意識の反響がまぶしい こころは透明な呼吸をしている あるがままの 限られた拡がりの中で 街を歩きまわりながら 互いに純粋なこころを求められない 敷石さえすでに浮かびあがり 哀しみが不規則に色彩された 街の空間は青みがかっている 目に見えない無数のこころが まったく孤独に光りつく ネオンや看板の反射を受けて ↑ 錯覚の季節 六月の雨には時たま晴れ間があって 雲の間から見る空は青い ぼくたちは 一日 時間に縛られていると 時には自由を想うものだが 冷たい嵐もなければ熱暑の日光もない くりかえしぼくたちの単調な日々は 太陽のような恋人に何も言い出せない 生温い墓石に直結する惰性の片想いだ 建物をひとめぐりして戻ってきた声のように ぼくたちのことばはあいまいになって いつしか 違ったことばに変化してしまうのではないか 言いわけも考えつかずに 愛の演技者でさえないのか ぼくたちの青春は 灰色の高層ビルの谷間 十字路の角で 方向感覚を見失った遭難者のように あてもなく 迷いつづけて ↑ 無声映画の世界に 私はひとり自作自演 無声映画の世界に生きる カメラアイは私をとらえ カチンコが口を閉じ 私の行くところはすべて 限りない沈黙の二十世紀 生活のかたすみで「人々」は歩きまわり 自動車は地面を震動し 飛行機は青空を切とってはいくが 私の耳の中の小さな貝がらの破片は そうした空気の振動には まったく無関心なポーズ 立体総天然色無声映画の はてしなく広がる三次元の世界 私はこの十年間を 私なりに歩いてきた? そうして孤独を受けとめてきた? 私の小さな貝がらの破片は すべてを自然の手にまかせたまま 安らかに沈黙を守っている この私の行く手のフィルムに いつかサウンドが刻みこまれる日を 私は二十世紀と神を意識しながら 静かに待っている ↑ |
メールはこちらへ |
ももちゃんワールド |