6月3日、午後5時。生徒発表会が全て終了すると、衣装、かつら、小道具等はすばやく数十個の荷物に纏め上げられた。数時間後には猿之助先生以下全員が早くも学内を去るのだ。
思い出多い授業との別れを惜しみ、中々立ち去る気配をみせなかつた学生たちもあらかたは姿を消し、ここ一週間は熱に浮かされたかのような空気に満たされていた直心館周辺も、黄昏の中、みるみるコンクリートの地肌もあらわな元のガランとした空間に戻りつつあった。
やがて瓜生山より望める、西山の連なりの向こうに陽が落ち、燃えるような夕焼けが始まった。間もなく能楽堂では、今回の授業に携わった先生側(猿之助以下役者一同)と、学校側(理事長、学長以下教授、職員等)との送別の宴か催されるという。
と、どこからともなく現れた学生の一団。おそらく男女合わせると30名近くはいると思われる。名残惜しさに耐え切れず、「せめてもう一度お別れを…」といった思いにかられ、三々五々と集まって来た者達ばかりなのだろう、手に手に花束を携えていた。
そして間もなく、パーティ会場のテラスに面したガラス戸側一面は、彼らの姿で埋め尽くされたのである。
別れを目前にたたずむ学生達の思いとは裏腹に、会場内は明るく華やいでいた。ガラス戸はどれもみな開け放たれていて、テラスにいても中の有り様は、人々の様子ばかりか、話し声や物音までもが手に取るようにわかる。
やがて理事長、学長の挨拶が終わり、続いて「一言を…」と猿之助先生が挨拶に立った。
|
まず、「私は歌舞伎を通して感動を伝えたいとこの学校にやって参りましたが、その通り感動を分ち合うことが出来たと思います。
たった一週間の授業、発表会の演技に至っては僅か三、四日の稽古しかありませんでしたが、みんなが一生懸命にやった結果、立派な成果を収めることが出来たことに、私も感動するとともに、大変嬉しく思っています」というような挨拶があった。続けて先生はさらに数通の手紙を取り出した。そしてテラスで聞き入る学生達に聞かせようとするかのように、ゆっくりと読み始めたのである。 |
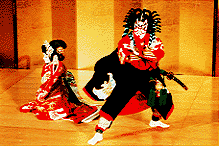 |
それは、早くも先生の手元に届いた、一般受講生からの集中授業に対する感想を綴った手紙であった。
『涙が出る程感動しました。私もこの大学の学生になりたかった』
『講師陣ばかりでなく、学生達のすごい真剣さにもうたれました』『発表会では、舞台から発せられる膨大なエネルギーと、その気迫に押されるように舞台を見守る人々との思いが一つになって、舞台としても、いい、最高のものになっていたと思います』etc
。
読み終えると猿之助先生は、外にいる学生達に向かって言った。
「皆さんも一生懸命になったら、こうして実際に人を感動させることが出来たんです。あなたたちは、感動を与えたんですよ!」と。
すると、まるでその言葉が合図ででもあったかのように、学生達の間には、さざ波のようにすすり泣きが広がり、それはあたかも夜の気配ただよう瓜生山の空気と溶け合って、パーティ会場となっ能楽堂一帯をスッポリと包み込んでしまったかのような有り様となった。
やがて、学生達の思いに打たれた学校側の計らいで、花束贈呈と学生代表の挨拶が許され、弁慶を演じた宮本佐知子が進み出た。
彼女は、手にしたメモに時々目を落としながら、一つ一つの出来事を思い出し、噛み締めるように話し始めた。
日々、新しい発見と感動に包まれていたこの一週間がいかに充実していたか。
全員がどれほど結束し、一生懸命になり、キラキラ輝いていたか。
毎日学校に来ることが、どんなに楽しかったか等々について。
そしてついには「いつまでも、いつまでもこの時が続いてほしい!皆さん、帰らないで下さい。お願いだから帰ってしまわないで下さい!!」と、こらえ切れなくなった思いをぶつけるかのように絶叫したのである。
彼女は泣きじゃくっていた。テラスを埋め尽くした学生達も、幼児のように、泣きじゃくっていた。こうして会場の内と外は、いつしか名残を惜しむ涙で溢れかえり、猿之助先生以下、集中授業に携わった役者一同、また、その信じられないような光景を目の当たりにした大学関係者も、思わず込み上げる熱いものを抑えることが出来なかった。 |