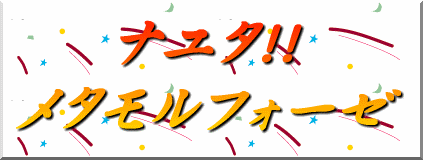
夜の帳(とばり)が降りる頃、活気に満ちていたルザイアの街も静けさに包まれる。軒先の明かりが、一つまた一つと消えていき、街全体がまた来る明日(あす)のために眠りについてく。
だが、夜になるとにわかに活気を帯びてくる一角がある。もちろん、それは酒場だ。一日の仕事を終えた男達の足は、自然と酒場に向かう。
大陸とは遠く離れた島国のため、冒険者や行商人達で賑わうことはない。酒場の扉を開ければ、自慢の手料理の香りと共に、いつものメンバーが顔をそろえている。
ある者達は飲み干した酒の量を競い合い、ある者達は歌い出し、ある者は世間話に花を咲かせる。平和なエルドランの国を象徴するかのように、賑やかな夜はいつまでも続いていく。
そんな喧噪を離れ、大通りを真っ直ぐに進むと一つの豪邸が建っている。この街の大富豪ゲイルードの屋敷であり、今回の物語の舞台となる場所だ。
屋敷の明かりはほとんど消えているため、辺りはずいぶん暗い。しかし、月明かりに照らされて、屋敷の方をじっと見つめる者がいた。”大盗賊”として知られる、シャドウだ。
闇の中に浮かぶ双眸はまるでナイフのように鋭く、黒装束に身を包んでいる。
シャドウは一瞬目を細め、白い歯をこぼした。その笑みは、今から狙う”獲物”を手に入れることへの喜びからであろうか。
それからシャドウは、物音一つ立てずに闇の中へと消えていった。
そしてここにもう一人、ゲイルードの屋敷に向かう男が一人いた。薄暗い夜道の中、度の強そうな眼鏡が月明かりに反射している。その姿は、いかにも頭が切れそうな探偵のようであった。その彼の後ろからは、一匹の狐がついてきている。大きさからいってまだ子供であろうが、尻尾は九本もある。
男はそのまま屋敷の門に向かって歩いていった。そして・・・・
コケた。
「いたたたた・・・・」
男は豪快に躓(つまづ)き、派手に転んだ。
「なにやっとんじゃ!」
またかといった感じで、狐が男に声をかける。
言わずと知れた、ナユタとナインテールの凸凹コンビだ。
「いや〜、暗くて前がよく見えなくてさ」
ナユタは服に付いた埃を払う。
「せっかくの登場シーンだってのに、なにボケをかましてんだ。まったく、お前のようなやつを主人公にするやつの顔が見てみたい」
悪かったね。
「どうせだったら、オレ様を主人公にすればいいんだ。天才妖怪ナインテール様が、その力を使って悪者をばったばったと懲らしめていく。サイコーじゃないか」
ナインテールを主人公にした妖怪アクションか。まあ、考えておこう。
「とにかく、上手くシャドウを捕まえられるといいね」
ナユタは改めてゲイルードの屋敷を眺めた。夜に見るのは初めてだが、なんだかいつもより大きく感じる。
「当たり前だろう!借金を返さねば、オレ様の住処がなくなってしまうじゃないか!」
ナインテールは、つばを飛ばしながら叫んだ。
「あの〜、この物語は一応ぼくが借金を返しながら自分の家を守るって話なんだけど・・・・」
「黙らっしゃい!お前の家がどうなろうと、オレ様の住処(すみか)が一番大事なんだ。このアンポンタンめが」
アンポンタン?もはや死語のような気がするけどなぁ。
「その話は置いておいて、早く屋敷に入ろうよ。このままじゃちっとも話が先に進まないよ」
「ふん、そんなことはどうでもいい。オレ様一人が登場してればそれで十分だ」
残念でした。作者の権限で先に進めます。
ナユタとナインテールは屋敷の門をくぐり、玄関の前までやって来た。はたして、二人はシャドウを捕まえることは出来るであろうか。
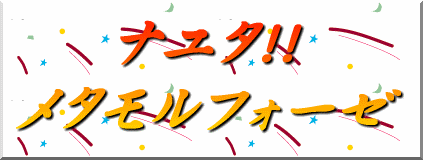
−第0話・中編−
ゲイルードの屋敷の特徴は、一つには窓が多いことだ。屋敷の正面の壁にはいくつも窓があり、豪華な屋敷の中を覗くことができる。それはまるで、来訪者に自分の富を示しているようであった。
また、太陽の明かりを浴びるとそれぞれの窓が光りを反射することから、”ガラスの館”とか”光りの館”とも呼ばれている。
二つめの特徴は、巨大な時計台だ。すべての人が見られるようにというゲイルードの言葉通り、時計が四方につけられている。
この街の名物の一つにもなっていて、四つの時計台の数字が書かれている部分には宝石が埋め込まれている。
屋敷の扉も、ひときわ豪勢なものであった。そこに取り付けられたノブは、獅子が鉄の輪っかを咥(くわ)えた彫刻であった。ナユタは来訪を告げるため、輪っかを二、三度扉にたたきつける。
「シャドウを捕まえるためにやってきました者です。開けてください」
夜だけあって、ナユタは少し小さめに呼びかけた。
「こうして改めて来ると、なんだか緊張するね」
ゲイルードの屋敷、つまりエレウシアの屋敷にはナユタも何度か来たことがある。もっとも、その時は舞踏会があるとかで強引に出席させられたのだが。それでも、やはり盗賊退治となるとなんだか気分は全然違う。
「しっかりしろよ。捕まえるのはお前なんだからな」
相変わらず頼りないナユタに、ナインテールも心配になってくる。
「分かってるよ」
ナユタは気を引き締めるように、真剣な眼差しをする。その姿は一丁前にカッコイイ。だが、中身はドジなナユタのままだ。
しばらくして、ギギィ〜っと扉が開いた。辺りが静かな分、その音は意外に大きかった。
「いらっしゃいませ」
屋敷の中から、執事が姿を見せる。
「げっ」
ナユタは思わず顔を引きつらせた。
「どういたしました?」
「いや、すいません」
ナユタは慌てて詫びる。
執事は、筋骨隆々の大男だったのだ。ナユタの知っていた執事は骸骨のように痩せた白髪の老人だったので、面食らってしまったのだ。
「旦那様がお待ちです。どうぞこちらへ」
「ああ、そいつはどうも・・・・」
この執事は何か不気味だ。ナユタは身体を強張(こわば)らせながら、いそいそと執事の後に付いていった。
<おい、まるでフランケンシュタインだな>
不意に、ナインテールの声が聞こえてきた。
「ちょっとナインテール。なんてこと言うんだよ」
ナユタは慌てて後ろを振り返る。
「どうかしましたか?」
いぶかしげに執事が訊ねた。
「いや、何でもないです。こいつがちょっと・・・・」
ナユタはナインテールを指さした。
「こいつ?誰もいませんが」
何を言い出すのかと、執事は怪訝(けげん)な表情をする。
「えっ、なに言ってるんですか?この狐のことですよ」
ナユタは何度もナインテールを指さす。
「狐なんかいませんが・・・・」
「そんな馬鹿な!」
執事はいたってまじめな顔をして答えているので、嘘を言っているとは思えない。ナユタ自身、訳が分からなくなっていた。
<馬鹿か、オレ様の姿はお前にしか見えないんだ。そして、オレ様の声もお前にしか聞こえない。例えばだ、お前は普通にオレ様と喋っているつもりでも、他人からはお前が何もないところに向かって喋っているようにしか見えない。それではお前が馬鹿丸出しだから、こうやってテレパシーを使うんだ>
「テレパシー?」
<そうやって口に出さなくても、お前が心で念じれば、それをオレ様に伝えることができる。オレ様達二人だけならいいが、他人がいる前ではその方が楽だろう>
「なるほどね。でも、心で念じるってどうやるんだい。ぼくはテレパシーなんかやったことないんでけど」
<それはだな〜・・・・>
ナインテールは考え込んでしまった。テレパシーのやり方を教えることまでは考えていなかったのだ。
まあ、こんなところで手間取ってもしょうがない。なぜかナユタはいきなりテレパシーができるようになったとして、話を先に進めよう。作者もその方がやり易い。
「横暴だな〜、相変わらず。それにテレパシーとか言いながら、『ニュージェネ』のパクリじゃないか(注:同じ作者が書いている『ニュージェネ』という作品に出てくるキャラが、同じようにテレパシーを使える)」
「ぼくたちの作者って引き出しが少ないんだよ、きっと」
・・・・・・。話を早く元に戻そう。
「すいません、何でもありませんでした」
その場を取り繕うように、ナユタは苦笑いを浮かべる。もっとも、いまさらそんな言い訳をしても遅いような気がするが・・・・。
一方そんな彼を、フランケン(執事)はあっけにとられて見つめていた。それは当然だろう。
幻惑でも見てるのかと思うほど意味不明な奇行を突然始め、挙げ句の果てに訳の分からぬ一人芝居を繰り返すナユタ。誰が見たって、いかれた人間にしか見えない。
「わ、分かりました・・・・」
とんでもない奇人がやってきたと思いながら、フランケン(執事)はナユタをゲイルードの部屋に案内した。
フランケン(執事)に連れられたナユタ達は、ゲイルードの私室にやってきた。
「旦那様、もう一人探偵の方がやってきました」
そう言って、フランケン(執事)はドアを叩く。
「通してくれ」
部屋の中から、ゲイルードのくぐもった声が聞こえてきた。
「どうぞ」
フランケン(執事)はドアを開け、部屋の中にはいるようにすすめる。
「失礼します」
ナユタは一礼して、ゲイルードの部屋に入っていく。
さすがに大富豪といった感じで、ゲイルードの部屋には豪華な調度品が所狭しと並んでいた。それを見て、こんな部屋にいてよく落ち着くものだとナユタは密かに思った。自分だったら、なんだか逆に疲れてしまいそうだ。
そして部屋の奥にはこれまた豪華な机があり、ゲイルードが腰掛けていた。
30代半ばのゲイルードは彫りの深い顔に口髭を豊かに蓄え、その眼はまるで鷹のように鋭い。男としてはまさに脂ののりきった時期であり、国王と見違えるほどの威厳を誇っていた。さすがは、一代で巨万の富を蓄えただけある。
彼の前には、三人の男女がソファーに座っていた。ナユタと同じように、シャドウを捕まえに来た面々であろう。
「そろそろ時間だ。どうやらあなたで最後のようだな」
ゲイルードの声はなかなか渋い。作者としては『ガンダム』のシャアの声が似合っているかなと思っているが、残念ながら声優さん(堀内って人だったかな?)の名前を忘れてしまった。
そんなことはともかく、ナユタはソファーに腰掛けた。
「それではこれから話を始めたいと思うが、その前にそれぞれ自己紹介をしていただこう」
ゲイルードは全員は見回す。
ゲイルードの言葉に従い、左端に座っているボサボサ頭の若者から自己紹介を始めた。
「ぼくの名前はコロンボ。見ての通り、探偵をやってます」
おそらくまだ二十歳(はたち)を超えていない、ノリの軽い男だ。パーマのかかったブロンドの髪をボサボサに伸ばし、ポツポツと無精ひげを伸ばしている。着ているシャツにもしわが目立ち、10年ぐらい使ってそうなボロボロの靴を履いている。
<よかったなナユタ、あんなダサイ格好をしなくて済んで。オレ様のセンスに感謝しろよ>
ナインテールが早速テレパシーを送ってきた。
<相変わらず口が悪いなぁ。それに、ぼくたちだって人のこと言えないよ。なんだか浮いてるもん、僕の格好って>
<いちゃもんつける気か?探偵を言えばその格好だろう>
分かりやすく言えば、今のナユタの格好は、かの有名なシャーロック・ホームズに近い。だがそれでは、実際のナユタの時代設定にはあっていないのだ。かっこよさにこだわるのもいいが、できれば時代設定に従ってもらいたい。
そのコロンボの隣には、30代ぐらいの女性が座っていた。
「わたしは特別治安官のメルフィーユといいます」
”治安官”というのは、今でいう警察と同じだ。なかなか魅力的な女性だが、警察官だけあっていかにもカタブツそうな雰囲気を受ける。
「わたしはずっとシャドウを追いかけてきました。褒美には興味はありませんが、必ずシャドウを捕まえて見せます」
どうやら、彼女の目的はシャドウを捕まえることのみのようだ。
<お仕事一筋って感じの女だな。あれでは男も寄ってこないだろう。もったいないな、まあまあ顔はイケてるのに>
ナインテールの毒舌が続く。
<だからやめてよ・・・・>
そのメルフィーユの隣りには、浅黒く肌の焼けた若者がいた。
「名前はバランとだけ言っておこう。細かいことをあんたらに言う筋合いはねえ」
まるでヤンキーのような男だ。ガムをクチャクチャ噛みながら、ズボンのポケットに手を突っ込み両足をテーブルの上に乗せている
<どう見たってゴロツキじゃないか。おおかた褒美が目当てだろうな、お前みたいに>
<確かに目的はお金だけどね〜、それは・・・・>
<オレ様の住処のため!>
<・・・・はいはい>
もはや反論する気にもなれない。
そのバランの隣りに、ナユタが座っていた。
「わたしはナユ・・・・」
そう言いかけて、ナユタは急いで口を閉じた。変身しているのだから、名前がそのままではマズイ。
「え〜と・・・・。そうだ、セシルでいい。私の名前はセシルです」
「はあ・・・・」
いかにも取って付けたような素振りであったが、ゲイルードはあまり気にはしなかった。
「わ、わたしも探偵をやっています。はい」
「分かりました。それではコロンボさん、メルフィーユさん、バランさん、セシルさん、これから説明を始めます」
一人ずつ名前を確認し、ゲイルードはおもむろに背後にあった金庫を開けた。その中には、目を見張らんばかりの美しい水晶が入っていた。
「それが”エルフの涙”ですか・・・・」
コロンボは、思わず身を乗り出して”エルフの涙”に見入った。メルフィーユとナユタもただタメ息をつくばかりで、一人バランだけが謎めいた笑みを浮かべていた。
「これほど素晴らしい水晶は大陸にだってないでしょう」
緑色をした巨大な水晶を、ゲイルードは誇らしげに見つめた。
「必ずやシャドウはこの水晶を狙ってきます。皆さんに依頼したいのは、そのシャドウを捕らえること。方法は皆さん一人一人にお任せします。それぞれのやり方でシャドウを捕らえてください」
ゲイルードは金庫を再び閉じると、胸のポケットから鍵を取りだした。
「この鍵は、私にしか使えません。例え鍵がシャドウに奪われたとしても、やつには使うことはできないでしょう。それにこの金庫全体にも魔法がかけられており、絶対に壊すことはできません。つまり、いかにシャドウといえども絶対に”エルフの涙”を奪うことは不可能なのです」
ゲイルードはこの日のために、最新式の金庫を用意していた。
「やつは宝石を盗むだけで、その価値を知ろうとはしない。宝石は、人の目に触れてこそ価値があるのです。その宝石を、やつは”奪う獲物”としか見ていない」
シャドウが盗んだ宝石は、すべて闇の中に消えてしまっている。その中には、貴重な宝石も数多くあるのだ。
「それが許せないからこそ、私はやつを捕まえて欲しいのです。もしやつが捕まれば、わたしは”エルフの涙”を博物館にでも飾りますよ。宝石は一人のためにあるのではなく、万人のためにあるのですから」
さすがに大富豪と言うべきが、その演説には聞く者に訴えかけるものがある。
<いいこと言うな、このオッサン。なんだか感動してきた>
<珍しいね、ナインテールが他の人のことを誉めるなんて>
<それはお前が情けなさ過ぎるからだろう。オレ様はこのオッサンのために一肌脱いでやろう>
おお、珍しくナインテールが燃えている。
「皆さんにはこれを渡しておきましょう」
そう言って、ゲイルードは一枚の紙切れを全員に渡した。
「これは何ですか?」
コロンボがしげしげと紙をのぞいている。そこには、地図のようなものが書かれていた。
「この屋敷の地図ですよ。ここは広いですから、初めての方はきっと迷ってしまうでしょう。ですから、行動するときはその地図を見ながら動いてください」
ゲイルードの言うとおり、この屋敷は迷路のように広い。慣れない者が下手に歩き回ったら迷子になるのがオチだ。
<ずいぶん広いんだな>
地図を見ながら、その大きさにナインテールも半ば感心している。
<ぼくも始めてきたときは苦労したんだよ。おまけにエレウシア達がワザと隠れるからさ、結局舞踏会には出られなくて・・・・>
<どうせ、お前はすぐに迷子になってたんだろ>
ナユタのからかわれている姿が目に浮かぶ。本当にアキレ果てるばかりだ。
<わ、悪かったね>
ナユタは頬を膨らませてすねる。
<今度は地図があるんだから迷子にならないでくれよ。その間にシャドウを捕まえられたらシャレにならないからな>
まあ、それはそれで面白いかもしれないけどね。
「この赤い印は何?」
メルフィーユが地図の上を指さす。そこには、赤い印が書かれていた。
「それは罠ですよ」
「罠ですって!?」
メルフィーユの声が1オクターブ上がる。
「気を付けてくださいね。盗賊防止のために、いろいろ罠を仕掛けてありますから」
「わたしたちのこと本当に信用してるの?」
メルフィーユの言い分はまったくだ。物々しい金庫に、厳重な罠。やりすぎにも程がある。
「用心に越したことはないですからね。商人の鉄則ですよ、”備えあれば憂い無し”ってね」
商人という者、神経質なぐらいの方が成功するのだろう。
「それでは皆さん、そろそろ始めましょうか」
ゲイルードの言葉と同時に、部屋にあった大時計が零時を刺した。それと共に仕掛けが作動し、「ボォ〜ン」と鐘が鳴り響く。それはまるで、対決の時を告げる知らせのようであった。
「敵は姿なき大盗賊。皆さんのご健闘を期待してます」
さすがに大富豪らしく、ゲイルードはかっこよくシメてくれた。しかし、まるで用意していたかのようなゲイルードの台詞に、水を差す男が一人。
「なるほど。姿を見せたことないと言うことは、わたしたちの中にシャドウが混ざっているということもあり得るわけですね」
もちろん、こんなことをしでかすのはナユタしかいない。
「はぁ?」
「シャドウが、この中の誰か変装しているかもしれないということです」
ナユタは得意げに目を閉じて腕を組み、口にくわえたパイプから煙を吐きながら、さりげなくかけていた眼鏡を直す。なかなか気取った格好でいかにも探偵らしいが、愚かなほど思慮が浅い。
<お前な〜、これからシャドウを捕まえようって時に疑心暗鬼を募らせるようなこと言うなよ>
まったくもってナインテールの言う通りだ。だが自分の世界に浸っているナユタには、ナインテールの言葉は届かない。こちらの期待通り、さらに愚行を重ねていく。
「それからこれはどうでしょう。これからシャドウのことを、”闇の徘徊者(はいかいしゃ)”と呼ぶのは」
ナユタの言葉に、他の者達は茫然としている。
(キマった!!)
ナユタは心の中でほくそ笑んだ。
(なんて素晴らしいネーミングだ。それも”徘徊者”なんて難しい言葉なんか使ったりして。みんなあまりの衝撃に立ち尽くしている)
たしかにナユタの言葉に衝撃を受けた。だがな、ナユタよ。あまりのくだらなさに、みんなは遙か冥王星の彼方まで引いてしまっているのだよ。
<どうだいナインテール。僕も探偵みたいに頭が切れるだろ>
そんなことはつゆ知らず、一人ナユタだけは勝ち誇っていた。
<呆れて何も言えんよ・・・・>
せっかくの緊迫した場面を、見事にぶち壊してくれたナユタ。おまけに、とんでもない爆弾発言までする始末。こんな男に、はたしてシャドウを捕まえることはできるのだろうか・・・・
静まり返った屋敷の廊下を歩くナユタとナインテール。
シャドウを捕まえるために集まった面々は、思い思いに屋敷の中へ散っていった。褒美を得るには、誰よりも先にシャドウを捕まえなくてはならない。
「それにしても半端じゃないぞ、この広さ」
そう言うと、ナインテールが急にナユタの頭の上に乗っかってきた。お腹をナユタの頭の上に乗せ、後ろ足を肩に乗っけている。
「ちょ、ちょっと。重たいじゃないか」
妖怪のクセに、ナインテールは意外に重かった。
「いいだろ。少し疲れたんだ」
「へぇ〜、妖怪も疲れるんだ」
ナユタには初耳だった。
「当たり前だ。疲れるし、ハラも減るし、眠くもなる。まあ、オバケには学校も試験もないがな」
古いネタだな〜。分かる人はいるんだろうか・・・・。
「そんなことより、めちゃめちゃ広いなこの屋敷」
ゲイルードからもらった地図は、地上三階建て、地下にも部屋がある。
「ホントにすごいと思うよ。エレウシアはいつもこんな屋敷で暮らしてるんだからね」
ナユタもため息をついた。
「まあ無理もない。この屋敷に比べたら、お前の家なんぞ犬小屋みたいなものだからな」
「それってヒドイんじゃない。一応ナインテールはその犬小屋の守り神なんだろ」
犬小屋扱いされて、さすがのナユタもカチンときた。
「ちょっとからかってやっただけだ。冗談の通じないやつだな〜」
冗談と言いながらも、少しも悪びれた様子はない。
「ナインテールの言葉は、本気なのか冗談なのか分からないんだよ」
犬小屋かどうかはともかく、エレウシアの屋敷に比べれば、ナユタの家は月とスッポンほどの違いは確かにある。
ここで、なぜエレウシアのようなお嬢様が、ナユタのような凡人と一緒の学校に通っているのかと疑問に思う人もいるかも知れない。だがそれは、決して口に出してはいけない。
例えばそれは、「なぜのび太やカツオは、いつまでも小学生のままなのか?」と訊ねるようなものなのだ。
この世の中、触れてはならない問題もある。どうか温かく見守っていて欲しい。
話を元に戻して。
そんな広い屋敷の中を、二人は地図を頼りに巡回していた。
「んっ?この先の通路に赤い印がついているな」
ナインテールは地図をのぞき込んだ。
「この先の通路に罠が張ってあるみたいだね」
ナユタは注意深く目を凝らす。しかし、別段変わった様子はないようだ。薄暗い廊下がずっと奥まで続いている。
「本当に罠なんかあるのかな」
何とナユタはそのまま進んでいってしまった。果敢と言おうか無茶すると言おうか、つくづく話をオイシイ方向に持っていってくれるやつだ。作者にとってはまことに有り難い。そのナユタに敬意を表して、素晴らしいプレゼントを用意してあげよう。
それから十歩ほど進んだとき、いきなり床のカーペットがめくり上がった。
「うわあっ!」
ナユタが驚いている間に、カーペットはまるで生き物のように二人を包み込む。
「おい、どうなってるんだ。このアホンダラ!」
「知らないよ!」
茶巾寿司のようにカーペットに包まれたナユタとナインテールは、そんなことも忘れて喧嘩を始めた。
「まったく、シャドウを捕まえるための罠になんでオレ様達がはまってるんだ!」
「まさかホントに罠があるなんて思わなくて・・・・」
「分からないように仕掛けておくから罠なんだろうが!知ってながら自分からはまりに行くようなやつなんかいるか、ボケ!」」
まったくだ。今度からナユタのために、”ここには本当に罠があります”って立て看板でも立てておこう。普通の人間にとっては恐ろしく無意味な罠だが・・・・。
「とにかく、ここから出る方法を考えよう」
「当たり前だろう。さっさと考えんか、スカタンめ!」
「う〜ん・・・・」
ナユタは腕を組みながら、探偵に変身した脳細胞をフルに使って考え込み始めた。
しかしそれからすぐに、それこそ作者が数十分もかけて考えたアイデアを、ナユタはたった一行であっさり考えついてしまった。なんだかくやしいなぁ・・・・。
「たぶん、何か合い言葉があるはずだよ」
作者は、いや違った、ナユタはこう考えたのだ。例えシャドウを捕まえても、いつかはカーペットの中から出さなくてはならない。その時に、なにがしかのことをカーペットにするはずだ。そういうときには、たいがい合い言葉だと相場が決まっている。
「で、どんな合い言葉なんだ」
「思い出してみてよ。さっきゲイルードさんがみんなの前で罠のことを言っていただろ。その時なんて言っていたのか・・・・」
「そんなこと覚えているわけないだろう」
ナインテールはじれったそうに答える。
「こうだよ」
それから一呼吸おき、ナユタはある言葉を呪文のようにつむいだ。
「備えあれば、憂い無し・・・・」
ナユタの言葉に反応して、カーペットが一瞬光ったのち元に戻ってしまった。
「すごいじゃないかナユタ。お前もやればできるんだな」
相変わらずナユタの頭の上に乗っているナインテールも、珍しくナユタを誉めた。
「へへっ」
ナユタは照れ笑いを浮かべる。
「さっ、気を取り直してシャドウを探しに行こう」
「ちょっと待て、この先にもまた罠があるぞ」
ナインテールの言うとおり、地図にはこの先にもう一つ罠の印がある。
「な〜に、心配ないさ」
しかし、ナユタはいたって落ち着いてた。
「おお、いつにいなく自信たっぷりだな」
ナインテールもナユタの豹変(ひょうへん)ぶりに驚く。
「今の罠は廊下の真ん中にあったろ。盗賊の心理としては、絶対廊下の真ん中には注意を払うはずさ」
そう言って、ナユタは廊下の真ん中を歩いていく。
「ということは、盗賊は壁際を歩くことになる」
ナユタは廊下の端に進んだ。
「それを逆手に取るのさ。おそらく今度は・・・・」
ナユタは注意深く一歩踏み出した。
その途端、反対側の壁の小さな穴から矢が飛んできた。その矢を、ナユタは尻餅をついて間一髪でよける。
「こ、こうなるのさ・・・・」
予期していたとはいえ、ナユタの顔も引きつっていた。
ただナユタが間一髪だったということは、その頭の上に乗っていた彼は当然無事じゃなくなる。
「なんだか頭がスースーするな〜」
ナインテールは、妙に寒く感じる額に前足を持っていった。
「なっ、ない〜!!」
絶叫して驚いたナインテールは、そのままナユタの頭の上から転がり落ちた。
「どうしたんだい、急に?」
「なっ、ないんだ〜!」
ナインテールは額を指さす。すると、額の一部がきれいに禿げ上がっていた。
「あはははは!もしかして・・・・」
ナユタは壁に突き刺さった矢を見つめる。そこには、ナインテールのものとおぼしき茶色い毛がはさまっていた。
「いつも口が悪いから罰を受けたんだよ。いや〜、それにしてもいい具合に禿げ上がってるね〜、うふふふふ」
ナユタがナインテールの額を指さして笑う。
「そもそも、お前がよけたからこうなったんだろうが!」
「だってしょうがないだろ、よけなきゃ僕の頭に刺さってたんだから」
「お前の腐った頭なんかどうでもいい。あと少しずれてたらオレ様は死んでたんだぞ!」
「死んでたって言っても、君は一度死んでるんだろ。確か・・・・、お腹がすいて死にそうになっていたときに、毒キノコを食べたっていうマヌケな死に方で」
ナユタはついに最終兵器を繰り出した。今のところ唯一の弱点はそこであり、それをナユタに握られているのがナインテールにとっては痛かった。
「おのれ〜、ナユタの分際で。妖怪を怒らせたらどういう目に合うか教えてやろう」
ナインテールの両目が怪しく光った。するとナインテールの身体がモクモクと煙に包まれ、その中から人間の赤ん坊ほどの大きさはあろうかと思うほどの巨大な蜂が姿を現す。
「な、何をする気だよ!」
この世のものとは思えぬほど巨大な蜂を前に、ナユタは後ずさる。
「せめてもの情けだ、苦しまぬそうに一差しで殺してやろう。地獄に行って後悔するがいい、ケッケッケ・・・・」
ナインテールはお尻から極太の針をキラ〜ンと出し、ナユタめがけて襲いかかっていった。
「正気かよ〜。ぼくが死んだらこの物語はどうなるんだよ」
ナインテールの目がマジなので、ナユタは慌てて逃げ出す。
「いつまでも脇役なんてやってられるか〜。安心しろ、お前より一億倍かっこよく主役を演じてやる」
巨大な羽根を振るわせて後を追うナインテール。その音はまるで車のエンジンのような・・・・って、この時代には車なんかないか。とにかくそれに近いような音を立てて、ナインテールはナユタを追う。
「うひゃ〜!!」
逃げるナユタ。しかし、アホなことにそのまま壁際を走っていた。
後ろからは巨大な針が迫り、横からは怒濤のごとく矢が放たれる。考えただけでも恐ろしい光景だ。
敢えていばらの道を進むナユタ。こいつ、ドジなんかじゃなくて、本当はマゾなんじゃないだろうか・・・・。
とっくに罠が終わっても、追走劇はまだまだ続いた。しかし、結局二人とも疲れて幕を閉じる。
「はぁ、はぁ・・・・。今日の所はこのぐらいで許してやる。命拾いしたな」
ナインテールも変身を解き、二人して壁により掛かっていた。
「ぜぇ、ぜぇ・・・・。ぼくたちはシャドウを捕まえに来たんじゃないの。なんでこんなコントをしてるわけ?」
「しょうがないだろ、今が前半の盛り上げ時なんだから。お笑いってのはな、カラダも張らなきゃいけないんだよ」
「まったく、キャラ使いの荒い作者だよ」
恋しさ余って憎さ百倍という言葉もあるだろう。これは作者からの愛のムチだと思いなさい。
さて。一瞬で疲れが直ったことにして、ナユタ達は再び巡回を始めた(確かにキャラ使いが荒いなぁ・・・・)。
「この先には何もないようだな」
「そうだね」
この先には長い廊下が続き、いくつか右側に通路が続いてT字路になっているところもある。左手には大きな窓が続き、月明かりが差し込んでいるのでそれほど暗くはない。
不気味など静まり返っているので、足音がやけに響く。なんだか幽霊でも出そうな雰囲気だ。二人は無言のまま進んだ。
それからちょうど二つめのT字路に差し掛かったとき、月が雲に隠れて辺りがスッと暗くなる。その瞬間、ナユタの目が鋭くなった。そしてナユタがT字路を過ぎ去ったあと、ニュッとT字路の影から人の足が伸びる。
そのまま進むナユタ。T字路から姿を現した影は、まるで獲物に襲いかかる獣のごとくナユタに飛びかかった。
「ふふっ、愚かな」
会心の笑みを浮かべて、ナユタは振り返る。
「こっちはすでにお見通し・・・・」
ガツッ!!
鈍い音が辺りに響く。やがて雲が切れ、再び月明かりが差し込んだ。そこには何と・・・・
ナユタの頭に木刀がきれいにヒットしていた。まさに会心の一撃だ。
「やっぱりいつも、こうなるわけね・・・・」
と最後の言葉を残し、ナユタは気絶する。ナユタ、危うし・・・・
ナユタを襲った男は、慎重にナユタの様子をうかがっている。そして完全に気絶していると分かると、フッとため息をついた。
「おい、上手くいったぞ」
男が後ろを振り返り、誰かに声をかける。その声は、紛れもなく若者のものだった。
「さすがね」
すると、通路の影から三つの影が現れる。今度の声は、少女のようだ。
「ねぇ、死んだりなんかしてないわよね・・・・」
別の少女の声が聞こえる。
「大丈夫だって。見てみろよ」
三人はナユタの顔をのぞき込んだ。そして残る一人が、手を振ってみたりしてナユタの反応を確かめる。スカートを履いていることから、三人目も少女だろうか。
反応がないことを確かめると、少女は無言のままコクンと首を縦に振った。
「ほら、心配ないわよ」
「良かったわ」
少女はホッと胸をなで下ろす。
「ダテにいつも鍛えてるわけじゃないからな。こんなことぐらい楽勝さ」
そう言って、男は素振りを始めた。
「サヤカ、あんたって本当に心配性なのね」
「そんなこと言わないでよ、エレウシア。クリスってば加減を知らないんだもん。前だって、体育の授業でナユタに怪我させるし」
「あれはあいつがドジなんだよ」
ナユタに襲いかかったのは、何とクリスであった。少女は、サヤカ、エレウシア、そして最後は当然レアだ。むろん自分たちが襲ったのが、ナユタが変身した姿であるとは知る由もない。
ちなみにクリスがナユタに怪我をさせた事件というのは、体育で剣技の練習をしていたときのことだった。ナユタが木刀を上段に構え、クリスがそこに打ち込みをやっていた。その時クリスがナユタに、靴ひもがほどけてると言ったのだ。ナユタはその冗談を信じ、自分の足元を見た。その時木刀をしたに下ろしてしまったため、予期していなかった(本当だろうか?)クリスは思いっきりナユタの頭に木刀をくらわせてしまったのである。
(何なんだ、この連中は・・・・)
そんな彼らを、側にいたナインテールは注意深く観察していた。もちろんナインテールがサヤカ達を見るのは初めてだし、サヤカ達はナインテールを見ることはできない。
<おいナユタ。さっさと起きないか>
ナインテールはテレパシーで呼びかけるが、答えは返ってこない。
「とにかくさ、早く確かめてみましょうよ」
エレウシアがクリスに声をかける。
「そうだな、目を覚ます前にさっさと確かめるか。シャドウがこのオッサンに変装しているかどうか」
四人はナユタの顔の当たりに集まる。
「ぱっと見た感じじゃ、おかしなところはないな」
クリスがナユタの顔をまじまじと見つめる。
「でも相手は変装のプロよ。簡単にはバレたりしないんじゃない?」
「そうよ、ここは確かな証拠を押さえなくちゃ」
エレウシアはナユタの鼻をつまみ、思いっきり引っ張った。
「鼻は本物みたいね」
「それじゃあ、次は全体的に」
クリスは、頬から顎、おでこや耳までナユタの顔を引っ張る。
「駄目みたいね。それじゃあ、この人は本物ってこと?」
「サヤカの言うとおり、この人は”白”みたいね」
エレウシアは残念といった表情で腕を組む。
「でもよ、こうやって遊ぶのって面白くないか」
クリスは相変わらずナユタの顔を引っ張って遊んでいる。鼻の頭を持ち上げて研ナ○コみたいにしてみたり、頬を口の方に寄せてブサイクな顔にしたりと、顔面体操をする。
「あははは!面白そう」
今度はエレウシアが、極めて偶然にも持っていたペンを取り出す。
「先ずはね〜」
ルンルン気分のエレウシアは、まず手始めにナユタの口の回りにドロボウ髭を書き始めた。ドロボウ髭ってのは、ドリフとかで有名な太くて丸い輪っかのような髭のことね。
「お次は〜」
さらに、頬にヤクザのような切り傷を描く。
「最後に〜」
締めくくりに眉毛をつなげる。どんな顔かは皆さんの想像に頼るしかないが、おそらく爆笑ものの顔が出来上がっていると思う。
「ぎゃはははは!」
エレウシアはお腹を抱え、クリスも笑い転げる。
(わはははは!こいつはお笑いだ)
ナインテールも、ナユタの顔を見て大爆笑していた。
(仕上げにこれをくらわせてやろう。さっきの仕返しだ)
そう言って、ナインテールは鼻くそをほじってナユタの鼻の穴に押し込んだ。
って待てよ・・・・。はたして狐の足で、鼻くそをほじると行った器用なことができるだろうか。う〜ん・・・・、ちょっと無理そうだな〜。まあいいや、そっちの方が面白そうだし。ナインテールは妖怪なんだから、そんなことぐらいお茶の子さいさいだろう。
笑い転げる男女と、狐の妖怪(くどいようだが、ナインテールは誰にも見えない)。さっきまでの静けさが嘘のように、廊下は笑い声に包まれた。
「ちょっと〜、かわいそうじゃない。間違ってたなら早く起こしてあげましょうよ」
さすがはサヤカだ。物語を元に戻してくれる。
「そうだな。一応詫びとくか」
クリスはナユタの上体を起こし、激しく肩を揺さぶった。
「お〜い、オッサン。起きてくれよ」
だが、それでもナユタは起きなかった。
「起きてくれってば〜」
クリスはさらにビンタをくらわす。でもやっぱりナユタは目を覚まさない。
「お〜い!」
クリスはさらに・・・・、ってやりすぎか。いくら何でもこれ以上やったらナユタのファンに怒られそうだな。
「いたたたたた」
ナユタは後頭部を押さえながら目を覚ました。
「あれっ、クリスじゃないか。それにサヤカ達まで。何でみんながこんな所にいるんだい?」
ナユタが不思議そうにクリス達を見回す。
「はぁ?何でオッサンが俺達の名前を知ってるんだ?」
逆に面食らったのはクリス達の方だった。赤の他人が自分たちの名前を知っていたのだから、無理もない。
「えっ!そ、それはつまり・・・・」
ようやくナユタも事態を理解し、何とかその場をやり過ごそうと頭をひねらせる。
「す、推理したんだよ。ぼく・・・・、いや、私は探偵だからね。あはははは」
とナユタは作り笑いを浮かべ、
「君の眼鏡をかけた愛らしい顔、まさに”サヤカ”って感じだ。君のキリッとした眉、いかにも”クリス”って感じだ。君の素晴らしい金髪、まさしく”エレウシア”って感じだ。君の聡明そうな眼、どう考えても”レア”って感じだ」
などと無茶苦茶な理由を並べ立てた。
もちろん、サヤカ達はあやしさ500%といった視線でナユタのことを見ている。
「と、ところで・・・・。何で君たちはこんなところにいるんだい?」
「俺達はエレウシアの友達だよ。エレウシアの屋敷にシャドウが盗みに入るって聞いたからな、友達として助けに来てやったんだ」
クリスは自慢げに話す。
「本当はナユタって子もいるんだけど、どこかに行っちゃって今はいないんです」
「ナユタ・・・・?」
サヤカの言葉にナユタはちょっとビックリした。どうやら自分も誘われてたらしい」
「まあ、あいつはいてもいなくてもいいんだけどな。なんたってドジだから」
「・・・・・・。そうなんだ」
ナユタは苦笑いを浮かべる。
「しかし、何で君たちはわたしを襲ったんだい?」
「なんだか怪しい人だけど、オッサンは大丈夫そうだから教えてやってもいいだろう。レア、頼む」
クリスの言葉に、レアはいつも通り無言で頷く。
「シャドウは、今日この屋敷にやって来た人の中にいます」
「そいつは本当なのか!」
ナユタの絶叫に、レアはただ頷いて答えた。
<どうだいナインテール。僕の直感はやっぱり当たっていたんじゃないか>
ナユタはテレパシーを送って自慢した。
<ふん、どうせオレ様のおかげだろうが>
そう。正しい推理ができたのは、ナインテールが探偵に変身させてあげたためであって、本来のナユタの脳細胞など1ミクロンも働いていない。
「シャドウは、必ずと言っていいほど予告状を出してきました。しかし、予告状を出すことに何のメリットがあるでしょうか。宝物を狙われた者達は、当然ながら警備を固めることになります。考えようによっては、その様な警備をかいくぐって盗みをすることを美徳としているのかも知れません。しかし本当の狙いが宝物にあるとすれば、わざわざ予告状など出す必要はないはずです。だとしたら・・・・」
と、レアには珍しく長い台詞を喋った。
「なるほど、読めてきたぞ」
もちろん、読めてきたのも探偵に変身したからだ。
「そうです。シャドウは予告状を出して、ワザと警備をつけさせたのです。そして自分は、その警備の誰かをすり替わる。シャドウの姿を誰も見たことがないというものこのためなのです。警備達は存在すらしない闇の中の盗賊に気を取られ、その隙にシャドウは宝を盗む。心理的なトリックを使った、意表をついたやり方です」
さすが頭脳明晰な天才少女レア。生みの親である作者の鼻も高い。探偵に変身しているとはいえ、アホなことばかりしているナユタとは天地の差だ。今度はレアを主役にしたサスペンスものを・・・・って、ナユタの主役の座がどんどん脅かされていくじゃん。哀れなやつだ。
「それで、今回もわたしたちの中にシャドウが潜んでいると思ったわけだな。だが残念ながらわたしはシャドウではない。ということは、シャドウは残り三人の内の誰かだな」
と、ナユタは真剣な顔つきで考え始めた。すると、クリスとエレウシア、およびナインテール(本当にくどいようだが、ナインテールの声はナユタ以外には聞こえない)がクスクスと笑い始める。
「ん、なに笑ってるんだい?」
まじめな表情でナユタは訊ねた。
「いえ、何でもないわ。あはははは」
堪えきれなくなったエレウシアは、お腹を抱えて笑い出す。
「何だいったい。人の顔に落書きでも書いてあるのか?」
ナユタは気付いていないが、もちろん二人はその落書きを見て笑っていた。ナユタがまじめな表情をするほど、かえって面白い顔になる。
<ナインテールまでどうして笑ってるのさ?>
<何でもないって、わははははは>
イタズラされていることにすら気付かず笑われるナユタ。本当に哀れだ。
「この人じゃないと分かったけど、これからどうする?」
サヤカがエレウシアに訊ねる。
「たぶんシャドウは男だから、次はコロンボって探偵かバランっていうヤンキーみたいな人ね。面倒臭いからそこのセシルさんにも手伝ってもらって、二人いっぺんに確かめてみましょう」
「そうだな。じゃあオレは、エレウシアとレアと一緒にコロンボの所に行く。サヤカとオッサンは、バランの所に行ってくれ」
クリスは、一人一人指さしながら指示を与えていく。
「いいでしょう。でも、どうやって二人の居場所を探すつもりかな?」
「それはこれに任せてよ」
そう言って、エレウシアは手の平大の水晶を取りだした。
「何だい、それは?」
「この水晶には特殊な魔法がかかっているの。ほら、水晶の中でいくつか点が光っているでしょ」
そう言われてナユタが水晶をのぞき込むと、確かに点が光っている。
「実はお父様があなた達にあげた地図にも魔法がかかっていてね。その地図を持っている人間がどこにいるのか、この水晶で分かる仕掛けになっているわけ」
「へぇ〜、そうだったんだ」
ナユタは地図をしげしげと眺める。彼らがナユタの居場所を分かっていたのも、そのためだったのだ。
「それじゃあ、お互いまたこの場所に戻ってこよう。相手は大盗賊かも知れない。気を付けていこう」
クリスの言葉に全員が頷いた。それから彼らは二手に分かれ、闇の中に飲み込まれていった。
「あ、あの〜・・・・」
サヤカが突然話しかけてきた。
「な、なんだい?」
変身しているため、いつものように気軽に答えることができない。サヤカも初対面の相手のせいか、二人の会話は自然とぎこちなくなっていた。
(まさかぼくがナユタだって、サヤカは思いもしないだろうな・・・・)
サヤカには打ち明けたい気持ちはあったが、それだと自分の借金のことも言わなくてはならなくなる。サヤカには余計な心配はかけたくなかったし、なによりも借金は自分の力で返したかった。
「実はさっき、エレウシアがセシルさんの顔に落書きをしてしまって・・・・」
「それは本当かい?」
ナユタは慌てて側にあった鏡を覗き込んだ。鏡には、眉毛がつながり、ヤクザの傷を付け、ドロボウ髭を生やした自分の顔が映っている。
「エレウシアもヒドイことするなぁ・・・・」
確か前にも、修学旅行で宿屋に泊まっているときに同じ様なことをされたことがある。
「すいません、友達が調子に乗ってしまって」
「ははっ。いいんだよ、いつものことだから」
「いつものこと?」
「ああっ、こっちの話し。気にしないで」
ナユタは笑ってごまかす。
「ちょっといいですか」
サヤカはポケットからハンカチを取りだし、ナユタの顔を拭く。
「すまないね」
「いいえ、これくらい」
ゴシゴシと擦っているうちに、落書きはほとんど消えていった。
「どうだい?」
「まだちょっとこの辺が・・・・」
サヤカは顔を近づけ、しつこく残っているインクを消そうとする。顔を間近で見つめられ、ナユタは何となく息苦しさを覚えた。
(まただ・・・・)
あの時以来、間近でサヤカに見つめられると何となく照れくさくなってしまい、息が詰まってしまう。それがなぜなのか、ナユタにはまだ分からなかった。
「もう大丈夫ですよ」
そう言って、サヤカが顔を離す。その時、ようやく緊張の糸が切れた。まるで全力で走ったあとの疲労感にも似たようなのようなものがどっと身体を突き抜けることが、不思議でたまらなかった。昔はこんなことなかったはずなのに。
「どうもありがとう」
ナユタは気分を切り替え、エレウシアにもらった水晶を見つめる。
この廊下を真っ直ぐ行けばバランがいる。ナユタ自身手荒な真似はしたくなかった。しかし馬鹿正直に調べさせてくれと言ってもバランを警戒させるだけし、バランがシャドウなら逃げられてしまうかも知れない。少々荒っぽいが、クリスのようにいきなり襲いかかって気絶させるしかない。
水晶を見ると、バランはこちらに向かって歩いてくる。ナユタの作戦は、クリスのように物陰から不意打ちをするものであった。
しかし、今回も同じでは読者が飽きてしまう。そこでナユタは、金持ちの屋敷によくある鎧人形の中に隠れることにした。これなら万が一シャドウが反撃してきても防ぐことができる。
「サヤカちゃん、君は遠くで隠れてみてるんだ。そしてもしわたしに何かあったら、クリス君達に知らせてくれ」
「はい、わかりました」
心配そうな顔をしながら、サヤカは遠くの物陰に隠れた。それを確認し、ナユタも鎧人形の中に隠れる。
「しっかし鎧って窮屈だな〜」
ナユタが思っていた以上に、鎧は身体にピッタリだった。胴は何とかなったものの、厚い革靴を履いていては足先が入らない。仕方なくナユタは裸足になった。
<本心としてはバランがシャドウであって欲しいけど、気持ちとしてはシャドウじゃない方がいいな>
ナユタはすぐ側にいるナインテールにテレパシーを送った。捕まえなければ褒美はもらえないことは分かっているが、相手は有名な大盗賊。下手すれば殺されかねない。
<もしシャドウがコロンボなら、クリス達が同じ目に合うんだぞ。それでもいいのか?>
<それもやだよ!>
ナユタの言葉に合わせて、鎧人形がガタガタ揺れる。
<オレ様達はシャドウを捕まえに来たんだろ。だったらバランとやらがシャドウであることを祈るんだ。大丈夫、オレ様がついている限り死なせはしないさ。だが、シャドウを捕まえるのはお前なんだからな。そこまではオレ様も力は貸せん>
<分かったよ。やれるだけやってみる>
廊下の奥からかすかに足音が聞こえてきた。
コツ・・・・コツ・・・・
その足音は、次第にこちらに向かってくる。ナユタの緊張は一気に高まっていった。
コツ・・・・コツ・・・・
今や足音は鉄兜を通しても聞こえてくる。
コツ・・・・コツ・・・・
バランがナユタの目の前を通り過ぎていった。まだ気付いていない。
コツ・・・・コツ・・・・
バランが通り過ぎていった。
(今だ!)
心の中で叫び、ナユタは背後からバランに襲いかかる。
だがその瞬間、突然バランが振り返った。
(気付いてたんだ!)
それでもナユタはみぞおちめがけて拳を振るった。さっきの自分のように、よけられなければ気絶させることができる。
しかし、それがナユタの大きな間違いであった。
「バレバレなんだよ!」
バランはナユタの拳を難なくかわす。勢い余ったナユタは反対側の壁に激突してしまった。
「ぐわっ!」
あまりの衝撃に、ナユタは悲鳴を上げる。
そして壁にぶつかった拍子に、身につけていた鎧がバラバラとあっけないほど簡単に落ちてしまった。
(なんて貧弱な鎧なんだよ〜)
さらに、エレウシアにもらった水晶も落として割ってしまった。
「オレの本当の姿はな、スコーピオン党の頭領バラン。そんなチンケな作戦に引っかかるか!」
スコーピオン党というのは、少年達で構成されているギャング団だ。喧嘩に明け暮れ、独自の護身術を身につけていると聞く。もちろん犯罪にも手を染め、窃盗や強盗、麻薬の密売や、さらにはピンポンダッシュまで。面白い設定が満載の集団である。
(なんでぼくの時だけこうなるわけ・・・・)
げんなりするナユタ。もちろん、物語を盛り上げるためだ。
しかもナユタは眼鏡を落としてしまったために、前がぼやけて見えない。
「めがね、めがね・・・・」
と、横山や○しの眼鏡ギャグをやりながら、ナユタはフラフラと眼鏡を探す。
するとナユタは何かに躓(つまづ)き、角の尖った柱に額を強打させた。
「いっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっった〜!」
ナユタのおでこにはタンコブが出来上がり、見る見るうちに大きくなっていく。
「くそ〜」
痛みを堪えて立ち上がろうとしたとき、今度は同じ角にすねをブチ当てる。いわゆる弁慶の泣き所という場所だ。
「ヒィ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜!」
ナユタはすねを抱えて飛び跳ねる。さらに柱から離れようとしたとき、今度は裸足の小指を角にぶつけた。
「!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!」
誰にも一度は経験あるだろうが、これは痛い。ナユタは声も出せず床の上を転げ回る。
すでに満身創痍のナユタ。バランはまだナユタに触れてもいないんだけどなぁ〜。
<ひとりでそんなコントをやってないでマジメにやらんか!>
そんなナユタに、ナインテールの容赦ない叱咤が飛ぶ。
<ぼくはいたってマジメなんですけど・・・・>
ナユタは何とか眼鏡を探り当て、ようやくかけることができた。バランは腕を組んだまま、薄笑いを浮かべている。
「あんたはセシルって探偵だな。オレにいったい何の用だ?」
「それはその〜・・・・」
ナユタは必死に言い訳を考える。
「そんなことより、君の顔に汚れがついてるぞ。わたしが取ってあげよう」
さっきのサヤカを思い出してひらめいたアイデアだ。汚れを取るといって顔をゴシゴシ擦れば、変装しているかどうか分かるかも知れない。ナユタは愛想笑いを浮かべてバランに近づく。
だがバランも、薄笑いを浮かべたまま後ずさった。
「それより先にオレの質問に答えろ。なんで俺に襲いかかってきた」
(くそ〜、嫌なやつだな〜)
ナユタの顔が引きつる。
「今日この屋敷に来た人間の中に、シャドウが変装している可能性がある」
<おいナユタ、なに馬鹿正直に答えてんだ!>
<まあ見ててよ>
ナユタの顔から愛想笑いが消えている。賭けに出たのだろう。
「どうしてそんなことが分かる?」
バランの問いに、ナユタはレアの推理を一から十まですべて話した。
「それで、オレを確かめようってのか?」
バランの表情にも薄笑いが消え、その目が一層鋭さを増す。
「もし君がシャドウじゃないのなら、協力して欲しい」
「あんたがシャドウかも知れないじゃないか」
「疑っているなら、わたしを調べてもいい」
「もしかしたら、オレはシャドウかも知れないぜ」
「もしわたしが君に殺されたら、わたしの仲間が君を捕まえる」
「断ったら?」
「君がシャドウであると思って捕まえる」
「抵抗したら?」
「力ずくでも捕まえる」
おお、何とも緊迫した展開だ。
「オレの答えは”ノー”だ。あんたの言っていることは可能性にしか過ぎないし、調べられる筋合いもない」
「こっちも手荒な真似はしたくないんだ」
「やるつもりならいいぜ。こっちはダテにスラムで十年以上も暮らしてないんだ」
「どうなっても知らないぞ」
「おもしれえ。どうなるか教えてくれよ」
バランはファイティングポーズを取る。
「なにも分かってないな、君は。取り返しがつかなくなるぞ」
「あんたを取り返しがつかなくさせてやるよ」
ついにバランが襲いかかってきた。
「うわ〜、ちょっと待てくれ!本当に襲いかかってくるな!」
ナユタは慌てて逃げ出す。
<なんだ、虚勢を張ってただけなのか。珍しくかっこよかったと思ったオレ様がアホだった>
<そんなこと言ってないで助けてくれ〜>
<知らん。自分で何とかせい>
<そんな〜>
「待てコラ〜!てめえから挑発してきたんだろうが!」
バランが叫ぶ。満身創痍にも関わらず、ナユタは必死に逃げる。
とその時、踏みつけた床が「カチッ」となった。
「ん、なんだ?」
ナユタが不思議に思っていると、天井の一部が音を立てて開き始め、何やら緑色の液体が降ってきた。いかにも罠が作動しましたよ〜、といった感じだ。
「こんな時に罠かよ〜!」
相変わらず不運なナユタだ。
後ろからはバランに追いかけられ、上からは怪しげな物体Xが降ってくる。ナユタは走った。走って、走って、走って、走って、走って、そして・・・・
ぎりちょんセーフ。液体をかぶる前に、ナユタは何とか通過した。今回もナユタが罠にかかると思った読者は残念でした。
と〜ぜん罠の餌食にはまったのは、ナユタを追いかけていたバランであった。
「うわっ、なんだこれは!」
緑色の液体はネバネバしており、身体にまとわりついてくる。バランは完全に身動きがとれなくなった。
「ラッキー!」
不幸な男であるとばかり思っていたナユタだが、こういうこともたまにはあるんだな。自分から傷だらけになったかと思えば、ただ逃げ回っただけでチンピラの親玉を負かしてしまったナユタ。まったく持って彼の実力は未知数だ。
「セシルさん、大丈夫ですか?」
たまらずサヤカが駆け寄ってくる。
「ああ、大丈夫」
無事であることを示すように、ナユタは笑顔で答えた。
「うお〜!何とかしろ〜!」
完全に動けなくなってしまったバランが喚(わめ)く。
「とりあえず、確認させてもらおう」
シャドウが変装していないかどうか確かめるため、ナユタはバランの顔を調べる。しかし、バランは変装などしていなかった。
「どうやら違ったみたいだな」
「どうします、この人?」
サヤカはナユタに訊ねた。相変わらずバランはわめいている。
「確か女の治安官の人がいたな。あの人にでも引き取ってもらおう」
「気の毒ですが、仕方ありませんね」
「ということは、コロンボがシャドウだったんだな。クリス君達と待ち合わせた場所に戻ろう」
「そうですね。無事に捕まえられてるといいんですが」
後でメルフィーユという女治安官に引き取ってもらうことにして、二人はバランをそのままに待ち合わせ場所に戻る。だがそこで、意外な事実が待っていた。
「コロンボが眠らされていただって!」
クリスからそのことを聞いたとき、ナユタは我が耳を疑った。そして、
「調べてみたんだけど、コロンボは変装なんかしていなかったんだ」
クリスの表情が暗くなる。おそらく、コロンボを眠らせたのはシャドウであろう。
先に待ち合わせ場所にいたクリス達は、てっきりバランがシャドウであると思っていた。しかし、ナユタからバランがシャドウでなかったことを聞いたとき、自分も同じように耳を疑った。
「ちょっと待って。あの二人がシャドウでないとすると、あのメルフィーユっていう女の人がシャドウなわけ?」
エレウシアは信じられないといった顔つきで口を開いた。
「それしか考えられんな」
まさかシャドウが女だったとは、ナユタは夢にも思わなかった。
「まったく、シャドウって盗賊には驚かされるぜばかりだ」
クリスの言うとおり、シャドウは巧みに人間の心理を利用する。恐るべき頭脳を持った盗賊だ。
「エレウシア、いまメルフィールはどこにいますか?」
ナユタは水晶を持つエレウシアに訊ねた。
「ちょっと待って。え〜と・・・・」
エレウシアは水晶をのぞき込む。そしてその表情が、一瞬にして凍り付いた。
「いけない、メルフィーユはお父様の部屋にいるわ!」
水晶の光りが示している点は、紛れもなくゲイルードの部屋だった。
「しまった。やつの狙いは”エルフの涙”だ!」
叫ぶと同時に、ナユタは駆けだした。目指すはゲイルードの部屋。はたしてナユタは間に合うことができるのであろうか・・・・
つづく・・・・