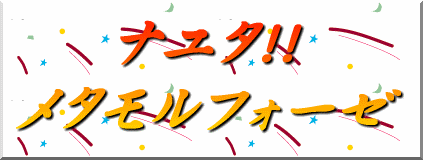
地下室には、一種独特な空気が流れている。階段を一歩下りるごとに、ひんやりと冷たい空気にのって様々な臭いが漂ってくるだろう。
例えば、埃臭さ。例えば、カビ臭さ。またあるいは、木の臭い、皮の臭い、鉄の臭い、何かの塗料の臭い。
まるで洞窟を探検するときみたいにワクワクした気持ちを、別世界の住人達が一斉に包み込む。
その地下室の中を、ランプを片手に一人の男が歩いていた。彼の後ろには、九本の尻尾を持った狐の妖怪が続いている。いまさら紹介するまでもないが、ナユタとナインテールだ。
惜しくも(?)シャドウを目の前で逃してしまったナユタ。今度はシャドウの狙っている”エルフの涙”を先に見つけて、そこで待ちかまえてという魂胆だ。
変身して得た探偵としての直感だけを頼りに、この地下室に”エルフの涙”があるとにらんで、ノコノコとやってきたのだ。
「なんか地下室ってさぁ、いかにも出そうだよね・・・・」
ランプの光りに淡く照らし出されるナユタの表情は、いくぶん不安げだった。わずかな空気の流れを感じたり、小さな物音がする度に、ナユタはビクッと首を動かしていた。
「出るって、まさか妖怪でも出るって言うのか?」
足下の方から、ナインテールの声が聞こえてくる。ナインテールはもともと狐の妖怪なので、暗い中でも夜目(よめ)が効いた。闇の中で、ナインテールの目が小さな光りを発している。
「ふぁ〜あ・・・・」
・・・・と、ナインテールは大きな欠伸(あくび)をかいた。妖怪の割には、夜に弱いようだ。
「ナインテールは恐くないの」
「オレ様は妖怪だぞ。それに九尾の狐っていえば、妖怪最強と呼ばれていてな」
ナインテールは自慢げに語る。真実かどうかは分からないが、某妖怪事典にはそんな風に書いてあった。
「へぇ〜」
それで高飛車で口が悪いのも納得がいくと、ナユタは改めて思った。
「なんだお前、恐いのか?」
「そ、そんなんじゃないよ。僕だって妖怪ぐらいへっちゃらさ」
痛いところを突かれ、声がうわずる。
「・・・・・・」
だがナインテールからは、答えが返ってこなかった。おまけに目の光りも消えている。
「お、おいナインテール。どこに行ったんだよ。冗談だろ?」
ナユタはキョロキョロと辺りを見回す。そして、背後に何者かの気配を感じた。恐る恐る振り返ってみるとそこには・・・・
「っ!!」
悲しげな表情を浮かべる女の顔が・・・・。
「はははっ、どうせナインテールだろ。驚かせようったって、そうはいかないよ」
またナインテールの仕業だろうと、女の顔をペタペタと触る。その顔は、本物さながらに冷たかった。
「ん?どうしたナユタ」
だが足下から、再びナインテールの声が聞こえてくる。ナユタの手は、まだ冷たい顔を触ったままだ。
「あ、あれ。なんでそこにナインテールがいるの。さっきは答えなかったじゃないか。目の光りだってなかったし」
「ああ、すまん。あまりの眠気で、半分寝ておったわい」
眠い目を擦っているのか、目の光りがチカチカする。
「じゃあこれは・・・・?」
ナユタが後ろを振り向いた途端。女の顔はスゥッと消えてしまった。ナユタの表情が恐怖に凍り付く。
「ぎゃあぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!」
ナユタはものすごい勢いで逃げ出してしまった。ナユタの叫び声とともに、ドタバタと物にブチ当たる音が地下室に響く。
静かな地下室は、一転して騒がしくなった。
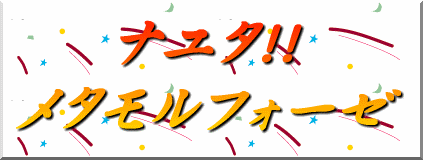
第0話・後編
16
地下には三つの部屋が並んでいた。地図によれば、それぞれの部屋の大きさはほとんど同じである。ナユタは、とりあえず一番手前の扉から手を掛けた。
ガラガラガラ〜
「なんだ。鍵がかかってるのかと思ったけど」
扉はあっけないほど簡単に開いてしまった。
「いい加減、作者もネタを考えるが疲れたんじゃないのか」
などと言いながら、ナインテールは部屋の中に入っていく。
「そうだね。展開も遅いし、そろそろ決着を付けたいんじゃない」
ナインテールに続いたナユタだったが、部屋の中に足を踏み入れた瞬間に部屋のランプが一斉に灯った。
「うわっ」
突然まぶしい光りを浴びたので、一瞬目がくらむ。
ふふふっ、ざま〜みろ。作者を馬鹿にした罰だ。
「なに驚いてるんだ。どうせ魔法か何かだろ」
「わ、分かってるよ」
そう答えるナユタだが、すっかり腰が引けている。
「まださっきのこと気にしてるのかよ。見かけ通り肝っ玉の小さいやつだな」
ナインテールは、わざと”見かけ通り”という言葉を強調する。
「別に驚かせるだけならいいんだけどね。誰かさんみたいに気苦労をかける方が、よっぽどタチが悪いよ。なんかさぁ、座敷わらしみたいなカワイイ妖怪に取り憑いて欲しかったなぁ・・・・」
しみじみと呟きながら、ナユタはため息を一つ付く。
「あん?その誰かさんっ誰だ?」
ナインテールがガンを飛ばす。
「い、いえ。何でもございません」
だからそのガンをやめろ〜と思いつつ、ナユタは苦笑いを浮かべた。
「そんなことより、ほれ。さっさと隠し部屋とやらを見つけんか」
ナインテールは手頃な椅子を見つけると、その上にジャンプして寝そべった。
(まるでこの国の王子みたいじゃないか)
ふとナユタは思った。
このエルドランの国の王子も、非常にわがままだともっぱらの噂になっている。
「はいはい。今からやりますよ」
再びため息を付き、ナユタは部屋の中を見つめる。
「へぇ〜、面白い部屋だな」
ナユタはすぐにその部屋の異様さに気付いた。壁にたくさんに絵が掛けられていたのだ。
「ここは絵を飾っておく部屋なのか?」
ナインテールもキョロキョロと部屋の中を見渡している。
「う〜ん・・・・」
ナユタはいつものように顎に手を当てて考え込む。
「気になるのは、すべて肖像画だってことだね」
ナユタの言うとおり、絵はすべて誰かの肖像画であった。
手に果物の入った籠を持つ女性の絵があるかと思えば、勇ましい老戦士が剣を構えた絵がある。子供がおもちゃを持って遊んでいる絵があると思えば、浅黒く日焼けした大工の男が、木槌を片手に釘を打っている絵まである。
すべての人物がこちらを向いているので、なんだか見つめられているようで薄気味悪い。
「何か絵に規則性でもあるんじゃないのか?」
「規則性って言われてもねぇ・・・・」
描かれている人物は、男もいれば女もいる。子供もいれば、老人までいる。おまけに職業もてんでバラバラだ。
「何とかならないのかよ〜。隠し部屋だとか言い出したのはお前だろ」
とナインテールは呆れ顔をした。
「そんな格好しながら言うなって・・・・」
ナインテールは椅子に寝そべったまま、髭の手入れをしている。
「とにかく、考えにつまったら別の方法を考えるのが鉄則だね。まだ部屋が残っているから、そこを調べてみよう」
「なんだよ〜、また歩くのかよ〜。なんだか疲れて腹が減ってきたぞ」
ナインテールは耳と尻尾を垂らして、やれやれといった感じに深くため息を付いた。
「おいナユタ。オレ様をおぶれ」
ナインテールはジャンプして、ナユタの背中にしがみついた。
「全くしょうがないなぁ〜」
仕方なくナインテールを背負って、ナユタはとなりの部屋に向かった。
ガラガラガラ〜
隣の部屋の扉も簡単に開き、先程と同じように魔法の明かりが灯った。
「なんだぁ〜、この部屋」
部屋に入るなりナインテールが呟いた。
最初の部屋と同様、この部屋も変わっていた。今度はナユタ達を取り囲むように、何体もの彫像が部屋の壁に沿って立っていたのである。
「・・・・・・」
ナユタは難しそうな顔をしながら、彫像を一体一体調べていく。
彫像は、きれいな白い石で出来ていた。表面は、蟻ン子も登れなさそうなほどつるつるしている。
「はっはっは、なんだその顔は」
彫像に顔を近づけていたナユタに、ナインテールは吹き出してしまった。
凹凸(おうとつ)の激しい彫像の表面に、ナユタの歪んだ表情が浮かんでいたのである。真剣な顔でのぞき込んでいただけに、その顔は一層面白い。
「んもぉ〜。人がせっかくマジメに調べてるのに邪魔しないでよ・・・・」
「邪魔とはなんだ。人(←お前は妖怪だろうが)がせっかく場を和ませてやろうと思っているのに。それより、何か分かったのか?」
「まあね。例えばさ、この彫像に見覚えないかい?」
そう言って、ナユタは正面に立っている若い娘の彫像を指さす。
「う〜ん・・・・。こ、これは〜!」
「そう、この彫像は・・・・」
「うなじのところにホクロがあるじゃないか〜!なんてオレ様好みなんだ!」
「あ、あのねぇ〜・・・・」
ナユタが引きつった笑みを浮かべる。
「そうじゃなくてさ〜。この女の人、隣の部屋にあった絵に描かれてた人だよ」
「おお、そういえばそうだな」
彫刻の娘は、隣の部屋で花を売っている絵の娘と瓜二つだったのだ。そればかりではない。描かれていたすべての人物の彫刻が、この部屋にはあったのである。
ただ一つ違うのは、全員なにも持っていないのだ。
「最後の部屋に行ってみよう。僕の考えが正しかった、面白いものが見れると思うよ」
「面白いもの?また体を張ったコントでも見せてくれるのか?」
「なんでさ〜。まぁ、見れば分かるよ」
何か確信を得たような表情で、ナユタは残る最後の部屋に入っていった。
「やっぱりだな」
ナユタはニタリと笑う。
最後の部屋は、まるで物置のようにいろいろな物が乱雑に置かれていた。剣にかなづち。子供のおもちゃがあるかと思えば、果物の入った籠まで。
「つまり、こういうことさ。二番目に入った部屋の彫像を、始めの部屋にあった絵と同じようにすればいいんだよ。例えば、老戦士の彫像には、あそこにある剣を持たせればいいんだ」
ナユタが指さす先には、絵にあった剣と全く同じ物が立てかけてあった。もちろん、残りの物もすべて混じっている。
「たぶんすべての彫像を絵と同じようにすれば、何かが起こるはずだよ」
「なるほどな。所詮お笑い作家の考える仕掛けなんて、そんなもんか・・・・」
お前が偉そうに言うな。
「よし、彫像があった部屋に戻ろう」
「ん、なんでだ?この部屋にある物を持って行くんじゃないのか?」
「僕にいい考えがあるんだ」
ナユタは親指を立て、ニッコリと白い歯をこぼす。
さて、二人はまた彫刻の部屋に戻ってきた。ナユタはいったい何をおっ始めようというのだろうか。
「ナインテール、ぼくを魔法使いに変身させてくれないか」
「なんでまた魔法使いなんかに?」
怪訝そうにナインテールが訊ねる。
「もちろん、魔法を使うためさ。いちいち運んでたら時間がかかるだろ。だから魔法を使って、パ〜ッと一気に片付けるのさ」
「おおっ。そいつはグッドアイデアだな。見た目にもカッコイイし」
ナインテールの判断基準は、カッコイイかどうかなのだろうか・・・・。
「よし、いくぞ」
ナインテールの両目が赤く光った途端、ナユタは黄金色に近い茶色のローブを着た魔導師に変身した。これまたナユタと正反対で、いかにも頭が良さそうな顔をしている。
「ねぇ〜、このローブの色を何とかしてくれない・・・・」
身に付けているローブを見て、ナユタは渋い表情だ。茶色いローブを着た魔導師なんて、ファンタジー界でも前代未聞である。
「ふふふ、名付けて”ナインテール・ブラウン”だ。今年はこれが来るぜ」
この妖怪の美的感覚はどうなっているんだろうか・・・・。
「まぁなんでもいいや。さっそく呪文を唱えよう」
ナユタは両手を前につきだし、精神を集中させる。
「&%$$&%&〜¥*+#*@@・・・・」
ナユタはわけの分からない呪文をつむぎ始めた。ナユタの顔も真剣そのものだ。不思議なもので、途端に部屋の空気が重く感じられ始める。
「おお、すごいなナユタ。いきなり知りもしないはずの魔法が使えるなんて」
「・・・・・・。いや、適当なんだけど・・・・」
「・・・・・・」
ガビ〜ン
せっかくの緊張感もぶちこわしだ・・・・。
「適当で上手くいくわけないだろ、どアホっ!」
でも上手くいっちゃうんだな〜、これが。
適当に呪文を唱えたはずなのに、なぜか隣の部屋から次から次に物が飛んできた。
「へへっ。どうだい、ぼくの才能は」
誇らしげに鼻の下をこすっているのはいいが、みんなお前の方に飛んできているぞ。
「うわっ!」
大きなハンマーが、ナユタの顔面の横を擦り抜ける。ナインテールのところには、コマがものすごい早さで回転しながら向かってきた。
「おい、どうなってんだナユタ!なんとかしろ」
「え、え〜と。^*&$#@・}〜「;&’%{}>@:=*・・・・」
またもや適当に呪文を唱えたが、当然ながら収まるはずない。今度は、リンゴだのオレンジだのスイカだのレモンだのパイナップルだのマンゴ−だの、果物が一斉に襲いかかってきた。
「この役立たずがっ!肝心なときに使えなくてどうする」
「ゴメ〜ン」
だが不思議なもので、ナユタ達を通り過ぎるとそれぞれきちんと彫像のところにおさまる。それもピッタリ絵の通りにだ。相変わらずナユタの能力は未知数だ。
さて果物の次は、花売りの少女が持っていた花だ。ここは面白くするために、バラの花を売っていたことにしよう。名付けて”ローズ・タイフーン”だ。トゲトゲ攻撃に耐えられるかな?
「とりゃ〜」
「おりゃ〜」
二人は紙一重にかわしていく。
う〜ん、なかなかやるなぁ。それでは次だ。なぜかタンスのコレクターがいたことにして、ナユタの身長を越えるタンスが次々と飛んできた!
「無茶言うなっ!」
ナインテールが抗議の声を上げる。恨むんなら、この惨劇を引き起こしたナユタを恨むんだな。
タンスが襲って来るという想像を超える世界の中、それでも二人は次々とタンスをかわしていった。
むむっ、そっちがその気なら最終兵器だ。何本もの剣が、刀身をきらめかせて向かっていく。題して”剣の舞”だ。
「おいっ、剣は一本だけじゃないのか!」
ナインテールが叫ぶ。
はて、そうだったかな(と、とぼけて)?
「うわあああ!」
二人の脇を、まるで流星のように剣が過ぎていく。どうやら無事だったようだ。よかったよかった。
「何とか終わったみたいだね」
ナユタは額の冷や汗を拭う。まるで嵐が過ぎ去ったように、部屋は静けさを取り戻した。
そしてナユタのにらんだ通り、部屋の壁の一部が「ズズズズッ」と開いていく。
「おお、本当に隠し部屋があったんだな」
「よし、行こう」
二人の姿が、隠し部屋の闇の中に消えていった。
17
ネットリとした空気が、締め付けるように身体にまとわりつく。一体どれぐらい時が止まっていたのだろうか。封印を解かれた重苦しい空気達が、不気味にナユタ達を迎え入れた。
「どこまで続いているんだろう?」
ナユタは、髪の毛に絡まった蜘蛛の巣を取り払う。
狭い通路は、一層恐怖を高めた。まるで、このまま黄泉の国にでも繋がっていそうだ。自分たちを照らし出すランプの灯火(ともしび)と、はるか後方に小さく見える部屋の明かりだけが救いだった。
「だが、いかにも何かありそうな感じじゃないか」
先を歩くナインテールの目が、暗闇の中でキョロキョロと動く。
「何か見えない?」
「いや、何も見えんな」
ナインテールの視界の先には、通路が続いているだけだった。
それから二人は、無言のまま歩き続けた。そして後ろに見えていた部屋の明かりがいよいよ見えなくなって来たとき、ナインテールが何かを発見した。
「ん?あれは・・・・」
ナインテールが遠くの方を覗いている。
「どうしたの?」
「金庫らしきものが見えるな」
ナインテールは急に走り出した。
「ちょっと待ってってば。置いていかないでよ」
目の光りだけを頼りに、ナユタはナインテールの後を追いかける。
やがてナインテールが立ち止まると、ランプの明かりの中にいかにも古そうな金庫が姿を現した。
「本当にこの中にあるのか?ずいぶん古そうだが・・・・」
ナインテールは金庫を見回した。上にはかなり埃が溜まっている。
「調べてみれば分かるさ」
ナユタはポケットから手袋を取り出すと、さっそく金庫を調べ始めた。ちなみに、すでにナユタは探偵スタイルに戻っている。
扉の上に方には、小さい穴がいくつか開いていた。そして中央部には金でできた取っ手あり、その下に鍵穴がある。
「たぶん、この鍵を開ければいいんだよ」
そんなもん誰にだって分かる。
「開けるったって、そんなことお前に出来るのかよ?」
「何のためにナインテールがいるのさ。ぼくを盗賊に変身してくれればいいんだよ」
「おお、相変わらず鋭いな。それでは早速」
闇の中でナインテールの目が紅く光る。探偵スタイルのナユタは、一瞬で盗賊に変身した。
「今度はまともそうだね」
念のためファッションを調べる。しかし今回は無難に、盗賊らしく身軽な格好であった。たった一つを除いては。・・・・
「あのさぁ〜。このヒラヒラに意味はあるの?」
ナユタは、首に巻かれたマフラーを指さした。しかも例によって、”ナインテール・ブラウン”とかいう趣味の悪い色だ。
「チャームポイントだ」
ナインテールはいたって真面目に答える。
「いるか〜、そんなもん!」
「そんなもんとは何だ!人(←だから、お前は妖怪だって)がせっかく考えてやったのに。オラッ、さっさと始めろ」
「はいはい・・・・」
まるで先輩に威圧された新入部員のように、しぶしぶナユタは作業を始める。
といっても、針金を取りだしてただガチャガチャやっているだけだ。普通の盗賊なら、金庫に耳を当てたりとかするもんだが。
「そんなんで大丈夫なのか?」
「盗賊とかが登場する小説なら、こうやってガチャガチャやってると・・・・」
カチャリ・・・・
「開いた〜!」
開けた当の本人が一番驚いている。
「なんてマグレな・・・・」
「マグレじゃないさ、これもぼくの実力だよ」
ナユタは針金を振り回しながら、得意げに答える。
「よし、早速開けてみろ」
「オッケ〜」
ついに本物の”エルフの涙”と対面できると思うと、自然に笑みがこぼれる。はやる気持ちを抑え、ナユタは取っ手に手をかけて回そうとした。
「あ、あれ?」
だが取っ手は、どんなに力を込めても回らない。
「どうしたんだ?さっさと開けろよ」
「それがさ、いっくら回しても開かないんだよ・・・・」
ナユタは力一杯に取っ手を回す。
「も、もしかして・・・・」
引きつった笑みを浮かべながら、ナユタが振り返る。
「なんだ?」
「さっきは鍵を開けたんじゃなくて、閉めちゃったのかも・・・・」
ナユタは鍵穴を指さす。
「つまりこうか。この金庫は始めから開いていて、お前がご丁寧にも鍵を閉めちまったと?」
「そうなるね・・・・あはははっ」
「笑ってごまかすな、どアホっ!」
ナインテールがつばを飛ばしながら激怒した。
「どうにかしろ!」
「どうにかって言われてもねぇ・・・・。どうせメチャクチャやったって開かないだろうし・・・・」
ナユタと作者は、「う〜ん」と唸って考え込んだ。
何かいい手はないものかと、金庫をじっと見つめる。すると視線が、扉の上の方に開いている小さな穴に止まった。
(あの穴・・・・)
ここでナユタと作者は、ピ〜ンときた。
「ねぇ、ナインテール。ぼくを人間以外にも変身させることは出来るよね?」
「当たり前だ。オレ様の辞書に不可能という文字はない」
「じゃあさ、ぼくを”か”に変身させてよ」
「”か”って、飛んでる蚊のことか?」
「そう。その蚊だよ、モスキートの」
何で英語なんだ?
「蚊に変身してちっちゃくなれば、あの穴から金庫に入れる。そして金庫の中に入ったら、また元に戻してくれればいいんだ」
「おお、なるほど。そいつは言い考えだな」
早速ナインテールは、ナユタを蚊に変身させた。
<じゃあ中に入ったらまたよろしくね>
ナインテールにテレパシーを送り、ナユタは扉の穴を通って見事に金庫の中へ入った。
<いいよ、ナインテール>
ナユタの合図に従って、ナインテールの目が再び紅く光った。すると、探偵姿のナユタが姿を現す。完璧な作戦だ。
<おい、ナユタ。”エルフの涙”はちゃんとあるのか?>
<ああ、バッチリだよ>
金庫の奥には、確かに水晶のような固い感触があった。
<よし、ここからが本番だ。ぼくは金庫の中に隠れているから、ナインテールは外でシャドウが来るかどうか見張っていてくれないか>
ナインテールはシャドウには見えないし、おまけに夜目が効く。まさに適役というわけだ。
<分かった、任せておけ>
果てさて、この作戦はうまくいくのだろうか・・・・。
18
一体どれほど時間がたったのだろうか。暗闇の中では、時間の感覚が全くなくなってしまう。ほんの数分しか経っていないのか、それとも、もう朝を迎えてしまったのか。
ナユタは金庫の中で、胡座(あぐら)をかいていた。だがそれでも、少し腰を浮かせれば天井に頭をぶつけてしまう。そして両手を広げれば、簡単に両端に届いてしまった。
暗く狭い金庫の中にいるのは、それだけで言いしれぬ恐怖を受ける。
<ナインテール、まだシャドウは来ない?>
ナユタは不安げにテレパシーを送る。唯一の心のよりどころが、外にナインテールがいることだった。
<いや、まだだな>
ナインテールから答えが返ってくる。例えどんな答えでも、ナインテールが答えてくれるだけでナユタは緊張感から解放された。
この作戦は、一種の賭だった。シャドウがここに気付くかも、そのシャドウを捕まえられるかも、ナユタには分からない。もしかしたら、もうクリス達が捕まえている可能性だってある。
だからこそ、早く来て欲しかった。この恐怖感に、いつまで耐えていられるか分からない。こんな狭苦しい場所にいつまでもいたら、しまいには窒息してしまいそうだ。
「げほっ、げほっ」
そんなことを考え始めた途端、本当に息苦しく感じ始めた。
「くそっ」
恐怖、不安、焦り。意識し始めると、一気に襲いかかってくる。
<ナインテール・・・・>
別に用はなかった。とにかくナインテールの声が聞きたかった。
<・・・・・・>
だが、ナインテールの声は返ってこない。
<ナインテールっ!>
<なんだ?・・・・・・むしゃむしゃ>
<なんだぁ〜。いるならすぐに答えてよ>
安堵のためか、緊張していた全身から力が抜ける。
<ああ、すまんな。むしゃむしゃ・・・・>
<ん、なんか食べてるのかい?>
何かを頬張っているような話し方に、ナユタは引っかかるものを感じた。
<ちょっと腹が減ったからな。隣の倉庫のような部屋に行って、干し芋を失敬してきたんだ>
<失敬してきたって、いつ行って来たんだよ。さっきまではずっと話してたじゃないか?>
そう。金庫の前にいるはずのナインテールと、ナユタはずっとテレパシーで喋っていたのだ。
<テレパシーはどこにいても通じる>
何だって、とナユタは心の中で思った。
<じゃあ、今までずっと隣の部屋にいたの?>
<ああ、なかなか食い物が見つからなくてな。苦労したよ>
<・・・・・・>
ナユタの額に、みるみる青筋が立っていく。
<この馬鹿ギツネ〜!>
ナユタは、金庫の壁を足でガツッと蹴飛ばした。
もしシャドウが来たらどうなっていただろうか。まだ来ていないと答えていたのも、すべて適当だったことになる。
さらに腹立たしいことは、てっきりすぐ側にいるものだと思ってとても心強かったことだ。それが、本当は隣の部屋で食べ物を探していたとは・・・・。
だが何の考えも無しに金庫を蹴飛ばすナユタも馬鹿だ。
「いてっ!」
靴を履いているとはいえ、鉄の金庫を蹴ったら痛いに決まっている。あまりの痛さに腰を浮かしたら、今度は天井に頭を思いっきりぶつけた。
「ぎゃあっ!」
頭に手をもっていこうとしたら、肘を壁にぶつけた。腕がビリビリと痺れる。
「ちくしょう・・・・」
<なんだ、食べられなくて怒ってるのか?>
<そんなわけないだろ〜!>
<まぁいいじゃないか、シャドウは来なかったんだから。はぁ〜、食った食った>
どこがいいというのだろうか。責任など、この妖怪は微塵も感じていないようだ。
<今度こそちゃんと見張っていてよ>
<わ〜てるよ。オレ様が見張っていてやるんだ、へっちゃらだって>
なんて説得力のない言葉だろうか。
「はぁ〜・・・・」
なんだか、ため息をもらすのが癖になってきたみたいだ。ナインテールと一緒にいると、本当に気苦労が耐えない。
(まったくもう・・・・)
そう心の中で呟きながらも、ナユタはうっすらを笑みを浮かべる。不思議なことに、ナインテールと言い争ったことで恐怖心は完全に吹き飛んでしまった。複雑な気分だ。
悩まされることは多いが、ナインテールがいてくれて本当に助かっていると思っている。今回も結局は、ナインテールに感謝をしなければいけないだろう。
そんなことを考えていると、ふと変な臭いが鼻についた。
(ん、何だこの臭い?)
ナユタは、クンクンと鼻を鳴らして嗅いでみた。
<ねぇ、ナインテール。何か変な臭いがしない?>
動物のなら鼻が利くと思い、ナインテールに訊ねてみる。
<な、なんだと?>
なんだか驚いたような答えが返ってきた。
<何か変な臭いがするんだよ。これって確か・・・・>
<お、オレ様は何にも知らないぞ。変な臭いなんかするわけないだろ!>
<あ〜っ!!!>
ナユタは鼻を押さえながら叫ぶ。
<ナインテール、オナラしただろっ!>
金庫の中に流れ込んできたのは、あの独特な臭いだった。
<オ、オレ様がそんなことするわけないだろ。どアホっ!>
<く、くさ〜!>
<臭いって言うなっ!オレ様のイメージが壊れるだろうが!>
<何でこんなところでオナラをするんだ〜>
一瞬でも感謝しようと思った自分が馬鹿だったと、ナユタは改めて後悔する。
<なんて臭さだ〜。こんな臭いは今まで嗅いだことない>
ナユタはわざと大げさに言う。さっきのお返しだ。
<う、うるさいわいっ!・・・・んん?>
<し、死ぬ〜。窒息しそうだ〜>
金庫の中のナユタは、声を押し殺して腹を抱えていた。いつも偉そうだったナインテールの狼狽している様子が、たまらなく可笑しい。
<ぎゃあっ!>
<ふふふふふ・・・・、えっ!?>
突然の叫び声に、ナユタは我に返った。
<ねえ、どうしたんだよナインテール?>
<・・・・・・>
<どうしたんだ、ナインテールっ!>
ナユタは慌てて小さい穴から外を覗こうとした。だがその時、強烈な光りが穴から差し込んでくる。
(まさか・・・・)
ナユタはその光りから逃れるように、慌てて隅に身を寄せた。それと共に、ガチャガチャと金属音が聞こえてくる。
(シャドウが来たのか?)
ナユタの心臓の鼓動が、一気にそのペースを早める。
不意に、穴から射し込む光がさえぎられた。その瞬間、ナユタは呼吸さえも止めてじっと身を固める。いや、正確には固まってしまったという方が正しいだろう。
小さな穴の向こうからでも感じられる、身を凍らせるような視線。その視線がこの金庫の中を漂っているのが、肌で感じられる。見た者を石に変えてしまうという、メデューサの伝説がふと脳裏を横切った。
やがて影がスゥッと横に移動し、再び穴から明かりが差し込む。呪縛から解放され、冷や汗と共に全身から力が抜けていった。だが、安息は長く続かなかった。
カチャリ・・・・
鍵が開いた音だ。
(どうすればいいんだっ!)
この時になって、初めてナユタは作戦をまるで考えていなかったことに気付いた。
シャドウが扉を開けた瞬間に襲いかかれば、確かに不意は討てるだろう。だがそれから、たった一人でどうやってシャドウを捕らえるのか。本物の盗賊を相手に、こちらは丸腰の探偵だ。
(どうすれば・・・・)
ナユタの頭の中では、この言葉が繰り返されるだけであった。
扉がゆっくりと開いていく。じわじわとナユタの方に迫ってくる外の明かりは、灼熱の溶岩のごとくだ。その光りを浴びたら、二度と助からないような。
(ええいっ!)
そんな中へ、ナユタは目をつぶりながら勇気を振り絞って身体ごと飛びこんだ。
「うわああああああ!」
外に飛び出した刹那、肩に何者かにぶつかった。短い悲鳴らしきものが聞こえる。ナユタはそれを離すまいと、無我夢中でしがみついた。
ドサッと、両者はもつれ合いながら倒れた。ランプがガシャンと音を立てて、相手の顔の近くに落ちる。
「だああああああっ!」
馬乗りになる格好になったナユタは、考えるよりも早く行動していた。気絶させるべく、拳を振り下ろそうとしていたのである。
「っ!?」
だがランプの横にあった顔は、シャドウとはまるで別人だった。ナユタはすんでの所で拳を止める。
「あなたは・・・・」
そこにあったのは、骸骨のようにやせ細った顔だった。暗い中で見ると、本当に骸骨男が現れたのではないと思うほどだ。
「あなたは確か執事さんでしたよね?」
「は、はい・・・・」
ナユタが昔からよく知っている執事の老人だ。頭は見事に真っ白になっており、顔も異常に白い。間違ってもフランケン(執事)ではない。
「すいません、いきなり驚かせてしまって」
老人の上に馬乗りになっていることに気付き、ナユタは慌てて骨ジイさん(執事)の身体を起こしてやる。
「一体こんなところで何をやってるんですか?」
ナユタは床に落ちたランプを拾い上げ、骨ジイさん(執事)に手渡した。
「それは私が聞きたいですよ。地下室の明かりがついているかと思ったら、隠し部屋まで開いているじゃありませんか。気になって金庫を開けてみたら、いきなりあなたが飛び出してくる始末ですし」
骨ジイさん(執事)は、ポンポンとズボンに付いた埃を払う。
「実は・・・・」
ナユタは、骨ジイさん(執事)に自分の作戦を打ち明けた。
「シャドウを捕まえるために?またずいぶんとおかしな場所に隠れたものですな」
「でもすごいでしょ、シャドウより先に本物の”エルフの涙”を見つけてしまうなんて」
ナユタの思った通り、金庫の奥には緑色をしたダイヤがあった。ランプの光が当たって、キラキラと鮮やかに輝いている。
「セシルさん、まことにお気の毒ですが・・・・」
「なんですか?」
「実はあれも偽物なんです」
「ええっ!?」
ナユタは言葉を失う。
「あのダイヤは、本物の”エルフの涙”ではないのです。ご主人様に言い使って私がここに置きましたから、間違いありません」
「では、本物の”エルフの涙”は・・・・?」
頭の中が真っ白になってしまったのか、ナユタの目は完全に焦点が定まっていない。
「それは、ご主人様にしか分かりません」
「そうなんですか・・・・」
ナユタはがっくりと肩を下ろす。
「分かりました。先に上がっていてください。わたしもすぐに上がります」
「そうですか。シャドウはまだ捕まっていないようです。よろしくお願いします」
執事らしく丁寧に頭を下げ、骨ジイさん(執事)は地下室に戻っていった。
「おい、ナインテール」
骨ジイさん(執事)の姿が完全に消えるのを待ってから、ナユタはナインテールに声をかけた。よほど驚いたのか、完全に白目をむいて気絶している。
「しょうがないな・・・・」
ナインテールが気絶してしまったこと、そして何より、ようやく見つけたはずの”エルフの涙”がまたしても偽物だたことに、ナユタはひどく落胆した。
唯一の救いは、まだシャドウが捕まっていないと言うことだろうか。
「一体どこに”本物のエルフ”の涙はあるんだ・・・・」
そしてシャドウはどこにいるのか。重い気持ちを抱えながら、ナユタは気絶したナインテールを肩に担ぐ。
19
窓の側に腰掛け、サヤカは外の景色を眺めていた。いつもは艶のある黒髪は、すこし蒼みがかっている。月明かりを反射する眼鏡の奥から、サヤカの瞳は街並みに向けられていた。
三階にあるゲイルードの寝室からは、街並みだけでなく遠くに連なる山脈の影まで見ることができる。この屋敷のなかでも、おそらく最も景色がいい場所なのだろう。
街の中には、チラホラと明かりが見える。まるでそこに海があって、夜空に点々と浮かぶ星を映し出しているみたいだ。
酒場から漏れる明かりだろうか。寝静まった街の中にも、人々の息吹はしっかりと感じられる。
それはこの屋敷も同じだった。この静かな闇の中に、だが確実にシャドウは潜んでいた。いつもと同じような夜なのに、眠気よりも緊張感の方がはるかに勝っていた。
「もうこんな時間になるのね」
外の景色を眺めていたサヤカが呟く。彼女の視線の先には、街でも有名な時計台があった。
自分の屋敷の中に時計台など立てたのは、もちろんゲイルードが初めてだった。それも自分だけのためではなく街の人々のために立てたというのだから、彼の評判はすこぶるいい。
すでに時計の針は深夜をずいぶん回っている。
「いろいろあったら、なんだかアッという間ね」
ベットに眠るゲイルードの傍らに座るエレウシアが答えた。
「クリス達、シャドウを捕まえてくれたかしら・・・・」
サヤカは、視線を時計台から部屋の中に移す。
エレウシアは、心配そうな表情でゲイルードの顔をのぞき込んでいた。ゲイルードは一向に目覚める気配はない。ただ、胸がゆっくり上下しているので眠っていることは確かのようだ。
「何かあったら、きっとすぐに知らせてくれるわよ。クリスを信じましょう」
今のエレウシアには、クリス達がシャドウを捕まえてくれるのを祈るしかできなかった。
「クリス達も無事ならいいけど・・・・」
まず何よりも不安が浮かんでしまう。サヤカのいつもの癖だった。
「心配ばかりしてたってしょうがないわよ。あいつは骨を折ったってヘ〜キな顔してるから。それにあいつがやられたら、このあたしがシャドウをフライパンでぶん殴ってやるわ」
エレウシアはハァ〜っと両手に息を吹きかけて、思いっきりスイングする仕草をした。
「ふふ・・・・。そうね」
サヤカは笑顔をこぼし、再び視線を外に向ける。その先には、銀色の丸い満月があった。
「神様・・・・、お願いします」
サヤカの姿は、さながら祈りを捧げる巫女のよう。
一方その頃、エレウシアの隣りに座っていたレアは、じっとゲイルードの館の地図だけを見つめていた。
「レア。いつまでもそんな難しい顔して考えてなくてもいいわよ」
ゲイルードをこの部屋に運んできてからずっと、レアは険しい顔をしながら地図とにらめっこをしている。普段の物静かなレアからは想像もできないほど、その表情には鬼気迫るものがあった。
「でも・・・・」
自分の考えた作戦でゲイルードを危険な目に合わせたことに、さらにそれでもシャドウを捕まえられなかったことに、レアは重い責任を感じていた。
「別にレアのせいじゃないって。そんなに気にすることないわよ」
だがそれでも、レアは地図から目を離さない。
「なにか、手がかりになるようなことを知らないかしら?」
「手がかりねぇ・・・・」
エレウシアはポリポリと頭をかいて考えるが、本物の”エルフの涙”に関しては自分さえも何も聞かされていない。
「なんでもいい、何か言っていなかった」
「う〜ん・・・・」
すがりつくようなレアの視線に、エレウシアも記憶の糸をたぐり寄せる。
「お父様が初めて”エルフの涙”を見せてくれたとき、わたしにこんなことを言ってたわ。”エルフの涙”は、万人のために財宝。だから、すべての人にこれを見せたいって」
「すべての人に、見せたい・・・・」
レアの口から、かすかにそんな言葉が漏れる。
「まぁ、あれも結局偽物だったわけだし。自分の娘にも偽物を見せるなんて、我ながら恐れ入る父親だわ」
そう言ってエレウシアは肩をすくめた。
ガタッ!
突然レアがものすごい勢いで立ち上がる。その拍子に、座っていた椅子が横倒しになった。
「ど、どうしたのよ・・・・」
エレウシアが訊ねる。サヤカも、驚いたような表情でレアの方を見ていた。
レアは大きく目を見開いて、地図の上のある一点を見つめている。
「分かったわ。本物の”エルフの涙”が、どこにあるかが」
「本当っ!」
サヤカが飛び上がって喜んだ。だがゲイルードがそばで寝ていることに気付き、顔を赤くしながら口を押さえる。
「行きましょ」
先程までとはうって変わり、レアの目には闘志がみなぎっていた。
「そうね、やっぱり私たちがシャドウを捕まえてやるのよ」
エレウシアは拳をぎゅっと握る。サヤカも力強く頷いた。
「お父様、ちょっと待っててね」
簡単な用事でも済ませてくるような言い方で、エレウシアはゲイルードにしばしの別れを告げた。
屋根の上を、滑るように動く影が一つ。身をかがめて足音一つ立てない姿は、さながら獣だ。
(さすが、大富豪といったところね)
シャドウは、額の汗を拭った。飛び散った滴が、闇の中でキラキラと光る。
これだけ苦労したのは久しぶりだった。
ゲイルードを眠らせる瞬間、彼は短剣を抜こうとしていた。反応していた証拠だ。もう少し反応が早かったら、自分の身が危なかったかも知れない。
(まさか偽物を用意しておくとは・・・・)
そして、裏をかかれるとも思わなかった。ゲイルードの部屋で”エルフの涙”を見つけた瞬間、完全に成功を確信した。だが心の底からわき起こってきた、言いしれぬ不安感。盗賊としての第六感が、自分に警告を与えた。
あの時もう一度”エルフの涙”をじっくり見つめ直したのは、今にして思えば幸運だった。そして偽物だと分かった瞬間、あまり悔しさにダイヤをたたきつけた。
(でも、もっと悔しいのは・・・・)
何よりもセシルとかいう探偵に自分の姿を見られたのは屈辱だった。まさか上の階から飛び降りてこようとは、誰が予想できようか。
「チッ」
小さく舌打ちする。盗みの途中で初めて感じた胸騒ぎ。本物の”エルフの涙”がある場所は、だいたい分かった。今はそこを目指している。
だが・・・・。
「ふっ、盗みにスリルは付き物よ」
そういって、シャドウは無理矢理自分を納得させた。いつもの自分なら、そんなことなど絶対に考えたりはしないだろう。いつしか抱いてしまった、盗みという名の魅力。
「でも、慎重さを失ってはいけない」
改めて自分に言い聞かせた。スリルは付き物だが、敢えて味わう必要はない。
「今日はこいつの出番が多そうね」
シャドウは頼りにしてきた自分の武器を取りだした。闇の中では目にも見えないほどの細さは、髪の毛を連想させる。確かめるようにクルクルと回すたびに、意外にも大きな光りを発した。
「”エルフの涙”は、わたしの物・・・・」
シャドウは再び身を低くし、闇の中にとけ込んでいった。その先には、満月を貫くようにそびえる一つの塔があった。
「お〜い・・・・」
一方その頃。
地下室から上がってきたナユタは、館の中をトボトボと歩いていた。背中に担いでいるナインテールは、いぜん気絶したままだ。
「ナインテール、目を覚ましてよ」
いい加減しょって歩くのも疲れたので、ナユタはナインテールを床の上に下ろす。
「ねぇ、ナインテールったらぁ」
何度もナインテールの身体を揺さぶるが、一向に反応がない。
「まったく、しょうがないなぁ・・・・」
ナユタはため息をつく。すると気を失っているナインテールを見て、ナユタはあることをひらめいた。
「そう言えばさっき(中編)、僕が気絶しているときに鼻くそを入れられたよなぁ・・・・」
ナユタが、クリス達に襲われたときのことだ。
「ふっふっふ、チャ〜ンス」
ナユタの目が、キラ〜ンと光る。
ナユタは鼻をほじり、ナインテールの鼻にゆっくりと鼻くそを近づけていった。
「さっきのお返しだ〜」
鼻くそが、ナインテールの鼻に迫る。
パチッ
「えっ!?」
ナユタは、ビクッと腕を止めた。突然なインテールが目を覚ましたのだ。
「何だ、その手は?」
ナインテールは、ギロッとナユタの手を見つめている。
「あ、いや。これは・・・・」
「その鼻くそをど〜するつもりだったのかねぇ、あ〜ん?」
ナインテールは、まるでヤクザのように絡む。
「さ、先程頂いた鼻くそをお返ししようと・・・・」
「ほぉ〜、そいつはどうもご丁寧に」
「い、いえ〜。それほどでも・・・・」
「じゃあ何でも止まってるんだよ、あ〜ん?」
「い、いや。だから・・・・」
「返してくれるんじゃないのぉ〜?」
「そう思ったんだけど・・・・」
「いいんだよ〜、別にぃ・・・・」
表情は笑いながらも、その眼はやれるもんならやってみろとでも言いたけだ。
(嫌なやつだなぁ・・・・)
「すいません、僕が悪かったです」
しぶしぶ罪を認め、ナユタは土下座して謝る。
「ふん、分かればよろしい」
(このぉ・・・・)
そもそも気絶なんかするから悪いのだと、ナユタは心の中で悪態をついた。
(まてよ、ナインテールが気絶したのは・・・・)
さあ、反撃の始まりだ。
「そう言えばナインテール。君はどうして気絶したのかなぁ〜?」
「あん?そんなもん知るか」
「ひょっとしてぇ、あの骸骨男みたいな執事さんを見て驚いたんじゃないのぉ?」
「そっ、それは・・・・」
「君さぁ、恐くないって言ってたよねぇ?」
「そんなことっ!」
「しかも君は妖怪だよねぇ。妖怪が普通の人間に驚くなんて聞いたことないなぁ」
「あっ、あれはいきなり現れたから」
「じゃあ認めるんだねぇ、ビックリして気絶したってぇ」
「うぅ・・・・」
「ねえったらぁ・・・・」
まるで蛇のようなしつこさだ。
「あっ、シャドウだっ!」
ナインテールはナユタの後方を指さす。
「はっはっは、どうせ嘘でしょ。その手には乗らないよ」
持ち前の勘の鋭さ(といっても変身したから得られたのであるが)のおかげで、ナユタは一笑に付した。普段のナユタならいとも簡単に引っかかっていただろう。
「本当だ。いま向こうの屋根の上で光る物を見たんだ」
「UFOでも見たんじゃないの」
『ナユタ』はSFではない。
「オレ様を信じろ」
「はいはい・・・・」
実は、本当にナインテールはシャドウの発した光りを見たのだ。シャドウが武器を手に取ったとき、光りを発したって書きましたよね。せっかくの能力だが、肝心なときにいつも役に立たないナユタ。やっぱりあこいつは、馬鹿だ。
「本当だって。あの変な塔の近くで見たんだ」
「塔って、あれは時計台だよ。ゲイルードさんが、街のみんなに見えるようにって・・・・」
そこまで言って、ナユタの表情がみるみる変わっていった。
(みんなに見えるように建てた時計台。そして、みんなに見せたいと願った宝石・・・・)
いままでバラバラだったパズルが、ナユタの頭の中で一つになっていく。そして浮かび上がってきた物は。
「そうか!そうだったんだよナインテール。はっはっはっは」
ナユタは大声を上げて笑いながら、ナインテールの頭をポンポンと叩いた。
「な、なにすんだ」
「見てよあの時計台。文字盤のところが、キラキラと光っているだろ。中編でも書いてあったけど、あそこには宝石が埋め込まれているんだよ。あれが本物の”エルフの涙”なのさ。はっはっはっは」
もう笑いが止まらなかった。完全にゲイルードに騙されていたのだ。
最初から、”エルフの涙”は一つの宝石ではなくいくつもの宝石の集まりだったのだ。ゲイルードが始めに”エルフの涙”を見せたのは、シャドウをおびき寄せるためだけではない。”エルフの涙”を、一つの宝石だと思い込ませるためでもあったのだ。万が一似も偽物が見破られたときのために。
レアさえもそれは知らなかったはずだ。シャドウだけでなく味方までも騙すとは、相当頭の切れる大富豪だ。
「行くぞ、ナインテール。今度こそシャドウを捕まえるんだ」
「お、おう」
最終対決に向けて、役者は集いつつあった。
20
「うひゃ〜、高いなぁ・・・・」
ナユタは恐る恐る下をのぞき込む。まるで、ミニチュアの庭を覗いているようだ。落ちたらさぞかし痛いだろうと、場違いなことがふと頭に浮かんでくる。
空を見上げれば、そこには迫ってきそうなほどの星空があった。まるで手を伸ばせば、星を掴めそうなほどだ。
有名な時計台は、屋敷の隣りにピッタリとくっついて建てられている。ナユタがいるのは、その途中の踊り場のような場所だ。屋敷の屋根よりも、さらに高い位置にある。
踊り場には、転落を防止するために人間の身長よりもさらに高い囲いが設けられていた。ナユタはその隙間から顔を出している。
目指す時計は、この少し上だ。塔に巻き付くように、螺旋状の階段が続いている。
<ナインテール、ちょっと先に入って様子を見てきてくれないか>
ナユタがテレパシーを送る。
<分かった>
ナインテールはぴょんぴょんと階段を上っていき、すぐに見えなくなった。
(いよいよか・・・・)
ゾクゾクッと、身震いが起きた。その震えを止めるように、ぎゅっと自分の身を抱きしめる。
幸いなことに、”エルフの涙”はまだ時計のところで輝きを放っている。だが、かえってそれが不気味であった。なぜなら、シャドウがこのあたりで潜んでいるのかも知れないのだから。すぐに狙わないあたり、シャドウも慎重になっているのかも知れない。
しばらくして、ナインテールが降りてきた。
<誰もいないな>
<そうか>
ナユタは時計を見上げた。
<じゃあ行くか。くれぐれも、慎重にね>
<それはこっちの台詞だ。オレ様の姿は誰にも見えないんだから、気を付けるのはお前の方だろう>
<それもそうだね・・・・>
わずかに笑みを浮かべたあと、すぐにナユタは表情を引き締める。
足音を立てないように注意を払いながら、ナユタは螺旋階段を上っていった。分かりやすくするために、ここで作者が描いたイラストをご覧頂こう。なお、下手だとかいう苦情はくれぐれも送らないように。作者だって、ペイントで一生懸命描いたんだから。

さて、ナユタは頭を半分だけ覗かせ、一応時計の辺りを見渡した。ナインテールの言うとおり、確かに誰もいないようだ。
(抜き足、差し足、忍び足・・・・)
まるでコソ泥のように、ナユタは目指す”エルフの涙”に近づいていった。とても探偵とは思えない。
「これが本物の”エルフの涙”か・・・・」
ナユタが”エルフの涙”を手に取ろうとしたその時、
バサッ!
「うわっ、何だ!?」
上から突然網が降ってきて、ナユタとナインテールを宙吊りにしてしまった。
「誰か引っかかったみたいよ」
時計台の中から、聞き覚えのある声が聞こえてくる。
「今よ、やっておしまいっ!」
「かしこまりましたっ」
扉を蹴破り、時計の中からイカツイ男が現れた。薄暗い中だが、一発でフランケン(執事)だと分かる。
「ぬおおおおおおっ、覚悟しろシャドウ!」
頭に血の上ったフランケンは、罠にかかったのがナユタであることなんか知りもしない。宙ぶらりんのサンドバックめがけて・・・・
殴る。
蹴る。
突く。
つねる。
ひねる。
伸ばす。
くすぐる。
ひっかく。
噛みつく。
ひっぱたく。
押しつぶす。
ぶちかます。
頭突きを喰らわす。
デコピンを喰らわす。
それから・・・・
鼻毛を引き抜く。
熱いおでんを食わせる。
ガムテープを張り付けて一気にはがす。
洗濯ばさみを付けて思いっきり引っ張る。
・・・・・・。書いてるこっちまで痛くなってくる。
「え〜いっ!」
さらに二つの影が現れた。
一人はサヤカ。ナユタの顔面に、調理場からくすねてきた唐辛子の粉が入った袋をブチ当てた。鼻といわず口といわず、唐辛子の粉がナユタを襲う。
さらにレアが、こちらも調理場からくすねた胡椒の入った袋をブチ当てた。
いくらシャドウ相手(本当はナユタだけど)とはいえ、ここまでする人たちもずいぶん酷いような気がするが。
「も、もう嫌だ・・・・」
それがナユタの最後の言葉だった。あ〜あ、また気絶しちゃった。
「お、お嬢様。この方はセシルさんですよ」
例のごとく、さんざん痛めつけた後にフランケンが気付く。
「何ですって!?」
慌ててエレウシアは網の中をのぞき込む。するとそこには、ボロ雑巾のようになって気絶しているナユタが・・・・。
「セシルさんって、ゲイルードさんの部屋で休んでいるはずじゃなかったっけ?」
「そのはずよね。何でこんなところにいるわけ?」
サヤカの問いに、エレウシアも答えることが出来ない。
「さぁ・・・・」
全員がふと考え込んだその時だ。突然球のような物が投げ込まれ、破裂した。球の中からは、灰色の煙がモクモクと広がる。
「ゲホゲホッ。なにっ!?」
咄嗟にエレウシア達は口を押さえる。
「はっはっはっ」
煙の中から姿を現したのは、シャドウであった。
「シャドウっ!ゲホゲホ・・・・」
エレウシアはシャドウを捕まえようと手を伸ばすが、手足が痺れたように動かない。
「安心なさい。その煙は眠気を誘うだけ。死にはしないわ」
「ま、待ちなさい」
鉛のように重い体を引きづりながら、それでもエレウシアは諦めない。
「そこの間抜けな探偵さんのあとを付けてきたのよ。念のため用心しておいて良かったわ」
何か罠が仕掛けられてはいないかと思って、シャドウは他に誰か来るのを待っていたのだ。そこに現れたのが、ナユタだった。
(ちっくしょ〜。目の前にいるのに・・・・)
手がシャドウの服に触れた瞬間、エレウシアは眠りに落ちてしまった。サヤカやレア、そしてフランケン(執事)も寝てしまっている。
「ふふっ、本物の”エルフの涙”はわたしのものね」
ダイヤよりも目を輝かせて、シャドウは”エルフの涙”に手を触れようとした。
「・・・・一人忘れちゃいないかい、大盗賊さんよ?」
「なにっ!」
屋根の上から、突然誰かの声がした。
「詰めが甘かったな。この勝負、レアの勝ちだ」
獲物を狙う鷹のごとく、クリスは屋根の上から一直線に舞い降りる。網による捕獲作戦が失敗したときのために、クリスが屋根の上で待ちかまえていたのだ。
「くそっ」
クリスをかわそうとして、シャドウは一気に囲いの上までジャンプした。驚くべき跳躍力だ。
「逃がすか!」
クリスは時計台を蹴って軌道を変える。
「捕まえたぞ!」
囲いの上で、クリスはがっちりとシャドウを捕まえた。だがそのためにバランスを崩し、二人は下の踊り場までそのまま落下していく。
「うわああああ〜」
「きゃあっ」
二人は絡み合いながら、真っ逆様に落ちていった。このままでは、二人とも頭から踊り場に激突してしまう。
「くそっ、離れろっ!」
シャドウはクリスの顔面に拳をたたき込み、身体を引き離した。
「ぐあっ!」
体の自由を取り戻すと、シャドウは鉤縄(かぎなわ)を取りだして塔に引っかける。鉤縄はガツッと塔に食い込み、シャドウは身を翻して踊り場に着地した。
「ちぃっ」
クリスもなんとか空中で身体をひねり、受け身の姿勢をとる。
ドシャ
意外にも大きな音が響いた。
「ふざけやがって」
クリスがヨロヨロと立ち上がる。激しく打ち付けたため、左の肩がだらりと下がっていた。
「シャドウっ、勝負だ!」
激痛に顔をゆがめながらも、クリスは残った右手に木刀を握る。
「ふっ、面白い・・・・」
まるで道化師のような笑みを浮かべながら、シャドウは武器を握った。
対峙する二人の間を、銀色の満月が分ける。だが決着の舞台に主人公の姿は、ない・・・・。
つづく・・・・