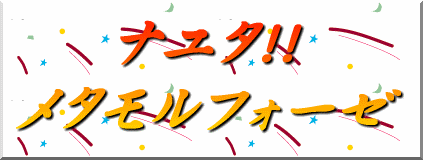
序
あなたはご存じだろうか、”エルドラン”という王国を。世界の一番東に浮かぶ、辺境の島に栄える王国だ。
しかし島といっても全体はかなり広く、どこにでもある王国と面積はさほど変わらない。
自然環境もかなり変化に富み、山あり谷あり、河あり森ありとさまざまだ。
だた一番近い大陸からは、海路で遠く離れていた。だからこそ、他国との交流はほとんどない。大陸に住む人間達からは、”忘却の孤島”と呼ばれている。
しかしエルドランの民は、そんな噂など気にしていなかった。平和な毎日が送れること。それが彼らの望みであった。その望み通り、この島から争いが絶えて久しい。
この島の中央に位置するのが、王都ルザイアである。人口は数万人を超え、人々は日々の生活に勤(いそ)しんでいる。
これは、ルザイアに住む一人の若者の愉快な物語である・・・・
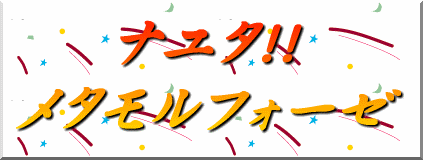
−第0話・前編−
朝が来た。
それを告げるかのように、顔を出した朝日がルザイアの街を照らしていく。夜の闇を払うように、まぶしい光りが街に広がっていった。
若者の家は、街の西側にある。小高い丘の上にある二階建ての建物。それがこの物語の主人公である、ナユタの家だ。ナユタの家にも、朝日が延びてきた。窓から射し込む朝日が、ナユタの顔を照らす。
「うう〜ん・・・・」
どうやらお目覚めのようだ。
ナユタは今年で十六歳。まだ幼さが残り、どことなく頼りない顔つきをしている。
「ふあ〜あ・・・・」
大きなあくびをして、ナユタはベットを降りる。そのままナユタは、窓の方に向かっていった。
ナユタは鍵を開け、窓を目一杯に広げる。その途端、目の前が真っ白になった。
「ううっ!」
あまりの眩しさに、ナユタは一瞬顔を背けた。やがて目が慣れ始め、真っ白な景色の中にルザイアの街並みが浮かんできた。
ナユタの部屋は二階にあるので、ここからルザイアの街並みが一望できる。色とりどりの屋根が眼下に広がり、その先にはうっすらと王城が見える。ここからの眺めが、ナユタは一番好きだった。
「はぁ〜、やっぱり気持ちいいなぁ〜」
ナユタは思いっきり伸びをして、さわやかな休日の朝の風をいっぱいに浴びる。そこへ、一羽のハトがやってきた。
「おっはよ、コロン」
ナユタが頭をなでると、コロンはクルクルとのどを鳴らす。
コロンは、毎朝決まってナユタの家にやってくる。始めは少しうるさかったが、今ではいい目覚まし代わりだ。人間に警戒心がないのか、すぐナユタになついてしまった。
コロンは再び羽を広げ、朝日に向かって飛び去っていく。
「あっ、おはようナユタ」
その時、横から少女の声が聞こえてきた。隣の家の窓から、眼鏡をかけた少女が顔を出している。
「おはよう、サヤカ」
ナユタは笑顔で答える。
サヤカは、隣に住むナユタの幼なじみだ。艶のある黒髪をしているが、いまは寝ぐせがついて少し乱れている。おっとりとした顔立ち通り、おとなしくて優しい性格の女の子だ。
そのサヤカの家にも、一羽のハトがやってくる。今度のハトは、足に紙切れを巻いていた。
「ボテ、ありがとう」
サヤカは紙切れをはずし、ボテに礼を言う。ボテも「クルックゥ〜」と返事をし、青い空に消えていった。
”ボテ”というのは、サヤカが付けた名前だ。ぼてっとしてるからという理由が、いかにもサヤカらしい。
ボテが運んできたのは、サヤカの父からの手紙だ。サヤカの父はあまり家にいないので、こうやって伝書鳩で連絡を取り合っている。
「だいぶ元気になったみたいね」
「うん、いつまでもメソメソしていられないからね」
実は先日、ナユタの父が突然死んでしまったのだ。小さい頃に母親を亡くし、ずっと父親に育てられたナユタにとって、それはあまりにも悲しい出来事であった。身寄りのないナユタは、ずっと家に籠もっていたのである。
「明日から、また学校に行こうと思う」
「本当!よかったわ」
二人は、”王立アカデミー”という学校に通っている。しばらく学校には行ってなかったが、久しぶりにみんなの顔も見たくなってきた。
「みんな心配してたんだからね」
その表情を見る限り、サヤカが一番心配していたようだ。
「そんなわけだから、また頼むよ」
「うん、またお弁当を作ってあげるね」
サヤカは料理が好きなので、いつも兄弟のために弁当を作っている。ナユタには母親がいないので、ついでにナユタの分も作ってもらっているのだ。
「じゃあ、また明日ね」
そう言って、サヤカは窓を閉める。
「さ〜て、ぼくはもう一眠りするかな」
気持ちいい風が入ってくるので、ナユタは窓を開けたままベットに戻っていく。
「フンフ〜ン」
などと鼻歌を歌いながら、ナユタはベットに横になった。
「おやすみ〜」
ナユタは気持ちよく眠ろうとした。だが何となく寝付けない。誰かに見られているような・・・・。
「ああ〜!」
そう思って目を開けた瞬間、またもや窓のところにハトがとまっていた。さっきのコロンよりは、いくぶん小さい。
「またお前だな、ミリー!」
このミリーと名付けたハトは、とにかくナユタの家を覗きに来る。それも決まってナユタの部屋を覗き、果てはトイレにまで覗きに来る始末の悪さだ。
「あっちいけ。シッシ!」
ナユタは窓のところに駆け寄り、ミリーを追い払おうとする。だがミリーはナユタの手の届かないところに飛び去ると、小馬鹿にするように鳴いた。
「こいつ〜、覗きバトの分際でぇ〜」
頭にきたナユタは、ベットから枕を持ち出してミリーに投げつけた。
だがミリーは難なくかわし、挑発するようにまた鳴く。
「人間を怒らせると恐いんだぞ〜」
ナユタは手近にあったガラスの玉を手に取った。大きさは赤ん坊の手の平ぐらいだが、玉の中には色とりどりのビーズが光っている。
このガラス玉はナユタの宝物だ。日光に当たるときれいなので、いつも窓の側にいくつか置いてある。
ナユタは、そのガラス玉をミリーになんの考えもなく投げつけた。せめて宝物なら、投げる前にミリーにかわされたらどうなるか考えて欲しいものだ。
「食らえ〜!」
といっている内に、愚かにもナユタはガラス玉を投げてしまった。もうどうなっても知らない。
当然というべきか、ノーコンのナユタの投げるガラス玉はミリーに当たらない。
ナユタに投げられたかわいそうなガラス玉は、放物線を描いて地面に落ちた。「ガシャッ!」という乾いた音が下から聞こえてくる。
「も〜怒ったぞ!」
おいおい、とっくに怒ってるじゃないか。
ナユタは次から次へとガラス玉を投げていく。そのたびに、ガラスの割れる音が響いた。
「くそぉ〜」
ついに最後の一個を投げ終え、ナユタは悔しそうにする。そして、ようやく大事なことに気が付いた。
「あ〜!ガラス玉がない〜!!」
頭を抱えるナユタ。そんなナユタを尻目に、ミリーは飛び去っていった。
「お前のせいで僕の宝物が〜!」
正確にはナユタのせいだ。ミリーはなんにも悪くない。
「あ〜あ・・・・」
落ち込みながら、ナユタはベットの上に寝ころんだ。まっ、自業自得なんだから仕方がない。
「もう寝よ」
さっさと寝ようと、ナユタは目をつぶった。
だが、またもや寝付けない。理由は簡単だ。枕がないからである。
「いまさら取りに行くのも面倒臭いし・・・・」
なかなか眠れないが、起きるのも面倒臭い。作者もたまにあるが、こんな時はツライ。
そんなこんなで、小一時間。ようやく眠気が訪れた。しかしやっと寝られると思った瞬間、玄関の扉が激しく叩かれる。
「お〜い、誰かいないか」
なんだかドスの利いた声である。面倒臭いので、ナユタは居留守を使おうとした。
「おい、誰かいねえのか!」
またもや玄関が激しく叩かれる。
「ああ〜ん、もう!」
ようやく寝ようとした瞬間にたたき起こされる。作者も経験があるが、ハッキリ言ってムカツク。だいたい人が寝ようとしているときに・・・・
えっ、あんたのことはどうでもいい?さっさと先を続けろ?こりゃあ失敬。
まあとにかく、ナユタは渋々ながら玄関に向かっていったわけだ。続きをどうぞ。
恐る恐る玄関を開けると、案の定ゴロツキのような風体の男達が三人いた。
「あ、あの〜。なんの用でしょうか・・・・?」
ナユタは引きつった笑みを浮かべる。
「ちょっと上がらせてもらうぞ」
三人の中でも一番偉そうな初老の男が、勝手にずかずかとナユタの家に上がってきた。その後ろから、残りの二人も無言で続く。
「ちょっと〜・・・・」
一体何事かと、ナユタは驚いた。
「おいボウズ、椅子に座れ」
初老の男は勝手に椅子に座り、ナユタに席に着くように命令する。残りの二人は、男の後ろで立っていた。
「座れって、ここはぼくの家なんだけど・・・・」
「いいからさっさと座らねえか!」
男が一喝する。
「一体何なのさ、急に人の家に上がり込んで・・・・」
などとぼやきながら、ナユタは椅子に座る。
「今日ここに来たのはな、お前の親父のことだ」
男が低い声で話し始めた。男は白髪混じりの髪をぼさぼさに伸ばし、右目には眼帯を巻いている。どう見ても危ない筋の人間だ。
「父さんのこと?」
一体なんだろうと、ナユタは首を傾げる。
「お前の死んだ親父はな、実はオレに借金があるんだ」
「借金!」
ナユタも初めて知った。
「これに詳しく書いてある」
そう言って、男は一枚の羊皮紙を取りだした。ナユタはそれを受け取り、食い入るように見る。
そこには確かに、ナユタの父の名前で今まで借りた借金が書かれていた。すべてを合計すると、開いた口が塞がらなくなるような金額になる。
「あいつが死んじまった以上、この借金を払うのはお前さんだ」
男は節くれ立った指をナユタに向ける。
「そんなの無理だよ!こんな大金」
借金は、一生働いても払えるような金額ではない。
「それはそっちの都合だろう。払えねえんなら、こっちにも考えがあるぜ・・・・」
男の声がさらに低くなる。その声を聞いて、ナユタは背筋がゾッとした。
「今日からこの土地はオレのものだ。この家をブッ壊して、俺の別荘を建てる。そこでお前は一生働いて貰う」
「そんなぁ・・・・。この家は曾曾おじいちゅんの頃からずっとある家なんだ。だから家を壊すのは勘弁してよ」
「だったら金を返すんだな」
男は素っ気なく答える。
「そこを何とか」
「しつこいガキだな。借金をしてるのはお前の方なんだぞ」
「・・・・・・」
ナユタは黙ってうつむく。
「だったら一年待って。一年経ったら必ず返す」
「その保証はあるのか?」
「ない。でも、必ず返す」
「そんなこと言って置いて、明日になったら首吊り自殺ってのはやめてくれよ」
男が首をすくめるような仕草をする。
「だったらこれをあげるよ」
そう言って、ナユタは首から掛かっていたペンダントをはずした。
「これは父さんから初めて貰ったプレゼント。ぼくの命よりも大切なものなんだ。これをあんたに渡しておく」
男はナユタの眼を見つめる。普段のナユタからは想像もできないほど、決意に満ちた目だった。
「は〜はっはっは!」
男は急に笑い出した。
「いいだろう、ボウズ。お前の覚悟はよく分かった。一年だけ待ってやる。それまでこれは預かっておくぜ」
男はペンダントを鷲掴みにし、席を立った。
「一年後にまた来る。それまでに金を用意できなかったら、その時は覚悟するんだな」
そう言い残し、男はお供を連れて玄関から出ていった。
「ふ〜・・・・」
男の足音が完全に消えた後、ナユタは全身の力が抜けて椅子にもたれかかった。
「ああは言ってみたものの、どう考えても無理なんだよな〜・・・・」
勢いに任せて大見得を切ってしまったが、冷静に考えれば借金を返すことは不可能だった。それも、たった一年では。
眠気などとうに吹き飛び、絶望にも似た念が重くおしかかる。
「水でも飲むか」
ナユタは不意にのどの渇きを覚えた。力無く椅子から立ち上がり、水瓶のある台所に向かう。
フラフラと台所に向かう途中、ふと神棚が目に入った。神棚にあるお供え物は、完全に乾燥してパリパリになっている。
「そう言えば、ずっとかえてなかったな」
すっかり乾燥してしまったお供えを捨てようと、ナユタは神棚に近づいた。するとその影から、黄色くて細長いものが突き出ているのが見えた。
「なんだ?」
ナユタは恐る恐る顔だけを覗かせた。そしてそこで見た物は・・・・
「き、狐じゃないか」
そう、神棚の影から突き出ていたのは、狐の足だったのである。大きさから言えば、まだ子供であろうか。
「なんで狐なんかがこんなところに・・・・」
ナユタは疑問に思った。さらに不思議なのが、尻尾が九本もあることだ。それに、何となく身体の輪郭がぼやけて言える。
「腹が減った・・・・。何か食わせてくれ」
「狐が喋った!!」
ナユタは腰を抜かすほど驚く。
「頼む・・・・。早くしないと死ぬ」
狐は苦しそうな声で喋り続けてる。
「・・・・夢か?」
ナユタはふと思った。
「そうだ、これは夢なんだ。借金のことも、みんな夢なんだ」
ナユタは思いっきり頬をつねってみた。夢なら、痛くもかゆくもないはずである。だが・・・・
「いててて・・・・」
思いっきり痛かった。
「夢じゃないんだ・・・・」
頬を押さえながら、ナユタは茫然とする。
「何してる、早く何か食わせろ・・・・」
「う、うん・・・・」
狐が喋ったことはすでに頭の中から吹き飛び、ナユタは慌てて食べ物を探す。
その時ちょうどいい具合に、テーブルの上に細長いパンが一切れあった。ナユタはそのパンを小さくちぎり、狐の口元に持っていく。
「ほら、食べ物だよ」
「うう・・・・、すまん」
狐はムシャムシャとパンを食べ始めた。
「もっとくれ・・・・」
「ああ、待って」
ナユタはもう一切れパンをちぎり、狐に与える。
「もっとだ」
狐はさらにパンをほしがる。仕方ないので、ナユタはパンを全部あげてしまった。
「ふ〜、生き返った」
腹一杯になったのか、満足そうに狐は立ち上がる。
「あ、あの〜・・・・」
ナユタが狐に声をかけようとする。だがその前に、いきなり狐が殴ってきた。
「この馬鹿者め、このオレ様のお供えを忘れるとはどういうつもりだ!」
「お供え?」
ナユタには何のことかサッパリ分からない。
「オレ様はこの家の守り神だぞ」
「守り神ってもしかして・・・・」
ナユタは神棚を見つめた。
「そうだ。この九尾(きゅうび)様が、この家の守り神だ」
「九尾って、あの妖怪の?」
九尾という名前は聞いたことがある。死んだ狐の魂が、妖怪として蘇ったものだ。いろいろなものに化けて、人間を驚かせるという。
「でもさぁ、何で妖怪がお腹が減って死ぬわけ?」
「うっ!」
痛いところを突かれたのか、今まで威勢の良かった九尾が言葉を失う。
「君も随分おっちょこちょいなんだね」
「う、うるさい。これでもお前より百年は長く生きてるんだぞ!」
九尾は再びナユタを殴った。
「痛いな〜。すぐ怒るなよ」
ナユタは殴られたところをさする。
「おおかた、君はお腹がすいて死んじゃったんじゃないの?それでさぁ〜、ようやく食べ物を見つけたんだけど、それが毒キノコで死んだんだ」
小狐に馬鹿にされた仕返しをしてやろうと、ナユタは九尾をからかう。
「・・・・・・」
それを聞いた九尾は恐い表情をする。
「だからすぐに怒るなって。冗談だよ」
ナユタは苦笑いを浮かべる。
「なぜ・・・・、分かったんだ?」
「えっ?」
「何故お前がそんなこと知ってるんだ」
九尾は怒っていたのではなく、驚いていたのだ。
「あっはっはっはっは!」
ナユタは腹を抱えながら転がり回った。
「それで死んでも死にきれずに妖怪になったのか」
「う、うるさい!お前に俺の気持ちが分かってたまるか」
「ようやく助かったと思ったのに死んじゃうなんてね〜。ホント間抜けだよね〜」
ナユタはなおも笑い転げる。
「お前ぇ〜、妖怪を馬鹿にするとひどい目に会うぞ」
「あはははは。ひどいって、どんなぁ〜?」
「妖怪の恐ろしさを見せてやろう」
そう言うと、九尾は両目を赤く光らせた。すると、のたうち回っていたナユタが急に煙に包まれる。
その煙の中から現れたのは、一匹のカエルだった。
「ゲコゲコゲコ・・・・」
カエルになってしまったナユタは、訳も分からず戸惑っている。
「ははは。どうだ、参ったか」
九尾の高笑いが響く。
「ゲコゲコゲコ!」
何か言いたげにナユタは叫ぶが、「ゲコゲコ」としか鳴けない。
「元に戻して欲しいのか?」
「ゲコゲコ!」
「だったら土下座するんだな」
「ゲコゲコ!」
ナユタは慌てて土下座をする。といっても、カエルが土下座している姿はいかにも滑稽だ。
「ふん、オレ様の寛大な心に感謝するんだな」
九尾がもう一度目を光らせると、ナユタは再び人間の姿に戻った。
「いや〜、妖怪ってすごいんだね」
改めてナユタは感心する。
「今頃気付いたか、愚か者め」
そう言うと、九尾はテーブルに向かっていった。
「おいナユタ、お前に話がある。こっちへ来い」
九尾は椅子の上にジャンプすると、器用に椅子に座る」
「何の話し?」
「いいからさっさと来い」
九尾は首をひねって、席に着くように指示する。
「何だよ、みんな偉そうに。ここはぼくの家だぞ」
ナユタはブツブツと文句を言う。
「何か言ったか?」
「何にも。いま行くよ」
ナユタは水も飲めないまま、九尾に言われたとおり椅子に座った。
「さっきの話を聞いていたんだが。大変なことになっているらしいな」
「ああ、知ってたの。大変どころじゃないけどね」
「お前がコキ使われようと何だろうと関係ないが、この家を壊されたらオレ様の住む場所がなくなってしまう」
「関係ないって・・・・。君はこの家の守り神だろ、こんな時こそ何とかしてよ」
「そこでだ、オレ様に考えがある」
「え、ホント?」
ナユタは期待して身を乗り出す。
「オレ様には、さっきも使ったように”変身”の能力がある。それもただの変身ではない。その者の能力も身につけることができるのだ」
「どういうこと?」
「つまりだ。超能力者に変身すれば、お前も超能力を使えるようになる。学者に変身すれば頭が良くなるし、戦士にでも変身すれば、剣技を身につけることができる」
「すご〜い・・・・。さすが妖怪だね」
ナユタは、少しは九尾のことを見直した。
「この能力を使って、お前が金を稼ぐという寸法だ」
「なるほどね。それじゃあ、大盗賊とかになれないの?財宝とか盗めば、一気に借金なんか返せるじゃん」
「犯罪を犯すようなことはオレ様が認めん!遺跡とかを探検して探してくるのなら話は別だが」
「それもそうだね」
ナユタもすぐに反省する。
「ただオレ様の変身能力も完璧ではない。技能は身につけることができるが、性格までは変えることができないのだ」
「べつにいいじゃん」
「アホか、そこが問題なんだ。お前の欠点、それはドジなことだ」
九尾はズバッと言う。
「う、うるさいな〜」
ナユタは頬を膨らませる。
「せっかく変身しても、ドジなお前では心配なのだ」
「確かにドジなことは認めるよ。でも、これしか方法はないんだろ?」
「仕方ない、これも住処を守るためだ。このオレ様が力を貸してやろう」
いくぶん不安げながらも、九尾は一度大きく頷く。
「やった〜。たまには君も役に立つんだね」
「たわけ!オレ様を誰だと思っているだ」
九尾は目頭をつり上げて怒る。
「そうだ、君に名前を付けて上がるよ。その方が呼びやすいし」
「いらん!だいたい”君”などと呼ばずに、”九尾様”と呼ばぬか」
「だって、小狐の姿じゃ守り神って気がしないんだもん」
話し方は妙に大人びているのだが、いかんせん姿に威厳がない。
「う〜ん、そうだな。九本の尻尾があるから、”ナインテール”ってのはどう?」
「そのまんまじゃないか」
文句を言う九尾だが、まんざら嫌でもなさそうだ。
「それじゃあナインテール、これからよろしくね」
「これから”も”だろ。いいか、すべてはお前にかかっているんだからな。それを忘れるなよ」
「任せておいてよ」
希望が出てきたのか、急に元気になるナユタ。それを見ながらナインテールは、苦労させられるであろうことをほぼ確信していた。
また朝がやってきた。
それを告げるかのように、顔を出した朝日がルザイアの街を照らしていく。っということは前に書いたので、以下同文。
しかし、ナユタにはいつも通りの朝はやってこなかった。
「何やってるんだ、ナインテール!」
朝一番でナユタの叫び声がする。
「うるさいな〜、あと十分でいいから寝かせろ」
「そんなことより、何で君がぼくのベットで寝てるのさ〜」
目覚めたとき、何故かナユタは床に寝転がっていた。そして、ベットの上ではナインテールが寝ていたのである。
「細かいことは気にするな。それより学校へ行く支度をしたらどうだ?」
「いまからするよ」
何を言っても無駄なので、ナユタは諦めて下におりようとした。
だがまだまだ眠いのか、ナユタは目をこすりながら階段に向かう。そしてフラフラと階段に近づこうとして時、ナユタは何かを踏んづけた。
ミ゛ャー!!!
その途端、足下から金切り声が聞こえてきた。
「あっ、ミケかい?ゴメンよ」
ナユタが踏んづけたのは、”ミケ”という三毛猫の尻尾。
ただ、ミケというのは何と安易なネーミングであろうか。いまどき、自分の子供に”太郎”とでも付けるようなものである。
ナユタは足をどかそうと、階段の方に飛び跳ねた。だが愚かなナユタは、そこに階段があるとは考えていない。
「うわあ!」
足を踏み外したナユタは、階段を転げ落ちていった。
ドドドドドドン!
ナユタの家が激しく揺れる。喜劇の舞台で演じれば大爆笑ものだが、いまは観客は誰もいない。悲しい一人芝居だ。
幸いなことに、ナユタの家は木造だった。レンガ造りの家で転げ落ちたら、0話にして主人公が死んでいただろう。ドジなのはナユタ一人で十分で、そんなアホな結末で物語を終わらせないでもらいたい。
「いてててて」
ナユタは後頭部をさする。あれだけ派手に転げ落ちたのだから、頭を打っていてもしょうがない。これでナユタのドジな性格が治ればいいのだが・・・・。
「朝からツイてないなぁ・・・・」
ナユタの胸の嫌な予感がこみ上げてきた。当然、その予感が的中しなければ話は面白くならない。
「紅茶でも飲むか」
ナユタは戸棚から茶碗を取りだし、熱い紅茶を半分ほど注いだ。その中に、砂糖をやや多めに入れる。
甘党のナユタは、紅茶に砂糖をたっぷり入れるのが好きだ。コーヒーも同じで、砂糖とミルクを入れないと飲めない。父はブラックで飲んでいたが、ナユタには信じられなかった。
ナユタは茶碗を口に近づけ、熱い紅茶を流し込む。
「ぶはっ」
だがその途端、ナユタは勢いよく紅茶を吹き出した。
「しょっぱ〜」
しょっぱい紅茶などあり得ない。オチが読めたかも知れないが、ナユタは砂糖ではなく塩を入れてしまったのである。
だいたい、塩と砂糖を同じ柄の容器に入れて、並べて置いておくナユタの方が悪い。ドジとかいう以前の問題だ。
「紅茶はいいから、ご飯を作ろう」
気を取り直し、ナユタはフライパンに油を引く。その上に卵とハムを落とし、火にかけた。
「学校は久しぶりだな〜」
と、油の入った瓶を片手に学校のことを思いめぐらせていると・・・・
「あっ、そうだ!生徒手帳を無くしてたんだ」
思い出したかのようにナユタは叫んだ。最後に学校に行った日、家に生徒手帳を忘れたのである。だが帰ってきても、手帳は見つからなかった。
「また忘れたら先生に怒られるからな。探さなくちゃ」
ナユタは、大急ぎで部屋に戻っていった。
それからたっぷり三十分ぐらいして、ようやくナユタは手帳を発見した。
「ミケのやつ、自分の寝床に持っていっちゃうんだもんな〜」
手帳があったのは、ミケの寝床であった。しかし大切なことを思い出したのはいいが、一つ忘れていることがある。
「ん?なんか焦げ臭いな」
下の部屋から、鼻につく臭いと共に白い煙が立ちこめてきた。
「まさか!」
ナユタは大急ぎで階段を駆け下りた。卵とハムを焼いていたことをすっかり忘れていたのだ。
「焦がしちゃったか・・・・」
てっきり朝ご飯が丸焦げになっていると思い、ナユタは台所の覗いた。
ふふふ、甘いぞナユタ。そんな分かりやすいオチなわけないだろう。
「か、火事だ!!」
そう、食べ物ではなく、台所までも丸焦げになっていたのである。
生徒手帳のことを思い出したとき、ナユタは急いで部屋に戻った。その時持っていた油の瓶を、ナユタはフライパンの近くに置いてしまったのである。その瓶が何かの拍子に倒れ、ファイヤー地獄になったのだ。
ナユタは慌てて布団を上からかぶせ、何とか消火させた。
「ふぅ〜、何とか収まった」
冷や汗を拭い、ナユタはチラリと時計を見る。
「いけない、学校に遅れる!」
モタモタしている間に、時間が来てしまった。朝ご飯は諦め、ナユタは学校へ行く準備をしに自分の部屋に戻る。
「え〜と、カバンカバン」
散らかっているゴミの下から、カバンを引っこ抜く。
「そうだ、まだ教科書とか入れてなかったんだ」
ナユタは時間割を見て、教科書をカバンに詰め込んだ。
さらに制服に袖をとおし、何とか準備を整える。
「じゃあミケ、学校に行って来るからね」
ミケに挨拶し、ナユタは家を飛び出す。
「何よ〜、その顔・・・・」
サヤカが呆れたような表情をする。一緒に学校へ行こうと家の前で待っていたら、ナユタがひどい顔で現れたのだ。
「いや〜、ちょっとミケとふざけたら・・・・」
顔中傷だらけでは、ほとんど説得力ない言葉だ。
「猫とふざけ合ってどうしてそんな傷になるのよ」
さっきすごい音がしたので心配していたが、案の定この有様だ。サヤカは、やれやれとため息をつく。
「ちょっと家に来て。薬を塗ってあげるから」
「いいよ、早くしないと学校に遅れちゃうし」
「そん怪我して放っておけないでしょ、早く来なさいよ」
半ば強引に、サヤカはナユタを家の中に引っ張っていった。
「そこに座ってて」
サヤカはテーブルを指さし、棚から薬箱を取り出す。
「そういえば、サヤカの家に入るのって久しぶりだね」
小さい頃はよくこの部屋で遊んだものだが、最近ではめったに来ることはなかった。置いてある家具などは、いくつか見覚えるあるものもある。しかし、何となく部屋全体が狭くなったように感じられた。自分が大きくなったからであろうか。
「人の家のなかをジロジロ見ないでよ、もう」
サヤカはナユタと向かい合って座り、綿のかたまりに薬をしみこませる。
「ちょっと我慢してね」
サヤカは傷口に綿を押しつけた。
「うっ!」
すぐにナユタは顔をしかめる。
「ゴメン、しみた?」
「当たり前だよ!」
「少しの辛抱だから」
サヤカは、ナユタの顔を押さえながら薬を塗っていく。ナユタは痛みをこらえるのに必死だ。
「ああー、ナユタ兄ちゃんだ!」
その時、男の子の声が聞こえてきた。
「げっ、あの声は・・・・」
ナユタはドキッとする。サヤカには幼稚園生の弟がいて、ナユタはその弟が苦手だった。
「エディン・・・・」
案の定そこにいたのは、サヤカの弟のエディンだった。
「姉ちゃん、おはよう〜」
そう言って、エディンはサヤカに抱きつく。
「ちょっとエディン、危ないわよ」
突然抱きつかれたサヤカは、バランスを崩してナユタを押し倒す様に倒れる。
「ちょっとー!!」
ナユタは悲鳴を上げたが、そのまま二人は床に倒れた。
「いててて」
またもや後頭部を打ってしまった。
「はっ!」
そして気が付いたとき、目玉が飛び出んばかりに驚いた。サヤカの顔が目の前にあったのである。そして二人の視線が合う。
ナユタは思わずサヤカの顔を見つめてしまった。倒れた拍子にどこかへ飛んでしまったのだろうか、サヤカは眼鏡をかけていない。初めて間近で見るサヤカ。しかも眼鏡をとったその顔は、いつもとはまるで別人のようにかわいい。さらに鼻先にかかっているポニーテールからは、若草のようないい匂いがしてくる。
胸の鼓動がどんどん早くなり、息苦しくなる。同じく自分を見つめるサヤカの瞳に、妙にドキマギした自分の顔が映っていた。
「こ、こらエディン!」
思い出したかのようにサヤカは立ち上がり、エディンを叱る。
それを見ながら、ナユタも起きあがった。だがその頭のなかは、サヤカのことで一杯だった。
「ナユタ兄ちゃん、もう元気でたのか?」
エディンが訊ねてきた。
「う、うん」
そう答えるナユタの表情は、ほとんど上の空だった。
「どうしたの?なに赤くなってるの?」
エディンが不思議そうに見つめる。
「ああ、何でもないよ。ははは・・・・」
ナユタは笑ってごまかす。自分でもハッキリ言って何がなんだか分からなかった。
「そう。それじゃあまた遊べるね」
エディンが笑顔を浮かべる。
「そ、そうだね・・・・」
反対にナユタは苦笑いを浮かべた。
近所では、エディンは悪ガキとして有名だ。何度か遊んであげたこともあるが、その度にひどい目にあった。
サヤカにはもう一人、ファレーナという名前の妹がいる。ファレーナは、サヤカに似ておとなしい女の子だ。
一方父親は、今は家にはいない。この島では数少ない船乗りとして、いまは海の上の人だ。たまにしか見たことはないが、自分の父親と仲がよかったのは覚えている。
「何してるのサヤカ、学校に遅れるわよ」
その時キッチンから、サヤカの母が現れた。
「あ、サラおばさん。おはようございます」
「あら、ナユちゃん。おはよう」
ナユタがいたことに少し驚く。
「いろいろ大変だったわね。もう大丈夫なの?」
「はい、今日からまた学校に行きます」
「早く行かないと遅刻するわよ」
「そうだ、早くしないと」
ナユタは急いでカバンを抱え、学校に行こうとする
「ナユタ待って」
サヤカも慌ててナユタを追う。
「ほらサヤカ、お弁当を忘れてるわよ」
サヤカの母が慌てて注意した。
「いっけな〜い」
サヤカは自分の分の弁当と、ナユタの弁当をカバンに詰める。
「気を付けて行きなさいよ」
母の言葉が終わらないうちに、サヤカは家を後にした。
目の前に、まるで神殿を思わせるような白い建物が見えてきた。ナユタ達の通う、”王立アカデミー”である。
キンコンカンコーン・・・・
始業の鐘が鳴った。
「ナユタ早く〜」
サヤカは後ろを振り返り、ナユタに声をかける。あの鐘が鳴りやまない内に校門をくぐらないと、遅刻になってしまうからだ。
「う、うん」
ナユタも懸命に走っていた。だが傷がうずいて、なかなか早く走れない。
もうすでに校門は見えている。同じように遅刻しそうな生徒が、急いで校門をくぐっていた。そしてその脇には、生徒指導のフェルマー先生が立っていた。
校門まで一直線。果たしてナユタは間に合うだろうか。
「おう、ナユタ。お前もぎりぎりか」
その時声をかけてきたのが、同級生のクリスだった。短めの髪をツンツンに逆立て、制服の袖をひじの上までまくり上げている。”ミスター遅刻王”という異名を持つ、遅刻の常習犯だ。
「そうなんだ。だから早くしないと」
校門まであと少し。だが、鐘もあと少しで終わる。生徒指導のフェルマーは、遅刻の生徒をとっ捕まえるべく、にやついた笑顔を浮かべながら準備を始めた。
フェルマーは筋骨隆々の大男で、ハゲ上がっていることから”金剛”と呼ばれている。
ナユタは全力を振り絞り走る。何とか間に合いそうだ。だがその時、またもクリスが声をかけてきた。
「おいナユタ。チャックが開いてるぞ」
そう言って、クリスはナユタの股間を指さす。
「ええっ!?」
ナユタ一瞬立ち止まった。急いで出てきたから、もしかしたら閉め忘れたのかも知れない。ナユタは慌ててチャックを確認する。
「あれ?」
しかし、チャックはちゃんと閉まっていた。
「ねぇクリス・・・・」
クリスに声をかけようとしたナユタだったが、そこにはもう誰もいなかった。
「ナユタ、お先に〜」
無事に校門をくぐったクリスは、笑いながら手を振っている。それと同時に、始業の鐘がむなしく鳴り終わった。
「ああー!クリス!!」
ようやくナユタは理解したようだ。自分がハメられたことを。
「久しぶりに来たと思ったら、いきなり遅刻かナユタ。しかも、無遅刻週間の初日に遅刻するとはいい度胸だな。生徒指導室でこってりしぼりあげてやろう」
フェルマーは、むちゃくちゃ厳しいことで有名だ。
「これはクリスが・・・・」
「いいわけは署の方で聞こう。お前を連行する」
問答無用とばかり、フェルマーはナユタを生徒指導室に連れていく。もちろん、こっぴどく叱られたことは言うまでもない。
朝礼が終わり一時間目の授業が始まる頃、ナユタは教室に戻ってきた。かなりブルーになっているようだ。
だが、久しぶりに見る教室というもの新鮮な感じがする。何だが別の教室に来てしまったみたいだ。作者も病気などで学校を休んでいて、久しぶりに自分の教室に入ったときにそう感じたことがある。
「災難だったわね」
席に着くと、右隣の席のサヤカが声をかけてきた。
「ホント災難だよ。ちゃんと間に合ってたのに・・・・」
あの男がいなかったら、フェルマーに叱られることはなかったのだ。
「おっはよう、ナユタ。お前も運がない男だな〜、朝っぱらから”金剛”に叱られるなんて」
その男は、少しも悪びれた様子もなくナユタの前の席に座る。
「クリスのせいじゃないか!」
ナユタが怒るのも無理はない。
「すまんすまん。でも仕方ないだろ、チャックが開いていたように見えたんだから」
そう言いながらもヘラヘラ笑うクリスの言葉は、どう考えても嘘だ。
クリスは武芸百番の人間で、剣技の成績は抜群だ。しかし頭を使うことは苦手で、それ以外の成績はオール1だ。そこぬけて明るい性格で、体育会系によくあるタイプだ。
さらに困ったことに、ナユタをからかうことに生きる喜びを感じている。何かにつけてはナユタをからかい、その反応を面白がっているのだ。根はいい奴なのだが、ナユタにとっては迷惑な話だ。
「まったくもう!」
ナユタは、ふてくされるようにそっぽを向く。
「あ〜らナユタ、おはよう」
今度は明るい女の子の声が聞こえてきた。彼女はカバンを机の上に載せ、クリスの隣の席に座る。
「おはよう、エレウシア」
そう言って、目の前に立つ金髪の女の子に挨拶をする。
彼女の名はエレウシア。このルザイアに住む大富豪の娘だ。”お嬢様”という言葉がピッタリなほど綺麗で、ソバージュのかかった金髪を腰の辺りまで伸ばしている。だが、性格にかなりの問題があった。
”お嬢様”によくあることだが、とにかく高飛車なのだ。物事が自分中心でなくては気が済まず、自分から勝手にクラス委員長になってしまった。
そんな彼女だが、不思議と人気は高い。少々男勝りだが、裏表のないハッキリとした性格を持っている。仕切りタイプだが、実際にみんなをまとめるのは上手い。多少自意識過剰なところはあるが、それが許されるだけの可愛さはあるし、お嬢様にしては珍しく炊事洗濯もできて、さらに音楽の才能は抜群だった。ナユタも一度彼女のピアノの演奏を聴いたことがあるが、同じ年の女の子の演奏とは思えなかった。
「な〜に朝からふてくされてんのよ、もっとシャキッとしなさいよシャキッと」
そう言って、エレウシアはナユタの背中を叩く。
「一人になっちゃったのが寂しいならさ、私の家で雇ってあげようか?使用人でも豪華な食事が食べられるし、何より毎日私と会えるのよ。ダンスパーティーにだって出られるし、寂しさなんか吹っ飛んじゃうわ」
端から聞けばただの自慢話だろうが、彼女なりに元気付けようとしているのだろう。確かに久しぶりに学校に来たんだから、いつまでも暗い顔をしているのはやめよう。
「ありがとう、エレウシア。なんか元気が出てきたよ」
「まっ、これも委員長としての仕事だからね。お父さんが亡くなって悲しいのも分かるけど、いつまでもメソメソしてたら天国のお父さんに笑われちゃうわよ」
そう言って、エレウシアは一時間目の準備を始めた。
「そうだ、もうすぐ授業が始まるんだ」
ナユタもいそいそと準備を始めた。
「あ、そうだ。参考書ありがとう、」
カバンの中に入っていた参考書を見て、ナユタは左隣の女の子に話しかけた。
「遅くなっちゃってゴメンね、レア」
本当ならすぐに返すつもりだったが、しばらく学校に来てなかったので遅くなってしまった。
「いいわ」
レアはそう短く答えただけで、参考書を受け取る。
レアはショートカットの女の子だ。頭がよく、IQが200を越えると言われている。だが普段はほとんど無口で、自分から話しかけることはほとんどない。いつも本ばかり読んでるし、いつも硬い表情ばかりしている。
だが”影のある美女”という点が逆に男心をくすぐるのか、密かに彼女のことを気にかけている男子も多い。
「今日からまたよろしくね」
「そうね」
ナユタとしては元気に挨拶したつもりだが、レアの返事は相変わらず短かった。
その時、一時間目の授業の開始を告げる鐘が鳴る。
「おっと、準備しなきゃ」
ナユタは慌てて準備を続ける。
「え〜と、一時間目は”歴史”だったよな」
そう呟きながら、ナユタは歴史の教科書を机の上に広げる。
「ナユタなにやってんの?」
隣からサヤカが声をかけてきた。
「何って?授業の準備だよ」
「一時間目は”歴史”じゃなくて”魔法の基礎”よ」
「サヤカこそ何言ってるんだよ。今日の一時間目は”歴史”だろ」
「それは昨日じゃない。今日は”魔法の基礎”よ」
「だって、今日は水曜日だろ?」
「違うわよ。今日は木曜日だって」
「げぇ〜、間違えた〜!」
ナユタは頭を抱える。
「呆れた〜。本当にナユタってドジね〜」
サヤカは、”ドジ”という言葉をわざと強調する。
「朝忙しかったからだよ」
こういう日に限って、同じ授業がないことが多い。つまり、今日の授業の教科書をナユタはすべて忘れてしまったのだ。
「ああ〜、どうしよう・・・・」
今日は本当にツイてない。
「わっはっはっは!いきなりやってくれるねぇ〜、ナユタ君」
それを聞いたクリスが、すかさずナユタを攻撃する。
「ほ〜んと、あんたって間抜けね」
なまじ上品な声だけに、エレウシアの言葉は心にグサッとくる。
「しょうがないわね、わたしが見せてあげるわ」
呆れ顔をしながらも、サヤカは机をくっつける。
「わるいね」
ナユタは手を合わせて謝る。だが学校での災難は、これだけではなかった。
昼休み。
生徒にとっては待ちに待った時間だ。家から持ってきた弁当を広げる者、そして食堂で買ったパンを並べる者。教室の中は、いろいろな料理の臭いが入り交じっている。
「サヤカ、弁当は?」
ナユタも腹の虫が押さえきれず、サヤカから弁当をもらおうとする。
「ちょっと待ってて」
サヤカはカバンの中から、自分とナユタの分の弁当箱をとりだした。
「はい、ナユタ。久しぶりにナユタに作ってあげるから、腕によりをかけちゃった」
「そいつは楽しみだな」
そんなことを言われれば期待は高まるが、渡させた弁当箱はやけに小さい。
「なんだか小さくない?」
これではまるで子供用の弁当箱みたいだ。
「変ねぇ、包みはちゃんとナユタの物なのに」
言われてみれば、確かに小さいとサヤカも思った。
「本当にいいの?」
幾分疑問を浮かべながらも、ナユタは包みを解く。そして中から現れたは、かわいいウサギの絵が描かれた弁当箱だった。
「何だこれ?」
ナユタは思わず拍子抜けしてしまった。どう見てもお子さま用の弁当箱だ。その弁当箱のふたには、こう書かれていた。
きくぐみ えでぃん
「ゴメ〜ン、これエディンのお弁当箱だったわ」
朝のドタバタで、サヤカは弁当箱を間違えてしまったのである。
「ど〜してくれるんだよ〜!」
とても他人には見せられないので、ナユタは慌てて包みで隠そうとする。だがそれよりも一瞬早く、あの男に見られてしまった。
「あ〜はっはっはっは、な〜んだこの弁当箱?」
「あっ、クリス・・・・」
クリスはナユタの弁当箱を奪い取ると、見せびらかすように高々と掲げる。
「いや〜ナユちゃん、かわいいお弁当箱でちゅうね〜」
ナユタをからかうように、クリスは途端に赤ちゃん言葉になる。
「坊や、何なら私がおっぱいをあげましょうか?」
さらにエレウシアが追い打ちをかける。まるで客を誘う娼婦のような表情をしながら、胸を強調するような仕草をする。
「・・・・・・」
そんなエレウシアの仕草を見て、ナユタは恥ずかしそうにうつむいた。
「ナユタの奴、真っ赤な顔をしてるぜ」
もはやクリスは止まらない。もはや教室中の注目がナユタに集まる。自分に向けられた爆笑の渦のなかで、ナユタは顔を真っ赤にしながらうつむいていた。
キンコンカンコーン・・・・
終業の鐘が鳴った。校舎の中から、一斉に生徒達が吐き出されていく。
「本当にゴメンね〜」
プンプン顔をして前を歩くナユタに向かって、サヤカは何度も謝る。
「ゴメンで済んだら警察はいらないよ」
昼休みの悪夢は、もう二度と思い出したくない。
人のことは言えないが、サヤカにもおっちょこちょいなところがある。それはそれで、サヤカの魅力の一つなのだが・・・・。
「今日は家でじっとしてるか」
今日は、下手の動くとロクなことがなさそうだ。
「え〜、エディンと遊んであげるんじゃなかったの?」
と、サヤカはとんでもないことを言い出す。
「冗談じゃないよ!」
この上あの悪ガキと関わったら、どんな災難に巻き込まれるか分かったものじゃない。
「ホントはナユタのこと好きなのよ。お父さんが出かけてるから、家には女しかいないでしょ。だからナユタに意地悪してかまって欲しいのよ。」
サヤカの言うことも分かるが、加減というものがある。どう考えても、エディンは面白がっているとしか思えない。
「もう決めたんだよ。今日はすぐ帰る」
そう言って、ナユタは早足で我が家の方に歩いていった。
「あ〜、待ってよ〜」
サヤカは慌てて追いかける。
それからしばらく歩くと、大きな屋敷の前に人集(ひとだか)りができているのを見かけた。
「何だろう?」
興味に駆られて、ナユタは人垣の方に歩いていく。
「ここって、確かエレウシアの家よね」
まるでお城のような館を眺めながら、サヤカは言った。
「そう言えばそうだね」
サヤカの言葉に、ナユタも思い出す。この館の主は、ルザイア一の大富豪ゲイルードだ。そしてその一人娘が、ナユタの同級生であるエレウシアなのだ。
「あの〜、何があったんですか?」
ナユタは商人風の男に声をかけた。
「あの張り紙見てみろよ」
そう言って、男は門の前に張り出されていた張り紙を指さした。
「なになに・・・・」
求ム!!名探偵
昨日、あの怪盗”シャドウ”から予告状が届きました。
奴が狙いを付けたのは、”エルフの涙”です。
腕に覚えのある方は、屋敷の警備に参加しませんか。
今晩見事シャドウを捕らえた者には、我が家の財宝を差し上げます。
ゲイルード
シャドウとは、最近このルザイアに出没する盗賊のことだ。シャドウは予告した者を必ず盗み、さらにその姿を見たものは誰もいない。
「”エルフの涙”って何ですか?」
ナユタは商人に尋ねる。
「最近発見された水晶だ。全体は丸くて、緑色をしてるそうだぜ。その緑があまりにも鮮やかだから、森の妖精エルフにちなんでその名前が付けられたって話だ」
その”エルフの涙”を、先日ゲイルードが手に入れたのだ。あまりにも素晴らしい水晶なので、値打ちが付けられないらしい。
「シャドウに目を付けられるなんて、エレウシアの大変ね」
サヤカが心配そうな表情をする。
「まあ、友達の家が盗賊に狙われるのは心配だけどね。そうは言っても僕たちにはどうにもできないし・・・・」
とそこで、ナユタはあることを思い出した。
(そうだ、これだよ!)
ナユタはいきなり駆け出す。
「ナユタ、どうしたの?」
「すまないサヤカ、急用ができたから先に帰るよ」
ナユタは後ろも振り返らず、あっという間に消えてしまった。
「ナインテール、さっそく事件だぞ」
早くナインテールに知らせようと、ナユタは勢いよく玄関を開ける。いきなり儲け話にありつけるとは、何ともさいさきのいいことだ。
「おお、ナユタか。どうした?」
だがそのナインテールは、テーブルの上にのって何かをムシャムシャ食べている。
「おいナインテール、何やってるんだよ!」
ナユタはナインテールの姿を見て、思わず叫ぶ。
「何って、リンゴを食べてるんだよ」
ナインテールは、テーブルに上がってリンゴを食べている。
「そのリンゴってもしかして・・・・」
「ああ、さっき知らないおばさんが来てな。ここに置いていったんだ」
「それってサラおばさんだよ。せっかく楽しみにしてたのに〜!」
隣のサラおばさんは、よくリンゴをくれる。普通のリンゴよりずっと美味しいので、ナユタはいつも楽しみにしていた。
「しかも全部食べてるし・・・・」
満腹になったナインテールは、満足そうに毛繕いをしている。
「まぁそんなことはどうでもいいから、事件って何だ?」
「おぼえてろよ〜」
ナユタ残念そうに食い散らかされたリンゴを見つめる。
「実はこうなんだ」
そう言って、ナユタはエレウシアの家での出来事を話す。
「なるほどね。まっ、ちょうどいいウオーミングアップだろう」
「でも相手は有名な怪盗だよ。注意しなくちゃ」
「前にも言ったが、すべてはお前にかかっているのだからな。しっかりやってくれよ」
「うん、分かってる」
ナユタは力強く頷く。
「よし、それじゃあいくぞ」
ナインテールは目を光らせる。途端にナユタは煙に包まれ、探偵に変身したナユタが現れた。
頭には茶色い帽子、灰色のコートを身にまとい、口にはパイプをくわえている。
「う〜ん、なかなかいいな」
口調や言葉も、すっかり探偵らしくなっている。
「それでは行きましょうか、ワトソン君」
「誰がワトソンじゃ。本当に大丈夫か・・・・」
すっかりその気になっているナユタの後を、ナインテールは冷めた表情で突いていく。
つづく・・・・
ってつづくのかよ。これって短編じゃないの?
長編作家の僕に、小さくまとまった話なんて無理無理。
後編では、いよいよナユタとナインテールのコンビが活躍します。無事にシャドウを捕まえることができるのでしょうか。
まっ、簡単に捕まっちゃあ面白くないけどね。ふふふ・・・・