ハードディスクはなくなるか?
はじめに
昨年、パソコンに関連したちょっと話題になったのが、フラッシュメモリで稼動するパソコンである。夏頃、某パソコンメーカーがハードディスクの代わりにフラッシュメモリで稼動するパソコンが発表された。これまでパソコンにおける補助記憶媒体はハードディスクが主流であり、DRAM等の半導体メモリはあくまでも一時的に情報を蓄積する主記憶装置(CPUと直接情報をやり取りするという意味で主)という位置付けであった。それが、変わってきたのである。この変化は音楽プレーヤーにも見られ、1年ぐらい前までは20ギガバイトのハードディスクプレーヤーが主流であったが、最近は数ギガバイトのメモリプレーヤーへと移行が進んでいる。
ムーアの法則
半導体に関しては、ムーアの法則というものが存在する。これはインテル社の創始者の一人であるゴードン・ムーアが述べたもので、「半導体の集積密度は18〜24ヶ月で倍増する」という法則である。
これまでの実績をみる限りこのムーアの法則は成り立っていたが、近年、その限界が叫ばれていた。これは高集積化を図るためにセルという記憶素子の微細化を進めると、電流が漏れてしまうためである。しかしながら、フォローティング・ボディ・セル(細かな内容は分からないので省略します)等の新しい技術の投入、立体化等による構造の見直しや新素材の投入によって、更に微細化を進めることが可能になってきているようである。
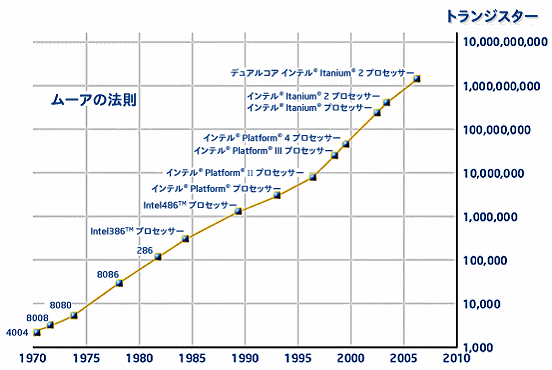
出典;インテル社ホームページ
ハードディスク
ハードディスクにムーアの法則というものはないが、半導体と同様に記憶容量が高まっている。三浦(2006)によると、ハードディスクの記憶密度は50年間で8,000万倍に拡大しており、昨今では1インチ当たり100ギガバイトとなっている。
ハードディスクに関しても、これまで用いられてきた水平磁気記録方式が高密度化の物理的限界に近付いていたが、1975年に東北大学の岩崎俊一名誉教授によって発明された垂直磁気記録方式のハードディスクが昨年から実用化され、さらに記憶密度が向上すると予想される。既に1テラバイトのパソコンは珍しくなくなってきているが、2010年くらいには1インチ当たり1テラバイトのハードディスクが出てくると予想される。
おわりに
半導体メモリの大容量化が着実に進みつつあり、ハードディスクに肉薄しつつあることは確かであるが、まだしばらくはハードディスクの利用が進むと予想される。それにはいくつかの理由がある。
一つはハードディスクの小型化、省電力化が進んでいるため、半導体メモリに代えても重量や電力の面で大きな変化が期待できないことである。例えば、某社が出したフラッシュメモリのパソコンでは、ハードディスクの場合と比較して75グラムしか軽量にならず、バッテリーもち時間も30分しか延びない。そのかわり価格は高く、ハードディスクよりも6万円以上、高くなるようである。
もう一つの理由は、我々が取り扱うデータの容量の大きさである。従来のテキスト情報だけでなく、音楽や映像情報もパソコンで管理する場面が出てきており、その容量は膨大である。ビデオカメラに関しては、ちょうどハイビジョンへの移行が進んでおり、これからもっと大容量化していくと予想される。加えて、OS等の移行もあり、今後、数十ギガ程度の補助記憶装置では心許ない。セカンドライフに見られるような仮想化の動きがより拡大し、将来的にマトリックスのようなバーチャルな世界を実現するようになるためにはテラやペタという記憶容量では全然足りず、エクサ、ヨタという単位が求められる。そのような大きな容量へ近付くためにはやはりハードディスクを活用することが不可欠ではないだろうか。
したがって、所得に余裕がある人向けのハイパフォーマンスマシンとして半導体メモリという選択肢は増えていくと思うが、もうしばらくはハードディスクの時代が続くのではないかと予想される。
参考文献
三浦義正(2006)、「.情報化社会とストレージ技術」、電子情報通信学会誌vol.89 No.11
Copyright(C) Tadashi Mima ALL Rights Reserved.