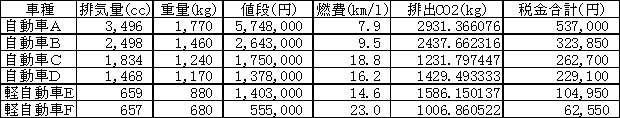
環境税について(version 2.0)
1.環境税とは
環境税は環境の利用者に課せられる税金である。通常、環境は所有者が存在しないように見えるので、環境が浪費される(環境への負荷が過剰になる)傾向があり、これを適切な量に改善するために企業や国民に課せられる税金を指す。環境税というとCO2に課せられる炭素税を指す場合もあるが、CO2以外の有害排気ガス(NOX、SOX、フロン等)、排水、土壌汚染、産業廃棄物、一般ゴミ等、地球環境に負の外部性を有するものすべてが、課税の対象となる可能性がある。
2.環境税の必要性に対する個人的見解
公共経済学的な見地から考えると、現在の我が国の経済活動やそれを取り巻く制度は地域間や所得層間の格差を緩和する方向にはある程度機能していると考えられるが、世代間の格差を緩和する方向には機能しているとは言い難い。むしろ、現世代を優先するあまり将来の世代に対して負債を背負わしている、つまり、将来の世代の経済的な価値を現世代に移転している傾向にある。これが顕著に見えるのが膨大な財政赤字であり、世代間の責任分配が曖昧なまま、現世代の便益を確保するため拡大を続けている。環境も同様であり、現世代の便益が優先され、それによる地球環境の悪化が将来の世代にもたらされる構造になっている。環境税は企業や国民の行動を環境の損失が少ない方向に誘導するものであり、環境に関する世代間の格差を緩和するための手段として必要性が非常に高いと考える。
なお、CO2は排出量等を見ると、先進諸国と発展途上国との格差も存在しており、これらの緩和を行うことも必要であろう。
一方、環境を保護するという目的だけを考えると税だけでなく他の代替手段も存在する。OECD(先進29カ国が加盟する経済協力開発機構)では、環境保護のための経済的な手段として、「税・課徴金」の他に、「補助金」、「排出権取引」、「デポジット制」を挙げている。ここでは税以外について解説することは回避するが、それぞれ運用に一長一短があり、それぞれ実現性やコストを加味し、最適なものが選択される必要がある。また、政府による「直接規制」も現在一般的に用いられている手法である。
3.環境税の考え方
環境税に関しては、ピグーとボーモル=オーツの考え方が有名である。ピグーは私的限界費用と環境負荷等を考慮した社会的限界費用との差が環境税に相当すると考えた。しかし、この考え方は社会的限界費用の測定が非常に困難であるという問題があり、そこで、ボーモル=オーツは汚染物質の排出量といった定量的に把握が可能なものに対して課税することを提唱した。これはボーモル=オーツの接近方法と呼ばれており、まず恣意的に排出量の削減目標を設定し、この目標が達成されるまで、随時税金を変動させていくというものである。CO2の排出量に課税する炭素税はボーモル=オーツの考え方を基礎とするものであり、環境税の制度運用上の効率性、説明性等の観点からこの考え方が主流となっている。ただし、ボーモル=オーツの考え方においても1単位当たりにどの程度の税金を課すことが望ましいか、つまり恣意的に設定される削減目標が妥当であるかどうか、の判断が困難であり、また、税金は制度であることから柔軟に調整ができないことも問題点として挙げられる。
また、環境税の目的が税収ではなく、環境負荷の低い活動への誘導であることを考えると、徴税だけでなく、環境への負荷の低い活動への税控除、補助金等も環境税として捉えることができる。いわゆる「バッズ課税・グッズ減税」である。
4,環境税の導入状況
環境税の比較的古い取り組みとしては、ドイツで1981年から導入された「ドイツ排水課徴金」が代表的な事例として挙げられる。しかし、この課徴金に関しては、植田和弘により「水質改善目標を達成するだけのインセンティブ効果はない」と評されている。
一方、炭素税に関しては、現在、北欧4カ国(フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク)、およびオランダにおいて導入が行われており、一番最初に導入したのが1990年に導入したフィンランドであった。その後、他の4カ国においても90年代初頭において炭素税が導入されている。税率はノルウェー、スウェーデン、デンマークが1〜2万円/トン、フィンランドとオランダが2〜3千円/トンであり、植田和弘によると「税率が低く、CO2の排出削減を促進する効果は期待できない」とされている。
しかしながら、スウェーデンの自然保護庁が行った調査によると、CO2の排出量は1987年の41,600キロトンから1994年の33,600キロトンまで約19%減少したとされており、この内、60%が炭素税によるもの(残りはエネルギー利用の効率化)とされている。
5.我が国における環境税実施に関する個人的見解
我が国においても企業や個人の活動を環境負荷の低い方向に誘導するため環境税を活用することが有効であるが、課税対象、課税方法、税収の用途等に関しては十分な検討が必要である。
課税対象に関しては、基本的に汚染物質の排出者に課税することが基本であるが、汚染物質の計測性や実施コストによって課税対象も異なってくる。課税方法に関しては、徴税だけでなく、補助金や税控除等を適当に組み合わせることが望ましいであろう。
例えば、自動車の排出する汚染物質であるが、実際に自動車のマフラーすべてに計測器を設置して汚染物質排出量を計測することは不可能である。そこで、北欧諸国で行われているように燃料であるガソリンそのものに税金を課すことが想定される。
我が国でも既にガソリンには揮発油税と地方道路税という2つの税金がかけられているが、これらは環境目的税ではなく、その用途はもっぱら道路の建設・維持に利用されている。また、同じ量のガソリンを消費しても有害排気ガスを排出する量は自動車により異なる可能性もあり、ガソリンに課税することは同じ燃費でも環境に負荷の小さい自動車を選択するインセンティブを消費者に与えないという問題もある。
このガソリン税において完全な公平性を保つためには、利用している自動車の環境負荷等も考慮することが妥当である。つまり、「ガソリンの消費量×自動車個々の環境負荷」で税金を割り出すことで低公害車購入へのインセンティブが創出される。現在、我が国では一律に低公害車への補助金を支給する方法が取られているが、消費者がどの程度走るか分からないことを考慮すると、上記の方法の方がより応益的であると考えられる。ただし、自動車の環境負荷のランク付けをしたり、それをガソリンスタンドのレジに反映する等の実施コストが大きく、実際には、補助金+ガソリン税が効率的であろう。
一方、自動車取得に関する税金に関しても環境への配慮がなされていないが、ガソリン税と異なり応益的な設定ができるのではないだろうか。現在の自動車税制が環境負荷を考慮していないことは以下の表からも明らかである。以下の表は、国内の特定のメーカーの車種をいくつか抽出し、3年間で支払う税金の額(除くガソリン税)と一定の距離(1,000km/月)を走る場合の二酸化炭素の排出量を比較したものである。自動車C、Dは軽自動車Eより二酸化炭素の排出量が少ないにも関わらず、2倍以上の税金の支払いが必要である。また、自動車Bの税金は自動車Cの1.2倍程度であるのに対して、二酸化炭素の排出量は約2倍になっている。このように、実際の環境負荷と自動車取得に関する税金はリンクしておらず、環境に配慮した消費行動の誘因とはなっていない。しかし、燃費データ等の詳細な情報がメーカーかも公表されていること、情報処理技術が向上していることから、自動車取得に関する税金において環境に配慮した詳細な設定は可能ではないかと考える。
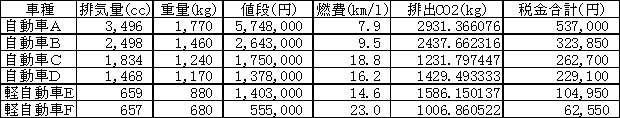
環境税の目的は、税金を徴収することではなく、人や企業の活動を環境負荷の低い方向へ誘導することであるから、環境負荷による税金の違いが実感できるような仕組みにすることが非常に重要である。つまり、国民に対して一律に環境税をかけたのでは、環境負荷の低い活動へのインセンティブは働かないので、実施コスト等を考慮しつつも可能な限り応益的にすることが望ましい。
税収の用途に関しては、環境負荷の低い活動に与えられるインセンティブ(補助金、税控除等)への活用が適当であろう。その他、環境意識の啓蒙活動資金等も用途として考えられるが、環境税本来の目的から他の用途への転用は望ましくなく、行政(地方公共団体)においては環境税を一般財源として捉えるべきではないと考える。地方分権推進計画の決定をうけて、1999年7月に地方分権一括法が制定され、地方公共団体が特定の政策目的に充てる法定外目的税として、環境税を導入することも可能になってきた。実際、いくつかの地方公共団体でも検討が進められているようであるが、財源確保を目的とした導入は回避されるべきである。また、新たな税金の導入に関しては、不必要な税金の見直しと併せて検討する必要があり、国レベルでの税金の見直しと複合的に行われること、もしくは国から地方公共団体への税源移管が不可欠ではないかと個人的には考える。実際には、産業立地面で不利になることもあり、特に工場の立地を重視する地方都市等では独自に環境税を導入することが難しいであろう。
6.環境税の経済に与える影響についての個人的見解
環境税の本格的な導入が行われていない我が国であるが、炭素税、だけでなくゴミや排水等、多様な環境汚染を対象に、環境負荷軽減方策の一つとして環境税の導入が期待される。しかし、急激な導入は国民や企業の活動に新たな負荷を創出し、国内の経済活力低下や企業の国際競争力低下につながる恐れがある。我が国の景気は依然として停滞傾向にあり、新たな負担自体が受け入れられない可能性も高く、経済活動への影響を考慮した段階的な導入はやむを得ないであろう。だだ、現状の歳出には無駄な公共事業もあることから、これらの事業を見直すことにより、必要なくなった税源を環境税に振り替えることで、企業や消費者の負荷を軽減することが可能である。つまり、税の総額に関しては現状を維持しつつ、環境負荷に応じた税の配分を重視する方向に税制をシフトするのである。具体的には、不採算道路の建設に利用されているガソリン税の環境税化、そして、先に問題として提議したように環境負荷に応じた自動車取得税の設定等が挙げられよう。また、現状において環境負荷の大きい製品を生産している特定企業への影響も苦慮されるが、このような企業には猶予期間を与えることで、環境対策の再検討を促す等の対応を取らざる得ないであろう。
この他、どの文献においても触れられているが、炭素税等の導入においては経済的な格差を踏まえた国際的な強調が不可欠である。CO2の排出量を見ると、米国、中国、ロシア、日本の4カ国で全世界の排出量の半分を占め、上位15カ国で全世界の4分の3を占めるという驚くべき統計が出ている。CO2のような気体に関しては流動的であり全世界的な影響あること、先進諸国と発展途上国との間にCO2排出における格差あること等を考慮すると、世界的な機関により何らかしらの統制を行い、公平性を確保することが急務であろう。また、このような統制は、ODA等の発展途上国支援とは独立して検討されることが望ましい。
参考文献
J.E.スティグリッツ『公共経済学(上・下)』東洋経済新報社(1996)
石弘光『環境税とは何か』岩波新書(1999)
植田和弘・岡敏弘・新澤秀則『環境政策の経済学』日本評論社(1997)
神野直彦・金子勝『地方に税源を』東洋経済新報社(1998)
環境問題関連ホームページ
東京都主税局他、税金関連のホームページ
自動車メーカーのホームページ
自治省のホームページ
Copyright(C) Tadashi Mima ALL Rights Reserved.