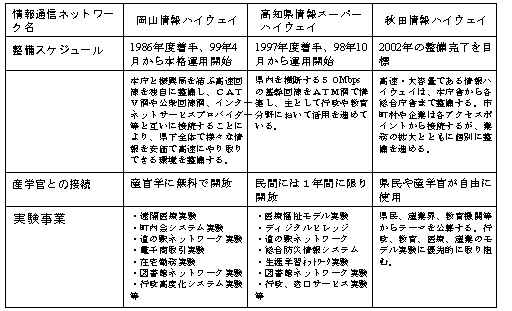
地方公共団体による情報通信ネットワーク整備に関する考察
1.はじめに
社会全体における高度情報化の進展に合わせて、地方公共団体が提供している公共サービスも情報通信技術を活用して高度化すべきであり、そのために地方公共団体自体も情報化を進めるべきである、という点に関しては現在のところ個人的にも異論はない。問題となるのは、「地方公共団体主導で進められる地域情報化がどこまでを範囲とするべきか」とういことである。一般的には、「行政が何もしなくても民間企業においてサービスが提供される都心においては民間主導で情報化を進め、民間によるサービス提供が期待できない地方や過疎地域においては行政主導で進めるべきである」と言われているが、本当にそうであろうか。昨今では、アウトソーシング、PFI(Private
Finance Initiative)、PPP(Public Private Partnership)等、民間活力を活用する手法が注目を集めているが、このような潮流を踏まえると、可能な限り行政主導から民間主導へ切り換えていくべきではないかとも考えられる。また、何を規準にして民間と行政の役割分担を行うべきなのかも大きな疑問であり、我が国の現状を見ると役割分担が曖昧なまま、すべてが政府(地方公共団体)に委ねられている感がある。
一方、ここ数年におけるインターネット普及の進展は目覚ましいものがあり、『平成11年版通信白書』によると、平成10年における我が国のインターネット人口は約1,700万人と推計され、商用利用開始後わずか5年間でインターネットの世帯普及率は10%を突破している。マルチメディア情報を扱うこのインターネットの普及にともない、大容量の通信回線へのニーズも年々高まってきており、米国の事例を参考として、我が国でも独自に情報通信ネットワーク(通信回線を含む)を整備する地方公共団体が出てきている(注1)。そこで、本稿では、本当に地方公共団体において整備することが望ましいのかどうか、情報通信ネットワークの整備の理由をもとに考察したい。
2.情報通信ネットワーク整備の理由
地方公共団体が自ら情報通信ネットワークを整備するのにはいくつかの理由が考えられる。以下に、理由を簡単に整理し、次節以降、この理由について詳しく検討する。
1)公共的側面とユニバーサルサービス
インターネットを含む新たな情報通信サービスは家庭や産業分野において急速な普及を見せており、「日常の活動に不可欠となってきている」ことから公共的な性格が強くなり、ユニバーサルサービス(注2)が求められている。しなしながら、民間企業を中心とした情報通信サービスの供給体制においては、ネットワーク整備も市場性の高い都心から進んでしまう。そこで、「インターネット等を利用できる環境をあまねく整備する」というユニバーサルサービス実現の観点から、公共サービスを司る中心組織として地方公共団体が情報通信ネットワークの整備を行っている、と捉えることができる。
2)地域間競争の手段
政府や地方公共団体の存在理由は元来、市場の失敗を理由としており、市場において十分な提供が確保されない公共財や公共サービスの提供等が主な目的とされてきた。しかし、近年において、地方公共団体の役割の1つに地域間競争の担い手としての側面が強調されており、地域の競争優位として情報通信ネットワークの整備の必要性が増してきた、と捉えることも可能である。
3)行政組織そのものの情報化
昨今の企業における情報通信ネットワーク整備は目覚ましいものがあり、LAN(Local Area Network)やWAN(Wide Area Network)はもとより、企業間のWANを構築して業務の効率化を図る事例も珍しくない。このようなことから地方公共団体においても組織そのものの情報化や業務の効率化を図る上で、本庁と出先機関、関連機関を結ぶ情報通信ネットワークが必要になった、とも捉えることができる。
4)政策決定の特性
政策決定の過程においては少なからず政策決定に関わる者の志向や上位機関の意向が反映される。このような政策決定過程の政治的な特性により、ある地方公共団体では情報化施策が重視され、情報通信ネットワーク整備に至った、と捉えることもできる。
3.公共的側面とユニバーサルサービス
従来から通信サービスは、電気、ガス、水道、交通等と同様に公共性の高い公益事業の代表とされてきた。単純に、このような公共性の高い公益事業は政府、もしくは地方公共団体が行うべきであるとも考えられるが、一般に企業組織の方が効率的であるとの観点から、これらの公益事業のほとんどが民間企業、公営企業、特殊法人等により運営されている。だが、一方で、その公共性を確保するために、それぞれに法律等による公的な規制を設けている(注3)。通信サービスに関しても同様であり、1952年に設置された日本電信電話公社、いわゆる電電公社が、1985年に日本電信電話株式会社(以下、NTT)として民営化される際に制定された電気通信事業法、およびNTT法により規制されている。このようなことから、通信サービスは公共的な性格が非常に強いと考えられるが、ここで注意しなければならないのは、ここで言う「通信サービス」とは電話を中心とした従来型のサービスであり、インターネットに代表されるような新たな「情報通信サービス」とは異なるということである。従来から提供されている電話等による通信サービスに関しては、NTT法においてユニバーサルサービスの提供がNTTに課せられているが(注4)、現状において新たな情報通信サービスに対してユニバーサル・サービスを規定した法律はない(注5)。つまり、昨今の急速な高度情報化の進展にともない新たな情報通信サービス、および情報通信ネットワークの公共性が高まったにもかかわらず、ユニバーサルサービス等の制度面における対応が遅れたため、地方公共団体が民間企業に代わって情報通信ネットワークを整備したと捉えることができる。
このような現状から情報通信ネットワークの整備は、各地域における公共サービスの中心を司る地方公共団体の対応として妥当性が高いものであると考えられるが、ここで問題となるのは、台頭してきた新たな情報通信サービスが公共性やその他の観点からユニバーサルサービスに値するかどうかということである。
公共性を検討する場合の1つの視点は、公共財か私的財か、ということである。公共財の特徴は、非排除生(財の消費に関して対価を支払わない者を排除することが困難なこと)、非競合性(財の消費に参加するものがお互いに競合しないこと)を有することであるが、完全な非排除性、非競合性を持つ純粋な公共財はほとんどなく、国防と外交等が代表的なものとなる。先に挙げた電気、ガス、水道、交通等はこれらの特徴が不完全な状態で存在する準公共財である。ここで、情報通信ネットワークが公共財に該当するか、インターネット(この場合ネットワークを構成する通信回線や機器も概念として含む)を例にして検討してみる。インターネットは商用サービスとして提供している場合、対価を支払わない個人を排除することは商用サービスを提供している企業において容易である。しかしながら、インターネット全体として特定の個人を排除することは非常に困難である。また、インターネットの利用に関しては、よく交通に例えられるが、通信回線や機器の容量を超えない範囲において利用する場合、つまり一定数までは新たな利用者による競合性は存在せず、一定数以上に利用者が増加した場合のみ混雑現象による競合性が発生する。このようなことからインターネット等に代表される情報通信ネットワークは、不完全ながら非排除性、非競合性を持つ準公共財であり、従来の通信サービス同様、公共性が高いと言える。加えて、情報通信ネットワークには「ネットワークの外部性」と呼ばれる正の外部性が存在するため、社会的に望ましい供給量よりも少ない量で均衡すると予想され、これも政府(地方公共団体)の介入を必要とする理由の1つと言えよう。
では、国民の生活に不可欠な存在になっているかどうか、という観点ではどうだろうか。ここでもインターネットを例に取るが、『平成11年版通信白書』によると、我が国のインターネット普及率は、世帯普及率で11.0%、利用人口は約1,700万人(総人口の約13.5%)となっている。したがって、急速に普及が進んでおり、企業普及率も80.0%と高いものの、国民への普及率から見ると、国民生活に不可欠なものであり、ユニバーサルサービスに値するとは言い難い(注6)。
以上の検討から、インターネットに代表される情報通信ネットワークは公共性を有している反面、依然として国民生活に十分浸透しているとは言えず、現状ではユニバーサルサービスに値するとは必ずしも言えないと言える。また、このユニバーサルサービスの担い手として地方公共団体が適切かどうかも問題を残すところである。郵政省『マルチメディア時代に向けた料金・サービス政策に関する研究会報告書』(1998年6月)では「普及初期においては地方公共団体における先導も必要」としているものの、ユニバーサルサービスの担い手としては民間企業を念頭においており、地方公共団体における情報通信ネットワーク整備には民間企業との棲み分けといった課題も存在する。
4.地域間競争の手段
昨今の景気低迷にともない地方公共団体の財政が逼迫する中、各地方公共団体においては税源を確保するための産業の育成・誘致、人口の維持・増加が1つの大きな課題になっている。そこで、各地方公共団体ではこの課題を達成するために地域の魅力を高める様々な施策を展開している。日本全国における人口や産業の総数は急に増加しないので、ある地域への産業・人口の集積が進めば、別に産業・人口の減少する地域も存在する。このような背景により、1988〜89年に行われた「ふるさと創生1億円事業」以来、各地方公共団体独自の施策を基にした地域間競争が激化しているように見受けられる。
情報通信基盤は産業に不可欠なインフラストラクチャーであり、企業誘致の観点から情報通信ネットワーク整備の重要性は高まっていると言える。ただし、情報通信ネットワークを提供する民間企業はユーザーのあるところにサービスを提供するので、どうしても事後的な対応にならざる得ない。したがって、企業誘致等の観点からを地方公共団体が自らが先行的に情報通信ネットワークを整備したり、これを基に立地企業に安価な通信環境を提供することは、ある程度有効であろう。また、高度な情報通信サービスを安価に住民に提供することにより、これらのサービスを嗜好する者が転入し、住民増加等も期待できる。しかし、情報通信ネットワークは住民や企業を誘引する要因の1つに過ぎず、交通、市場、住環境等様々な要因を含めてトータルに評価されることを地方公共団体は認識する必要があろう。加えて、前項で述べたように民間企業のサービスと競合する可能性についても考慮することが不可欠である。
また、情報通信ネットワークの整備が地域間競争における競争優位として有効なことと、このような地域間競争の側面が望ましいかどうかは別問題である。企業においては市場における競争が商品やサービスの向上に寄与するものとして歓迎されるが、これは競争に負けた製品や企業の淘汰が一方において起こっている。しかしながら、このような淘汰のない地方公共団体では市場原理が機能しているとは言い難く、過当な地域間競争が、不必要な公共施設整備や、採算の取れない第3セクターの設立、等多くの問題をもたらしてきたことも事実である。今後、政策評価等により地域間競争のための過大な施策展開へのチェック機能を強化するとともに、肥大化した機能の縮小を念頭においた地方公共団体の改革も方向性としてあり得るのではないだろうか。一方で、複式簿記による会計制度の見直しや政策評価等の必要性が叫ばれていることから、これまで以上に地方公共団体における企業的側面が強調されてきており、公共サービスの供給が不十分となることも危惧される。
以上の検討から、地域間競争の手段として地方公共団体が情報通信ネットワークを整備することは有効であると考えられるものの、政策評価を行い、適切な投資規模や民間企業との役割分担等について十分な検討を行うことが必要不可欠である。
5.行政組織そのものの情報化
高度情報化の進展にともない、企業だけでなく地方公共団体の内部においても情報化、いわゆる行政情報化が進んでいる。1963年に大阪市がコンピュータを導入したのを始めとして、地方公共団体では当初、税務、住民記録等の大量提携業務を処理の効率的な処理を目的として、汎用型の大型コンピュータの導入が進んだ。だが、近年では、企業同様、否定形業務の増加への対応、内部におけるコミュニケーションの効率化、住民サービスの向上等を目的として庁内LANやネットワーク型の情報システムの整備、インターネットへの接続等が進んでいる(注7)。このような中で、本庁舎と支庁舎、出張所等の出先機関において同様の情報システム利用を可能にするために広域的な情報通信ネットワークの整備が想定され、特に昨今では教育分野(公立の小・中学校)におけるインターネット利用を実現する目的からも、ある程度の容量を持つ情報通信ネットワークの確保が望まれている。
しかし、現状における本庁舎と出先機関との情報流通量、加えて小・中学校における利用等を考慮しても、都道府県でも数Mbps〜数十Mbps、市町村では数百Kbps〜数Mbps程度の通信速度で十分であると予想され、いくつかの都道府県の情報通信ネットワーク整備構想で示されているような広帯域の光ファイバー網は過大ではないか、と考えられる。また、地方公共団体のみの利用であれば、民間の通信事業者から回線を借り受ける等の選択肢もあり得る。実際、これらの構想を見ると、産学官への無料開放や、多くのアプリケーション実験事業の実施を想定している事例が多く、これが情報通信ネットワーク整備の理由の1つになっているように見受けられる。加えて、このような大容量の情報通信ネットワークを地方公共団体が自前で整備するべきかどうかも疑問であり、近年注目されているPFI等の選択肢もあるのではないだろうか。
以上のことから、地方公共団体そのものの情報化は進んでいるものの、現状の利用においては大容量の情報通信ネットワーク整備を必要とするには至っておらず、将来的な行政サービス・アプリケーションの実験的な側面が大きい。また、産官学への無料開放等は、情報通信サービスを提供している民間企業の活動を圧迫する側面が少なからずあり、これに関する言及が為されていないことも政策の不透明性な部分ではないだろうか。
図表1 地方公共団体の情報通信ネットワーク整備の構想概要
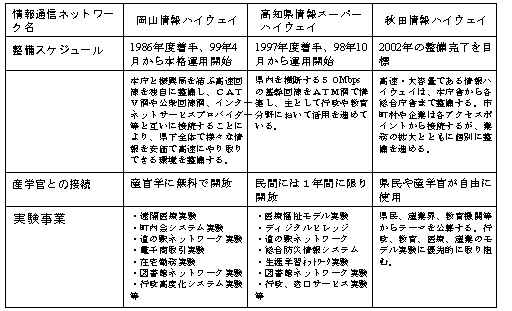
出典:各種資料から作成
6.政策決定の特性
政策決定が政治過程から多大な影響を受けることは珍しくない、足立幸男も「公共政策は一般に純粋な知的分析の産物ではないし、そのようなものとすることもできない。端的にいって政治過程の産物にほかならない。」と言及している。(注8)
地方公共団体における情報化の推進に関しては、アンケートによる地域のニーズ抽出等の分析過程がないわけではないが、事前に決定している政策を裏付ける情報を抽出するために情報収集が行われることもあり、首長や一部のキーパーソンの政策的志向が反映されている場合も多い。特に岐阜県の梶原知事、高知県の橋本知事、三重県の北川知事等は情報化の推進に関して強力なイニシアチブを発揮していると見受けられる。また、端末を配布したことで有名になった富山県山田村の事例に関しても、倉田勇雄というキーパーソンと小西助役が先導的な役割を果たしたことが倉田勇雄『山田村の行進曲はインターネット』から窺える。したがって、情報通信ネットワークを整備するという政策に関しても、純粋に公共的な見地からのみ提案されたのではなく、首長やキーパーソンの志向が少なからず反映されたものになっていると予想される。
一方、「3割自治」という言葉に代表されるように、地方公共団体の財源の多くは中央省庁からの補助金や地方交付税交付金でまかなわれており、それ故、中央省庁の政策的な方向の影響を受けざるを得ない。昨今、政府により景気回復に向け公共事業拡大が実施されたが、農道やダム等を中心とした従来型の公共事業の反省から、都市環境の改選や情報化事業等を中心に据えた都市型公共事業への転換を図っており、これが地方公共団体の政策にも影響を及ぼしていると考えられる。実際、1998年11月に政府が実施を掲げた『21世紀先導プロジェクト』には先端電子立国の形成するための2つのプロジェクトの1つとして「情報ハイウェー、光ファイバー網・CATV網の整備・高度利用」が示されている。
以上の検討から、地方公共団体における情報通信ネットワーク整備という政策は、特定の個人の志向や上位機関の政策から少なからず影響を受けていると言える。前者に関しては政策を決定するのが人であり、首長をトップとした議会組織により政策が決定される以上、このような影響があることは当然であるとする考え方もあり、一概に悪いとは言えない。一方、後者に関しては、税の配分等、我が国の行政システムそのものの見直しを行わなけらばなくなることはないであろう。
図表2 『21世紀先導プロジェクト』の概要
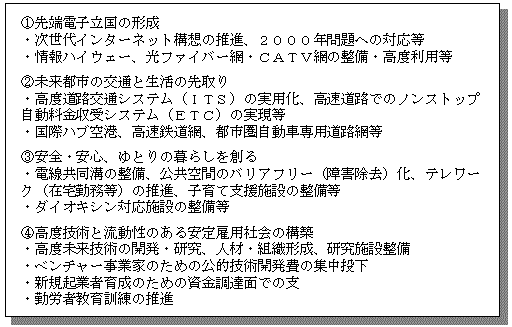
出典:自由民主党のホームページ
7.おわりに
上記の検討から、インターネット等の情報通信ネットワークに関しては公共性があるもののユニバーサルサービスに値するとは現状において言えず、地方公共団体による情報通信ネットワークの整備という政策は、実験的な要素や地域間競争の競争優位創出としての性格が強いと言える。また、政策決定過程によりおいても、特定の個人の志向や上位機関の政策が少なからず反映されており、公共性や地域特性を踏まえると必ずしも最適の施策となっているか疑問である。
一方、産官学に無料開放している事例もいくつかあり、同様の情報通信サービスを提供する民間企業との役割分担に関しても問題点がある。「市場原理にともなう地方における情報通信基盤整備の遅れ」を各地方公共団体とも主な整備理由として挙げており、現状のみを考慮すると、この理由の妥当性は高い。しかし、将来的に民間企業におけるサービスが展開されるようになった場合の役割分担はどのようになるのであろうか。情報通信ネットワークに関わる組織のみNTTのように民営化されるのであろうか、それとも地方公共団体から民間企業に払い下げられ、移管されるのであろうか。このような点に関する検討が不十分のであることも指摘される。
したがって、この政策を否定するまでの要因は見つからないものの、いくつかの問題点や課題が存在しており、情報通信ネットワークを構築した、もしくは構築を政策として打ち出した地方公共団体においては、このような政策の特性を踏まつつ定期的に政策評価を実施し、運営形態や将来の展開等に関して随時見直しを行うことが求められよう。
また、いくつかの地方公共団体では大容量の情報通信ネットワーク整備が先にあり、アプリケーションは後から検討する、という手順により政策が実施されているが、この手順にも問題がある。政策のアカウンタビリティ(説明性)という観点から考慮すると、アプリケーションの検討がまず先にあり、アプリケーションの活用に必要な規模の情報通信ネットワークの整備が提案されるべきであろう。したがって、今後、同様の政策を検討する地方公共団体においては上記のような手順を踏むことが望ましく、加えて、自前の整備だけでなく、PFI等により民間活力を用いた整備も選択肢として検討する必要があろう(注9)。
政府、地方公共団体に限らず、政策が常に最適なものであるという保証はなく、将来を考慮した長期的なスパンの政策になればなる程、ある程度のズレや失敗が生じることは否定できない。しかし、限られた労力と期間において可能な限り妥当性の高い政策を選択する必要があり、この過程において「市場の失敗」だけでなく、「政府の失敗」も考慮し、可能な限り市場(民間企業)に委ねるようにすることが望ましいのではないだろうか。また、政策決定においても、政治的な過程を否定する訳ではないが、公共性、採算性等の分析過程を重視することも不可欠と考える。
(注1)米国では、1992年にの大統領選挙等を契機として「情報スーパーハイウェイ」を構築するという『NII(National
Information Infrastructure:全米情報基盤)構想』が打ち出され、ノースカロライナ州、アイオワ州等、いくつかの州では独自の情報通信ネットワーク構築も行われた。これを受け、我が国でも1996年に岡山県が『岡山情報ハイウェイ構想』を打ち出したのを始め、秋田県、石川県、高知県等においても同様の政策が発表され、光ファイバーによる情報通信ネットワーク整備が進められている。
(注2)ユニバーサルサービスとは、「誰でも、どこに住んでいても、妥当な価格でサービスが受けられること」を言う。
(注3)電気は「電気事業法」(1964年公布)、ガスが「ガス事業法」(1954年施行)、水道は「水道法」(1957年制定)等により規制されている。
(注4)NTT法では「電話の役務のあまねく日本全国における安定的な供給の確保」として、NTTに対してユニバーサルサービスの提供が課せられている。
(注5)具体的な法律、規制はないものの、郵政省では『マルチメディア時代のユニバーサルサービス・料金に関する研究会報告書』(1996年5月)において「ユニバーサルサービスの範囲を電話に限定するのではなく、マルチメディアサービスを含めたものに拡大することが必要である」と提言している。
(注6)郵政省『マルチメディア時代に向けた料金・サービス政策に関する研究会報告書』(1998年6月)によると、国民生活に不可欠と言うための最低限の普及率は50%であり、EUでは75%を目安としているようである。
(注7)自治省の『電子計算機の利用状況調査』(1998年4月)によると庁内LANシステムの整備状況は都道府県91.5%、市町村37.5%であり、この庁内LANシステムの内、出先機関に接続しているものがそれぞれ57.8%、53.0%、インターネットに接続しているものがそれぞれ15.0%、6.0%となっている。
(注8)足立幸男『公共政策学入門』有斐閣、1頁
(注9)確かにいくつかの構想には「民間活力を活用する」等の記述も見られるが、具体的な方策や棲み分けの規準は示されていない。
参考文献
政府『緊急経済対策資料』
高知県『高知情報スーパーハイウェイに関する資料』
秋田県『秋田情報ハイウェイ基本構想』
岡山県『岡山情報ハイウェイ パンフレット』
石川県『いしかわマルチメディアスーパーハイウェイ基本構想報告書(案)』
郵政省『マルチメディア時代のユニバーサルサービス・料金に関する研究会報告書』
郵政省『マルチメディア時代に向けた料金・サービス政策に関する研究会報告書』
郵政省『平成11年版通信白書』
自治省の『電子計算機の利用状況調査』
足立幸男『公共政策学入門』有斐閣
石井春夫『現在の公益事業』NTT出版
三友仁志編著『マルチメディア経済』文眞堂
福田豊・須藤修・早見均著『情報経済論』有斐閣
倉田勇雄『山田村の行進曲はインターネット』くまざさ書房
野長瀬裕二「地域情報化戦略に関する研究」、『オフィス・オートメーション 1998 Vol.19』73〜79頁
Copyright(C) Tadashi Mima ALL Rights Reserved.