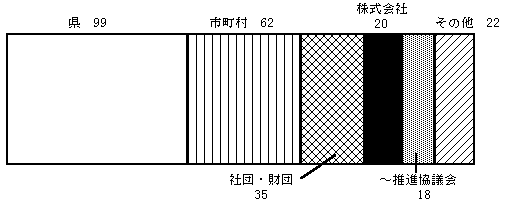
地域情報化における情報メディアの活用−パソコン通信に関する考察−
1.パソコン通信の現状
日本には約2,400局のパソコン通信ネット局があり、総会員数の合計は約260万人になると推計されている(平成6年度『全国パソコンネット局実態調査』)が、パソコン通信を利用している者の中には複数のネットに加入している者も多く、「260万人」という数字が示すほど利用者は多くない。
しかしながら、昨今における低価格化の進展、ユーザーインターフェースの発展にともない家庭へのパソコンの普及は急速に進んでおり、今後、パソコン通信がメディアの1つとして期待されることは必然的である。
本稿では、地域情報化におけるパソコン通信の活用に関して考察することとし、パソコン通信ネット局の中でも特に地方自治体、公共団体、第3セクター等の運営するものに焦点をあて、現状、地域情報化における役割、導入・運営におけるポイント等について整理した。
2.地域情報化におけるパソコン通信の活用状況
地方自治体、公共団体、第3セクター等が設立している。もしくは設立を予定しているパソコン通信ネット局は全国で256局あり(平成6年版『地方公共団体における地域情報化施策の概要』)、都道府県平均5つのネット局があることとなる。設立年次をみると、だいたい1987年頃から設立が開始されており、1990、91年に最盛期を迎え、現在、設立数は減少傾向にある。
会員数は既存の242局の合計で約25万人となっており、平均すると1ネットあたり約千人程度ということになる。しかし、実施はK−NET等の比較的大きな一部のネット局が半分近くの会員を占めており、8割以上のネット局が会員千人以下となっているのが現状である。
3.パソコン通信ネット局の概要
地方自治体、公共団体、第3セクター等が設立しているパソコン通信ネット局の概要を整理すると以下に示すような特徴がみられる。
1)事業主体
地方自治体が直接運営しているネット局が多く、県、市町村を合わせて約6割を占めている。一方、第3セクターによる運営はCATVと比較して少なく、これは企業として採算をとることの難しさを反映していると予想される。この他、ニューメディア推進協議会や商工会議所等が運営しているネット局もみられる。
図表1に事業主体の内訳を示す。
図表1 パソコン通信ネット局の事業主体の内訳
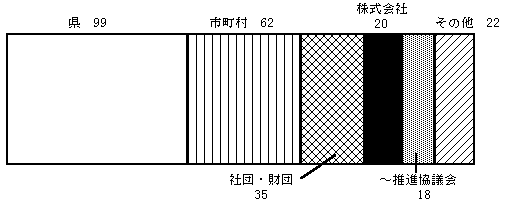
出典:平成6年版『地方公共団体における地域情報化施策の概要』
2)会員
会員を無制限としているネット局は93局であり、6割以上のネット局が会員の範囲に何らかの制限を設けている。制限の種類としては、以下に示すようなものがみられる。
・居住地域を限定<ヒューネットいたばし(板橋区)、TOSMIC(栃木県)等>
・特定の団体に限定<ふれあいネット(北海道)、TAOシステム(奈良県)等>
・庁内職員に限定<行政ネットワークシステム(滋賀県)>
・農業関係者に限定<アグリネット石川(石川県)、RACC内子(愛媛県)>
・学者、研究者等に限定<静岡県研究情報ネットワークシステム(静岡県)等>
3)サービスメニュー
電子メール、電子会議室、電子掲示板、情報提供等は一般的なサービスとなっているが、ユーザーキャビネット、ゲートウェイ、ファックス配信等のサービスを行っているネット局はまだ少ない。また、情報提供のみを行っているネット局もいくつかあり、行政情報だけでなく観光情報、図書館情報等を提供している。
4)設立経緯
テレトピア構想、ニューメディア・コミュニティ構想等、中央省庁における地域情報化支援施策の指定を受けたことにともない、地域情報化事業の一環として設立されたネット局と、地域独自に検討して設立されたネット局がある。
4.地域情報化におけるパソコン通信の役割
地方自治体が地域情報化事業のねらいとするところは、「住民サービスの高度化」、「地域の活性化」、「住民の情報リテラシー向上」等であり、パソコン通信は、CATV、コミュニティFM等と同様に、これらの目的達成を促す1つのツールとして位置付けられている。
現在、パソコン通信の普及が十分に進んでおらず、地域情報化において果たす役割も他の情報メディアほど大きくないが、パソコンの急速な普及にともない情報メディアの1つとして着実に発展している。現状、および将来においてパソコン通信に期待される役割を以下に示す。
1)地域全体における情報化推進
パソコン通信ネット局を設けることは地域住民の情報化に対する意識高揚に寄与する。特に地方自治体が直営する場合は、内部に運営を担当する専門部署が設置される場合があり、住民だけでなく、庁内の情報化にも貢献している。
また、会員の交流会を開いているネット局も多く、通信上の情報交流だけでなく、フェイス・トゥ・フェイスの情報交流にも一役買っている。
2)産業の高度化、ネットワーク化
パソコン通信ネット局には中小企業振興公社等が運営しているものもあり、地域の中小企業のネットワーク化に貢献している。具体的には、地域企業のデータベースを構築することで企業間の提携、技術交流を促進したり、地域企業全体における受発注のバランス取りを行っている。この他、農業、漁業、観光等、他の産業分野に関する情報提供に特化しているネット局もあり、それぞれの産業の高度化に寄与している。
また、このようなパソコン通信ネットワークの整備は、地域におけるソフト産業の発展に貢献することも将来的に期待される。
3)地域情報の提供
地方自治体が運営しているネット局のほとんどはメニューの1つとして行政情報の項目を設けており、議会や公共施設の利用等に関する情報を提供している。中でも休日における病院の開院状況等、医療に関する情報は比較的利用が進んでおり、住民の利便性向上に寄与している。
現状では、行政県連の情報提供サービスを行っている事例が多いが、今後は商店街情報、図書館情報、リサイクル情報、交通情報等の生活に密着した地域情報サービスの拡充も期待される。また、阪神大震災の例からも窺えるように、地震等の災害時における情報伝達手段の1つとしての役割も期待される。
5.地域情報化におけるパソコン通信活用のポイント
地方自治体や公共団体が地域情報化を進める上でパソコン通信を活用する場合、以下のポイントに留意することが重要である。
1)目的の明確化と必要性の検討
地域においてパソコンの普及が進んでいない場合、ネット局を開設しても得られるメリットは少ない。目的が「住民の情報リテラシー向上」であるならば、無理にネット局を開設せず、既存の商用ネットを活用した啓蒙活動を行うことの方が有効である。また、「住民に対する情報提供」が目的である場合は、他の情報メディアとの比較を行い、その必要性を十分に検討する必要がある。
また、地元に任意の団体が運営し、成功しているパソコン通信ネット局がある場合、無理に行政独自のネット局を開設する必要はなく、そのネット局と協力した地域情報化を模索することも考えられる。
2)運営主体の検討
パソコン通信ネット局の運営は、専門の知識があり、パソコン通信が好きな者により行われることが望ましい。現在、約6割のネット局が地方自治体により直営されているが、パソコンに対する知識のない者が運営部署に配属されることもあり、事前に内部人材の検討を図る必要がある。もし、内部にネット局運営に適した人材がいない場合は、以下に示すような対応を図ることが望ましい。
・運営主体として第3セクターを設立し、人材を募集する
・教育を行い運営能力のある人材を育成する
・機器の運用等を大手商用ネットにアウトソーシングする
・任意のボランティアに運営を委託する
3)大手商用ネットとの差別化
地域のパソコン通信ネット局が大手商用ネットと同様である場合、住民が大手商用ネットの会員となる可能性は高い。そこで、どのような点で大手商用ネットと差別化するかが地域ネット成功のキーポイントとなる。差別化のポイントとしては、「地域独自の情報提供」と「密着したサービス」の2点が挙げられる。
地域独自の情報においては、行政情報だけでなく、生活に密着した商店街情報、図書館情報、リサイクル情報等の充実が必要である。
また、交流会を開催して会員のフェイス・トゥ・フェイスの交流を図ったり、会員のハードトラブルに対応する等は大手商用ネットでは困難な密着したサービスであり、差別化の大きなポイントとなる。
4)女性、子供、高齢者の利用促進
現在、パソコン通信の会員のほとんどが成人男性である。そこで、今後、女性、子供、高齢者の利用をどれだけ拡大することができるかが成功の大きなキーポイントとなる。ネット局は、女性、子供、高齢者の利用を促進するために以下に示すような対応を図ることが望まれる。
・スーパーマーケットの食材の値段に関する情報提供、ホームショッピング等、主婦の望むサービスメニューの充実
・学校におけるコンピュータ教育と連動したパソコン通信の啓蒙活動
・ゲーム関連のフォーラム等による子供が望むサービスメニューの充実
・講習会の開催やモニター制度の実施による啓蒙活動
Copyright(C) Tadashi Mima ALL Rights Reserved.