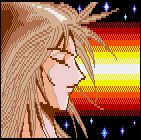 ここでの主人公『ディーク』
ここでの主人公『ディーク』
すべてはセルジュア帝国の反帝国暗殺集団”犬狼の牙”
を牛耳る頭ハンズの一人息子ディークの嫁とり問題に始ま
った。ディークはこの年21歳。結構な美丈夫で、暗殺集
団の大抵の若い娘達は彼の姿に魅せられた。
21歳にもなると、身の周りの者達は彼も当然妻をめと
ってもよい頃と考えるようになり、彼との会話の内容とい
えばほとんど「ディーク様!御結婚はいつですか?」とか
「未来の”犬狼の牙”をしょってたつ方であられる以上は
ハンズ様のご心配もおさしになってくださいまし。」とか
「キャー!!ディーク様、私を嫁にもらってー。」という
ものばかりである。しかし、ディーク自身は結婚というも
のには全く関心を持っていない。今でも色好きな父親と比
べて彼はそれぼど異性に深い興味がないのである。とにか
く彼に言わせれば、結婚がどうだというんだ。”犬狼の牙
”の頭の息子だからといって結婚をしなければならない義
務などない。第一、暗殺集団の頭を世襲で決めるなどそん
なバカげた話があるか。力ある者が頂点に立ち、下の者を
束ねればいいのだ。俺は別に頭になりたくはないし、ただ
暗殺者としての生き方をまっとうできればそれでいい。と
いうことになる。それを口に出して言えばさらに騒ぎを増
やすだけなので、彼は沈黙を守っているのだが、結婚の話
がもちだされる度に舌打ちを禁じ得なくなるのである。
そんな彼を父ハンズはある晩、彼の寝室に訪れた。一人
の美女を連れてである。その美女は”犬狼の牙”の領地で
最も美しいとされている黒髪に暗緑色の瞳をもつ19歳の
アメリアという健康的な女性で、それを見たディークは「
美しい女だ。」と簡素な感想をもったが、それよりも、な
ぜ親父とこの女が俺のところに来たのだろうと疑問にとら
われた。その答えはすぐに父の口から発せられた。
「ディークよ、お前はこのわしと同じ血が流れているとい
うのに21にもなって今だ女の良さを知っていない。いや
、知ろうともしない。なあ我が息子よ、男はな、女に奉公
すべき生き物なのだ。女もそうされたがっている。それを
お前は全くしようとしないではないか。恥ずべきことだぞ
。」
「ふん、勝手にお前の理念を俺に押し付けるなよ。俺はア
ンタとは違うんだ。」
と心に思いつつディークはハンズの話を黙ったまま聞き
続けた。
「わしはお前が心配でならん。そして周りの者達も同じく
心配してくれている。お前がこのまま女に見向きもせずに
一人身で生きていくのではないかとな。しかし、お前はわ
しの子だ。必ずや女に興味があるであろう。そう、お前は
自分の好みの女に出会っていないだけだったのだ。そこで
今日はこの娘を呼んだ。名はアメリア。男であれば誰しも
心ひかれる美しい娘だ。気立てもいいともっぱらの噂だ。
その娘が前々からお前に恋い焦がれていたのだという。ど
うだ?後はお前の意志次第だぞ。悪い話ではあるまい。」
ははぁーん、そういうことか。ディークはようやく父親
の魂胆を見抜いた。しかし、夜にこの娘を呼ぶというやり
方が気にくわない。どうせ、俺が欲にかられて彼女と一夜
を共にしたことを証拠に結婚を拒否できなくするというの
がおおよその魂胆なのだろう。何てくえない親父なんだ!
アメリアとはいうと、こうである。
「ディーク様、私でよろしければ、それは私にとってこれ
とない幸せでこざいますわ。」
と一言。もうその気であるようだ。娘は純粋な恋心で、
父は一応純粋な親心で言っているのであろう。だが、ディ
ークにしてみれば勝手過ぎる迷惑話であり、ついに今まで
心の奥でくすぶっていた怒りの感情が忍耐を越えて目に見
えるかたちで爆発した。
「もう、いい加減にしてくれっ!!!」
それは館中に響き渡るほどの怒号であった。ハンズとア
メリアは驚きのあまり3歩ほど後ろへよろめいたが、ディ
ークは気にもせず続けた。
「女なんてどうだっていいっ!俺はこのままの生き方で満
足しているんだ。親父、俺達は帝国に打倒する暗殺団なん
だぞ、こんなことで悩んでいるよりもすべきことがあるの
ではないのか!?」
たしかにディークの言い様にも正しい部分があるのかも
しれない。しかし、頭としてこれからも暗殺集団の存続を
約束しなくてはならない立場であるハンズとしてはそのま
ま引き下がる訳にはいかない。もしも、頭の正統な後継者
がいない事態に陥ったときは暗殺団という組織柄から必ず
内部で権力闘争が起こることは間違いないからである。よ
って人の上に立つ者は妻をもうけ、自分が次代の後継者と
なる子を得られることを皆に知らしめておかねばならない
。これは義務であるのだ。
一瞬、息子の威勢にたじろいていたハンズであるが、決
心したような真顔になるとディークに言った。
「お前の言いたいことはよく分かった。だが、お前が妻を
めとらないことを頭としてどうしても認める訳にはいかぬ
。よって、お前に命令する。明朝、即刻この領地を発ち、
お前にふさわしい女性を見つけてこい。それまでここへ戻
ってくることを断じて認めん。これは決して追放ではない
。条件を満たし帰還したその時には、わしはお前に頭の地
位を譲ろう。」
いきなりの父の命令にディークは言葉を失ってしまった
が、それはそれでおもしろい、受けてやろうじゃないか。
と心に決め、彼は命令を承諾した。そして、彼は約束通り
、明朝この地を発ったのである。彼に考え直させようとし
た者達の説得を押し切って・・・
それから3日後、ディークは平民の服装、一本の三日月
刀、そして少々の金銭を持ち、セルジュア帝国首都テセナ
にたどり着いた。そこで彼がよく耳にした話題は第一王女
メルナートについてである。なんでも彼女を見た吟遊詩人
が彼女を「美の神々が創りあげた至高なる芸術」と評した
ほどの美しい女性であるらしく、貴族の若者達が血気盛ん
に彼女の気をひこうとしているということだ。そこで彼の
頭にひらめいたこととはこの女性を自分の妻にしてはどう
だろうか、ということであった。したくもないのに妻とす
る女を捜さなければ”犬狼の牙”へ戻れないのだ。どうせ
なら、ただの女より特別な女を見つけてやる。そしてあの
くそ親父の度肝を抜かしてやる。それにはその王女が打っ
て付けだ。もちろん、正面から彼女に求婚するのではない
、略奪によって為すのである。彼女にしてみれば、甚だ迷
惑なことであろうが、そんなことは知ったことではない。
そして彼は夜を選び王宮侵入を実行した。暗殺者として
の才能は他の誰よりも非常に秀でている彼は今回の侵入に
対して優れた能力を発揮し、間もなく王女の私部屋にたど
りついた。その時、その王女はベットの上に座って窓の外
の夜空を眺めていた。何者かの侵入を察知した彼女は扉の
方へ振り向き、そこに一人の男が立っていることを知った
。その男ディークは明かりがないせいか彼女の姿がよく見
えなかったが、そのシルエットが想像していたよりずっと
小さいように見え、小柄な女性はそう少なくないだろうと
判断すると、早速、行動に移ったのだった。
「王女メルナート、あんたの身をいただきに来た。悪く思
わないでくれ。」
彼女は何か言おうとした様であったが、ディークは俊敏
な動作で彼女のみぞおちを打ち気絶させると肩に彼女の身
を抱え、この場を去った。
無難にテセナのはずれバーグルの森まで逃げ延びたディ
ークは王女誘拐があまりに容易にできてしまったことへの
少々の失望があったが、それよりも生きた芸術とまで評さ
れているこの女性を早く鑑賞したいという願望にとらわれ
、森の中にある月の明かりに照らされた泉まで移動した。
この泉には昔より神によって運命づけられた男と女を恋人
にまで結び付ける力があるという言い伝えがあり、今でも
若き恋人達がここに思いを寄せてやって来るという。もち
ろん、そんなことはディークは全く知らないのだが、まさ
か、この泉が彼を祝福しここへ導いたとは今の時点では知
る由もない。
ディークは月の光が当たった王女の顔をまじまじと覗き
こんだ。ところが、その顔はあまりにも若い、年齢にして
13、4歳程度の少女のものであった。
「た、確かに美しいといえば美しいかもしれない・・・。
だが、メルナートという王女は聞いた話では年は20歳で
あるはず、この女は全くの別人ではないのか!?・・も、
もしや、この女は第3王女のフィルネアでは!?」
その疑念が確信に変わるのはそう時間を要しなかった。
フィルネアの名を呼ぶ多人数の声が自分が逃げてきた方向
から聞こえてきたのだ。王女誘拐をディークに安々と成功
させてしまった間抜けな衛兵共がようやくこの事態に気付
いたらしく、ここまで探索に来たようだ。さて、と心の中
で呟くと、ディークは今だ気を失っている第3王女を見た
。
「もう、この女がメルナートでないと分かった以上、連れ
ていく理由はなくなった訳だな。それに、この子をここで
手放せば俺も追われることもないだろう。ん!?・・」
途中で言葉を切らしてしまった。この少女、よくよく見
ると本当に奇麗だな。今は子供に過ぎないが、メルナート
と同じ年頃になった頃にはメルナートをも凌ぐ美しさを兼
ね備えるかもしれないのではないか?ディークはこの少女
を手放すことに少々の戸惑いが生まれると、それは次第に
大きくなっていった。しかし、時は彼に長くは考えさせて
くれる余裕を与えたりはしなかった。段々とフィルネアを
呼ぶ衛兵達の声が大きくなり、そう遠くない距離まで来て
いることを明らかに示していたのだ。衛兵達の声にハッと
我に返ったディークは遂にフィルネアを引き続いて連れて
いくことを決心し、彼女の身を抱え、さらに森の奥へと消
えていった。
この夜、ついに衛兵達はフィルネアを捜し出すことがで
きず、ことの一部始終を聞いたフィルネアの父、皇帝ビジ
ュナーは大いに嘆いた。真夜中の愛娘の失矼はどう考えて
も不可解で、何者かによる誘拐と断定するとビジュナーは
王女誘拐を回避できなかった王宮警備を受け持つ者達の処
分を適当に済ませると、き下の兵の一部を削って、王女探
索の任を与え、王女を見つけだした者には多額の報酬で報
いることを約束し、各地へ出発させた。
それから一週間、皇帝を喜ばせる知らせは1つとなく、
ただ偽りの情報で金をくすねとろうとする者の出現がある
だけで、皇帝は悲しみと怒りの頭痛に悩まされていた。そ
んな時、帝国の宰相ゼコルドが皇帝に自慢の策を提案した
のである。ゼコルドは既に老年で、若い頃より王宮に仕え
、彼の特異稀なる才覚は帝国の発展に大きく貢献してきた
が、ここ数年前、彼の家筋に伝わる宝剣を盗まれてしまっ
たことがあり、困っていた末に駄目で元々の気持ちである
占い師に宝剣のありかを尋ねたところ、驚いたことにその
占い師の告げた隣国マスベルターの質屋でその剣が発見さ
れてしまったのだ。えらくその占い師に感激したゼコルド
はそれ以来、彼を厚く遇するようになり、相談役として王
宮へ彼に足を運ばせさえするようになってしまった。これ
に見兼ねた周囲の者達は迷信深くなる代わりに彼自身の才
能を曇らせてしまった老宰相を見放すようになり、ついに
は皇帝に老宰相の解任を勧める者まででる始末であった。
そして今回、そのゼコルドが皇帝に持ちかけた策とは、や
はり占い師を通じて作られたものであった。ただでさえ不
機嫌なビジュナーはこの老人に不快感を持ったが、彼がし
つこく進言を希望するので話だけでも聞くことにした。
「私が厚い信頼を寄せている占い師の占いによると、フィ
ルネア様はバーグルの森にある古代迷宮で一人の男に監禁
されているということでございます。」
「あの古代迷宮にフィルネアがいると?」
「御意でございます。」
「だが、そうは信用できぬな。何の証拠を以てその占い師
とやらはそういえるのだ?」
「あやつの占いは真実のみを語るものでありまして、それ
は私が自信を持って保証いたします。」
説得力の全くない返答にビジュナーは内心舌打ちしつつ
、もう一つの疑問をぶつけてみた。
「あの古代迷宮は確か、いにしえの魔物が巣くっていると
歴史書で読んだことがある。そのような所に我が兵を派遣
するのは正直気が進まんのだが、もし迷宮にフィネルアが
いなかった場合を考えると後世の笑い話になってしまうぞ
。私は占いごときで政を処した愚帝ビジュナーという汚名
を世に残すつもりはないのだがな。」
ビジュナーは皮肉っぽく言ってみせたが、老宰相はそれ
に動じる様子を見せずに言った。
「それには心配に及びませぬ。私めに考えがあります。」
「ほう・・、自信ありげだな。申してみよ。」
「こうしてはどうでしょう。国中に触れをだすのです。迷
宮に囚われたフィルネア様を救った者にはそれ相応の報酬
を与えると、必ずや多くの強者が馳せ参じることでしょう
。さすれば皇帝陛下の兵を全く傷つけずともことは足りま
しょう。」
悪くはないな。こやつの言う通り、私の名誉には何も傷
つくことはないであろう。フィルネアが見つかれば、それ
はそれで願ったりであるし、それに失敗した場合には、こ
の目障りな老人を私の目に届かぬ所へ追いやる口実が出来
るというものだ、と毒のある考えを持ったビジュナーはゼ
コルドの案を用いることを決定したのである。
こうして国中の腕に覚えのある強者どもが古の迷宮へ次
々と結集したのであった。


