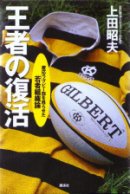
内容は単にラグビー部の再建の話だけでなく、一般の組織のあり方を考えさせられる話も含まれていた。
王者の復活
慶応ラグビー部を甦らした「若者組織論」 上田昭夫著
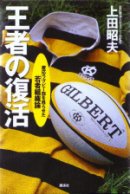 |
慶応ラグビー部は1986年、社会人王者のトヨタ自動車とラグビー日本選手権を争い18対13で勝利したが、その後長く低迷していた。1999年に慶応ラグビー部創部100周年を迎えた。上田昭夫が1994年に8年ぶりに監督として復帰して、創部100周年に向けてラグビー部の再建に立ち向かった。これはその時の組織のリーダーとしての体験談である。 内容は単にラグビー部の再建の話だけでなく、一般の組織のあり方を考えさせられる話も含まれていた。 |
![]() 上田式指導法
上田式指導法
![]() 自分たちのラグビーが見るている人に感動してもらえるチームをつくりたい。感動を与えるとは、常に一生懸命やること、これまでの努力を披露すること。そして、何かをしようとする努力を見せること。そのメッセージを伝えることだ。
自分たちのラグビーが見るている人に感動してもらえるチームをつくりたい。感動を与えるとは、常に一生懸命やること、これまでの努力を披露すること。そして、何かをしようとする努力を見せること。そのメッセージを伝えることだ。
![]() 効率的な練習の基本は、「何のための練習であるか」明確に意識したやり方を考えることである。なるべく選手が楽しめる練習方法を工夫するのが指導者の役目である。
効率的な練習の基本は、「何のための練習であるか」明確に意識したやり方を考えることである。なるべく選手が楽しめる練習方法を工夫するのが指導者の役目である。
![]() 明るい雰囲気というのは、監督の指導だけでつくれるものではない。今の学生の感覚に合ったクラブにするには、枠組みづくりを学生に任せるのがいちばん手っ取り早い。最低限ルールは監督が決めるが、それ以外は学生の自主性に委ねる。
明るい雰囲気というのは、監督の指導だけでつくれるものではない。今の学生の感覚に合ったクラブにするには、枠組みづくりを学生に任せるのがいちばん手っ取り早い。最低限ルールは監督が決めるが、それ以外は学生の自主性に委ねる。
![]() 今の若者は、自分なりに納得した上で行動したいと思っている。意味もわからずやみ雲に指示どおり行動したりせず、自分が納得すれば一生懸命やる。
今の若者は、自分なりに納得した上で行動したいと思っている。意味もわからずやみ雲に指示どおり行動したりせず、自分が納得すれば一生懸命やる。
![]() 慶応は「精神面重視のラグビー」を伝統としてきた。この伝統は、ひとまず捨てる必要がある。技術を高めなければ、本当に強いチームにはならないからだ。だが、技術さえ向上すれば精神力など必要ないかといえば、答はノーだ。技術が拮抗した相手と戦うとき、最後に精神力が勝負を分けることがあるのは、スポーツの常である。精神力(自信、といってもいい)は勝利を積み重ねることで、自然とチーム全体に備わっていく。だとすれば、やはりまずは技術を磨くことで勝利という経験を得ていくしかない。
慶応は「精神面重視のラグビー」を伝統としてきた。この伝統は、ひとまず捨てる必要がある。技術を高めなければ、本当に強いチームにはならないからだ。だが、技術さえ向上すれば精神力など必要ないかといえば、答はノーだ。技術が拮抗した相手と戦うとき、最後に精神力が勝負を分けることがあるのは、スポーツの常である。精神力(自信、といってもいい)は勝利を積み重ねることで、自然とチーム全体に備わっていく。だとすれば、やはりまずは技術を磨くことで勝利という経験を得ていくしかない。
![]() プロのチームは、ある程度まで完成した選手が入ってくるが、学生チームの場合は違う。土を耕すところから始めて、種を蒔き、肥料や栄養剤を与えながら花を咲かせるのが、学生チームの監督だ。さらに、咲いた花を品種改良していく作業もある。学生たちを指導する上での最大の楽しみは、彼らの成長ぶりを目の当たりにできることだ。プロや社会人に比べれば到達レベルは低いが、その「伸び率」を比較すれば学生のほうが格段に大きい。
プロのチームは、ある程度まで完成した選手が入ってくるが、学生チームの場合は違う。土を耕すところから始めて、種を蒔き、肥料や栄養剤を与えながら花を咲かせるのが、学生チームの監督だ。さらに、咲いた花を品種改良していく作業もある。学生たちを指導する上での最大の楽しみは、彼らの成長ぶりを目の当たりにできることだ。プロや社会人に比べれば到達レベルは低いが、その「伸び率」を比較すれば学生のほうが格段に大きい。
![]() 負け犬根性を叩き直すには、とにかく試合で結果を出させるしかない。選手自身が勝利の味を肌で実感しなければ「どうしても勝ちたい」という意欲は湧いてこないからだ。結局、敗北に慣れきった体質を改善するのに五年間かかった。
負け犬根性を叩き直すには、とにかく試合で結果を出させるしかない。選手自身が勝利の味を肌で実感しなければ「どうしても勝ちたい」という意欲は湧いてこないからだ。結局、敗北に慣れきった体質を改善するのに五年間かかった。
![]() 危機管理というのは、まず危機感を持つことから始まる。したがって。「これはヤバイ」と感じるのは、早ければ早いほうがいい。浮かれた気分のままシーズンに突入してしまったら、どこかでつまずいて危機意識が芽生えても、修正する時間がないからだ。
危機管理というのは、まず危機感を持つことから始まる。したがって。「これはヤバイ」と感じるのは、早ければ早いほうがいい。浮かれた気分のままシーズンに突入してしまったら、どこかでつまずいて危機意識が芽生えても、修正する時間がないからだ。
![]() 組織には、必ず目的がある。大学のラグビー部なら、それは「勝利」だ。
組織には、必ず目的がある。大学のラグビー部なら、それは「勝利」だ。
![]() 本当にチームとして強くなろうと思ったら、部員同士の競争が不可欠である。本気でレギュラー・ポジションがほしければ、たとえばライバルがケガなどで戦列を離れたときに「しめた」と思うぐらいでちょうどいい。ケガをした選手には気の毒だが、それは他の選手にとって一つのチャンスなのだ。
本当にチームとして強くなろうと思ったら、部員同士の競争が不可欠である。本気でレギュラー・ポジションがほしければ、たとえばライバルがケガなどで戦列を離れたときに「しめた」と思うぐらいでちょうどいい。ケガをした選手には気の毒だが、それは他の選手にとって一つのチャンスなのだ。
![]() チーム力というのは、いちばん高いレベルの選手に左右されるものではない。仮に、試合に出ている15人のうち、1人が低いレベルならば、チーム全体のパフォーマンスもその低いレベルになると考える。したがってチーム力を上げるには、ハイ・レベルの選手を特化して鍛えるよりも、下のレベルの選手を底上げすることを考えるべきだろう。今の慶応なら、およそ100人が一つのチームをつくっているわけだ。レギュラーの15人、あるいはリザーブを含めた22人ではなく、100人によるチームワークを機能させなければ、本当に強いチームはつくれない。
チーム力というのは、いちばん高いレベルの選手に左右されるものではない。仮に、試合に出ている15人のうち、1人が低いレベルならば、チーム全体のパフォーマンスもその低いレベルになると考える。したがってチーム力を上げるには、ハイ・レベルの選手を特化して鍛えるよりも、下のレベルの選手を底上げすることを考えるべきだろう。今の慶応なら、およそ100人が一つのチームをつくっているわけだ。レギュラーの15人、あるいはリザーブを含めた22人ではなく、100人によるチームワークを機能させなければ、本当に強いチームはつくれない。
![]() 練習ですべての事態を想定して、「次に何をすべきか」を決めておくことなど、当たり前だが不可能だ。それに対応するには、選手の状況判断力を磨いておくしかない。今のチームに対しては、いろいろなプレイについて「あまり決めごとにするな」といっている。その時々のベストのプレイは何かを、自分で考えられるようになってほしいのだ。学生がラグビーで状況判断力を身につけていれば、それは、社会に出てからも大いに役立つに違いない。
練習ですべての事態を想定して、「次に何をすべきか」を決めておくことなど、当たり前だが不可能だ。それに対応するには、選手の状況判断力を磨いておくしかない。今のチームに対しては、いろいろなプレイについて「あまり決めごとにするな」といっている。その時々のベストのプレイは何かを、自分で考えられるようになってほしいのだ。学生がラグビーで状況判断力を身につけていれば、それは、社会に出てからも大いに役立つに違いない。
![]() 明確な将来のビジョンを持つことが、組織を立て直すための第一歩となる。苦境に立ち向かうには、旺盛なチャレンジ精神が必要だ。しかし、目標がないところにチャレンジ精神は湧いてこない。
明確な将来のビジョンを持つことが、組織を立て直すための第一歩となる。苦境に立ち向かうには、旺盛なチャレンジ精神が必要だ。しかし、目標がないところにチャレンジ精神は湧いてこない。
![]() 今の学生は、叱りつけるよりも「説得」して「納得」させたほうが言葉が伝わる。相手のいうことに耳を傾けながら方向を正していくタイプの指導者になった。
今の学生は、叱りつけるよりも「説得」して「納得」させたほうが言葉が伝わる。相手のいうことに耳を傾けながら方向を正していくタイプの指導者になった。
![]() 一定の状態を永遠に続けることが、「伝統を重んじる行動」なのではない。今の状態に新しいものを積み重ねていくことが、「伝統を引き継ぐ」ことなのだ。「次」を考えなければ強い集団は維持できないし、伝統を守ることもできない。リーダーとして「次」への準備を怠らないためには、できるだけ固定観念を捨て組織全体をみておく必要がある。
一定の状態を永遠に続けることが、「伝統を重んじる行動」なのではない。今の状態に新しいものを積み重ねていくことが、「伝統を引き継ぐ」ことなのだ。「次」を考えなければ強い集団は維持できないし、伝統を守ることもできない。リーダーとして「次」への準備を怠らないためには、できるだけ固定観念を捨て組織全体をみておく必要がある。
![]() 自分自身にとって生きた情報は、自分の足で歩かないと手に入らない。自分の足で歩くというのは、受け身ではなく、常に何かを感じ取ろうという気持ちで自らアクションを起こすということだ。自分から電話する、手紙や電子メールを出す、人に会いに行く、行ったことのない街に行ってみる。「次」に何が起こり、自分が何をすべきか判断するには、いつも生きた情報に触れるように心掛けながら、嗅覚を研ぎ済ます以外にない。
自分自身にとって生きた情報は、自分の足で歩かないと手に入らない。自分の足で歩くというのは、受け身ではなく、常に何かを感じ取ろうという気持ちで自らアクションを起こすということだ。自分から電話する、手紙や電子メールを出す、人に会いに行く、行ったことのない街に行ってみる。「次」に何が起こり、自分が何をすべきか判断するには、いつも生きた情報に触れるように心掛けながら、嗅覚を研ぎ済ます以外にない。
![]() 人材確保に奔走するのも重要な仕事だが、こればかりは贅沢をいい始めるとキリがない。確保した人材のレベルがどうであろうと、それをいかに育て上げるかがリーダーの腕の見せ所なのだ。
人材確保に奔走するのも重要な仕事だが、こればかりは贅沢をいい始めるとキリがない。確保した人材のレベルがどうであろうと、それをいかに育て上げるかがリーダーの腕の見せ所なのだ。
![]() 選手を育てようと思うなら、大事なのは長所を伸ばしてやることだ。「何ができるか」を探したほうが、その人材をチームで生かす早道になる。欠点を修正するのは、その後の話だ。
選手を育てようと思うなら、大事なのは長所を伸ばしてやることだ。「何ができるか」を探したほうが、その人材をチームで生かす早道になる。欠点を修正するのは、その後の話だ。
![]() 部下がもっとも安心するのは、リーダーが自分のことを「知っている」と実感できたときだろう。信頼関係というのは、そこから築き始められる。学生たち一人ひとりの「個人情報」を頭にインプットするように心がけている。
部下がもっとも安心するのは、リーダーが自分のことを「知っている」と実感できたときだろう。信頼関係というのは、そこから築き始められる。学生たち一人ひとりの「個人情報」を頭にインプットするように心がけている。
![]() 組織の仕事がキャンバスに一枚の絵を描くものだとすれば、リーダーの仕事は絵の輪郭を描くことだ。色づけは一人ひとりの選手が持っている個性だ。手元にある絵の具を最大限に使って、自分の描いた輪郭がより美しく見えるように作品を仕上げていけばいい。チームカラーというのは、そうやって自然にでき上がっていくものだ。
組織の仕事がキャンバスに一枚の絵を描くものだとすれば、リーダーの仕事は絵の輪郭を描くことだ。色づけは一人ひとりの選手が持っている個性だ。手元にある絵の具を最大限に使って、自分の描いた輪郭がより美しく見えるように作品を仕上げていけばいい。チームカラーというのは、そうやって自然にでき上がっていくものだ。