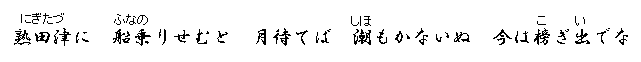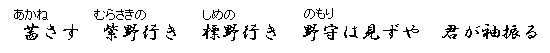額田女王 井上靖著
 額田女王は幼くして郷里大和の家を出て、宮中の祭事に関係ある大和国平群郡額田郷の額田氏に引き取られて育った。そうした特殊な家で生い育ったので、祭事に仕えることができた。額田女王は神事に奉仕することを任務とする女官であって、歌才に恵まれ、時には天皇の命によって、天皇に代わって歌を詠むこともあった。
額田女王は幼くして郷里大和の家を出て、宮中の祭事に関係ある大和国平群郡額田郷の額田氏に引き取られて育った。そうした特殊な家で生い育ったので、祭事に仕えることができた。額田女王は神事に奉仕することを任務とする女官であって、歌才に恵まれ、時には天皇の命によって、天皇に代わって歌を詠むこともあった。
斉明天皇七年(661)三月にはいって、突如熟田津(伊予)滞在は打ち切られることが発表になった。船団は熟田津を出て、一路筑紫を目指すことになったのである。
全船団が発航する当夜、老女帝(斉明天皇)の御座船において、出陣を神に告げる儀式が執り行われた。儀式は月の出を待って行われた。その席には中大兄、大海人、鎌足を初めとして、主な朝臣たちのことごとくが居並んだ。中央に祭壇が祀られ、神に出陣を告げる儀式は厳かに営まれた。そしてそれが終わると、出陣を祝う祝宴が開かれた。
こうした席の慣例であったが、額田にこの月明の出陣について作歌するようにという詔がくだった。額田は予め何首かの歌を用意して来ていたが、この時、そのすべてを棄てることにした。
額田は、今なら中大兄皇子の心の中に自分ははいり込めると思った。中大兄に代わって、そのいまの出陣の心情を歌に綴ろうと思った。額田は、自分のために中大兄皇子が選んでくれたに違いない月明の海に眼を当てていた。長いこと身動きをしなかった。
額田は席を立つと、老女帝に向かって、歌を捧げた。
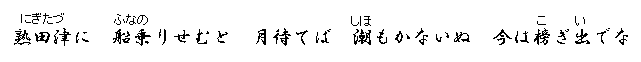
額田は二回詠い終わると、席に戻った。一座の反応を確かめようなどという気持ちはなかった。額田は中大兄皇子の心になりきっている自分を感じた。女帝の命で作った歌であったから、歌の調べは女のそれであったが、盛られている心は中大兄以外の誰のものでもなかった。全船団はいっせいに潮の上を動き始めていた。潮も光り、船団も光っている。実際には船団は動き出していなかったが、額田にはそれがはっきりと、現実の一情景として見えていた。
天智天皇七年(668)五月五日、近江の蒲生野に遊猟のことがあった。近江へ遷都してから初めての朝廷を挙げての明るく楽しい遊楽であった。一日の行楽は終わり、一行は幾つかの集団になって、蒲生野をあとにした。一行はそのまま王宮の中にはいり、湖の見える広庭に設けられた宴席の中に吸い込まれて行った。宴席は賑やかに続けられた。上下の別を取り外した無礼講の行楽の一日はまだ終わっていなかった。
やがて、今日の行楽で取材した歌を披露する時が近づいて来た。天皇の指名で最初の一人が立って自分の歌を披露する。次ぎはその最初の蒲生野によって指名された者が立たなければならなかった。そして次々に前の詠歌者によって次の詠歌者が指名されて行く。
やがて、額田は顔を上げた。自分の名が呼ばれたからである。額田は立ち上がって宴席のまん中に出、玉座の方に礼をした。そして、いま天皇は自分の方に眼を向けておられるに違いないと思った時、ふいに額田は今まで考えていたとは全く違った歌を口から出そうと思ったのであった。瞬時にして歌はまとまった。歌の方が自分から額田の頭の中に飛び込んで来たようなものであった。額田は天皇に話しかける言葉を、そのまま歌の形に整えたのである。
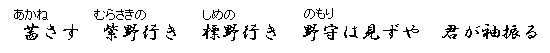
宴席は水を打ったように静かであった。額田が大胆な恋歌を発表したと思ったからである。一体”君が袖振る”の君は誰であろうか。誰もこのことに関心を持たずにはいられなかった。額田に対して袖を振った人こそ額田の意中の人である。誰もがそう思った。
額田はこの歌は誰に判らなくても、天智天皇だけには判ってもらえるに違いないと思った。天皇に判らぬ筈はないと思った。
額田が立ってから何人目かに、大海人皇子の名が呼ばれた。やがて額田は宴席のまん中に現れる大海人皇子の眼を当てていた。大海人皇子がいかなる歌を詠うか興味があったからである。
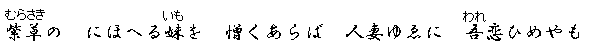
一座の者には、これもまた、額田に劣らず大胆な恋歌として受け取られた。”紫草の”という詠い出しによって、一座に居る誰もが、これが額田に対して詠われたものであると思ったのは当然であった。額田の歌に対して、まるで応答歌ででもあるような、大海人皇子の歌なのである。
しかし、その歌の持った大胆さが人を驚かせはしたが、不思議にそれは深刻なものとしては受け取られなかった。いかにも額田と大海人皇子が企んで、座興としてたわむれに恋の歌のやりとりをしているとしか思われなかった。大海人皇子の何人もの妃たちもそこに居合わせていたが、おそらく誰もたわむれの恋歌以上のものとは感じなかったに違いない。
ただ一座の中で額田だけはこの大海人の歌に対して違った思いを持っていた。これは一座の者にはたわむれの歌としか思えなかったであろうが、それは額田の心の中だけは違った屈折の仕方をした。たわむれの歌どころではなかった。大海人皇子は天智天皇に聞かせると共に、額田にも聞かせるために、この歌作っていた。そういう意味では怖ろしい程よくできた歌であった。人妻ゆえに詠っていることで、相手が天智天皇の女性であるという見方をはっきりと示しており、はっきり示すことにおいて天皇をたてているわけで、そしてまたそういう女性でも自分は恋さずにはいられないと詠うことで、所詮たわむれの歌に過ぎないという性格を巧みに出していた。
額田は大海人皇子がこのような歌を作る才能を持っていようとは、これまで一度も思ってみなかったことであった。額田の歌に呼応して、天智天皇の持ったかも知れない誤解を、大海人は大海人で解こうとしているのであった。
もう一つ額田が舌を巻いたことには、この歌が天智天皇に対して詠われていると共に、額田に対しも詠われていたことである。額田には大海人のはげしい眼が感じられた。多くの人は私のこの歌をたわむれの歌として受け取るだろう、しかし、たわむれを装った中にちゃんと本心もはいっていることは、あなただけには解っている筈。そういう大海人の声が額田には聞こえて来るようであった。
宴席は額田と大海人皇子の二つの歌によって、一層浮き浮きした楽しい明るいものになって行った。蒲生野遊猟の日の夜は、近江朝の朝臣や武臣たちにとっても、妃たちや、侍女たちにとっても、かってなかったような無礼講の楽しいものになって行った。宴はいつ果てるとも判らなかった。

 額田女王は幼くして郷里大和の家を出て、宮中の祭事に関係ある大和国平群郡額田郷の額田氏に引き取られて育った。そうした特殊な家で生い育ったので、祭事に仕えることができた。額田女王は神事に奉仕することを任務とする女官であって、歌才に恵まれ、時には天皇の命によって、天皇に代わって歌を詠むこともあった。
額田女王は幼くして郷里大和の家を出て、宮中の祭事に関係ある大和国平群郡額田郷の額田氏に引き取られて育った。そうした特殊な家で生い育ったので、祭事に仕えることができた。額田女王は神事に奉仕することを任務とする女官であって、歌才に恵まれ、時には天皇の命によって、天皇に代わって歌を詠むこともあった。