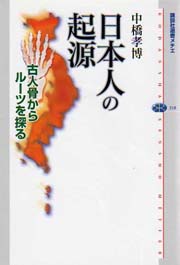
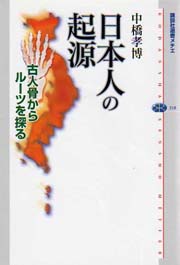
 |
 |
| 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿貝塚の縄文人 | 福岡県筑紫野市隈・西小田遺跡の弥生人 |
縄文人の顔は、高さが低い割りに横幅が広く、いわゆる低・広顔傾向が強い。眉間や眉弓部が膨らんでいる。頬骨が強く横に横に張り出して、四角くごつい印象を与える。眼球を入れる眼窩は四画形に近い。歯並びは、整然としている個体が多く、虫歯も比較的に少ない。歯のすり減り方は激しく、中年以降になるとほとんど歯根だけしか残っていないことも珍しくない。歯のすり減り方が激しいことや、あごのエラが張り出していることからも推察されるように、縄文人は現代人などにくらべはるかに物をかむことが多かったし、その力も強かったと見られる。縄文人の歯が後世の日本人にくらべかなり小さいことが指摘された。身長は低身長で男性では160cm弱、女性では150cmに満たない人が多い。
北部九州・山口地方弥生人(北部九州甕棺墓、山口県土井ヶ浜遺跡)の顔は、のっぺりした面長をしている。眼窩も高くなってその上縁は直線的だった縄文人とは違って丸みを帯びるようになる。鼻が低く扁平性が強い。鼻の低い扁平顔は、日本人の共通した特徴となって、近・現代まで引き継がれていく。鼻が低いのは寒冷適応した人たちの影響を受けた結果のようである。身長は高身長で、男性では163cm前後、女性も151cm〜152cmの平均身長を持つ。
北部九州の弥生中期頃に集中して出土する人骨は、大陸の人々に非常によくにた特徴を持っている。もし、渡来人が土着縄文人と頻繁に混血したのなら、当然、両者の中間型や中には縄文人にそっくりの人がかなりの割合で混じっているはずである。ところが北部九州の弥生人の特徴はそうはならず、全体的に見た場合、ほとんど大陸の人そのものに近い特徴になってしまっている。
北部九州で起きた激しい変革は具体的にどのような人たちによって実現されたのだろうか。
一つの解釈は、土着の人々が水稲耕作などの新しい文化を生活の中に取り入れ、自ら社会を変革していった、というものである。弥生早期の、水田遺構が最初に発見される時期の遺跡では、大陸系の土器や石器、木製農耕具などが出土するが、それらは当時の生活用具の一部を占めるにすぎず、大部分は縄文時代以来の伝統を残したものを使い続けていることが、多くの考古学者によって指摘されている。長年、北部九州で発掘を続けてきた専門家たちの中で渡来説が容易に受け入れられなかったのは、こうした発掘事実に基づく判断があったからであろう。そうして、支石墓という渡来系の墓に縄文系の特徴をもった人々によって営まれていたという事実が加わったのである。墓制がそうなら、水稲耕作なども同様に考えればすむではないかというわけである。この解釈を採る人たちも、弥生時代の渡来人の存在をまったく否定しているわけではない。渡来人の遺伝的な影響がおよびだしたのは、弥生開始期ではなく弥生前期末以降の、北部九州で青銅器などの大陸系遺物が急増する時期や、あるいはそれより少し前の板付式土器文化が成立し始める時期を想定する意見が多い。
もう一つの解釈は、渡来人に変革の主体を帰す解釈で、水稲耕作を主生業とする渡来人がまず北部九州に定着し、ある程度は在来の縄文系住人との遺伝的な交流を経て、急激に人口を増やしながら弥生社会を作り上げていったとする考えである。古人骨が与えてくれる情報から判断すると、このように考えるのが最も合理的だと、人類学者の筆者は考えている。
人口増加のシュミレーションの結果、弥生初期の福岡平野で、少数の渡来人でも地域住民の多数を占めることは、十分可能であることを示している。おそらく最初に北部九州にやってきた水稲稲作集団は、土着の縄文集団が希薄な沿岸低地で水田を作り始めたのだろう。狩猟・採集と多少の原始農耕で生活していた縄文人にとって、沿岸の特に低湿地などは必須の土地ではなく、新来の渡来人が住み着く上で大きな摩擦もなかっただろう。彼らは、周辺の縄文人たちともある程度、人的、文化的な交わりを持ちながら、自分たちの生活スタイルである水田稲作を最初は細々と始めたに違いない。それがしかし、後続集団も加えながら二代、三代と世代を重ねるうちにみるみる人口と水田域を増やしていき、やがては丘陵部や山際など土着系住民の生活域まで侵すようになっていったろう。もちろん土着住民の一部には新しい生活文化を取り入れた人たちもいただろうが、おそらく摩擦を避けて内陸部へと移動した人たちも少なくなく、あるいは新たな疾病の影響なども重なって、総体として彼らの人口の伸びはかなり低かったに違いない。やがては数でも生活力においても渡来系の優勢が顕著になって、もともと人口が多くなかった縄文系住人には対抗する術もなくなっていたのではなかろうか。時の流れとともに彼らは渡来系の遺伝子集団の中に取り込まれ、あるいはさらに山中か周辺地域へと移動をよぎなくされて、次第に歴史の中に消えていったのだろう。