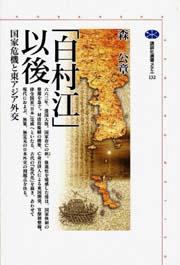
「白村江」以後 国家危機と東アジア外交 森公章著
|
|
倭の外交目的が、弁辰の鉄の獲得にはじまり、百済からの人質の派遣と文物の確保、さらに新羅に対する任那の調(服属の意味を含んだ貢納品)の要求と、モノの獲得に重点があった。倭の外交は、基本的には百済支持で、百済との外交を主としており、伽耶地域に進出しようとする百済を支援することで、伽耶地域への影響力、物資獲得を実現しようとした。伽耶地域をめぐる百済と新羅の争奪戦では新羅の侵攻が優勢であり、554年、百済の聖明王の対新羅戦における敗死を一つの画期として、562年には新羅が伽耶地域を支配することになった。この間、倭は一貫して百済を支持し、援軍を送ったりしているが、結局百済の東方進出策は失敗した。新羅が伽耶地域を領有した後、新羅は倭に任那の調を貢納した。
当時の東アジア情勢は激動期で隋(581年 -619年)、唐(618年 -
907年)の成立と朝鮮半島三国抗争の激化を迎えつつあり、任那の調をきっかけに本格的な対新羅外交に乗り出すが、倭の外交切り換えが十分な成果を上げない中で、以前からの百済との関係がつづき、白村江への道をたどる。
660年、唐・新羅連合軍が百済を滅亡させた。そして、663年8月、倭国は百済復興軍を助けて出兵し白村江の戦いで大敗した。ここに百済は完全に滅亡し、倭国はそれまでの朝鮮半島との関係に終止符を打つ。
白村江の敗戦に際し、多くの百済人が倭国に亡命した。百済復興運動の中心であった貴族階級の人々から、一般の百姓まで1000人規模で倭国に定住をはたした。当時の倭国の人口は500万〜600万人と推計され倭国には亡命百済人を受け入れる余地が充分にあった。防衛施設の建設、土地の開発、中央官制の整備において、亡命百済人がはたした役割は非常に大きかった。
評は、律令制下において地方支配の要となった郡の前身となる行政区画で、701年の大宝律令制定の際に、その名称が郡に改められている。670年には最初の全国的な戸籍、庚午年籍(こうごねんじゃく)が作成される。この庚午年籍は、評内の中小豪族配下の民衆に対する評司(ひょうし)の把握を強化することになった。評制を充実させることで部民制に依存しない地域区画による収取を可能にした。
672年の壬申の乱では、ほとんどの中央有力豪族は大友皇子に味方し、大海人皇子の下には中小の地方豪族や地方貴族が集まるだけであった。しかし、当時の地方豪族が地方支配の実権を握っている側面が強く、中央集権的国家機構という正規のルートで募兵をおこなった近江方には充分な兵力が集らず、地方豪族を味方につけ、その配下の兵を集めた大海人皇子の大勝利となった。近江朝廷を支持した中央大豪族の多くは昔日の権力を失った。壬申の乱に勝利した天武天皇の代になると、新羅にならって、急速な唐風化が進められ、社会・文化の変革が行われた。百済文化への依存、中央豪族の勢力が残る天智朝では、前代の旧習をたちきれなかったのに対して、壬申の乱で中央豪族が没落し、「神」としての権威を高めた天武天皇の下において、中央官僚の整備、中央集権的な地方制度の確立、律令法や中国風な都城の建設が進められた。そして国号も日本と改め、唐と同質の律令国家という課題が達成される。
その背景として、半島における唐と新羅の戦争(670年−676年)の勃発により、新しい国家構築の時間が確保されたこと、唐との対立の後ろ盾を求めた新羅が倭国に朝貢し、文物の供給者として登場し、文物の輸入が可能になった。ただし倭は唐・新羅戦争に不介入の姿勢をとり、傍観に徹するというのが外交政策の基本であった。
この時期、倭国の遣唐使は670年の一度だけである。670年に遣唐使は唐・新羅戦争のどちらを支持するか明確に意思表示する必要はなく、668年の高句麗平定を祝賀するだけですんだと思われる。これ以後701年、大宝度の遣唐使までの約30年間、唐との正式な通交がおこなわれなかった。倭国としては唐と一線を画し、半島情勢への介入を強制されることを避けるため、対唐外交を消極的なものにとどめた。
白村江の敗戦後、倭国と新羅の関係は、668年9月、新羅使の来日によって再開される。668年9月といえば、高句麗が滅亡する時であり、新羅としてはこうした半島情勢の変化を伝えるとともに、来るべき対唐戦争を予想して、少なくとも倭国が唐側につかないように布石を打っておく必要があった。新羅はその後も八世紀初めまでほぼ毎年倭国に使者を派遣しており、倭国もこれに応じて、その都度遣新羅使を送っており、両国の親密な関係はしばらくつづくことになる。660年に百済が滅亡し半島との接点を失った倭国は、唐文化を輸入するルートを失い、かといって唐には白村江の戦で完敗を喫し、670年頃には唐の倭国征伐の風聞があったことからなお警戒心を抱いており、結局、百済の代わりに新羅を足がかりとして唐文化を輸入するしか道がなかったのである。唐という国に対しては警戒をゆるめず、敬遠していたものの、唐の文化・国家機構には尊重すべきものが多く、倭国の今後の国家機構の手本としてどうしても必要だったからである。