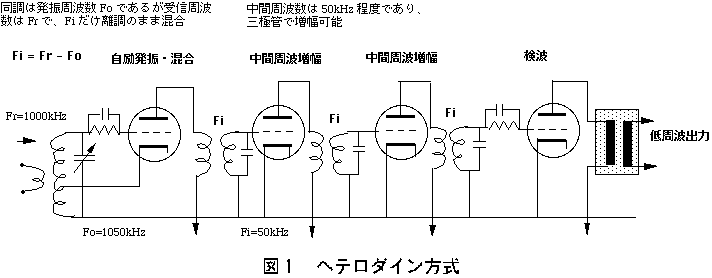
そこで、ヘテロダイン方式という回路が考案されました。発明者は、中波のオートダイン受信機の応用で、検波管の発振周波数と受信数周波数の差(ビート)を増幅すれば安定した増幅ができ、三大要素を満たすことができるとの発想でした。
すなわち、再生検波管のプレート回路には音声信号トランスではなく、例えば 50kHz 位のビート周波数を通過させる「中間周波」(これをヘテロダイン周波数という呼び方がありました)トランス (IFT=Intermediate Frequency Transformer) を挿入し、以後何段かの安定な「中間周波増幅」を行った後に二度目の検波を行い、音声信号を得るものです。
低い固定周波数の中間周波増幅ならば、三極管でも楽に安定で高いゲインと選択度が実現できました。 なお、中間周波増幅を含む高周波増幅回路については、後に細述します。
ヘテロダイン方式では、検波段の同調コイルの共振周波数は、再生検波の発振周波数にセットされており、アンテナからの受信信号は中間周波数だけ「離調」した状態で動作するわけです。 したがって、中波において 50kHz 位の離調状態によるゲイン低下 (15 db 位か) を我慢すれば、三極管単球でこのような「混合回路」と「発振回路」から構成される「周波数変換回路」が実現できました。 ヘテロダイン方式の同調操作は従って、再生検波の発振周波数を可変とすれば、中間周波数だけズレた周波数の信号が受信できることになります。
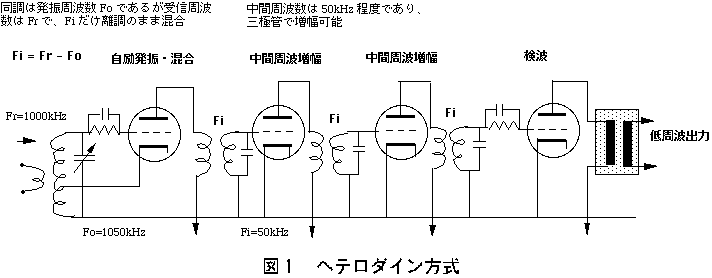
オートダイン (Autodyne) とは「自力」の意味で、一つの回路で発振と受信周波数とを混合する発想ですが、一方ヘテロダイン (Heterodyne) とは他力の意味で、他の周波数のお世話になるとの意味と理解されます。 低価格の真空管式 FM チューナの周波数変換回路は、古くて新しい実に 6AQ8 の1ユニットによるヘテロダイン方式で構成されていました。但し、発振強度と受信信号強度とのバランス等を考慮した適正な動作点にセットする必要があり、広い周波数範囲の安定動作は難しいものです。 FM では、周波数の上下比が 76 MHz〜90 MHz (日本) または 88 MHz〜108 MHz (欧米) と小幅なので中波の周波数変換回路よりも遥かに容易でした。
検波回路の動作は、むしろ検波というより、一つのグリッドに受信信号と発振信号を入力し、やや深いバイアスによる検波管の非直線性の強い部分を利用して、受信信号と発振信号の和または差を得る「周波数混合」の機能です。この回路は、音声信号をとり出す目的の検波回路とは区別して「混合回路」詳しくは「周波数混合回路」と言います。
この回路の動作時には混合管のプレートに、受信信号、発振信号、和信号、差信号の周波数が現われますが、そのうち一般に差信号だけを中間周波トランスにて選択します。 中間周波増幅以後の構成はヘテロダイン方式と同じです。 一方、発振回路は、混合回路に対して受信信号より中間周波だけ離れた周波数をもつ発振信号を供給する回路です。 構成は再生検波回路と同じものですが、外部からの信号は貰わず、無変調の発振回路のみ、または外部への接続による影響を取り除く緩衝増幅を含む回路にて構成され「局部発振回路」と呼ばれます。 「混合回路」および「局部発振回路」をセットにして、「周波数変換回路」と呼ぶのが一般的です。
混合回路を、後の音声信号を得る「第二検波回路」との対比において「第一検波回路」という場合があります。しかし、業務用等の高性能受信機では二度の周波数変換を行なうダブル・スーパー、三度の周波数変換を行なうトリプル・スーパーなどの構成もあります。 それぞれの混合回路または周波数変換回路に対しては第n混合回路、第n周波数変換回路と呼び、音声信号をとり出す目的の最終の検波回路を単に検波回路とする方が、混乱防止の観点からも好都合です。
ヘテロダイン方式では選局操作が1ダイアルで済んだのに引き替え、スーパーヘテロダイン方式の同調操作は、混合回路への入力信号の同調調整と局部発振回路の発振周波数調整の、異なる周波数のダイアル2個を操作する必要があります。 まず局部発振を受信周波数+中間周波数に設定して、次に混合回路の同調を受信周波数に設定します。
後になって、「二連バリコン」(並三ラジオの製作にてご紹介した)を利用して、バリコンのどの設定角度に対しても、常時二つの周波数の関係が保たれる様な、調整可能なLとCの組み合わせによる「トラッキング調整」方式が開発され、同調操作を1ダイアルとする「ワン・コントロール方式」が可能となりました。
スーパーヘテロダイン方式の操作性のイノチは上記のトラッキング調整によって支えられると言えるでしょう。
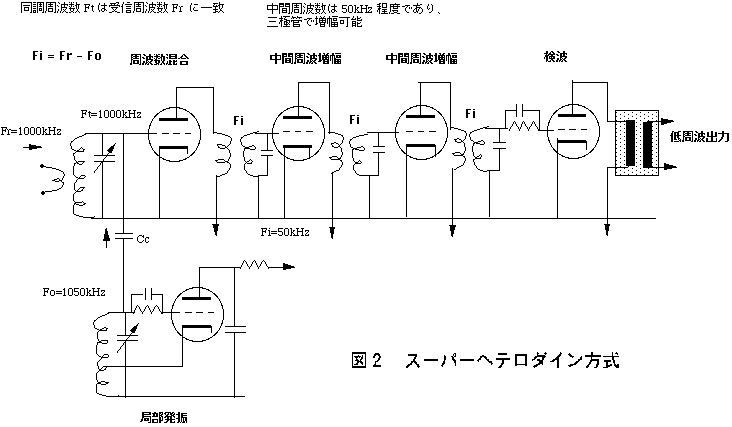
◇広義の高周波増幅:
あらゆる高周波増幅の総称です。 これにはヘテロダイン方式で出てきた中間周波増幅、および下記の狭義の高周波増幅が含まれます。
◇狭義の高周波増幅:
受信信号周波数のまま増幅する場合が該当します。1-V-1 の高周波増幅段はこれに相当します。 この名称は明らかにストレート方式時代の命名法を引きずっています。 本当は「無線周波増幅」という別名で区別するのが正解です。
スーパー方式でも周波数変換回路の前に無線周波増幅回路を置く場合があります。
◇入力と出力のインピーダンス整合、
◇発振の防止、
◇ゲイン調整の方法、
と言う三点でしょう。 これらが揃わないと正常な増幅ができません。
高周波増幅用真空管素子としては、「表1 高周波増幅用真空管素子と回路」に示すように、三極管によるものと四/五極管によるものがありますが、五極管のカソード接地 (プレート負荷) 回路がゲインおよび回路構成の簡単さにおいて主流で、殆どがこれです。 三極管1ユニットによる増幅回路では普通のカソード接地回路も使えますが、それ以外にグリッド接地方式があり、その変形にて2ユニットを合成して使う、カスコード接続、カソード結合等の変形回路があります。
三極管1ユニットだけの増幅では、プレートに現われた出力がプレート〜グリッド間の静電容量によって直ちにグリッドに入力され、発振を起こします。 そこで中和回路というブリッジによるプレート〜グリッド間容量りの打ち消し回路にて発振を防止します。 但し広い周波数範囲をカバーするのはバリコンの容量変化がブリッジのバランスを崩すため困難です。
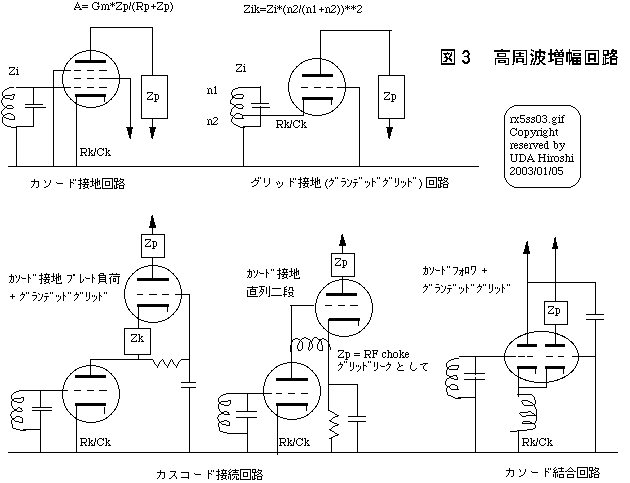
| ◎:ラジオは殆どがこれ | △:FM チューナ以外では殆ど見ない | |
| X:送信機の終段例あり | ○:テレビのフロントエンドの後段、専用管としては 6J4 のみ | |
| ○:テレビのフロントエンドの例 (6AK5-6J4) あり | ○:テレビのフロントエンドの例 (6BQ7) あり | |
| X:まれに発信回路、混合回路として |
|
| ||
| Cpg 結合による発振 | 各真空管が持つ固有の P/G 間静電容量によるPG 帰還 | 入力 and/or 負荷インピーダンスを減少する。 同調を外す(仮処置)。 MT ソケットセンターシールドの接地を確認する。 シールド板を追加する。 中和回路を設ける、球の品種を変える。 |
| コイルの結合 による発振 | 前段の同調回路と後段の同調回路との電磁結合、静電結合 | 同調回路の相互位置を離し・角度を変えて結合を除く、電磁・静電の遮閉 (シールドケース、ついたて) を講じる。 |
| 配線の結合 による発振 | P/G の配線が接近(Cpg 結合発振と同じ原理) | P/G の配線を短く、かつ離す、場合により部品配置を改善する |
| 回路の不良による発振 (1) | RF 増幅出力が B 電源に回りこんでいる。 | 増幅段毎にデカップリング回路を入れる |
| 回路の不良による発振 (2) | RF 増幅出力がヒーター電源に回りこんでいる。 | 増幅段毎のヒーター配線の両側に C を入れてグランドに落し、 ヒーター配線の RF 電位を下げる |
| 接地不良 | SG 回路 または K 回路のバイパス不良 | バイパスCの接地およびその場所を確認する |
ゲイン A は、 A=Zp/(Rp+Zp) * Gm
但し Zp= 負荷インピーダンス、Rp= 内部抵抗、Gm= 相互コンダクタンス
から求められます。 Gm が高ければゲインも取れると思われがちですが、雑音、安定度、負荷インピーダンス、帯域幅、Cpg 等の制約から、どんな球でも良いという訳にはいかず、最適な球が選択されます。
高周波増幅のゲイン調整方法には下記があります。
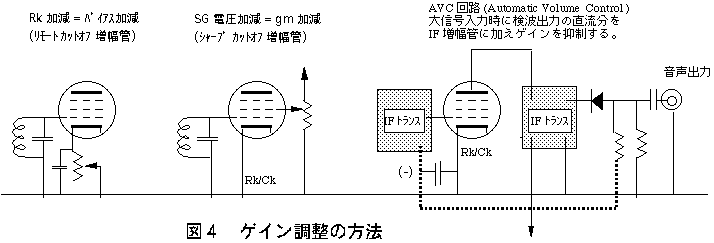
●手動
◇入力信号をポテンショ(ヴォリューム)で加減するもの−(例)アンテナ入力を絞る。
◇高周波増幅管の スクリーン グリッド(G2) 電圧のポテンショ調整によるもの − Gm
値を加減する。
◇可変μ高周波増幅管の バイアス電圧のポテンショ調整によるもの − Gm 値を加減する。
可変μ高周波増幅管 (バリアブルμ管、バリミュー管) は、別名リモートカットオフ管 (R/C 管) とも呼ばれ、 Eg-Ip 特性の内、深いバイアスを与えてもカットオフせずに、バイアス値に沿ってプレート電流がダラダラの坂にそって流れるため、大入力に対して深いバイアスで Gm を低下させながら対応できる構造の球です。
●自動 また、受信周波数ダイアルをスキャンしながら受信する場合、弱い信号でも強い 信号でも、同一音量レベルにて動作するには、ゲイン・コントロールから手を離せないことになります。 そこで検波出力から得た整流電圧をR/C 管による増幅回路 のバイアス値に加えて、大入力時のバイアスは深く、小入力時のバイアスは浅くするフィードバックによる AVC (Automatic Volume Control) またはもっと精密な AGC (Automatic Gain Control) が考案されました。
◇安定な周波数、
◇(可変周波数の場合の)安定な出力、
◇可変周波数の場合の周波数帯の確保、
となります。 どの事項についても、外部に出力を供給する場合に発振周波数または接続する負荷による変動を最小にする必要があります。
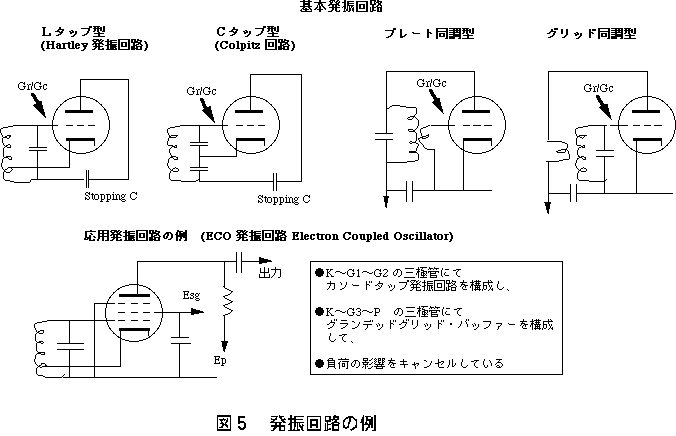
基本的な発振回路は三極管(用途としては発振管といいます)で構成されます。 その基本回路を五極管に応用したものもあります。 下記のプロトタイプがあります。
◇カソード・タップ式−−Lのタップ Hartley 回路の原形 −−Cのタップ Colpitz 回路 の原形
◇プレート同調式 −−プレートに同調回路を入れ、グリッドにコイルで結合
◇グリッド同調式 −−グリッドに同調回路を入れ、プレートからコイルで結合
以前「並三ラジオの製作」にて例示した実験機は上記 1. カソード・タップ式、オリジナル回路は上記の「グリッド同調式」に該当します。 Hartley, Colpitz はその回路の考案者の名前です。
◇供給電圧(ヒーター、B 共に)、発振管の内部抵抗 (=B電圧の変化)、
◇同調回路のインピーダンス(L/C)、タップのインピーダンス比、結合コイルとの結合度、
◇コイルとキャパシタの温度特性
L/C による発振回路では特別な電圧管理および温度管理を行なわなくても、総合で ΔF/F = 1/1000 すなわち 1MHz では 1kHz 位の精度と安定度を得ることができます。 この値ならば、標準の中波放送帯では実用上問題ありませんが、短波帯では、この程度の精度・安定度では受信機としての基本性能の問題となります。
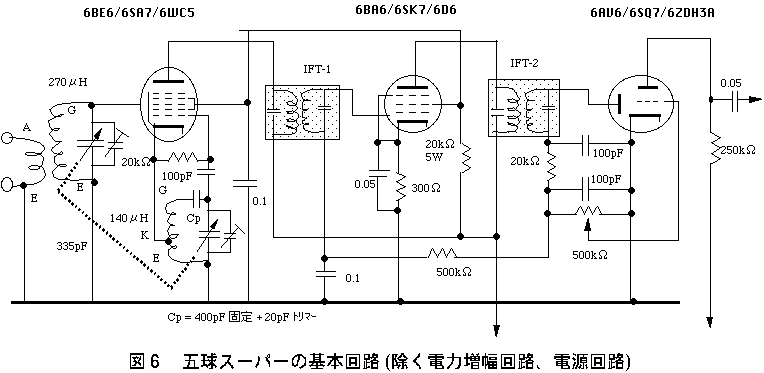
複合管: 周波数変換 − 中間周波増幅 −検波・低周波増幅−電力増幅−整流 ・・・五球
単一管:<周波数混合+局部発振>−中間周波増幅−<検波+低周波増幅>−電力増幅−整流 ・・・七球
五球スーパーの構成を、本来の回路単位毎に別の球を使うバラ構成をとれば、7球になります。 しかし製品とするには、球数とコストの関係から、周波数変換および検波・低周波増幅には複合管を利用して5球になりました。 また、既存のモノ・シングル・アンプとその電源を利用するならば、周波数変換、中間周波増幅、検波までの三球でも、五球スーパーと同じ構成になります。
このような構成以外に、無線周波増幅を周波数変換の前に配置した「高一スーパー」、中間周波増幅を二段重ねた「中二スーパー」等があり、高一と中二を構成した「RF1 - IF2」がアマチュア無線では標準的受信機であった時代があります。 その後、感度、安定度、選択度、および受信周波数の精度を実現するため、各種の形式によるダブル・スーパーまたはダブル・コンバージョンが標準になりました。
◇古典 2.5V 管 2A7 - 58 - 2B7 - 2A5 - 80
◇ 6.3 V ST 管 6A7 - 6D6 - 6B7 - 42 - 80/ 6A7 - 6D6 - 75 - 42 - 80
◇ 6.3 V 全メタル管 6A8 - 6K7 - 6B8 - 6F6/6V6 - 5T4
◇ 6.3 V 新メタル管 6SA7 - 6SK7 - 6SQ7 - 6F6/6V6 - (5Y3GT)
◇トランスレス ST 管 12WC5 - 12YR1 - 12ZDH3A - 12ZP1 - 24ZK2
◇ 6.3 V ST 管 6WC5 - 6D6 - 6ZDH3A - 42 - 80 (80K)
同小出力 6WC5 - 6D6 - 6ZDH3A - 6ZP1 - 12F (12FK, 80HK, 80BK)
◇標準 6.3 V GT 管 6SA7GT - 6SK7GT - 6SQ7GT - 6F6GT/6V6GT - 5Y3GT
◇標準トランスレス GT 管 12SA7GT - 12SK7GT - 12SQ7GT - 35L6GT - 35Z5GT
◇標準 6.3 V MT 管 6BE6 - 6BA6* - 6AV6** - 6AR5/6AQ5/6AK6 - 6X4/5MK9 *6BD6 可 **6AT6 可
◇同大出力 6BE6 - 6BA6 - 6AV6 - 6BQ5 - 6CA4/5RK16
◇標準トランスレス MT 管 12BE6 - 12BA6 - 12AV6 - 30A5 - 19A3
但し、戦前系の周波数変換管 (2A7, 6A7, 6A8 他) は標準 (6WC5, 6SA7, 6BE6) のものとは異なる発振回路の形式なので、周波数安定度に若干の問題がありました。
また戦前系の検波・低周波増幅管の主流は二極・五極管 (2B7, 6B7, 6B8) でしたが、二極・三極管 (2A6, 75, 85) も存在しました。
試作するとすれば、標準 6.3V MT 管が最も入手しやすいと思いますが、アンプ用の球も流用してデコボコの混成チームとするのも楽しいものです。
アンテナ端子からアンテナコイルの同調巻線にL結合されたアンテナ巻線を通ってアースに抜け、同調巻線とバリコンの容量によって同調した受信信号 (Fr) は周波 数変換管のコントロール・グリッドに入力される。
◇局部発振回路
周波数変換管の G1/G2〜G4 は三極管を構成しており、バリコンと発振コイルからなるカソード・タップ式の発振回路を構成して、Fo =受信周波数(Fr)+中間周波数 (Fi)を発振し、カソード・タップに生じた局部発振電圧が、受信信号とともに周波 数変換管のコントロール・グリッドに加えて入力される。
◇周波数変換管
周波数変換管の G3〜G4〜G5 は五極管を構成しており、プレートには Fr, Fo, Fo - Fr, Fo + Fr が現われるが、 Fo - Fr = (Fr + Fi) - Fr = Fi 中間周波数 Fi に変換された中間周波信号だけがプレートの負荷に用意された 第一中間周波トランスの一次側に受け入れられる。
◇周波数変換ゲイン
同調コイルの共振、周波数変換管の増幅等で総合ゲインは 12〜15 db (4〜5倍)といわれる。
◇中間周波増幅 第一中間周波トランスの二次側に誘起された中間周波信号を、中間周波増幅管の G1 に入力し、増幅する。増幅された中間周波信号は、中間周波増幅管のプレートの負荷に用意された第二中間周波トランスの一次側に受け入れられる。
◇総合ゲインは一段にて 46 db (200 倍) 程度といわれる。
◇低周波増幅 検波出力をハイμ三極管にて約 30db (30 倍) 程度増幅する。
ここまでの合計ゲインは 12 + 46 - 20 + 30 = 70 db (3,000 倍) であり、ラフな計算では1mV の電波が 3V の出力となって電力増幅管に入力されることになる。
このようなゲイン配分方法はオーディオ・アンプの設計と類似しています。
バリコンにトリマーキャパシタが組み付けのものと、ないものがあります。 ないものでは30PFぐらいの適当なトリマーを予め取り付けておくと便利です。 三連があれば調整時に使い回しが効き、改造しながら受信を楽しむ余裕があります。
バリコンの羽根は、半円の中心からはずれています。何故でしようか? バリコンの形式には容量直線形、波長直線形、周波数直線形の三通りがあります。回転角に対してそれぞれ容量、波長、周波数が比例するように羽根の形を設計してある訳です。 容量直線形を主同調に使うと、羽根が入った方では周波数変化の効きが悪く、抜けた方では効きすぎとなることは、
同調周波数 F = 1/{2*π*SQRT(LC)} 但し、SQRT(LC) は LC の平方根
となり、角度に対して C が平方根でしか効かないことによるものです。 ただし、小容量の容量直線形を補助同調に使う場合は、平方根でも一次係数近似になり、均等な目盛が期待できます。短波用受信機では、小容量の三連などにて混み合った短波放送周波数帯を拡大して展開するバンドスプレッド・バリコンを併設しました。
周波数直線形では角度Δに対して 定数1+定数2 * Δ二乗 とすることによって、角度と周波数の関係を直線としたものです。周波数直線形ではモノサシのよ うな整ったダイアルが使え、且つ目盛の間は一次補間により、直読が可能です。 市販のジャンクは、JES に定める波長直線形近似の形式で、正確な波長直線ではなく半円に偏芯シャフトを取り付けた、スペース・ファクタとコスト、直線性のカネアイの製品となっています。
◇アンテナコイル
受信周波数は 526.5〜1606.5 kHz (周波数比 (Fr) = 3.051) に合わせることになります。 335pF のバリコンにて 526.5 kHz に同調するに必要なインダクタンス (Lin) は、
Lin = 1/{ (6.28 x 526.5 x 10**3)**2 x 335 x 10**(-9) } := 270 μH
これは、並三の時に設計したものと同じもので、グリッド側コイルには 35mm ボビンに 0.3mm 線を 90 回程度、アンテナ結合コイルには 20 回程度巻いたものです。
◇発振コイル
アンテナコイルと同様です。アンテナコイルのような結合コイルはありません。
できればアンテナコイル、発振コイル共に、ダストコア入りの可変Lにしたいものです。 適切なタップ位置を求めるため巻きもどしにて減ったLをコアの調整で逃げ、かつトラッキング調整にも利用できるからです。 しかし、コア入りボビンが秋葉原で手に入ればいいのですが、売っているとしても大体ボビンが細すぎて巻き切れないでしょう。 むしろトランジスタラジオ用のアンテナコイルおよび発振コイルを流用する術があります。
所要のインダクタンスは以下の附加Cの計算の後に計算します。
局部発振回路は、バリコンがどの角度にあっても、常に受信周波数+中間周波数の関係を維持する必要があるため、発振コイルには同調コイルよりもインダクタンスの少ないものを使い、バリコンは容量を減らすために直列にC〜パディングキャパシタ= Padding Capacitor 、附加Cを入れます。 局部発振周波数は 526.5+455 〜 1,606.5+455 kHz → 981.5 〜 2,061.5 kHz となり、 上端と下端の周波数比 (Fr) = 2,061.5/981.5 = 2.10 となり、最大容量が最小容量の約4倍ですむことになります。
◇附加キャパシタ(附加C)
従って、同調コイル+パリコン (Cv) にて得た三倍の周波数比を得るに必要な容量の 4/9 の容量 Cs を実現するに必要な附加C (Cp) は下記の式から求められます。
Cs =1/ (1/Cv + 1/Cp) → 4/9 x Cv = (Cv x Cp) / (Cv + Cp) →
4/9 Cv + 4/9 Cp = Cp → (1-4/9) Cp = 4/9Cv → Cp = 4/9 / (1-4/9) x Cv
= 5/4 Cv
この計算によれば、335pF のバリコンを使う場合、 Cp = 1.25 x 335 = 419 すなわち、局部発振側のバリコンには 419 pF の附加Cを直列に挿入すれば、
1/(1/335 + 1/419) = (335 x 419) / (335 + 419) = 186
となり、最大容量が 186pF のバリコンに置き換えられるわけです。 附加Cは可変の方が調整が楽なので 400pF の固定キャパシタに 30pF 程度のトリマーを抱かせたものが良いでしょう。 従って、局部発振の下端周波数 981.5 kHz を発振するに必要なインダクタンス (Losc) は
Losc = 1/{ (6.28 x 981.5 x 10**3)**2 x 186 x 10**(-9) } := 141.5 μH
となり、インダクタンスは巻き数に比例するので、発振コイルはアンテナコイルと同一ボビンに約半分の 45 回程度を巻き、2〜3 回加減できるように用意することになります。 なお、タップ位置は巻き数全体の 5%〜7%〜10% 位の引きだしを用意して、雑音・感度の最も良いものにセットすると快適でしょう。
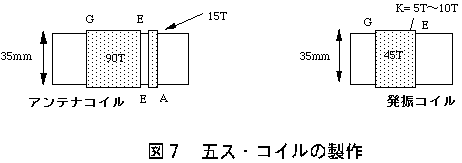
| ドライブ・シャフトの自作 | ヴォリュームのシャフトの一部をグラインダーで細くして、ストッパーを外せばOKです。 |
| ドラムの自作 | 丸い缶詰の空缶の底を 5mm 位に切り取り、縁に銅線をハンダ付けして、中心にはツマミをハンマーでこわして取り出したシャフト止め金具をハンダ付けし、スプリング掛けと糸穴を縁の一箇所にあければ完成です。 スプリングにてドライブ糸に一定の張力を掛けます。 |
| ドライブ糸 | 太めのナイロン道糸などが利用できましよう。 ドライブ・シャフトに2〜3回巻き付けてスリップを防ぎます。 |
| ダイアル指示 | ドラムに目盛板をじか付けして回し、パネル面の窓から周波数を読んでも良し、バリコンのシャフトをパネル面の外側に飛び出させて、ツマミを壊して得たシャフト止め金具に針をハンダ付けし、固定の目盛板上を針が動く形式もよし。 後者はプラスティック・ケースの蓋などでカバーすれば測定機風になります。 |
信号の進行方向に沿ってL字型にコイル、球、中間周波トランスを交互に、バリコンを中央からやや右に配置するとスッキリします。 なお、中間周波トランスはパワートランスに近くに配置すると磁気漏洩ハムの原因となるので、余り接近しないほうが無難です。
全面パネルに小型のスピーカまで組み込むならば、横長の配置が使い易いかもしれませんが、机上に置くならば設置幅を狭くして縦長とする配置も通信機みたいでカッコウが良いでしょう。 アウトプットトランスはパワートランスから離して高周波関係の部品のなかに潜り込みハム対策とするのも手です。
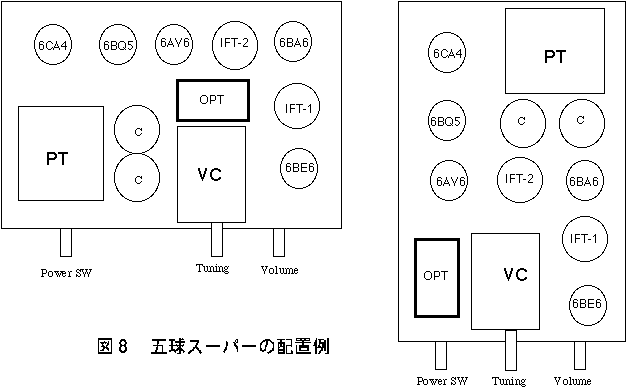
調整棒とは、プラスティック棒の一端にはダストコア、他の一端には金属環がはめられていて、Lを増やすには〜ダストコア、Lを減らすには〜金属環をコイルに挿入してLの値が過大か、過小か、または同調した周波数が過大か、過小かを判定する道具です。
調整は次の順番で行ないます。
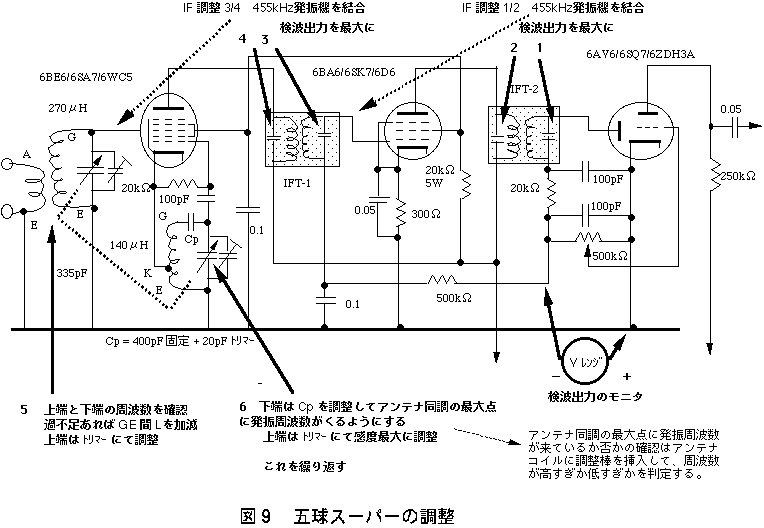
ここまではアンプの初期試験と同様です。
テスオシ出力または並三/並四ラジオのアンテナ端子を、中間周波増幅管のグリッドに、5pF 程度の微小容量のキャパシタ(被覆線を撚り合わせたもので可)を介して接続し、中間周波トランス [2] の検波入力LCおよび中間周波増幅管の負荷LCの同調をとります。 検波出力電圧をテスターであたり、最大値になる所が同調点です。 もし同調点がタダッ広くて良くわからない場合は、中間周波トランスの同調Cを増やしても減らしても出力電圧が減る、丘の中央あたりにとどめておきます。
次に、テスオシ出力または並三/並四ラジオのアンテナ端子を、周波数変換管のグリッドに、5pF 程度の微小容量キャパシタを介して接続し、中間周波トランス [1] の中間周波増幅入力および周波数変換管の負荷の同調をとります。 検波出力電圧をテスターで当たるのは上記と同様で、最大値をさがします。
もし、中間周波増幅が発振し始めれば、検波出力電圧が異常に増加し、テスオシ出力または並三/並四ラジオのアンテナ端子をはずしても出力電圧が残るので識別ができます。 発振対策は前記「3.2 高周波増幅回路の要件」◇発振の防止 (高周波五極管に限定) に示した何れかの対策をとります。
受信同調周波数は、厳密には 526.5〜1606.5 kHz (周波数比 (Fr) = 3.051) に合わせることになりますが、NHK第一 (594 kHz) が、バリコンを 20 度位に抜いた所で同調すればOKです。 もっとバリコンが深い所で同調する場合はグリッド・コイルを巻きたし、もっと抜いた位置ならば巻きもどしです。 上端の受信周波数は、1,600 kHz 辺りの信号をテスオシまたは並三/並四ラジオで発生させ、トリマーを調節すれば終わりです。
実際の調整の要領は、「アンテナコイルにて決められた周波数に、局部発振周波数が追髄していることを」意味するので、バリコンの入った位置、真ん中あたり、抜けた位置の3ポイントで感度最大の設定調整ができれば、実用上は問題ありません 実際にはテスオシはなくても放送波を受信して、調整が可能です。 ただし深夜に停波する局は深夜の調整には使えませんけど。
受信周波数の下端 (NHK第一:594 kHz)、中央 (TTBS:954 kHz) 、上端 (文化放送?:1242 kHz か、もっと上)・・・言い替えればバリコンの入った所、真ん中、抜けた所でそれぞれ、附加C、インダクタンス、トリマーで調整ができます。 これを三点調整と言います。これら三つの可変要素のどれを触っても全体が崩れるので、下から上へ繰り返し3回程度の兼ね合い調整が必要です。
少しインチキな方法としては、下と上だけ合わせて真ん中は逃げてしまう方法もあります。 これは二点調整です。 下 (NHK第二:693 kHz)は附加Cのみ加減して合わせ、上はトリマーをいじってカンベンしてもらう訳ですが、実用的には差し支えないレベルに追い込む事ができます。
何故このようなヤヤこしいことになるかと言うと、直列の附加Cを背負ったバリコン角度〜容量カーブが、裸のバリコンのそれとは比率的に一致しないことに原因があります。 式に値を与えてカーブを描けば判るはずですが、真ん中が弛むかまたは盛り上がる可能性があり、これを抑え、局部発振周波数がアンテナコイル〜裸バリコンの変化に中間周波数だけずれて追髄していく必要があるからです。
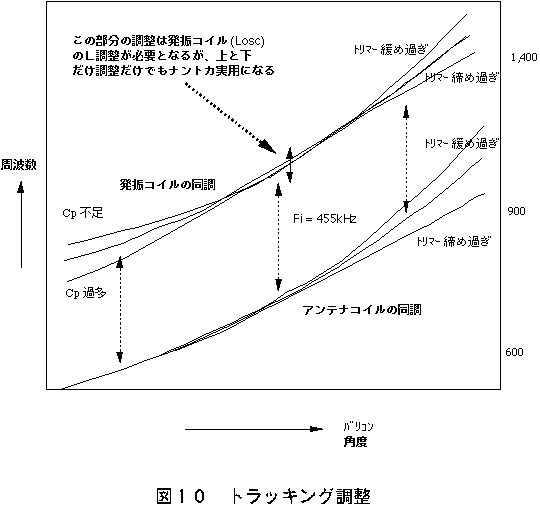
FM 放送などカバーする周波数比が小な場合は二点調整、極めて小な場合は真ん中一点とします。 高一ラジオまたは、無線周波増幅付のスーパーラジオでは無線周波増幅段の同調と検波または周波数変換段の同調についてもトラッキングが必要ですが、同じ二連または三連バリコンを使うので、容量カーブが同一であり、下端をLで合わせ、上はトリマーで合わせ、二回繰り返しにて調整が完了します。
この段階で、別途に調整用・比較用として用意した中波ラジオ(基準機)の受信周波数の上限と下限と、試作機のそれらを比較して、ひどく異なる場合はアンテナコイル及び発振コイルのインダクタンスを再検討し、巻きたしまたは巻きもどししながら、トラッキング調整をし直して、基準機のダイアル指示に近づける必要があります。