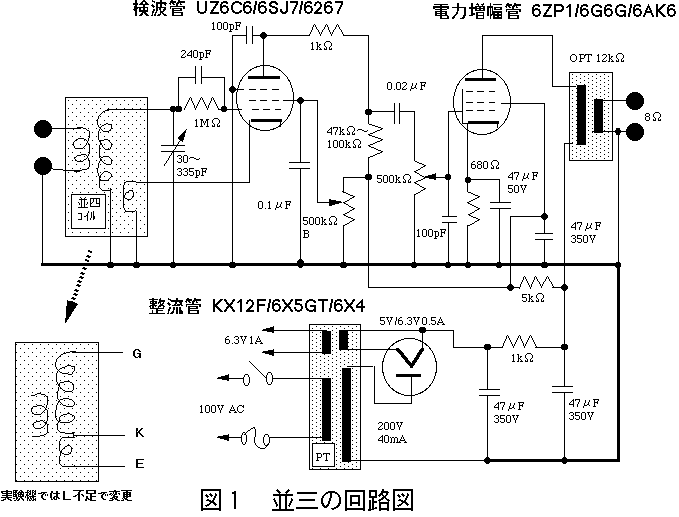
現在では、中波 (MW) 放送が AM (振幅変調方式) なので AM 放送と言い習わされていますが、これは明らかに誤用で、短波 (SW) 放送でも AM ならば AM 放送ですが、慣用語にはかないません。 一時中波放送を標準放送 (Standard) Broad Casting と称し、略して BC と呼んだ時代もありました。 一方、1950 年代に米国で超短波 (VHF) による FM (周波数変調方式) 放送が出現するにおよび、AM 放送に対して FM 放送と呼ばれるようになり、日本もこれを倣いましたが、この FM と言う呼び方も AM と同様に誤用です。 何故って、中波・短波でも FM 放送は技術的には可能なわけですから。
中波放送の開始当時、スピーカから音声を聴くことができる AC100V を電源とする受信機の最小構成が「並三」でした。 並三という名称は、主要回路それぞれに、真空管を一本づつ使った三球構成の受信機を意味するものらしいのですが、並三が出現してからずっと後になって、役所か NHK が統制品としての受信機のクラス別の正式な分類名称を考え「並三球式受信機」と呼んだのでは、と想像しています。 このあたりの事情をご存じの方、どうぞご教示くださいませ。
第二次大戦後 (以下、戦後)、欧米列強の植民地だった多くの国が独立し、それぞれの国が自主放送するため、周波数需要が増加し、一方船舶通信は VHF 電話などの機器の開発と利用が進展したため、中波利用の必然性が減少し、一部を放送波に譲りました。 通信条約会議を通じて 1950 年頃 535kHz 〜 1,605kHz の周波数帯に拡大されました。 また送信する中心周波数は 540kHz から1,600kHz を10 kHz 毎に区切って使うよう原則づけられました。 1980 年代の途中では、さらなる周波数需要に応えて、割り当てピッチが 9kHz 毎に変更され、割り当て可能周波数が 10kHz 毎の時代に比べ一割増加するとともに、現行の 526.5kHz 〜 1606.5kHz の周波数帯となり、初期に比べ全体では130kHz 広くなりました。
この変更では、各放送局の中心周波数を 10 の整数倍 kHz から直ぐ上の 9 の整数倍 kHz に変更し、例えば NHK第1 は 590kHz → 594kHz と端数が付くようになりました。 何故直ぐ上かというと、従来の送信アンテナはそのままで、主発振機以外の機器は交換せずに調整の範囲で周波数を変更できるからでした。
一次拡大割り当ておよび現行割り当てでは上端・下端ともに周波数に端数がついていますが、各送信周波数に対して単に中心周波数を割り当てるのではなく、AM 方式の場合、音声エネルギーは上下に発生する側帯波と言う波により伝達されるため、これを考慮して一つの中心周波数の前後 5kHz または 4.5kHz を含めて「帯域」と捉える考え方が反映されました。 すなわち、中波放送帯を 9kHz セパレーションとした場合は、最下端の中心周波数 531 kHz の 4.5kHz 下は 526.5kHz、同様に最上端の中心周波数 1,602kHz の 4.5kHz、上は 1606.5kHz となり、現行割り当てではこの幅を中波放送周波数帯と定めたものです。 前後 5kHz または 4.5kHz の帯域幅では、隣の波と混信を起こします。 しかし、国内の中波放送に関しては、局の地域別、周波数、電力の割り当てをうまくやって強力な局同士が接近しないように設定しているので、実用上は問題ありません。
◇電波から音声信号を取り出す「検波回路」、検波段=検波管
◇音声信号をスピーカを鳴らすよう増幅、「電力増幅回路」、電力増幅段=電力増幅管
◇B電源を作る「整流回路」〜適当な整流素子がなかったことも一因=整流管
ラジオでも、アンプのように単位機能回路に対して「段 (stage)」と呼ぶことがあります。 各々の段に使用する真空管はその用法の分類名称として、検波管・電力増幅管・整流管とも呼ばれます。 真空管の用途上の分類でも同じ呼び方が適用されます。
ラジオ受信機の構成には、並三以前に、もっと原始的な金属酸化物の整流作用を利用した「鉱石ラジオ」(後のゲルマラジオ)、並三より遥かにポピュラーな低周波増幅を一段追加した「並四」、より微弱な放送もキャッチできる「高一」という構成および名称がありました。
レシーバと言う名称こそ本来の (無線または放送) 受信機ですが、今日では更に意味が変り、家電メーカおよび家電販売業界では、チューナつきアンプをレシーバと称しています。 今日のヘッドフォンは当時はレシーバと呼びました。 この名称も誤用ですが、こちらは放送開始以前から存在した電話機用語として、耳当て式受話器をレシーバと称したことに由来しています。
並三/波四のイノチは検波回路にあります。 検波は高周波と低周波のゲートウェイであり、並三/並四では回路全体がシンプルな故に非常に重要です。
電力増幅回路および整流回路は、皆様が日夜ご苦労の、否もとえ、お楽しみのシングルアンプのそれと全く変りません。 従って検波段のみを製作されれば一応並三/並四は完成します。 検波回路は、下記のような幾つかの要素から構成されます。
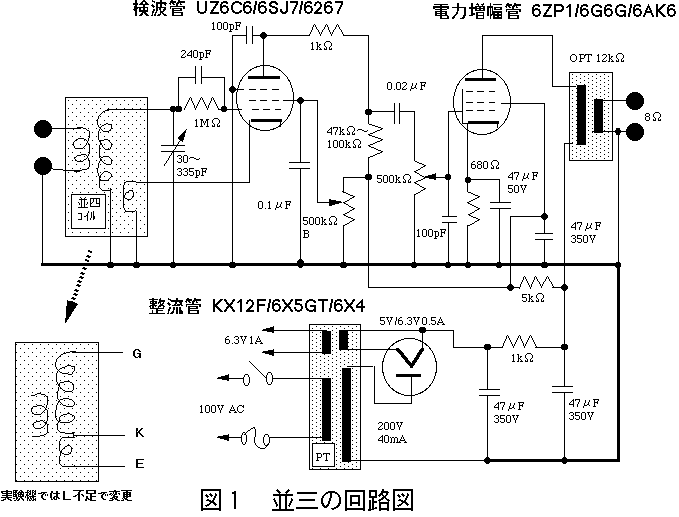
グリッド検波方式の他に真空管による検波方式には、プレート検波、無限インピーダンス検波、前記の二極管の半波整流による検波、ブリッジによる検波、倍電圧検波もあります。 しかし、真空管および各パーツが高価であった当時には、真空管の使用本数や使用部品点数が増える方式は敬遠されて、グリッド検波方式およびスーパーヘテロダイン受信機に用いられた UY75, Ut6B7, 6ZDH3A, 6B8, 6SQ7, 6AV6 等による二極管検波方式以外は一般的ではありませんでした。
再生検波方式では、うまく調整してこの発振の直前にセットし、同調回路のインピーダンスを高めゲインを上げて高感度にする、正帰還動作をうまく利用した回路で、別名「オートダイン」とも呼ばれます。
従って、受信調整時には一旦自己発振と受信波とのビート(唸り)がピーキューギャーと賑やかにしてから発振の直前に持っていくことになります。 再生検波段の総合ゲインは 55db 位と言われ、再生作用の効果はプラス 20db 位と考えられます。
初期的な検波回路には、ソフトバルブと言う真空度の低い球が使われたため、再生検波段をVと表わしましたが、後に検波段の意味に変り、またVの後の数字は低周波増幅段数を、Vの前の数字は高周波増幅段数を表わしました。 従って、
●高周波増幅なし、検波、低周波信号出力または直ヘッドフォンの構成は 0-V-0
●高周波増幅なし、検波、低周波増幅1段の構成は 0-V-1、「並三」に相当
●高周波増幅なし、検波、低周波増幅2段の構成を 0-V-2、「並四」に相当
●高周波増幅1段、検波、低周波増幅1段の構成を 1-V-1、「高一」に相当
となります。 また、高一では高周波増幅の価値〜感度と分離度が目立っため、特に低周波の段数は論じなかったようで、「高一低一」等の名称はありません。 なお、曾てのハム用短波受信機には 1-V-2 構成が大変ポピュラーであったし、業務用・軍用には 2-V-2 構成の長中波受信機もありました。
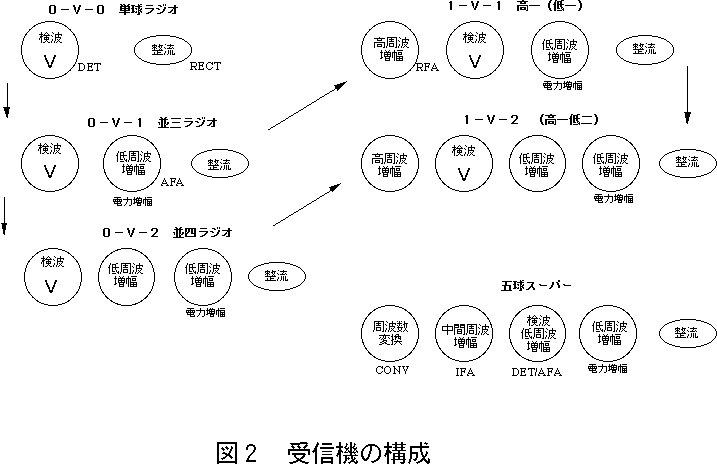
当然、三極検波管の負荷はトランス結合にして、ゲインを稼いだ訳ですが、先輩格にあたる更に低周波増幅を一段加え感度の高い「並四」が並三の存在を脅かしていました。 但し量産型並四の使用球は整流管以外はすべて三極管であり、四極管や五極管を混用したものは殆どありませんでした。 また当時は B 電源用に適当な整流素子がなく、整流管がかならず使われたため当然球数に含まれ、また複合管は現われる前なので、一球一素子でした。
その後、四極管 UY224, UY24A, UY24B や五極管 UZ57 の検波管が出現して、検波ゲインが上がり、また五極電力増幅管 UY247, UY47, UY47B の起用により、並三の総合ゲインは並四に並びました。 が、しかし結局メーカ製品の量産型並三はあまり数は増えませんでした。 その原因は下記が考えられますが、どれが支配的要素なのかよく判りません。
●初期の並三の感度不足との不評が後々まで尾を引いた
●ユーザには球数が多い並四の方が高級に見え、並三は安物乃至倹約型と写った
●総合ゲインでは並四にくらべて不足だった(個人的にはそのように感じていますが)
●メーカや販売店がそのように誘導宣伝した
●メーカに並四製品・材料の在庫があった
●並四がかなり普及していて、精々買い換え需要だった
●買い換え需要の一部が高一に流れた
●オール三極管構成の並四に音質的に負けた (補足1)
●並四の UX12A は並三の UY47B よりヴォイスコイルの断線が少ない (補足2)
(補足1) :音質は並三、並四ともにカンチレバー式のマグネティック・スピーカで、お世辞にもいい音ではありませんが、クセの強い五極電力増幅管 UY47B よりは、三極電力増幅管 UX12A の方が、それなりにソフトだったかもしれません。
(補足2) :またプレート電流も UY47B=20mA に引き替え UX12A=8.5mA と少なく、しばしば起きたスピーカのヴォイスコイルの断線を回避できたこともありましょう。
●改良例 UX112(ナス 5V0.25A) 〜UX12A(ST 5V0.25A) 〜UX12AK(ST 5V0.4A
傍熱型*)
●改良例 UY227(ナス 2.5V1.75A) 〜UY27(ST μ=9) 〜UY27A(1.5A) 〜UY27B(1.0A
μ=27)
〜最終的には UY56 に移行した。
●改良例 UY224(ナス 2.5V1.75A) 〜UY24A(ST) 〜UY24B(改良点不明)
〜UY57S(57 の G3/K 共通)
●改良例 KX112(ナス 5V0.5A) 〜KX12B(ST) 〜KX12F(?) 〜12FK(傍熱型)
●消滅例 UX226(ナス 1.5V?A) 〜UX26B(ST 1.5V1.05A)
フイラメント電圧が 1.5V と特殊なため使用されなくなり、消滅した。
●縮小例 UY247(ナス) 〜UY47(ST) 〜UY47A(?) 〜UY47B(規格縮小) 〜3YP1(6ZP1 改、傍熱型*)
傍熱型* 注:管内でヒータの中点にカソードを接続して直熱管とのソケット互換を確保している。
●初期型ナス管構成 三極+三極 UY227 -(T)- UX112A - KX112B いずれも低感度並三
●初期型 ST 管構成 → UY27/A/B -(T)- UX12A - KX12B 検波管の改良
●高性能標準型構成 四極+五極 UY24A/B - UY47B - KX12B
UY224 -UY247 構成は不明
●マイナーな構成 五極+三極 UZ57 - UX12A - KX12B/12F
●量産高性能標準型 五極+五極 UZ57 - UY47B - KX12B/12F
●戦時型トラレス球 五極+五極 12YR1 - 12ZP1 - 24ZK2
並三では四極+三極 (UY24A/B + UX12A?) の組み合わせ製品は見聞きしたことがありません。 メーカ系列が別で成立しなかったのかもしれません。
●初期型ナス管構成 UY227 -(T)- UX226 -(T)- UX112A - KX112B
●標準型 ST 管構成 UY27/A/B - UX26B - UX12A - KX12F 検波管の改良が適用された。
●バリエーション UY56 - UX26B - UX12A - KX12F
●後期型 ST 管構成 UY27B - UY56 - UX12A - KX12F この頃には並三も認められてきた。
●例外的 ST 管構成 UZ57 - UY56 - UX12A - KX12F 小型セット一例だけ記憶がある。
戦後 1955 年頃までは、手軽な娯楽と言えばラジオと映画だけで、テレビが家庭に普及する前の時期でした。 また戦時中は、球も部品もすべて軍需優先であって、民生品のラジオや部品製造が中断していたため、戦前製ラジオおよび不良部品の多い戦時型ラジオは、相当の台数が故障の憂き目に遭っていました。 この状況に対応するため、当時 NHK は全国修理キャラバン隊を組んで、公民館等にて巡回ラジオ修理を定期的に行っていました。
当時、町の電気店には既製品のセットの他に球や修理パーツ一式が置いてあり、店主も修理が暇な時には自家製品を作って売るような状態で、特殊品以外は秋葉原に行かなくても一応用が足り、仲良くなるとアマチュアにも色々教えてくれ、逆に教えてあげたりしたものです。
私事ながら、当時通信工学系の学生であった筆者にも多様なラジオの修理依頼が持ち込まれ、球と部品、回路の近代化更新を含む修理に精をだしました。 保守品種となった球を使っているセットは、球+ソケット交換で近代化しました。極端な例では 2.5V 球構成の高一を、外観はそのままにして出力管、整流管を残して、前段3球を MT にて近代化し、5球スーパーに改造した例もありました。 また、自家用以外にアルバイト兼ボランティアで2〜3球のパーソナル・ラジオを延べ15 台ぐ らい、パーツ代の2割程度の薄利で受注製造した経験がありました。 キッカケは長期療養で入院している友達から「イヤフォン・ラジオを作ってくれ」と頼まれ、製作納入したことでした。 そのセットを見た療養仲間から次々と発注が掛かり、製造〜納品に多忙な時期がありました。 何分病床で使うラジオなので、何よりも小型であり、スピーカは装備しても常時はイヤフォン聴取であり、アンテナは長く張れず、ノイズはなく、ツマミは少なく操作は簡単で、安全性は高く、ということで利用者が申し出る以外の本来の要求仕様を満たす厳しい条件を、MT 管を利用して構成し懸命にクリアーしたものです。
このようなラジオの世代交代を通じて、ほとんどの真空管は 6.3V 球に移行しました。 従って 6.3V 球によるメーカ製並三、並四受信機は生まれる機会がなかったのです。 一方、皆様ご存知の 6ZP1 は大戦中に生まれたトランスレス球の 12ZP1 と同規格で、オリジナルは米国の 6AK6/6G6G であり、五球スーパーの電力増幅管として大活躍しました。
●36 - 38 - 84 or 77 - 41/89 - 84 戦前の車載系 6.3V 球
●6C6 - 6ZP1 - 12F (12FK/80BK/HK), 6C6 - 42 - 80 教科書的標準構成
●6J7/6J7G/6SJ7/GT -6G6G/6K6GT - 6X5G/GT (5GK3) メタル、GT/G管構成
●6SH7/GT - 6V6/6F6GT - 5Y3GT 同上強力版
●6AU6 - 6AK6/6AR5/6AQ5 - 6X4 (5MK9) 7ピンMT スリム構成
●6CB6 - 6CL6 - 6CA4, 6SH7 - 6AG7 - 5T4 ハム色の濃い MT/GT/メタル構成
●6267/EF86 - EL84(6BQ5) - EZ81(6CA4) 欧州ムード 9ピンMT 構成
なお、筆者が本文の裏をとるために行った実験は、カンニングになりますが 1991 年に組んだ 6C6 -37 -6ZP1 -12F 構成のプラグイン・コイル式 0-V-2 =並四をベースにしました。 茨城の田舎にある拙宅では、並三ではNHK1/2 以外はやや弱く、FEN が感度不足なのです。
並三の回路は[図1 並三の回路図]に示したとおり極めて簡単です。 電源は Si ダイオードでも、半波整流でも、全波、ブリッジ、倍圧、何でも結構です。 結局、再生検波回路以外は普通のアンプと同じです。 アンプを組める方にとっては、並三で難しい箇所は、同調回路と再生回路だけです。 それには回路部品、特にコイルの自作が必要となり、その調整作業が必要となります。
真空管の種類 |
再生検波の適性 |
コメント |
評価 |
| 三極管、パワー管 | 感度が低く利用価値少なし。 | 初期並四の検波が三極管でした。敢えて挑戦することもないと思います。 | △ |
| 高周波用 G3 〜K が接続された5極管(S/C,R/C を問わず) | 管内で G3 と K を接続した球は回路により不安定。 | 回路によってはボディエフェクト (注1) が出ます。但しカソード接地回路ならOK。中波では問題なしです。 | △ |
| 高周波用4極管 | 使える。 | UY24B, UY36, 6CY5 等の高周波4極管は安定しています。 | ○ |
| 高周波用リモートカットオフ(R/C)5極管 (注2) | 使える。 | 6BA6 が安くて優秀です。 | ○ |
| 高周波用シャープカットオフ(S/C)5極管 (注2) | これがベスト | 57, 77, 6C6, 6SJ7, 6AU6 が標準です。 6267/EF86 はローノイズで素晴しいです。 | ◎ |
(注1) 6AG5, 6AK5, 6SG7, 6SH7 等が 該当、回路が不適当な場合・・・同調回路からタップをとりカソードに帰還をかけるHartley 式発振回路の発展形である ECO 回路 [Electron Coupled Oscillator] で G3 をカソードに接続した場合・・・短波では受信機に手などを接近すると、受信周波数がずれて操作が困難となる現象=ボディエフェクト body effect が起きます。 G3〜K を別に引きだした球でも G3 を K に接続すると同様の現象が起きて、それは正しい ECO 回路ではないのです。
(注2) G3〜Kが別に引きだしてある球、殆どはこれですが、G3 を接地すればボディエフェクトは起きません。
以下、同調回路と再生回路の設計と製作、調整作業について詳しく述べます。
◆共振周波数Fは F(Hz) =1/{2π x SQRT (L(H) x C(F) ) } で求められます。 但しSQRT (A) は A の平方根の意味です。
◆例えば、100μHのコイルと 100 pF のキャパシタによる共振周波数は、
1/{2 x 3.14 x SQRT( 100 x 10**(-6) x 100 x 10**(-12) ) } = 1/{ 6.28
x SQRT( 10**(-14)) } =1/{6.28 x 10**(-7)} =10**(7)/6.28 = 10,000,000/6.28 =1.59 x 10**(6) =1,590,000 Hz =1.59 MHz
但し10**(-6) は 10 のマイナス6 乗、**(6) は6 乗の意味です。
と求められます。もしLを4倍にすれば、Fは半分になり、Cも同様に4倍にすればFは半分になります。そこでL=2倍、C=4倍とすれば、Fは8の平方根
2.82 で割った値、1.59/2.82 = 0.564MHz となります。
中波の放送周波数帯 (現行の電波法規では 526.5kHz 〜1606.5kHz) をカバーするためには、もう少しL、CいずれかまたはLCの積を大きくする必要があります。 そこで、LCの積を周波数から逆算します。
0.564/0.5265 x 2.82 = 3.02 , 3.02**2 =: 9.1 となります。 但し =: は約の意味です。
これから、前記のLC積 (100x100=10,000) を 9.1 倍の 91,000 とすれば、丁度予定の周波数帯の下限周波数になります。
バリコンは現在でも秋葉原のジャンク屋にて入手できます。
殆どが AM 用二連 に FM 用の小容量三連を併設したバリコンで、シンセサイザ以前の紐かけダイアル式の AM-FM チューナに使われていたものです。 AM 用二連または FM 用三連併設でも、AM 用では大きいセクションと小さいセクションとで構成されたものがありますが、五球スーパー用の「トラッキング・レス」と呼ばれるもので、大きい方のセクションが使えます。 リサイクル・ショップにて紐かけダイアル式 AM/FM チューナのジャンクを購入して、バリコンをプリント板から外すというテがあります。(2004/06)
無理して古い「単連」を探す必要はありません。 また古いラジオから抜き取るのもテですが、むしろ修理して原形動態保存するほうが絶対楽しいので、それは止めましょう。
送信機などに使う、羽根の数が 10 枚位の絶縁体がステアタイト(陶器)で小型のバリコンは、容量が少なくて中波放送帯をカバーできません。 しかし並列に色々な容量の固定キャパシタをロータリ・スイッチで切り替える覚悟があるとおっしゃるのなら、一切お任せいたします。
また半導体のバリキャップに与える電圧を可変としても可能です。 但し 9 倍もの可変比が得られるものがあるのか、筆者は確認していません。 ある程度の可変容量が得られるなら、上記の小型バリコンと同様に並列固定キャパシタ切り替えとすれば、可能性が十分あります。(2004/06)
バリコンはシャーシへの取り付けます。 筆者はL型のアルミ板にてバリコンの前後にビス止めして、さらにシャーシへ固定する金具を作り、マウントしました。 AM/FM チューナ用のものなら、高さ 60mm のシャーシ内に取り付け、バーニア・ダイアル駆動が可能です。(2004/06)
以下、最も入手可能性の高い FM 付き二連を想定して説明します。 並三用としては大きい1セクションだけを使います。
ジャンク・バリコンの中波用ユニットの最大容量は約 335pF です。 コイルのインダクタンスは、上記の計算から、
91,000/335 = 272
・・・と、約 270μHのインダクタンスが必要となります。 実際には入手したバリコンの規格がハッキリしているとは限らないので、所要Lは加減が必要です。 もし素性の知れないバリコンの場合は、様子の判っているバリコンを並列にして受信動作すれば、概略の容量が比較できます。
同調回路がカバーできる下端と上端の周波数の比 (Fr) は、バリコンの最大容量 (Cmax) と最小容 量 (Cmin) に、各々真空管の入力容量、配線の浮遊容量等の合計 (Cs) を加えたものの比の平方根となります。 すなわち、Cs はバリコンがどのような容量にセットされようと常時加えられるからです。
Fr = SQRT [ (Cmax+Cs) / ( Cmin+Cs) ] SQRT:平方根のことです。
もし、Fr を大きく取りたければ、Cs を極力少なくしなければなりません。 しかし、バリコン自体にも最小容量があり、どんなにガンバッテも Fr は4倍位が限界です。 中波放送周波帯では、前記の「2.2 中波放送の周波数」にて述べたように、精々Fr = 3 強となり、問題ありません。
初期のラジオに使われた単連中波用バリコンは Cmax = 300 pF 程度でした。 所が1960年頃には短波を受信できるオールウェーブのスーパーが現われ、スイッチを使ってコイルを切り替え、またトラッキング調整という幾つかの同調回路が可変でかつ連動した状態で同一周波数とするため、トリマキャパシタを使い調整しますが、その余裕を見こんで、前記の Cs が大きくなりました。 これでは Fr が確保しにくくなるので、Cmax = 430〜450pF 程度の大容量のものが標準となった時代がありました。
その後、家庭用ラジオでは短波受信に対する興味がうすれ、むしろ FM の併設が標準となって、中波 (AM) 用と FM 用を一つのバリコンに組み込むようになりました。 現在ジャンク屋の店頭にならべられているのは、主にこのタイプです。 AM - FM のセットではコ イル切り替えが不要なため、また小型化の要請もあって、中波 (AM) 用の Cmax は昔の容量に戻っ て 335 pF 辺りに設定されています。
機能 |
巻き数の目安 |
線材、巻き方 | |
| アンテナコイル | 同調コイルに、アンテナのインピーダンスの影響を与えることなく高周波信号をマッチングさせる | 同調コイルの 1/10 程度 | エナメル線またはアミラン線 0.3mm 単層密接巻き |
| 同調コイル | バリコンと組み合わせて受信周波数を決め、検波管のグリッドに高周波信号を供給する | ボビンの直径が = 25mm なら130 回 位、 = 30mm なら100 回 位、 = 35mm なら 80回位 | 同上 |
| 再生コイル | 帰還信号を同調コイルに与え検波管に発振を起こさせる | 同調コイルの 1/20 程度の巻き数のタップを出してもよいが調整がやや面倒になる | 同上 |
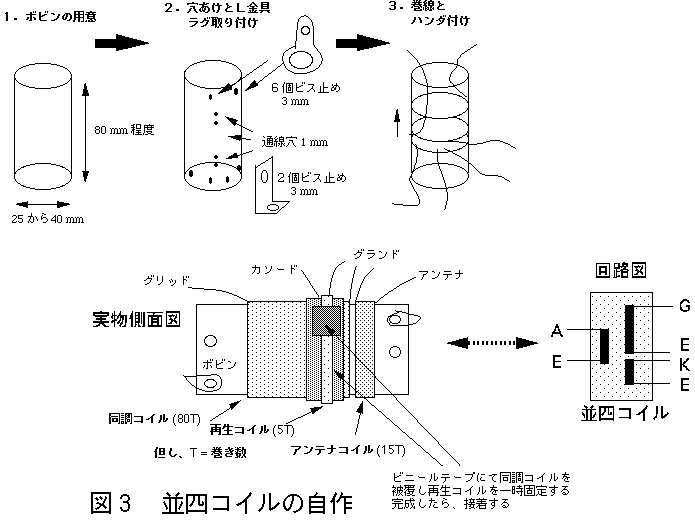
IL = K・ n**2/a (但し K は定数)
巻幅も IL に関係します。 断面積との関係をもつ定数(K: 楕円関数)となり、数表のお世話になる必要がありますが、無視して調整にて逃げるものとします。 但し、太い線で巻き、幅が長くなると誤差が出るので、直径:巻幅=1:1前後となる線が良いでしょう。
実際には巻幅、バリコンの容量、配線および検波管の入力容量等の誤差を考慮に入れると、巻き数は「〜回位」の、当たらずとも遠からずの目安と考えた方が安全です。 筆者の試作では、35mm ボビンに、巻線はDIY店で売っている0.32mm 10m 巻きを全部巻くと、計算上は 90回程度となりますが、結果的に少し不足で、更に 0.4mm のエナメル線を 10回巻き足しました。 もしかするとバリコンの容量が推定値より少ないのかもしれません。 巻き幅は 0.3mm で約 30mm 強となりますが、線の太さで変ります。 調整時にほどく可能性があるので、予め 2mm 位離した予備穴を2〜3コ位開けておき、タップを出して置くとL調整が簡単にできます。 巻き終わったら、線の端は被覆をハガして、ラグにハンダ付けします。
筆者の場合はこの方法でL不足を解決して、下端は丁度 531kHz になりました。 Lが決まれば、バリコンを全部抜いた状態でカバーする上端の周波数が決まります。 バリコンの最小容量=Cmin 約 15pF 、配線および検波管の入力容量等=Cs 約15pF として、
531 kHz x SQRT {(Cmax+Cs)/(Cmin+Cs)} = 531 x SQRT{(335+15)/(15+15)}
=: 1,814 kHz
と 1,800kHz 辺りになります。 上端はナリユキまかせでも別段構わないのですが、どうしても気になる方は半固定のトリマーキャパシタか適当な固定キャパシタ、またはビニール線を二本よじった代用キャパシタをバリコンに並列に接続して Cs を増やし、上端を 1,610kHz 位に抑えればよろしいでしょう。 「アンテナコイル」は同調コイルのグランド側の反対側に、同調コイルと同じ方向に10〜15 回程度巻き、被覆をハガしてラグにハンダ付けします。
中波用コイルの自作をマスタすれば短波用のコイルもどうということはありません。 Lが少ないので巻数が少なく、作りやすい反面、高い周波数では調整範囲が 1/2 回など微妙になります。 そのような場合は、ボビンの中に予め半巻を残して、それを巻方向に合わせて曲げればLが増え、反対方向に曲げればLが減るので、受信しながら非金属の割りばし等で曲げて調整します。
この再生コイル(またはタップ)が検波管のカソードに正しく接続されていれば、試作機を動作させ、検波管のスクリーン電圧を変える再生調整ツマミを上げていくと、ある角度以上で「ポッ」または「サッ」と発振を開始する音がスピーカから出ます。 この状態でアンテナを接続して同調をとる〜バリコンを回すと、ピョーというビート音を伴って、どこかの放送が入感します。 そこでビート音の周波数をゼロに近くなるように同調をとり直し、発振が止まるように再生調整ツマミを下げれば、聴取可能状態であり、一応 50% は完成です。
なお、発信状態では近所のラジオに一斉に妨害電波を捲散らすことになるので、速やかに調整ツマミを戻して発信状態を止める必要があります。 筆者の場合は、再生コイルを本来の同調コイルの下に追加して、タップを出した状態にして、UZ6C6 (=UZ57/UZ77) の例では 5回巻で OK でした。
もし、全く発振を開始しない場合は、再生コイルの向き(位相)が逆の可能性があります。 点検して再生コイルに接続した二本の線を入れ替えれば解決します。 次に、大変悩ましい下記の調整を行います。
(1) バリコンがどの位置にあっても、円滑に発振できないと、バリコンを回してカバーできる周波数全部を感度よく受信できないので、受信機としては未完成です。 再生コイルの巻き数が少ないか、またはスクリーン電圧が不足だと、バリコンが一杯に入った部分で発振が開始できません。 これを巻き足しにて解決します。
(2) 再生コイルの巻き数が多いと低いスクリーン電圧で発振を開始してしまうため、検波段のゲインが十分にとれません。 更に極端に巻き数が多いと、ソフトな発振ではなくブロッキングを伴うビロビロ発振となる場合もあります。 いずれも、巻きもどしでこれを解決します。
最終的には、上記の(1)(2)のカネアイで、バリコンのどの位置でもガマンできるような再生コイルの巻き数を見つけるのがこの調整です。 場合によっては巻き足しすることも必要です。 従って予め多めに巻き、様子を見ながら少しづつ巻きもどします。
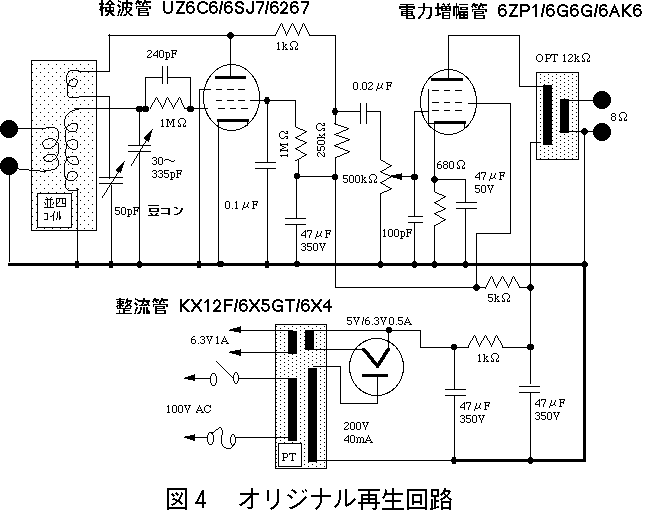
まず、読み取り精度の高い、すなわち受信周波数とダイアル目盛との一致度が高い中波放送受信機を検定機として用意します。 検定機は、パワーをいれて所定の周波数にて受信状態に置き、ヴォリュームを上げておきます。 一方並三実験機を発振状態にして、同調ダイアルを下から上へ、またはその逆に回してみると、周波数が一致した点で検定機からシューバサッと受信音がでます。 このときの周波数が実験機の受信周波数です。 シンセサイザ・チューナの検定機なら、周波数がバッチリ、ディジタル表示されます。 但し、実験機が発振状態にないと、すなわち再生回路がうまく調整されていないと、この計測法は成立しません。
●アンテナを短くして、信号入力を絞る。
●アンテナ端子からアンテナコイルに至る間に可変抵抗を直列に入れ、入力を絞る。
●アンテナ端子からアンテナコイルに至る間にバリコンを直列に入れて入力を絞る。
●アンテナ端子とアース端子の間にポテンショメータを入れて、可動端子からヴォリューム加減のスタイルにて、絞ってアンテナコイルに入力する。
最初の方法は、ちょっと実用的ではありません。 二番目の方法は実用的です。 三番目の可変抵抗の代わりのバリコンは高く付き、グランドから浮かせるので取り付けが面倒です。 最後の方法は、常時ポテンショメータがアンテナコイルに並列にはいり、気持ちが悪いのですが、中波放送帯ならば無視してもいいでしょう。 二番目または最後の方法の、可変抵抗またはポテンショの抵抗値は、実験で決めて下さるようお願いします。 おそらく 500Ω見当だと思います。
信じ難いことですが、実はこのようなアンテナ入力加減装置は並三、並四にはありませんでした。 安い製品では音量調整ツマミもなくて、やむを得ず混信の少ない側に離調して音量調整を代用していたのです。 ホントですよ。