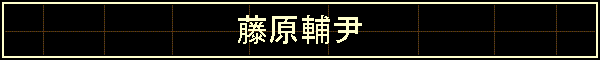|
生年未詳。父は藤原興方。大納言藤原懐忠の養子となる。従五位下正家の猶子という説もある。
正暦四(993)年、六位蔵人となる。このころ道兼の家司であった。
道長の周辺において活躍し、『本朝麗藻』に漢詩が見える。
寛仁五年ごろまでは生存したらしい。
家集『輔尹集』がある。
ここに着目!
 | ニックネームは「あらはこそ」 |
輔尹は『枕草子』第二百三十段に登場するが、「すけただは、木工允にてぞ、蔵人にはなりたる。いみじく荒々しくうたてあれば(たいそう粗暴で鼻つまみ者なので)、殿上人、女房、『あらはこそ(露骨さま?)』とつけたる」と描写される。さらに「左右なしの主(無類の乱暴者)、尾張人の胤にぞありける」とまで歌われ、一条帝がこれを笛で吹いたことが記してある。「あらはこそ」の意味か明瞭でないけれども、一条帝が、今日は輔尹がいないからこの歌を歌おうか、と言っており、宮中では嘲笑の的だったらしい。
気になるのは、輔尹が尾張人の胤だという歌詞である。『枕草子』は輔尹が尾張安居兼時という者の娘であることを注記しているので、輔尹の祖父が兼時だとわかる。宮中の御神楽で人長を務めた兼時は、『紫式部日記』に登場する舞の名手であった。と同時に、『今昔物語集』にも幾度か登場する。近衛府の舎人仲間と稲荷詣でに行き、参詣に来た女をからかったり(巻第二十八第一)、徴税に応じない国司の邸に乗り込んで、出された料理で腹を下したり(巻第二十八第五)、右近馬場の競馬(くらべうま)で下野敦行に負ける(第二十三第二十六)など、概して武人肌の、よく言えば豪放磊落な、悪く言えば粗野な人だったらしい。
輔尹はそんな兼時の血を引いて、粗暴だったのかもしれない。当時の婚姻形態からしても、母方の祖父と同居しており、影響を受けたとも考えられる。兼時は天元五(982)年四月の競馬に出場して相手に勝っている(『小右記』)くらいだから、年老いてなお、かなり達者だったことが明らかである。
ただ、輔尹の父は興方という受領階級の人で従五位上、尾張守であったが、輔尹を大納言懐忠の養子にしている(正家という殿上人の猶子という説もある)。輔尹が何歳のときのことか明らかでないが、懐忠自身は実子が絶えたときのことを考えて、幼少の輔尹を引き取ったのかもしれない。興方としても、懐忠のほうが身分的にも上で、子の将来のためにもなると考えたのだろう。『尊卑分脈』では輔尹の母が重尹(懐忠の実子で輔尹には弟になる)と同じ尹忠の娘となっているが、これは養母であると考えれば無理がない。養子になったのはやはり成人前だろう。
となると、輔尹の乱暴な性格が先天的なものかどうかは判別しがたいが、養子となったことも原因の一つに考えられるのではないだろうか。養父懐忠にはすでに男子があり、また輔尹の下にも男子が生まれている。義兄弟との確執などがなかったとは言えないだろう。四十歳ごろになっても粗暴と言われているので、若い時分ぐれたという程度ではなく、かなり根深いものがあったと思われる。
もっとも、『枕草子』の「すけただ」が藤原輔尹のことを指していないのでは、という説もある。木工允で蔵人を兼ねているというのが輔尹に当てはまらない、というのだ。が、興方は尾張守の経験があり、その縁で尾張人である兼時と知り合ったということも考えられる。清少納言が記憶違いをしていたなら、輔尹である可能性は捨てきれない。
家集からはしかし、輔尹の粗暴な面は伺い知ることができない。七十首ほどの歌の中で、目立つのは月の歌、それに不遇な我が身をかこつ歌であろうか。「山しろになりて、よの中すさまじきに、大殿にて、月まつ心よめとおおせれしに、『山しろのいはたのもりのいはずともおもふ心をてらせ月かげ』」などは、現在の官位への不満が皎々とした月光の冷たい雰囲気とあいまって、思わず身震いしてしまうような寒々とした歌になっている。
そのほかにも、五位六位と二人の男と付き合っている女に緋色の衣(五位の者が着用する直衣の色)も緑の衣(六位の色)も区別しないのかと、官位を意識した歌を送っているなど、どうやら昇進が思うに任せなかったのは確からしい。養父が公卿である割にはさほど昇進していないのは、当人の粗暴な気性のためかもしれない。だが性格を直すことは難しい。年を取って狷介になってゆく輔尹は、次第に孤独になる。清少納言のもと夫、橘則光が陸奥守となって下向する折には、都に留まって待っている身のほうが老いてしまう、別れは人のためではなく、我が身のためだと嘆いている。老い先短く、再び会えるかどうかわからない友との別れは悲痛である。
この輔尹、『尊卑分脈』では男子が三人あったと記録されているが、子や孫に囲まれた大往生を遂げることができたのだろうか。
|
|